リーガルチェック依頼メールとは?目的と重要性
リーガルチェック依頼メールは、単なる形式的な連絡手段ではありません。依頼の質が、その後のレビュー精度とスピードを決定づけます。ここでは、依頼メールが法務業務において果たす役割と、適切な依頼がもたらす効果について解説します。
そもそもリーガルチェック依頼メールはなぜ重要か
リーガルチェックとは、契約書の内容が法令や自社方針に適合しているか確認する業務です。リーガルチェックの依頼メールは、その業務のスタート地点にあたります。依頼文が曖昧だと、法務側は内容を正確に理解できず、確認の往復が発生しやすいため、結果としてレビューが遅れ、取引機会の損失やリスク見落としにつながるおそれがあります。
メール依頼が失敗する3つの原因(曖昧・長文・漏れ)
1. 依頼内容が曖昧
「契約書を確認してください」という一文だけの依頼は、法務担当にとって最も困るパターンです。 どの契約類型か、何を確認してほしいのか(例:責任範囲・支払条件・期間など)が明確でないと、法務側は目的を正確に判断できません。 その結果、不要な往復や手戻りが発生し、確認に数日かかってしまうこともあります。
依頼時は「確認してほしい論点」や「特に注意してほしい条項」を箇条書きで具体的に伝えることが重要です。
2. 長文で要点不明
取引背景や経緯を丁寧に説明しようとするあまり、長文になってしまうケースもよく見られます。 しかし、法務担当がまず知りたいのは「契約の目的」「確認してほしい箇所」「期限」の3点です。
背景説明が長すぎると、肝心の依頼範囲が埋もれてしまい、読み手の負担が増します。 背景や経緯は1〜2文程度に要約し、詳細が必要な場合は別途資料やコメント欄に添えるのがベストです。
3. 資料漏れ
契約書ドラフトを添付していても、比較版や関連資料(基本契約書、既存NDAなど)が欠けているケースがあります。資料が不足していると、法務側は過去契約との整合性を確認できず、再依頼が必要になります。
特に再委託や責任範囲のように、既存契約との関係性が重要な条項では、差分比較版や関連書類を必ず添付することが鉄則です。 資料が整理されているほど、レビュー精度とスピードが向上します。
押さえておきたい「リーガルチェック依頼メール」5点セット
件名:依頼・契約名・期限を必ず明記する
件名は、リーガルチェック担当者が最初に確認する情報です。件名で依頼の概要が分からないと、対応の優先度付けができず、後回しにされるケースもあります。「【リーガルチェック依頼】」「【至急】」「【確認希望】」などのラベルを付け、契約名と期限を含めるのが基本です。
記載例
- 【リーガルチェック依頼】業務委託契約書(10/10まで希望)
なお、複数契約を同時に依頼する場合は、件名に「(2件)」など件数を加えるとさらに親切です。
背景と目的:1文で取引の位置づけを説明
法務が判断を行うには、契約の「目的」と「位置づけ」の把握が欠かせません。たとえば同じ業務委託でも、既存顧客との追加契約か、新規取引かによって審査の観点が異なります。そのため、背景説明は長文ではなく、次のように1文でまとめます。
記載例
- 「新規取引先〇〇との業務委託契約締結にあたり、契約条件の適正性を確認したいです。」
このように簡潔に説明すると、法務担当が「重要度」「リスクレベル」「審査の深さ」を瞬時に判断できます。取引経緯や過去のやり取りなど詳細は、必要に応じて添付資料やコメントで補足しましょう。
懸念事項:どこを見てほしいかを具体的に伝える
契約書のレビューをお願いする際は、「どんな観点で見てほしいのか」を具体的に書くと、リーガルチェックがスムーズに進められます。その際は難しい法律用語を使う必要はありません。「自分が心配な点」や「取引上の重要条件」をシンプルに箇条書きで伝えましょう。
たとえば、次のような書き方です。
記載例
- 契約内容について、以下の点をご確認いただけますでしょうか。
- 全体の法的観点からの確認:契約書の中に法令に抵触する可能性や、当社にとって過度に不利な内容が含まれていないかご確認ください。
- 取引条件の妥当性:特に、支払い条件や契約の終了に関する取り決めが実務上問題なく運用できる内容になっているかご確認をお願いします。
このように具体的なテーマを挙げて依頼することで、リーガルチェックの方向性が明確になります。
また、もし特に注意してほしい箇所(たとえば「損害賠償の上限」「再委託の扱い」など)があれば、Wordのコメント機能で該当部分にメモを入れておくと、確認がさらにスムーズになります。
期限:具体的な日時と優先度を伝える
法務担当者や弁護士の多くは、日々多数の契約が並行して処理されます。「なるべく早く」「今週中」といった曖昧な表現では、どの案件を先に対応すべきか判断できません。
以下のように具体的な日時を明示しましょう。
記載例
- 10月10日(木)までに確認をお願いします
たとえば「取引先から契約締結期限を指定されているため」など、期限理由を添えることで法務の理解と協力が得やすくなります。
また、相手の負担を考慮し、余裕をもった締切を設定することが望ましいです。対応が難しい場合に日程調整できる旨を添えると、スムーズなコミュニケーションにつながります。
今すぐ使える依頼メールの文例(社内・弁護士・英語)
社内法務向け依頼メールテンプレ
件名:【リーガルチェック依頼】業務委託契約書(10/15まで)
宛名
お疲れさまです。〇〇部の△△です。
下記の契約書について、リーガルチェックをお願いできますでしょうか。
■ 契約概要
新規取引先(株式会社ABC)との業務委託契約です。
開発支援業務を依頼する内容で、成果物の権利帰属や再委託の扱いを中心に確認をお願いしたいです。
■ ご確認いただきたい点
契約全体を通じた法的リスクの有無
成果物の著作権・利用権の扱い
再委託や責任範囲に関する条項の妥当性
■ 希望期限
10月15日(火)17:00までにご確認いただけますと助かります。
ご都合が難しい場合は、調整いたしますのでお知らせください。
■ 添付資料
契約書ドラフト(Word)
修正差分版(相手方修正入り)
既存NDA
ご多用のところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
————
〇〇部 △△
内線:0000
メール:△△@example.co.jp
弁護士向け依頼メールテンプレ
件名:【契約書レビュー依頼】業務委託契約書(10/18まで/見積依頼)
弁護士 〇〇先生
お世話になっております。〇〇株式会社の△△と申します。
添付の契約書について、レビューをお願いできますでしょうか。
■ 契約の概要
新規サービス開発を委託する取引で、当社が発注者となります。
責任範囲や成果物の権利帰属に関して、当社に不利な内容がないかを中心にご確認いただければ幸いです。
■ ご依頼内容
法的リスクの有無
責任制限・再委託・知的財産権条項の確認
■ 希望納期
10月18日(金)を目安にご対応いただけますでしょうか。
ご都合が難しい場合は、別日でも問題ございませんのでご相談ください。
■ お見積り
ご対応可能な場合は、費用の目安も併せてご提示いただけますと助かります。
■ 添付資料
契約書ドラフト(Word)
修正差分版(相手方修正入り)
参考契約(基本契約書)
何卒よろしくお願いいたします。
————
〇〇株式会社 △△
TEL:03-XXXX-XXXX
Mail:△△@example.co.jp
英語での依頼メールテンプレ
Subject: Legal Review Request – Master Service Agreement with ABC Ltd. (by Oct 18)
Dear [Attorney’s Name],
I hope this message finds you well.
We would appreciate your review of the attached draft agreement related to our new service development project with ABC Ltd.
Scope of Review:
Identify any potential legal or compliance risks.
Review liability limitation, subcontracting, and IP ownership clauses.
Timeline:
Could you kindly review it by October 18 (Fri)?
If that schedule is difficult, please let us know an alternative date.
Attachments:
Draft agreement (Word)
Redline version
Existing NDA
Thank you very much for your kind support.
Best regards,
△△
Legal Team, 〇〇 Corporation
依頼後の流れとフォローのポイント
リーガルチェックを依頼したあとも、契約が締結されるまでにはいくつかの確認工程があります。特に、修正の反映確認や版管理が曖昧なままだと、思わぬ齟齬や誤送信が起きやすくなります。
ここでは、依頼後に行うべき差戻し対応・バージョン管理・情報共有のコツを整理し、スムーズな最終化までの流れを解説します。
レビュー後の差戻し・再確認のコツ
法務から修正案を受け取ったら、まず自分の依頼内容が反映されているかを確認しましょう。特に、「修正済」「要再確認」などの状態を自分でも明示しておくと、見落としが防げます。
たとえば、Wordコメント機能やスプレッドシートで「反映済/未反映」を管理し、未対応部分だけを再依頼する方法がおすすめです。意図と異なる修正が入っていた場合も、「この点は〇〇の理由で元の案を希望します」と具体的に伝えると、再修正がスムーズに進みます。
修正後は、社内決裁者にも最新版を共有し、どの版が最終版かを明確にしておくことが重要です。
バージョン管理と情報共有の注意点
契約書の最終化で最も多いトラブルが「どの版が最新か分からなくなる」問題です。これを防ぐには、ファイル名・フォルダ構成・共有ルールを統一することが効果的です。
具体的には、ファイル名に「契約名_日付_v1.0」などの形式を採用し、送信・差戻し・完了のステータスを明示します。また、Google DriveやLegalOnのような法務マターマネジメントツールなどを利用して、履歴を一元管理するのがおすすめです。
社内共有時には、メール本文に「最新版はこちらです」とURLを添付し、古いファイルを使用しないよう周知しましょう。この基本を徹底するだけで、契約書の二重管理・誤送信リスクを大幅に減らせます。
仕組み化でリーガルチェックの効率を高める方法
メールやチャットで契約書の依頼を回すだけでは、どうしても「抜け漏れ」や「対応の重複」が起こりやすくなります。法務も事業部も、確認の行き違いで時間をロスしてしまうのが実情です。
こうした課題を解消するには、依頼の受付からレビュー、締結後の管理までを一つの流れとして仕組み化することがポイントです。ここでは、実務で効果の高い3つのステップを紹介します。
依頼フォーム化で抜け漏れを防ぐ
最初のステップは、メール依頼を「フォーム形式」に置き換えることです。フォーム化すると、契約名や相手先、期限、確認してほしいポイントなど、法務がレビューに必要な情報を最初から揃えて受け取れるようになります。
たとえば入力項目を次のように整理します。
- 契約名・相手先名
- 契約の種類(業務委託/売買/NDAなど)
- 希望の回答期限と理由
- 確認してほしい内容(支払条件・責任範囲など)
- 添付ファイル
こうしておくと、法務側はすぐに優先度を判断でき、不要なやり取りが減ります。
LegalOnの「マターマネジメント」では、こうした依頼フォームをそのまま案件登録につなげられます。フォームに入力された内容が自動で整理され、担当者や期限、進捗がひと目で分かる状態になります。メールを探したり、スプレッドシートで追う手間が削減できます。
マターマネジメントで法務案件を一元管理する
依頼が集まったあとは、「今どの契約がどこまで進んでいるか」を可視化することが重要です。マターマネジメント(法務案件管理)では、各案件のステータスや担当者、対応期限を一覧で把握できます。
たとえば、「受付 → 審査中 → 差戻し → 承認待ち → 締結 → 完了」といった流れで案件を管理すれば、進捗が明確になります。
LegalOnのマターマネジメント機能では、案件ごとのやり取りやファイルをナレッジとして蓄積でき、過去の類似案件をAIが自動でレコメンドしてくれます。「以前の同種契約ではどう修正したか」をすぐに確認できるため、判断のばらつきが減り、ナレッジ共有にもつながります。
AI契約レビューでリスクの見落としを防ぐ
契約書のレビューをすべて人の目で行うと、時間がかかるうえ、担当者の経験によって精度に差が出てしまいます。ここで活用したいのが、AIによる一次チェックです。
LegalOnの「レビュー」機能は、契約書の条文をAIが読み取り、リスクが高い条項や見落としやすい項目を自動で抽出します。たとえば「下請法」「独占禁止法」「フリーランス新法」「印紙税」など、重要な法令との整合性も自動でチェックできます。
AIが基本的なリスクを洗い出してくれるので、法務担当者はより重要な交渉ポイントに集中できます。レビュー結果はWordやExcelで出力でき、事業部との共有もスムーズです。
締結後の台帳化と更新アラートで管理を自動化
契約が締結したあとも、管理の仕組みは欠かせません。更新日や自動更新の期限をうっかり見逃すと、不要な契約が延長されたり、解約の機会を逃したりすることがあります。
電子帳簿保存法対応のLegalOn「コントラクトマネジメント」では、契約書をアップロードするだけで、AIが開始日・終了日・更新有無などを自動で抽出します。その情報をもとに、更新期限や契約満了日のリマインドを自動で通知できるため、管理ミスを防げます。
電子契約ツールとの連携や検索機能も備わっており、紙とデジタルの契約をまとめて管理できます。
よくある質問(FAQ)
弁護士に依頼する場合、費用と納期はどう伝える?
弁護士に依頼する際は、最初のメールで「希望納期」を明確に伝えるのが基本です。
法務案件の多くは、緊急度や契約の重要度によってレビューの深さが変わるため、先に希望条件を提示することで、弁護士側も見積とスケジュールを正確に出せます。
例文
10月15日までに契約を確定したく、〇日までにレビュー案をいただけますでしょうか。費用の目安も併せてご提示いただけますと助かります。
緊急依頼の優先度と理由の書き方は?
緊急依頼では、件名に「【至急】」「【期限:〇/〇】」などのタグを付けて、ひと目で優先度が伝わるようにします。本文では、なぜ急ぎなのか(相手方の締切、社内リリース日、役員決裁日など)を簡潔に説明しましょう。
理由を添えることで、法務担当も背景を理解し、対応順序を調整しやすくなります。
また、「難しい場合は調整します」と一文添えると、相手への配慮が伝わります。
例文
先方から10月10日までの締結を求められており、至急ご確認をお願いしたく存じます。ご都合が難しい場合は調整いたしますので、お知らせください。
NDAを結ばずに契約書を送ってもよいか?
結論から言うと、NDA(秘密保持契約)を締結してから送るのが原則です。ドラフト段階とはいえ、契約書には社名・取引条件・金額など、企業の内部情報が含まれます。NDAを交わしておけば、情報が外部に漏れた場合の責任範囲を明確にでき、交渉過程での安心感も高まります。
ただし、既に取引関係がある相手で「包括NDA(全取引に適用)」が有効な場合は、個別のNDAを結び直さなくても構いません。運用ルールを社内で統一しておくと安全です。




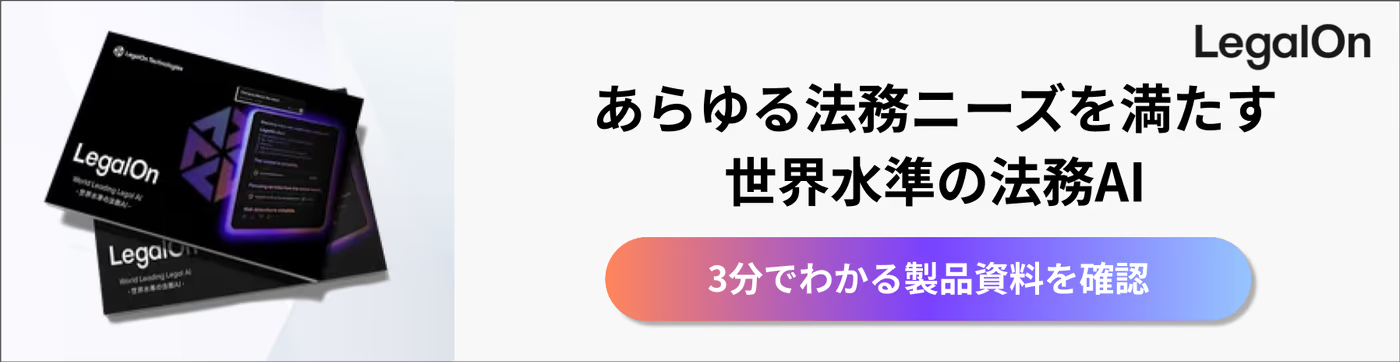
.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)

(1).webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
