株主総会議事録とは
株主総会議事録とは、株主総会で話し合われた内容や決定事項を記録した正式な文書です。会社法により、株式会社が株主総会を開催した際には必ず作成することが義務付けられています。この議事録には、会議の日時や場所、参加者の氏名、議事の進行内容、決議の結果などを正確に記載することが必要です。
株主総会議事録は会社の重要な意思決定を証明する法的効力を持つ文書として位置づけられており、税務調査や登記手続きの際にも提出を求められることがあります。
株主総会議事録の必要性
株主総会議事録の作成は会社法第318条により法的に義務付けられており、作成を怠ると100万円以下の過料が科される可能性があります。一人会社や、株主が一人のみの場合でも株主総会議事録の作成は必須です。この議事録は会社の重要な意思決定プロセスを公的に証明する役割を果たすため、税務調査の際には必ず確認される重要な書類となります。
また取締役の選任や報酬の決定、定款変更などの登記申請を行う際にも添付書類として提出が求められます。さらに、株主や債権者から閲覧請求があった場合には開示する義務もあるため、会社の透明性を保つためにも不可欠な文書です。
株主総会議事録は誰が作成するか
株主総会議事録の作成責任者は取締役と法的に定められています。複数の取締役がいる場合は、そのうちの誰が作成してもよく、代表取締役が作成することも可能です。
作成者となった取締役は議事録の内容について法的責任を負うため、正確で適切な記録を残すことが求められます。実際の作成作業については、総務部門や法務部門の担当者が行うことが一般的ですが、最終的な責任は必ず取締役が負うことになります。
議事録には作成者である取締役の氏名を明記する必要があり、この記載は会社法施行規則で義務付けられている必須事項となっています。作成後は適切な保管体制を整え、必要に応じて関係者が閲覧できる状態にしておくことが重要です。
株主総会議事録の記載事項
株主総会議事録には会社法施行規則により定められた記載すべき事項があります。これらを正確に記載することで法的要件を満たすことができます。
株主総会が開催された日時・場所
株主総会議事録には、開催された正確な日時と場所を必ず記載する必要があります。日時については年月日だけでなく、開始時刻と終了時刻も明記することが重要です。
場所については会社の本店所在地で開催される場合が多いですが、貸会議室やホテルなどで開催した場合は、その具体的な住所と建物名、会議室名まで詳細に記載します。
これらの情報は株主総会が適法に開催されたことを証明する基本的な要素となるため、記載漏れや間違いがないよう十分注意して記録する必要があります。
株主総会議事録の経過要領・決議内容
議事の経過要領では、株主総会でどのような流れで議事が進行されたかを時系列で記載します。開会の宣言から始まり、議長の選任、議案の説明、質疑応答、採決、閉会までの一連の流れを要点を絞って記録しましょう。
決議内容については、各議案に対する賛成票数、反対票数、棄権票数を正確に記載し、可決または否決の結果を明確に示す必要があります。
特に重要な決議については、決議に至った経緯や主な議論のポイントも簡潔に記録しておくことで、後日の参照時に有用な情報となります。
会社法規定に定められた特定の意見・発言内容
会社法では、株主総会で述べられた意見や発言のうち、特定のものについては議事録に記載することが義務付けられています。具体的には、株主から提出された質問や意見、それに対する取締役や監査役の回答内容を記録することが必要です。
ただし、すべての発言を詳細に記録する必要はなく、議事の進行に影響を与えた重要な意見や、会社の経営に関わる質問とその回答を中心に記載します。
会社法規定に定められた特定の意見・発言内容は主に以下のものがあります。(条文順)
- 監査等委員である取締役の選任・解任・辞任に関する意見の記載(会社法第342条の2第1項)
- 監査等委員である取締役が辞任後最初の株主総会で辞任理由を述べる旨の発言(同第2項)
- 監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任に関する意見の記載(同第4項)
- 会計参与の選任・解任・辞任に関する意見の記載(会社法第345条第1項)
- 会計参与が辞任後最初の株主総会で辞任理由を述べる旨の発言(同第2項)
- 監査等委員である取締役の報酬に関する意見の記載(会社法第361条第5項)
- 会計参与が、一定の書類の作成に関して取締役と意見が異なる場合における意見表明(会社法第377条第1項)
- 会計参与が株主総会で述べた意見の記載(会社法第379条第3項)
- 株主総会の議案または添付書類が法令・定款に違反する場合における監査役の報告義務(会社法第384条)監査役が報酬に関して株主総会で述べた意見の記載(会社法第387条第3項)
- 非公開会社において、会計に限定された監査役による会計議案に関する調査結果の報告(会社法第389条第3項)
- 会計監査人が株主総会に出席して意見を述べた場合の意見の記載(会社法第398条第2項)
- 監査等委員による株主総会への報告の記載(会社法第399条の5)
記載する際は発言者の氏名と発言内容の要旨を正確に記録し、会社の意思決定プロセスが適切に行われたことを証明できるようにします。
株主総会に出席した各取締役の氏名・名称
株主総会議事録には、株主総会に出席したすべての取締役の氏名を漏れなく記載する必要があります。これは会社法施行規則で定められた必須事項であり、記載漏れがあると法的要件を満たさない議事録となってしまうのです。
取締役だけでなく、監査役、執行役、会計参与、会計監査人が出席した場合も、それぞれの氏名または名称を正確に記載します。
法人が監査役や会計監査人を務める場合は、法人名と代表者名の両方を記載することが一般的です。
株主総会に議長を立てた場合の氏名
株主総会で議長を選任した場合は、その議長の氏名を議事録に明記する必要があります。多くの場合、代表取締役が議長を務めることが一般的ですが、他の取締役や株主が議長に選任されることもあります。
議長は株主総会の進行を統括し、議事の整理や採決の実施などを行う重要な役割を担うため、その選任過程と氏名を正確に記録することが求められるのです。議長が途中で交代した場合は、その旨と新しい議長の氏名も併せて記載します。
議事録作成を行った取締役の氏名
株主総会議事録の末尾には、議事録を作成した取締役の氏名を必ず記載する必要があります。これは会社法施行規則で定められた必須事項であり、記載がない議事録は法的要件を満たしません。
議事録作成者となる取締役は、記載内容について法的責任を負うことになるため、事実に基づいた正確な記録を作成することが重要です。複数の取締役が共同で作成した場合は、全員の氏名を記載します。
記載漏れがあった場合の対処法
株主総会議事録に記載漏れが発見された場合は、速やかに修正することが必要です。軽微な誤字脱字程度であれば訂正印による修正も可能ですが、重要な事項の記載漏れがある場合は、改めて正しい議事録を作成し直すことが推奨されます。
修正した議事録は、作成責任者である取締役が内容を確認し、修正日と修正理由を明記した上で保管します。記載漏れが登記申請や税務申告に影響する場合は、関係機関への届出や修正申請が必要になることもあるため、発見次第早急に適切な対応を取ることが重要です。
株主総会議事録の記載例と書き方ガイド
実際の株主総会議事録がどのような形式で作成されるのか、具体的な書き方を記載例付きでご紹介します。以下は中小企業でよく使用される定時株主総会の議事録例です。この例を参考に、自社の状況に合わせて内容を調整してください。
【株主総会議事録の記載例】
引用:株主総会議事録|法務局
この記載例は最も基本的な形式です。会社の規模や業種によって若干の違いはありますが、基本的な構成要素は共通しています。実際に作成する際は、自社の定款や過去の議事録も参考にしながら、適切な内容となるよう注意深く作成してください。
1. 総会の基本情報の記載
見出しの書き方
- 「第〇回定時株主総会議事録」と明記
- 議事録の回数は総会の開催回数に応じて記載(例:第10回)
開催日時と場所
- 「令和〇年〇月〇日 午前〇時〇分から」など、正確な日時を記載
- 開催場所も「当会社の本店において」等、登記簿上の本店所在地であることが多い
2. 株主および議決権の状況
記載する目的は、総会の成立要件(定足数)を確認することです。
- 株主の総数:議決権のある株主の人数を記載
- 発行済株式の総数:会社が発行している全株式数(自己株含む)
- 自己株式数:※あれば記載。「会社が保有する自己株式」であり、議決権なし
- 議決権行使可能な株主数・議決権数:招集通知を受けて議決権を行使できる者の数
- 出席株主数:実際に出席した人数(委任状提出者含む)
- 出席議決権の数:有効な議決権の合計数
- 出席取締役・監査役:出席した役員の氏名(○○ などで記載)
3. 開会宣言と総会成立の確認
出席状況を踏まえ、定款に基づいて総会が適法に成立していることを記載します。議長(多くは代表取締役)が議事を開始する旨も明記します。
4. 議案の内容と決議事項の記載
第1号議案(例:計算書類の承認)
- 決算期(事業年度の起点と終点)を明記
- 対象となる計算書類の一覧を記載 例:
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 議長が説明した上で、承認状況・結果を記載
第2号議案(例:取締役・監査役の選任)
- 任期満了による退任の説明
- 改選の必要性と選任方法(議長に一任など)を記載
- 指名された候補者名と、再任・新任の別、就任承諾の旨を記載
5. 閉会の記載
- 議長が議事終了を宣言した時刻を記載(例:午前〇時〇分)
- 最後に、「議長・出席取締役・出席監査役が署名押印する」旨を記載
6. 議事録への署名
- 開催日を記載(令和〇年〇月〇日)
- 商号(会社名)・総会の名称
- 署名欄:代表取締役、出席取締役、出席監査役の氏名欄を設ける
議事録ひな形の入手先
株主総会の議事録を一から作成するには手間と時間がかかるため、企業ではひな形のテンプレートを使うことが多いです。主な入手先には法務局や会社設立時に作成された議事録などがあります。
それぞれの入手先について詳しく説明します。
法務局が提供するひな形
法務局では、株主総会用の議事録記載例が確認できます(参考:「添付書面の記載例」法務局)。
株主総会議事録の例や株主の氏名、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)の例などがあります。企業は内容をコピーして使用できるため、ひな形をもとに株主総会の議事録を作成することが可能です。
会社設立時の議事録ひな形
会社設立時に作成した議事録をひな形として作成する方法もあります。
株式会社設立時は定款の設定や役員の報酬など決定すべきことが多いため、株主からの承認を得るために株主総会が招集されます。会社設立時に作成した議事録が保存されていれば、ひな形として使用することで新たな株主総会で利用可能です。
他にも、インターネット上には株主総会向けの議事録テンプレートを無料提供していることが多いので、自社のひな形を用意できない時はダウンロードを検討してください。
LegalOn Cloudは、決議内容に応じた80種類以上の株主総会議事録ひな形に加え、契約書・規程・社内文書など、合計2,000点超の法務書式を収録。あらゆる業務シーンに対応し、文案作成の手間を削減。作成業務の効率化と品質向上を実現します。ぜひチェックしてみてください。
株主総会議事録に押印は必要?
株主総会議事録を作成する際、多くの企業担当者が疑問に思うのが押印の必要性です。現在の会社法では、原則として押印は義務付けられていません。しかし、一部のケースでは押印が必要となる場合もあります。また、法的な義務がなくても実務上の理由から押印を行う企業も多く存在します。
原則として押印義務はなし
現在の会社法では、株主総会議事録への押印は原則として義務付けられていません。以前の旧商法では議長と出席取締役の署名・押印が必要でしたが、平成18年の会社法施行により押印義務は廃止されました。
現在は議事録作成者である取締役の氏名を記載するだけで法的要件を満たします。従って、押印がなくても税務調査や登記申請時に問題となることはありません。
もっとも、実務上は旧商法時代の慣習が残っており、現在でも議長や出席取締役・監査役の押印を行う対応を継続している会社が多いのが実情です。特に中堅企業や非公開会社では、社内管理や証拠性確保の観点から任意に押印を続けるケースが一般的です。
押印が必要となる例外的なケース
押印義務がない一方で、以下のように押印が必要となる例外的なケースも存在します。
- 定款で押印を義務付けている場合
- 取締役会を設置していない会社が代表取締役を選定する決議を行う場合
- 特定の登記申請や金融機関の手続きで、押印済み議事録の提出が求められる場合
最も多いのは、会社の定款で議事録への押印を義務付けている場合です。また、取締役会を設置していない会社が代表取締役の選定決議を行う際には、議事録への押印が法的に求められます。さらに、特定の登記申請や金融機関での手続きにおいて、押印された議事録の提出を求められることもあります。
これらのケースでは法的義務として押印が必要となるため注意が必要です。
以下の記事では定款について詳しく説明しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>【法律用語解説】定款とは? 作成から認証、記載事項や管理・保管まで徹底解説
株主総会議事録の保管義務・保管期間について
株主総会議事録は作成後に適切に保管することが会社法により義務付けられています。保管期間は本店では10年間、支店では5年間と定められており、この期間中は議事録を紛失や破損から守り、必要に応じて閲覧できる状態にしておかなければなりません。
ハードディスクやUSBメモリーなどの電子媒体で保存できるため、管理が簡便です。クラウドサービスを利用した保存も電子データ保存に含まれることから、企業に合わせた保存方法を選択可能です。
株主総会議事録を電子的に保存する場合、会社法上の保存義務を満たす必要があり、また文書の見読性や完全性(改ざん防止措置)など、e-文書法の要件に準じた措置を講じることが求められます。
具体的には、以下のような項目が要件となっています。
- 見読性:明瞭な状態であること
- 完全性:改ざん・消去がないことの確認ができること
- 検索性:すぐにデータを引き出せること
- 機密性:第三者への情報漏洩防止
上記項目をチェックした上で、株主総会の議事録を電子データとして保存するかどうか検討してください。
保管義務を怠った場合のリスク
株主総会議事録の保管義務を怠った場合、会社法違反として取締役や監査役に100万円以下の過料が科される可能性があります。また、税務調査の際に議事録の提示を求められても対応できず、税務上の問題が生じるかもしれません。さらに、登記申請時に必要な議事録が紛失していると手続きが困難になり、業務に大きな支障をきたすことになります。
株主や債権者から閲覧請求があった場合にも応じることができず、会社の信頼性に深刻な影響を与える可能性があります。
株主総会議事録の閲覧請求への対応
株主総会議事録は、株主や債権者から閲覧請求を受けた場合に開示する義務があります。ただし、すべての請求に応じる必要はなく、正当な理由がある場合に限って対応することが求められています。
閲覧請求への対応は会社の透明性を示す重要な機会でもありますが、一方で企業秘密の保護や営業活動への配慮も必要です。適切な判断基準を持ち、合理的な対応を行うことで、法的義務を果たしながら会社の利益も守ることができます。
閲覧請求が認められている者
株主および債権者は、株主総会議事録の閲覧を請求することができます。株主は持株数に関係なく、議事録の閲覧や写しの交付を請求する権利を持っています。この権利は会社法で保障されており、株主が会社の経営状況を把握し、適切な判断を行うために重要な制度です。
また、債権者についても正当な利害関係がある場合には同様の閲覧権が認められています。閲覧請求は会社の営業時間内であればいつでも可能で、事前の予約や特別な手続きは必要ありません。
ただし、請求者は株主であることの証明や債権者としての利害関係を示す必要があります。
正当な理由の判断基準
閲覧請求が正当な理由に基づくものかどうかは、請求の目的や必要性を総合的に判断して決定されます。一般的に、株主権の行使や債権回収のための情報収集、会社の経営状況の確認などは正当な理由として認められる傾向にあります。
一方で、同業他社への情報提供や営業妨害を目的とした請求、単なる興味本位での請求などは正当性に疑問が生じるでしょう。判断が困難な場合は、請求者に具体的な目的や必要性を説明してもらい、慎重に検討することが重要です。
閲覧請求を拒否できる場合
会社は請求者の目的が不当であると判断される場合には閲覧請求を拒否することができます。具体的には、営業秘密の不正取得や競合他社への情報提供を目的とした請求、会社の営業活動を妨害する意図が明らかな請求などが対象です。また、請求者が反社会的勢力に関係している場合や、過去に不当な要求を行った履歴がある場合も拒否理由となり得ます。
ただし、拒否する場合は会社側が不当性を立証する責任を負うため、明確な根拠を持って判断することが必要です。拒否の際は理由を明確に説明し、可能な限り代替案を提示することが望ましいとされています。
バーチャル株主総会(オンライン・ハイブッド)における議事録作成のポイント
バーチャル株主総会(オンライン・ハイブッド)とは、インターネット環境を利用して株主をオンラインで招集する株主総会です。
場所や時間の制限がないため、株主が参加しやすい点がメリットです。一方、使用するシステムの性能や通信環境によっては、一度に参加可能な株主の数に制限が生じる場合があります。大規模な総会の場合は、システムや通信環境の性能を事前に確認することが望ましいでしょう。
また、株主がオンライン会議システム等を用いて株主総会に出席した場合、オンラインかオフラインかという出席方法を株主総会議事録に記載することが推奨されます。ただし、株主がインターネットから審議等を確認・傍聴するだけであれば株主総会議事録の記載は不要です。
こちらの要件を理解した上で、バーチャル株主総会を開催して議事録作成を行うか検討してください。
まとめ
今回は、株主総会の議事録を作成する方法や押印方法、ひな形の入手先まで解説しました。株主総会の議事録は会社法によって作成が義務付けられているため、正しい書き方を理解しておく必要があります。
株主総会用の議事録ひな形があれば、作成をスムーズに進めることが可能です。ぜひ当記事で紹介した作成方法やひな形の入手先を参考にしながら、株主総会の議事録を作成してください。
<関連記事>



.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
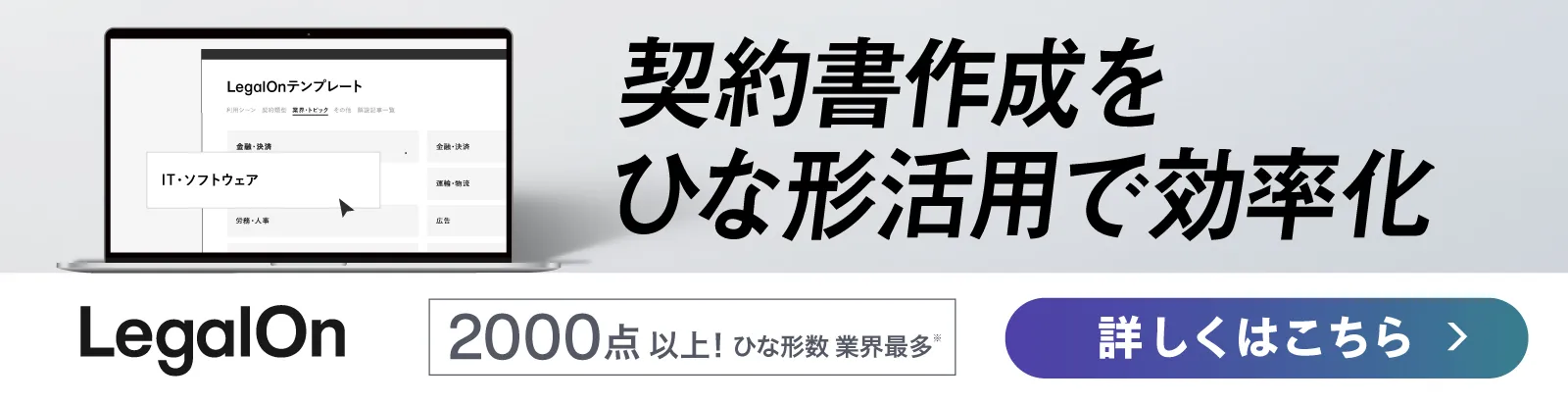
.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
