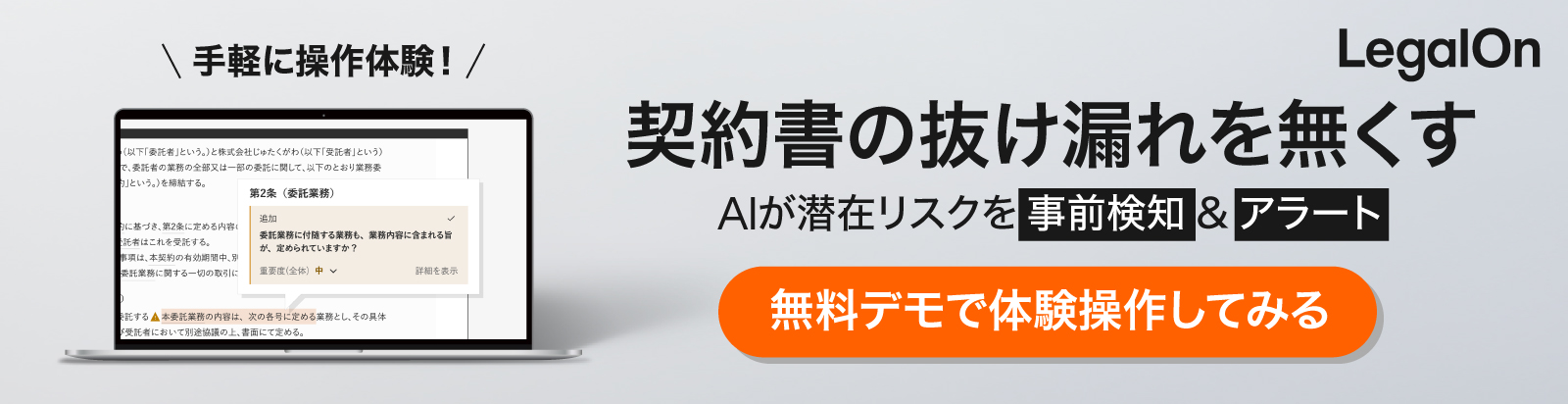建設工事請負契約書とは
建設工事請負契約書とは、マンション・ビル・店舗などの建設工事に関して、発注者と受注者が取り交わす正式な契約書のことです。
本章では、建設工事請負契約書の定義や特徴、一般的な契約書との違い、必要となる具体的なシーンについて、初めての方にもわかりやすく解説します。
発注者と受注者が工事内容を取り決める契約書
建設工事請負契約書とは、建設工事を発注する側(発注者)と受ける側(受注者)が、工事の内容や条件を明確に取り決め、合意内容を書面で交わす契約書です。工事内容・金額・工期などの重要事項を明文化することで、トラブル防止や法的な証拠としての役割を果たします。
一般的な契約と異なり、建設業法第19条により「契約書の作成と交付」が法的に義務化されている点が特徴です。すなわち、工事請負契約書を締結せずに工事を行うことは、法令違反に該当します。
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
また、国土交通省のガイドラインでは、原則として「工事の着工前までに書面交付を済ませること」が求められています。
建設工事請負契約書は、単なる合意文書ではなく、法令に基づいた正式な契約書であり、信頼ある取引を実現するための重要な基盤です。
参考:国土交通省|「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第3版)」8頁
工事請負契約書は発注者と受注者のどちらが作成する?
工事請負契約書は、発注者・受注者のいずれが作成しても法的には問題ありませんが、実務上は受注者(建設会社)が作成するケースが多く見られます。
建設業法第19条では「契約書を作成して相互に交付する」ことが求められており、どちらが起案者かまでは定められていません。つまり、両者が合意した書面であれば、発注者・受注者のどちらが作成しても適法です。
実務における作成者の違いは、以下の通りです。
- 発注者のタイプ:個人(マイホーム建築など)
- 契約書の作成主体:受注者(建設会社)
- 理由:発注者は契約書作成に不慣れであることが多く、建設会社が主導するのが一般的
- 発注者のタイプ:自治体・官公庁
- 契約書の作成主体:発注者
- 理由:法務・技術系職員が在籍しており、自ら契約書を作成する体制が整っている
- 発注者のタイプ:不動産会社・法人発注者
- 契約書の作成主体:発注者
- 理由:自社で用意した契約書フォーマットを提示するケースが多い
契約書の作成者に明確なルールはないものの、実務では発注者の属性や契約の規模に応じて役割分担されているのが実情です。
「完成責任」が求められる契約
建設工事請負契約書は、民法第632条に基づき、「仕事の完成」とその「成果物の引き渡し」が契約の成立要件とされています。
以下は、請負契約とその他の契約類型(委任契約・準委任契約・業務委託契約)の違いを整理した比較表です。
- 請負契約
- 主な目的:成果物の完成
- 成立要件:合意+完成
- 報酬発生の条件:完成後に報酬が発生
- 委任契約
- 主な目的:作業の遂行
- 成立要件:委任の受諾
- 報酬発生の条件:業務遂行で報酬発生
- 準委任契約
- 主な目的:非法律行為の遂行
- 成立要件:委任の受諾
- 報酬発生の条件:業務遂行で報酬発生
また、建設工事請負契約書では、以下のような完成責任に関連する義務が発生します。
- 契約に定めた工事を完成する義務(民法第632条)
- 工事の遅延により、契約解除や違約金の対象となる場合がある(民法第541条)
- 下請け業者等のミスも、原則として元請が責任を負う(履行補助者責任)
- 完成後に不具合(契約不適合)が判明した場合も補修義務が生じる(民法第562条以降)
- 災害・天候などの不可抗力による損害も、原則は請負人が負担(契約により変更可)
建設工事請負契約では「完成してはじめて契約を履行した」とみなされるため、契約時には完成責任の範囲や例外事項(災害時対応、保証保険の加入など)を明確に定めておくのが重要です。
建設工事請負契約書が必要となる具体的なシーン
建設工事請負契約書は、住宅・ビル・店舗などの建築工事を依頼・受注する際に必要となる重要な契約書です。
契約が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 住宅の新築:施主がハウスメーカーや工務店などと契約を結び、設計完了後に工事に着手する流れが一般的
- 住宅のリフォーム:壁紙の張り替えや設備の更新など、部分的な改修でも請負契約を結ぶケースがある
- 増改築・改装工事:間取りの変更やスペースの拡張を伴う工事では、仕様や責任範囲の取り決めが重要になるため契約が必要
- 外構・エクステリア工事:駐車場整備や塀・庭の造成など、建物外部の整備工事でも請負契約を結ぶことがある
- ビル・マンション・店舗の工事:不動産ディベロッパーやオーナーが、建設会社と新築・増改築・修繕工事の契約を交わす
上記の場面では、工事内容や責任範囲、金額、工期などを明確にしておく目的で、必ず書面での契約が求められます。
特に住宅の新築やリフォームは、一般の方でも関わる機会があるため、契約書の基本的な構成やチェックポイントを知っておくと安心です。
施工業者と注文者の所有権関係──工事請負契約における帰属と移転
建設工事で新築された建物の所有権は、原則として材料を提供した側に一時的に帰属します。
判例(大審院大正4年5月24日)などに基づき、建物の所有権は材料の提供者に帰属すると解されていることから、工事に使用される資材を誰が負担したかが判断の基準になります。
所有権の帰属・移転の仕組みは、以下の通りです。
- 状況:請負人が材料を提供(一般的なケース)
- 所有権の帰属:請負人(施工業者)
- 所有権が移転するタイミング:工事完成後、代金支払いと引き換えに注文者へ移転
- 状況:注文者が材料を提供
- 所有権の帰属:注文者
- 所有権が移転するタイミング:原則として最初から注文者に帰属
また所有権の移転は、登記上の名義変更を指し、残代金の支払い後に司法書士が法務局で手続きを行う流れで進められます。登記手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。
- 印鑑証明書(委任状用)
- 実印
- 身分証明書(本人確認用)
- 新住所の住民票(登録免許税軽減のため)
工事請負契約における所有権は、施工業者から注文者へ代金の支払いと引き換えに移転するのが一般的です。材料の提供者が誰かを明確にしておくと、契約トラブル防止にもつながります。
【ひな形】:「建設工事標準請負契約約款」
建設工事請負契約書を締結する際には、「建設工事標準請負契約約款(以下、標準約款)」の活用が有効です。
標準約款は、トラブル防止や契約の公平性を担保するために、国土交通省所管の中央建設業審議会によって策定された公的なひな形です。
民間工事の場合は、工事の規模等に応じて以下のとおり約款を使い分けるのが一般的です。
- 比較的大きな規模の工事(ビル、店舗用物件など)用ひな形 →民間建設工事標準請負契約約款(甲)
- 比較的小さな規模の工事(個人住宅など)用ひな形 →民間建設工事標準請負契約約款(乙)
- 下請工事用ひな形 →建設工事標準下請契約約款
標準約款を使えば、契約の抜け漏れや曖昧な表現を防ぎ、信頼性の高い契約書を作成できます。特に発注者として契約書を取り交わす際には、必ず約款の内容を確認し、業務の実情に合うようカスタマイズして活用するのが重要です。
建設工事請負契約書を結ぶ3つの目的
この章では、建設工事請負契約書を取り交わす3つの目的について、実務に即した観点からわかりやすく解説します。
工事の内容・範囲・責任を明確にしてトラブルを防ぐ
建設工事請負契約書を交わす第一の目的は、工事の内容や仕様、責任範囲をあらかじめ明確にし、発注者と受注者の間で起こりやすいトラブルを未然に防ぐことです。
工事請負契約では、建物の構造・設備・仕上げなど、仕様の細部まで取り決めておかないと、完成後に「思っていた仕上がりと違う」などのクレームが発生しかねません。
特に以下については、工事請負契約書でしっかり定めておくのが重要です。
- 使用する建築部材の種類や品番
- 防火性能・耐震性能など満たすべき基準
- 造作家具や設備の設置場所・仕様
- 壁・床などの仕上げ方法や加工の方法
明文化された仕様内容は、完成物に不具合があった場合に契約不適合責任を問う際の基準になります。契約書に上記の項目が盛り込まれていれば、完成後の解釈違いや責任の所在が曖昧になるのを防げます。
発注者・受注者の立場を公平に保つ
建設工事請負契約書を取り交わすことで、発注者・受注者の双方にとって公平な契約関係を築けます。建設業における請負契約では、資金や発注権限を持つ発注者のほうが、交渉上優位に立つことが少なくありません。
そのため、口頭や不完全な契約では、受注者側が一方的に不利な条件を受け入れざるを得ない場面もあるのが実情です。建設工事請負契約書を明文化すると、以下の対等な関係性を担保できます。
- 支払い時期や方法などを明記し、受注者が報酬を確実に得られる仕組みを構築
- 仕様変更や追加工事があった場合の対応ルールを明確化し、追加費用のトラブルを回避
- 損害賠償や契約解除の条件を契約時に共有し、どちらかが一方的に不利益を被らない状態を確保
建設工事請負契約書は、契約上のパワーバランスを是正し、発注者・受注者の双方が納得できる平等な関係を築くための土台となります。特に中小企業や個人事業主の施工業者にとって、自社を守る有効な手段といえるでしょう。
工期や代金の合意内容を証拠として残す
建設工事請負契約書は、合意した工期や代金を証拠として残し、万一の紛争時にも対応できる重要な文書です。工事が完了するまでには数ヶ月〜年単位の期間を要する場合も多いため、途中でトラブルが起きる可能性もゼロではありません。
万が一、発注者と受注者の間で契約内容に関する認識違いや支払いトラブルが発生した場合でも、事前に合意した内容が書面に明記されていれば、契約書が法的な証拠資料として機能します。
実際に訴訟などに発展したケースでは、契約書の内容に基づいて裁判が進められ、以下の項目が重要な判断材料となります。
- 工事の開始日・完了日などの工期の明記
- 請負代金の総額および支払い方法・支払日
- 支払い遅延や変更時の対応ルール
- 中止・変更時の代金精算の取り決め
あらかじめ契約内容を明文化しておくことで、双方にとって安心できる契約関係を築けるでしょう。
建設工事請負契約書に記載すべき項目一覧
建設工事請負契約書には、法律で必ず記載しなければならない内容が定められています。これは建設業法第19条に基づくもので、発注者・受注者のトラブル防止や公平な契約のために重要です。
以下が、契約書に明記すべき主な項目です。
- 工事の内容
- 請負代金の金額
- 工事の開始日と完成日
- 工事を行わない日や時間帯(必要な場合)
- 前金払いや出来高払いの条件(ある場合)
- 設計変更や工事の中止・延期があった場合の取り決め
- 自然災害など不可抗力による変更時の取り決め
- 物価変動による金額や内容の変更ルール
- 第三者への損害が発生した場合の責任分担
- 資材や機械を発注者が提供する場合の取り決め
- 工事完成時の検査方法と引渡しの時期
- 工事完了後の支払い条件
- 契約不適合や保証の取り決め(ある場合)
- 契約違反があった場合のペナルティ
- トラブル発生時の解決方法
- その他、国土交通省令で定められている事項
契約の内容は非常に多岐にわたるため、各項目を丁寧に記載することが求められます。次章からそれぞれの項目について実務上のポイントや注意点を詳しく解説していきます。
建設工事請負契約書に記載すべき基本項目
建設工事請負契約書には、多くの記載項目がありますが、中でも最初に押さえるべきなのが「工事名・場所・工期」などの基本情報です。
これらは契約の骨組みにあたる重要な要素であり、契約内容全体の理解を左右するだけでなく、工程管理やトラブル防止の基盤にもなります。本章では、工事に関する基本項目の記載内容や注意点についてみていきましょう。
工事内容・場所・工期などの基本情報
建設工事請負契約書を作成するうえで、まず押さえるべきは工事の基本情報です。これは契約の骨格にあたる部分であり、後々のトラブル防止や工程管理にも大きく影響します。
基本項目の記載例は以下のとおりです。
- 記載項目:工事名
- 内容の例:〇〇ビル新築工事
- ポイント:物件名+用途が明示されていると良い
- 記載項目:工事場所
- 内容の例:東京都〇〇区〇〇丁目
- ポイント:番地・地番まで正確に記載
- 記載項目:工事の期間
- 内容の例:
- 着工日:〇年〇月〇日
- 完成日:〇年〇月〇日
- ポイント:引渡日が別の場合は併記が望ましい
- 記載項目:非施工日・時間帯
- 内容の例:土日祝日は原則休工、夜間は作業不可など
- ポイント:周辺住民への配慮にもつながる
また、記載時の注意点として、以下の配慮も欠かせません。
- 工期は現実的に設定すること:天候や資材の遅れなども考慮し、余裕を持った日程を組む
- 休工日・施工時間帯の取り決め:近隣住民やテナントへの影響を避けるため、時間帯や曜日の制限を明文化
- 工事場所の表記ミスを避ける:地番や区画の誤記はトラブルの原因になるため、登記簿に基づいた表記が望ましい
工事に関する基本項目は、誰が見ても工事の全体像が分かるように、正確かつ網羅的に記載しておくのが大切です。
請負代金の金額・支払方法に関する項目
建設工事請負契約書では、請負代金の内容や支払い方法を明記するのが重要です。後々の支払トラブルを未然に防ぐとともに、契約上の義務・責任を明確にできるためです。
特に金額が大きくなる建設工事では、分割払いの回数やタイミング、支払方法のルールを文書化しておくと、双方が安心して取引を進められます。
請負代金に関して記載すべき主な項目は以下のとおりです。
- 記載項目:請負代金の額
- 内容の例:請負代金1,000万円(税抜)+消費税100万円、など
- ポイント:税抜金額と消費税額を明記する
- 記載項目:支払方法
- 内容の例:契約時30%、着工時30%、など
- ポイント:分割の場合は各回の支払額・タイミングを明記する
- 記載項目:支払時期
- 内容の例:契約締結時・工事開始時・上棟時・引渡時など
- ポイント:各支払いの時期を明示する
- 記載項目:代金変更のルール
- 内容の例:受注者は、発注者の責めに帰すべき事由による設計変更、追加工事等により、当初の請負代金の額を変更する必要が生じたときは、発注者と協議し、別途書面により変更契約を締結するものとする。
- ポイント:設計変更・中止などで金額が変動する場合の調整方法をあらかじめ定めておく
- 記載項目:法令上の留意点
- ポイント:不当に低い金額の設定は禁止(建設業法第19条の3)。標準請負契約約款に基づくのが望ましい
請負代金に関する取り決めを明確にしておくと、後の金銭トラブルを回避しやすくなります。特に大規模な工事や複数回の支払いを伴う場合は、契約前に詳細まで確認しておくのが大切です。
引渡しに関する取り決め
建物の完成後、きちんと検査と引渡しのルールを定めておくのは、トラブル防止の観点から重要です。検査や引渡しの段取りが不明確だと「引渡しが済んだはず」「まだ支払いが終わっていない」など、誤解や揉め事の原因になります。
完成検査と引渡しに関して、整理すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 記載項目:検査の時期・方法
- 内容の例:工事完成後、速やかに発注者が立ち会って実施する
- ポイント:合格をもって「完成」と判断されるため、手順は明確にする
- 記載項目:引渡しの時期
- 内容の例:通常は検査合格後、代金支払い完了後におこなわれる
- ポイント:支払いと引渡しの順序も契約で確認しておく
- 記載項目:引渡しの方法
- 内容の例:現地にて建物の鍵を手渡す、書面で受領確認を取るなど
- ポイント:細かく取り決めることで後の証明にも役立つ
- 記載項目:特約事項
- 内容の例:全額入金確認後に鍵を手渡す
- ポイント:引渡し条件を個別に定めたい場合は契約に追記する
建設工事標準請負契約約款をベースにしつつ、現場ごとの事情に応じて特約を加えることも検討しましょう。
工事の変更・トラブルに備えた取り決め
建設工事は、契約時に想定していなかった変更やトラブルが発生しやすい分野です。そのため、契約書には予期せぬ事態に備えた取り決めを明確にしておく必要があります。
本章では、工事の変更やトラブルが発生した際に備えた基本的なルールと、記載時のポイントについて具体的に解説します。
工期の中止・延長に関する取り決め
建設工事は長期にわたる作業が多いため、予期せぬトラブルや変更に備えて、工期の中止・延長のルールをあらかじめ定めておくことが重要です。
特に、天候や資材の調達状況、法的な制約などで工事の進行が難しくなった場合に備えておくと、関係者間のトラブルを未然に防げます。
工期中止・延長に関する取り決めの要点は以下のとおりです。
- 記載項目:延長・中止の条件
- 内容の例:予期せぬトラブル(天災、行政手続、用地収用など)が発生した場合
- ポイント:受注者が正当な理由をもって申請できるよう明記する
- 記載項目:手続き方法
- 内容の例:書面による通知と発注者との協議が必要
- ポイント:突発的な判断による混乱を避けるための対話が前提
- 記載項目:損害負担
- 内容の例:発注者または受注者のどちらが負担するかを明記
- ポイント:建設工事標準請負契約約款では状況に応じて定めあり
- 記載項目:特約の設定
- 内容の例:「土地が行政に収用された場合は中止可」など
- ポイント:現場条件によって、柔軟な特約を追加するケースもある
工期の延長・中止について明確なルールを盛り込んでおくと、契約後の交渉や賠償リスクを減らし、公平かつスムーズな契約運用が可能になります。
不可抗力発生時の対応ルール
建設工事においては、自然災害や予測不可能な事故など、工事の進行に大きく影響する不可抗力が発生する場合があります。こうした事態に備えて、契約書にあらかじめ対応策を明記しておくことが重要です。
不可抗力に関する取り決めをしておけば、トラブル時の責任の所在や損害の分担について、当事者間で混乱が生じるリスクを軽減できます。
不可抗力発生時の対応方法の例は、以下のとおりです。
- A案:善管注意義務を果たしていれば発注者負担
- ポイント:受注者に有利。契約時に明記が必要
- B案:善管注意義務を果たしていれば協議で負担割合を決定
- ポイント:中立的。協議により柔軟に対応可能
- C案:原則として受注者負担
- ポイント:発注者に有利。リスクを受注者が負う内容
建設工事標準請負契約約款では、上記のような選択肢を提示し、契約当事者の交渉によって柔軟に取り決める方式が採られています。
特に近年は気候変動の影響もあり、台風や大雪などの予期せぬトラブルが増えています。こうした事態に備えるためにも、不可抗力時の対応ルールは、事前に協議・明文化しておくのがおすすめです。
第三者への損害賠償に関する定め
建設工事に伴って第三者に損害を与える可能性があるため、損害賠償のルールを契約書で明確にしておく必要があります。
工事現場では、近隣住民や通行人、隣接する建物などに思わぬ被害を及ぼすリスクが常にあるからです。
万が一の事故発生時に責任の所在が曖昧だと、当事者間での対応が混乱するおそれがあります。
損害賠償に関しては、以下のような原則が一般的です。
- 損害発生時の原則:原則として受注者が負担
- 発注者の帰責事由がある場合:発注者が損害を負担
- 標準契約約款の規定:民間建設工事標準請負契約約款(甲)19条(乙)12条に準拠するケースが多い
責任の所在をあらかじめ取り決めてくと、トラブル時の対応がスムーズになります。損害賠償に関する条項は、必ず契約書に盛り込みましょう。
地中障害物の発見に関する取り決め
工事中に地中障害物(埋設物・廃材など)が発見されると、作業の中断や追加費用の発生につながるため、契約書で対応方針を定めておくことが重要です。
テンプレート契約書では規定がない場合も多く、現場でトラブルになるケースもあります。
地中障害物の発見に関する取り決めの例は、以下のとおりです。
- 発見時の対応:請負人は速やかに発注者へ報告
- 費用見積り:請負人が撤去費用を見積り、発注者の承諾を得る
- 追加費用の請求:承諾がない限り、追加費用は請求できない
- 実務上のポイント:一方的に請求できる条項はトラブルの元、協議ベースでの運用が望ましい
特に請負人は「撤去費用は発注者に請求したい」と考えるのが一般的ですが、実務上は「協議により対応を決める」条項とするのが現実的です。
契約書にあらかじめ報告義務と承諾条件を明記しておけば、追加費用の請求をめぐる紛争を防止できます。テンプレートを利用する際も、地中障害物に関する条項があるかを確認し、不足していれば追加する対応が必要です。
契約違反・品質問題・紛争時の対応
建設工事においては、どれだけ入念に契約を交わしても、工事の遅延や不具合、金銭面のトラブルが生じる可能性はゼロではありません。
こうした万が一の事態に備えて、契約違反・品質不良・紛争時の対応ルールをあらかじめ契約書に盛り込んでおくことが、双方のリスクを最小限に抑えるために重要です。
この章では、「違約金」「契約不適合責任」「紛争解決手段」などのリスク対応の基本項目について、実務上のポイントとともに詳しく解説します。
契約違反時の違約金の取り決め
契約違反があった場合に備えて、違約金の取り決めも明文化しておくべきです。建設工事は金額や責任が大きいため、一方的な契約解除や履行遅延などが発生すると、相手方に大きな損害が生じる可能性があります。
違約金条項の記載例は、以下のとおりです。
- 発注者の都合によって本契約を解除した場合、発注者は受注者に対して損害賠償に加え、違約金として◯◯万円を支払うものとする。
違約金の発生条件や金額、計算方法を明確にすると、双方が安心して契約を履行できます。違約金に関する条項は、当事者間の信頼関係を守る保険のような役割を果たします。
後々のトラブル回避のためにも、契約段階でしっかりと取り決めておきましょう。
契約不適合責任に関するルール
建物の完成後に引渡しを受けたあと、不具合や仕様と異なる点が判明した場合に備えるのが「契約不適合責任」の取り決めです。
これは、従来「瑕疵担保責任」とされていたものが、2020年の民法改正によって「契約不適合責任」として整理され、内容がより明確化されたものです。(民法第562条〜第566条)
民間建設工事標準請負契約約款においても、国土交通省が2020年に改正概要を公表しており、「契約不適合」に関する明記が推奨されています。
主な取り決め内容は、以下のとおりです。
- 記載項目:契約不適合の定義
- 内容の例:設計図書・仕様書と異なる内容での完成、明らかな施工不良など
- ポイント:民法第562条に基づく、従来の「瑕疵」と異なり、目的達成不能でなくとも責任が生じる
- 記載項目:補修の範囲
- 内容の例:請負人は自費で速やかに補修対応する
- ポイント:民間約款では「引渡しから2年間」などと期間を明記することが多い
- 記載項目:損害賠償
- 内容の例:補修不能な場合には、相当額の損害賠償を請求できる
- ポイント:請負代金を上限にするなど、金額の上限設定があるケースもある
- 記載項目:責任追及の期限
- 内容の例:発注者は不適合を知った時から1年以内に通知する必要あり
- ポイント:民法第566条の規定に従う
- 記載項目:保険の加入
- 内容の例:契約不適合責任に備えて、保証保険や瑕疵保険などの加入を義務づける
- ポイント:保険加入の有無は特約により明記する
上記のような契約内容をあらかじめ書面で定めておくことで、引渡し後の品質トラブルや解釈のズレを防ぎ、リスクを最小限に抑えられます。
紛争解決方法に関する取り決め
建設工事請負契約書には、万が一の紛争発生に備えた解決方法も明記しておくのが重要です。例えば「〇〇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」や「第三者機関によるあっせん・調停を優先する」など、あらかじめルールを決めておくと、トラブルが起きた場合もスムーズに対応できます。
実際に採用されている主な紛争解決手段は、以下のとおりです。
- 指定裁判所での訴訟による解決(例:東京地方裁判所など)
- 建設業協会や地方建設業協会によるあっせん・仲裁
- 日本商事仲裁協会(JCAA)などの第三者機関による正式な仲裁手続き
紛争解決の手段を明文化しておくと、リスク対策としても有効です。トラブルが起きてから慌てて対応するのではなく、契約段階で「どう解決するか」をしっかり定めておくことが、信頼関係の維持にもつながります。
建設工事請負契約書におけるよくあるトラブルと防止策
建設工事請負契約では、契約書を取り交わしていても、工期の遅延や仕様変更の行き違い、近隣トラブルなど、さまざまな問題が発生することがあります。あらかじめ契約書で対応ルールを明文化しておくことで、未然に防いだり、発生時の対処をスムーズにしたりすることが可能です。
本章では、建設工事請負契約における典型的なトラブル事例と、それぞれの防止策を実務目線で解説します。契約書作成や見直しの際に、ぜひ参考にしてください。
工期の遅延と違約金請求トラブル
建設工事では、工期の遅延が原因で違約金トラブルに発展するケースが少なくありません。そのため、事前に「遅延」と「違約金」の定義と計算方法を契約書に明記しておくのが重要です。
以下は、契約書に盛り込むべき違約金関連の要素を整理したものです。
- 適用条件:請負人の責めに帰すべき工事遅延
- 計算方法の例:延滞日数に応じて、請負代金の年14.6%以内の割合で計算(標準約款に準拠)
- 発注者の対応:契約書に基づき違約金の請求が可能
- 留意点:不可抗力による遅延(天候・災害等)は対象外とし、契約書に例外を明記しておく
特に請負人(施工業者)の責任による工事の遅延が生じた場合、発注者側が損害を被る可能性が高いため、あらかじめルールを定めておくことで、後の紛争を回避できます。責任の所在や例外事項まで定めておくと、トラブルの予防につながります。
騒音や近隣クレームによる工事停止
工事中に発生する騒音や振動によって、近隣住民からのクレームが原因で工事が中断されるケースがあります。そのため、「誰が・どのように・どこまで」責任を持つのかを明確にしておく必要があります。
実務上の対応ポイントは以下のとおりです。
- クレーム対応の原則:原則として請負人(受注者)が対応責任を負う
- 発注者の責任がある場合:発注者の責任による場合は、発注者が費用負担・工期延長に応じる
- 契約書に記載すべき事項:第三者への損害対応責任、費用の負担区分、工期変更の可否など
騒音や近隣クレームによる工事停止は、請負契約でよくあるリスクの一つです。あらかじめ契約書で第三者対応の責任範囲や費用負担のルールを明確にしておくと、トラブル発生時の対応がスムーズになり、信頼性の高い工事運営につながります。
建設工事請負契約書の見落としがちなポイントと締結時の注意点
建設工事請負契約書は、契約書類の中でも記載項目が多く、専門的な条文も含まれるため、重要なポイントを見落としたまま締結してしまうリスクがあります。
特に現場代理人の通知、下請け業者の活用、保証内容の明記、不利益な特約条項の存在などは、実務でトラブルに発展しやすい要素です。
本章では、建設工事請負契約書を交わす際に見落としやすい注意点と、それらを事前に防ぐための実務対応ポイントを具体的に解説します。
現場代理人を立てる場合の通知の明記
建設工事では、現場代理人を設置するケースが一般的です。しかし、発注者との間で「誰が代理人なのか」「どこまで権限があるのか」が明確でないと、トラブルの原因になります。
現場代理人の選任にあたっては、建設業法に基づく書面での通知が不可欠です。現場代理人の通知に関する実務ポイントは以下の通りです。
- 通知の必要性:現場代理人を置く場合、請負人は注文者に書面で通知する義務がある(建設業法19条の2第1項)
- 通知すべき内容:1.現場代理人の権限の範囲2.代理人の行為に対する意見申出方法(注文者→請負人)
- 契約書への記載:契約書内で現場代理人の権限や対応フローをまとめておくと実務上も便利
- リスク防止:現場での指示・判断をめぐる責任の所在を明確にし、後の紛争を回避できる
現場代理人は現場における意思決定者となるため、「誰が何を決められるのか」を事前に書面で通知し、契約書にも明記しておくのが重要です。現場での判断ミスや責任の曖昧化を防ぎ、スムーズな工事進行につながります。
下請け業者を活用する際の記載と責任範囲
建設工事では、請負人が下請け業者を活用するのは一般的ですが、一括下請負は原則禁止されています。その際、適切な記載がないと法令違反や責任の所在不明によるトラブルを招く可能性があるためです。
契約書には、下請け活用に関する同意取得や責任範囲の明記が必要です。下請け業者に関する記載事項は、以下の通りです。
- 一括下請負の禁止:現場代理人を置く場合、請負人は注文者に書面で通知する義務がある(建設業法19条の2第1項)
- 例外規定:1.現場代理人の権限の範囲2.代理人の行為に対する意見申出方法(注文者→請負人)
- 契約書の記載ポイント:契約書内で現場代理人の権限や対応フローをまとめておくと実務上も便利
- 責任の明確化:工事全体に対する最終責任は請負人にあり、トラブル時の対応責任も原則として請負人が負う
請負人が下請けを利用する場合でも、最終的な責任は請負人が負うことから、契約書に同意取得や責任分担のルールを記載しておくことが重要です。特に一括下請負の禁止や例外要件は、建設業法違反に直結するため、実務上も見落としのないよう注意しましょう。
保証・アフターサービスについての取り決め
建設工事では、引渡し後に不具合が発覚するケースが少なくありません。そのため、契約段階で保証やアフターサービスに関する取り決めを明記しておくことが重要です。
特に契約不適合責任への対応や、定期点検・補修体制の有無について、事前に確認・合意しておくと、引渡し後のトラブルを未然に防げます。契約書に盛り込むべき主な項目は以下のとおりです。
- 契約不適合責任保証の内容:引渡し後に発覚した瑕疵に対して、請負人が補修・損害賠償・契約解除に応じる責任(民法第562条)
- 保証期間:瑕疵が認められた場合に補修義務が適用される期間(例:住宅は10年保証が一般的)
- アフターサービス:定期点検・メンテナンス体制の有無や頻度、費用負担について記載
- 重要性:発注者の安心感向上、長期的な信頼関係構築につながる
住宅や建物は経年劣化も避けられないため、定期点検・補修・保証の有無と内容は契約時に必ず確認・記載しておくべきです。万が一のトラブル時にも、書面に明記されていれば、スムーズな対応が可能になります。
不利益な特約条項の見落とし防止
建設工事請負契約書では、自社に不利な特約条項が含まれていないかを、契約締結前に必ず確認する必要があります。特約によって、相手側の義務が軽減されたり、自社の義務が重くなったりするケースがあるためです。
これを見落とすと、損害や責任の負担が不公平になるおそれがあります。具体的な確認ポイントは以下のとおりです。
- 区分:義務の軽減
- チェックすべき特約の例:相手側の瑕疵担保責任を限定する条項
- リスク例:不具合発生時の補償を受けられない
- 区分:義務の加重
- チェックすべき特約の例:自社に無制限の遅延損害賠償責任が課される条項
- リスク例:軽微な遅延でも高額な違約金負担が発生
- 区分:標準との相違
- チェックすべき特約の例:建設工事標準請負契約約款と異なる責任分担
- リスク例:契約書全体のバランスが崩れる危険
特約条項は、契約全体のリスクを大きく左右します。契約書を受け取った際には、標準約款と比較しながら、必ずリスク精査を行いましょう。
標準約款(民間建設工事標準請負契約約款)の再確認
建設工事請負契約書では「民間建設工事標準請負契約約款」をそのまま適用するケースが多いですが、すべての契約に完全に適しているとは限りません。
現場ごとの条件や役割分担によっては、標準条項が不利益になる可能性もあります。確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 確認項目:約款の内容が実態と合っているか
- 内容:契約内容・役割・責任分担が現場の実情と一致しているか確認
- リスク例:標準どおりの責任では対応困難な場面でトラブルに発展
- 確認項目:特約との整合性
- 内容:特別条項が約款の条文と矛盾していないか
- リスク例:内容が重複・矛盾し、法的トラブルになる可能性
- 確認項目:リスクの偏りがないか
- 内容:一方の負担や責任が過剰になっていないか
- リスク例:自社に不利な条項を見落とすと損失が生じるおそれ
たとえ標準とされていても、約款は盲信せず、工事内容や契約相手に応じた再確認が不可欠です。必要に応じて修正や補足条項の追加も検討しましょう。
建設工事請負契約書と印紙税・電子契約のルール
建設工事請負契約書を締結する際には、紙で交わすか、電子契約にするかによって、発生する税金や手続きに大きな違いがあります。
本章では、印紙税の課税対象や税額の目安、電子契約に切り替えることで得られるメリットをわかりやすく解説します。
紙で交わす場合は印紙税がかかる
契約書を紙で取り交わす場合、印紙税の負担が発生するため注意が必要です。建設工事請負契約書は、印紙税法で「課税文書(第2号文書)」に該当することから、契約金額に応じた収入印紙の貼付が義務づけられています。
例えば、1,000万円を超える契約では2万円の印紙税が発生します。
また、契約書を2通作成する場合には、各1通ごとに印紙を貼付するのが原則です。
契約金額と印紙税額の対応表
- 1万円未満:非課税
- 1万円以上〜100万円以下:200円
- 100万円超〜200万円以下:400円
- 200万円超〜300万円以下:1,000円
- 300万円超〜500万円以下:2,000円
- 500万円超〜1,000万円以下:10,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下:20,000円
- 5,000万円超〜1億円以下:60,000円
- 1億円超〜5億円以下:100,000円
- 5億円超〜10億円以下:200,000円
- 10億円超〜50億円以下:400,000円
- 50億円超:600,000円
- 金額未記載:200円
契約金額が大きくなるほど印紙税も高額になるため、契約の段階で正しく把握しておくことが重要です。収入印紙の貼付を忘れた場合、税務調査で過怠税の対象となる恐れがあるので、確実に対応しましょう。
電子契約なら印紙税は不要
電子契約を活用すれば、建設工事請負契約書に印紙税を支払う必要はありません。金額が数千万円を超える場合でも、電子契約を使えば印紙代を丸ごと削減できます。印紙税法では課税対象を「文書」に限定しており、PDFなどの電子データは「文書」に該当しないためです。
国税庁でも建設工事請負契約において、注文請書の代わりに、電子署名を付したPDFデータをメールで送信する方式について、「電磁的記録は文書に含まれない」とされており、印紙税の課税対象にはならないと見解を示しています。
電子契約を導入することで、税コストの削減と業務効率化の両立が可能となるため、ペーパーレス化を進めたい企業は、導入を検討する価値が十分にある手段といえるでしょう。
以下の記事では、なぜ電子契約なら印紙税はかからないについて詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>電子契約で収入印紙が不要なのはなぜか?その理由・根拠や注意点を解説
建設工事請負契約書を正しく交わして、工事トラブルを未然に防ごう
建設工事請負契約書は、発注者と受注者の信頼関係を築き、スムーズな工事進行を実現するための「土台」となる重要な書類です。工事内容や工期、支払い条件、不可抗力や違約金などのリスク要素を明文化することで、トラブルを未然に防げます。
また、標準約款や関連法令との整合性を確認し、不利益な特約が含まれていないか慎重にチェックする姿勢も欠かせません。
LegalOnは、AIを活用して契約書の作成、レビュー、締結、管理まで、法務業務全般を効率化するクラウドサービスです。建設工事請負契約書をはじめとした 各種契約書のひな形提供、条項チェック、リスク分析を自動化 することで、業務の 正確性とスピードを飛躍的に向上 させます。
「法務の知識に自信がない」「見落としが心配」という担当者の方も、充実した テンプレートやレビュー機能 により、抜け漏れのない契約書作成が可能です。さらに、必要な機能だけを選んで導入できる柔軟性 があるため、初めてリーガルテックを導入される方にも最適 です。
まずは、以下の体験型無料デモで操作性と利便性をご確認ください。
【新任~若手法務の方へ】そもそも契約とは何か、なぜ契約書を作成するのか、正しく答えられますか?以下の無料資料をダウンロードして、契約の基本を網羅的に理解しましょう。
「建設工事請負契約書」のよくある質問
Q1. 建設工事請負契約書は誰が作成しますか?
A. 法律上は発注者・受注者のどちらが作成しても構いません。実務では、個人発注や小規模工事は受注者(建設会社)が起案、大規模・公的発注は発注者が起案することが多いです。
Q2. 契約書に必ず記載すべき事項は?
A. 工事内容、請負代金、工期、休工日・作業時間、設計変更・中止時の取り決め、不可抗力時の扱い、第三者損害の負担、検査・引渡し、支払条件、契約不適合・保証、違反時の措置、紛争解決などです(本文「記載すべき項目一覧」参照)。
Q3. 標準約款(甲・乙・下請)の使い分けは?
A. 目安として、ビル・店舗等の比較的大規模工事は「甲」、個人住宅等の小規模工事は「乙」、下請工事は「下請約款」を検討します。現場実態に合わせて特約で調整してください。
Q4. 電子契約でも問題ありませんか?印紙税はどうなりますか?
A. 電子契約は有効で、印紙税は不要です。紙で交わす場合は契約金額に応じた印紙税が発生します(本文「印紙税・電子契約」参照)。
Q5. 工事が遅れた場合の違約金はどう決めますか?
A. 「遅延の定義」「計算方法」「免責(不可抗力)」を条項で明確化します。標準約款の考え方を参照しつつ、現場条件に合わせて率や上限を設定してください。
Q6. 不可抗力(天災等)が起きたら誰が負担しますか?
A. 善管注意義務を前提に、発注者負担/協議で按分/受注者負担などの方式から、当事者で合意した案を条項化します(本文「不可抗力」参照)。
Q7. 引渡しの基準は?
A. 完成検査に合格し、契約で定めた条件(例:残代金支払)を満たした時点を引渡しとします。鍵の受け渡し方法・書面確認も明記すると安心です。
Q8. 現場代理人はどのように扱いますか?
A. 権限範囲と通知方法を契約・書面で明確化します。現場判断の権限と責任を曖昧にしないことが紛争防止に有効です。



.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)