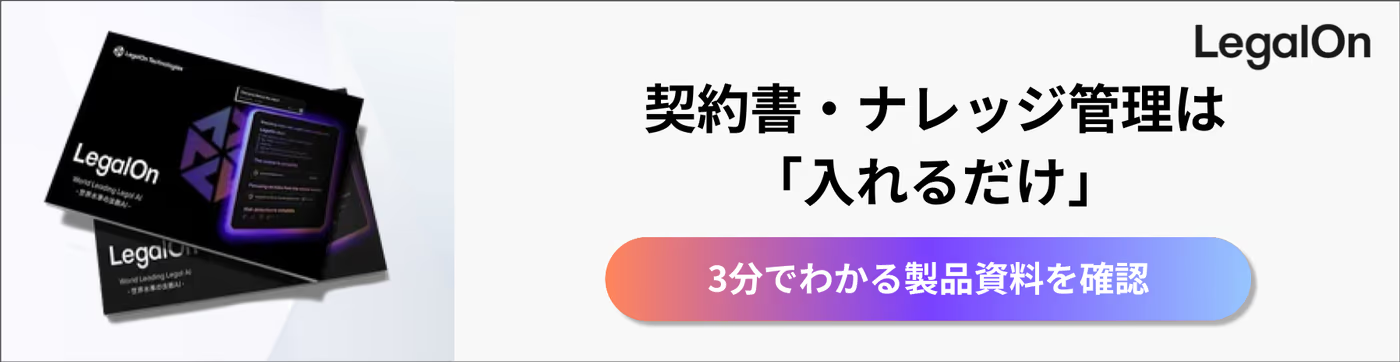契約書を効率的にファイリングして保管する方法4選
契約書は、あとで確認しやすくするよう整理してからファイリングして保管することが適切ですが、保管の前に手間がかかりすぎるのも好ましくありません。
会社の業態にあわせていくつかの方法を組み合わせて整理をし、ファイリングしてみましょう。
- 企業名やサービス名ごとに五十音順でファイリングする
- 業務内容ごとにファイリングする
- 案件ごとにファイリングする
- 日付や契約番号など数字ごとにファイリングする
それぞれ詳しく解説します。
方法①企業名やサービス名ごとに五十音順でファイリングする
まず紹介するのは、企業名やサービス名ごとに五十音順でファイリングする方法です。
とくにベンダー契約では、「文書保管サービス」「給湯機メンテナンスサービス」など各サービスの名称で整理すると特にわかりやすくておすすめです。
五十音順に並べることで契約書を探しやすくなる一方、社名の呼び方や英字・カタカナ・ひらがななど、人によってブレがあると探しづらくなる点には注意しましょう。
ファイル名一覧をいつでも手元で参照できるようにする、別名を併記しておくなどの工夫が必要です。
方法②業務内容ごとにファイリングする
業務内容ごとにファイリングする方法もあります。
たとえば、下記のようにファイルを分け、業務内容ごとにあとから確認できるようにしておく方法です。
- 通信関連
- 設備関連
- システム関連
ただし、業務の細かい内容によって契約書が分けられる場合は、ピンポイントで見たい契約書を探しづらいというデメリットがあります。
大分類である業務内容の下位に中分類や小分類を作成し、少なくとも2階層にして保管する工夫が必要です。
たとえば、大きなファイルは業務の大分類として作成し、ファイルポケットに業務の詳細な中分類を記したインデックスをつけてファイリングする方法が考えられます。
階層ごとに分類の一覧表をいつでも参照できるようにすると、あとから契約書がより探しやすくなるでしょう。
方法③案件ごとにファイリングする
コンサルティング業務を提供している会社やIT系の開発プロジェクトなど多くの案件を抱えている会社での契約書保管は、案件ごとにファイリングするとあとから確認するのに便利です。
1つの案件に複数種類の契約書がある場合は、案件で大分類を作成し、種類ごとに中分類や小分類を作成することにより、確認が容易になります。
ただし、同じ会社の契約書をすべて取り出す場合は、ファイルを横断的に確認しなければいけないため非効率です。
なるべく手間がかからないようにするために、エクセルファイルや契約管理システムで、どのファイルにどの会社の契約書が入っているのかを整理しておくことをおすすめします。
ファイルを取り出す手間は変わらないものの、どのファイルから取り出せばよいのかが確認しやすくなり、ファイルを探す時間が削減できます。
方法④日付や契約番号など数字ごとにファイリングする
数字でわけて契約書をファイリングする方法もよく取り入れられています。
- 契約した日付
- 契約書に振り分けた個々の契約番号
- 年度ごと
法務部内での契約書整理に使われることも多い方法です。
契約した日付や契約書番号の採番方式をよく理解している人なら探しやすい方法ですが、日付や番号などの数字が明確でない人がいる場合は、探しにくくなります。
日付や契約番号などの数字は法務部内での整理用に利用する、数字は主に契約書が同じか違うのか識別用にのみ使うなどとして、他よりわかりやすい方式を併用することが多いようです。
契約書をファイリングで保管する際の注意点やポイント
以下では、紙の契約書をファイリングして保管するうえでの注意点やコツについて解説します。
- ボックスファイルとインデックス付きクリアファイルを活用する
- 原本を廃棄したりパンチで穴あけしたりしない
- 施錠可能で安全な場所に保管する
- 保管場所などのルールを定めておく
それぞれ詳しく解説します。
注意点①ボックスファイルとインデックス付きクリアファイルを活用する
契約書保管におすすめなのが、ボックスファイルとインデックス付きクリアファイルの活用です。
いずれも背面やインデックス部分に分類を記載することができ、わかりやすく保管できます。
例えば、ボックスファイルに大分類を記入し、クリアファイルのインデックスに中分類を記載すると、中身の詳細を見なくても探したい契約書がだいたい絞られます。
大分類・中分類・小分類に加えて、番号でも見たい契約書を特定できるようにすると、過去の契約書はほぼ間違いなく探せるようになるはずです。
注意点②原本を廃棄したりパンチで穴あけしたりしない
契約書の原本は、できるだけそのままの状態で保管し、パンチで穴をあけてファイリングといったキズをつける行為は控えましょう。
契約書の製本や押印は、改ざんを防止する意味を持っています。パンチ式のファイルで保管するために穴を開けると、必要な文字や押印個所が欠落して読めなくなる可能性があり、万が一のときに改ざんしたと疑われかねません。
また、原本がないと裁判等で不利になってしまう可能性があるため、スキャンコピーがあっても原本は保管しておくことをおすすめします。
また、鮮明にスキャンできていなかった場合、原本があるとやり直しができますが、保管していないとやり直しができなくなるというデメリットもあります。
注意点③施錠可能で安全な場所に保管する
契約書は、会社の権利や取引相手方の義務、あるいは請求権を主張するために必要であり、裁判でも証拠として使われる非常に重要な書類です。
悪意のある人に持ち出されたり改ざんされたりしないよう、施錠できて安全な場所に保管しておきましょう。
防火金庫・鍵付きキャビネット・施錠可能な文書保管庫などでの保管が一般的かつ適切です。
契約書の原本が災害で喪失するリスクがあるため、防火体制が十分な場所や、水没しない場所に保管する工夫もしておきましょう。
注意点④保管場所などのルールを定めておく
契約書は誰が責任を持って保管場所に保管するのか、どのタイミングで保管場所へ持っていくのかなどルールを定めておきましょう。
また、保管に際してのマニュアルや手順書を準備し、誰もが必要に応じてスムーズに保管担当者に渡して預けたり、保管業務を行ったりできるようにしておくことが重要です。
ルールが定められていないと、勝手に個人のデスクに入れっぱなしにしたり、いつ誰がどこに保管したかわからなくなったりするため、全社で一元的な契約書管理ができなくなります。
契約書の紛失や改ざんなどのリスクが生じ、会社の所有権を主張することや取引相手方の義務の履行を請求することなど、会社の権利の主張が困難になることがあるため注意が必要です。
<関連記事>契約管理で発生しやすい課題は?解決方法とともに徹底解説
契約書の保管についてさらに詳しく知りたい方は、下記の無料ダウンロード資料もご利用ください。
契約書をファイリングで保存することによる問題点
紙の契約書をファイリングで保存することには、あらゆるコストや危険が生じます。以下で一例を紹介するので、チェックしてみてください。
- そもそもファイリングが手間
- 保管場所が必要になる
- 紛失や改ざんのリスクがある
- 必要なときに必要なものを探し出すのに時間がかかる
それぞれ詳しく解説します。
問題点①そもそもファイリングが手間になる
ファイリングは、必要なファイルを整理する、保管場所にもっていくなどそもそも手間なことであり、時間がかかるものです。
また、その分の人件費もかかります。会社内での役割分担を行うことで人件費を抑える工夫はできますが、限度があるうえ自動化することも難しいのが難点です。
問題点②保管場所が必要になる
紙の契約書は、もちろん保管場所が必要です。場合によってはかなりのスペースが必要になるため、会社の中にスペースを設けてその分の賃料を支払ったり、外部倉庫と契約して保管料を支払ったりするなどのコストがかかります。
問題点③紛失や改ざんのリスクがある
紙の契約書は簡単に持ち出しができてしまうため、改ざんされるリスクがあります。また、大量の紙を管理するうえでは、意図せずとも紛失してしまうリスクが避けられません。
紛失・改ざんされたことで商品やサービスの代金回収が困難になったり、契約書情報の漏えいを引き起こして取引先との守秘義務を違反してしまったりすることにもつながります。
保管する紙の契約書が多くなればなるほど、これらのリスクが会社にとって大きいものとなるのがデメリットです。
問題点④必要なときに必要なものを探し出すのに時間がかかる
どれだけきれいにファイリングして保管していても、必要な契約書をピンポイントで見つけ出すまでには一定の時間がかかります。
紙の契約書の量が多いと、細かい内容まで確認して特定のものを見つけ出さなければならないため、場合によっては多大な時間がかかってしまうのが特徴です。
電子契約書なら効率的で安全な保管が可能になる
電子契約はそれ自体有効な契約書として扱われ、紙の契約書を作成する必要がないのでファイリングは必要がありません。
電子契約書とは電子文書に電子署名することで締結する契約です。電子署名法第3条には次の通り定められています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
上記のことから、電子データで契約書情報を表すために作成された契約書は、本人により電子署名が行われていれば、紙の契約書同様に有効な契約書として通用すると考えられるのです。
電子契約では保管のスペースがいらなくなる上に、印紙税も必要がなくなり、コストカットの効果が高いと考えられます。
また、ファイルフォルダ内やシステム上での検索が簡単にできるようになるので、取り出す時間もかかりません。
電子契約を利用すれば、紙の契約書のファイリングに関するあらゆる問題点が解決できます。
<関連記事>契約書を電子化するメリットとは?電子契約の導入方法や注意点を解説
契約書管理の効率化には「LegalOn Cloud コントラクトマネジメント」がおすすめ
契約書のファインリグは、下記のような注意点がいくつかあります。
- 安全に保管する
- あとから見返しやすく保管する
- 廃棄したりパンチで穴あけしたりしない
また、紙の契約書である限り探しやすさを追求することには限界があるうえ、保管にコストがかかることや、改ざん・紛失のリスクも避けては通れません。
紙の契約から電子契約に切り替えると、保管場所などあらゆるコストやリスクがなくなり、契約書保管の課題を解決できます。
とくに電子契約で締結した契約書の管理に「LegalOn Cloud コントラクトマネジメント」を使うと、契約データのアップロードを行うことで管理台帳に⾃動で情報を登録してくれるため、エクセルで契約データを整理する手間もかかりません。
「LegalOn Cloud コントラクトマネジメント」なら契約書内容の検索もでき、契約書内の単語を検索し横断的に確認したい契約書を絞り込めるため、契約書を探す時間が省けます。
また、電子署名と連携し、システム上で契約締結を完了したあと、セキュアにデータを保管・管理できます。このように契約書作成から、管理・データ保管まで、システム上で効率的なリスク管理ができます。
- 管理台帳に⾃動で情報を登録してくれるため、データを整理する時間がなくなる
- 契約書内容の検索ができるため、探す時間が削減される
- 電子署名と連携しているため、自動でデータを保管・管理される
「LegalOn Cloud コントラクトマネジメント」の特徴や機能をまとめた無料の製品資料を以下のリンク先で配布しているので、ぜひダウンロードしてみてください。
【法務担当の方へ】
法律上契約書は何年保管すればいいのか、知っていますか?
以下の無料資料をダウンロードして、契約書の保管期間と保管方法を網羅的に理解しましょう。