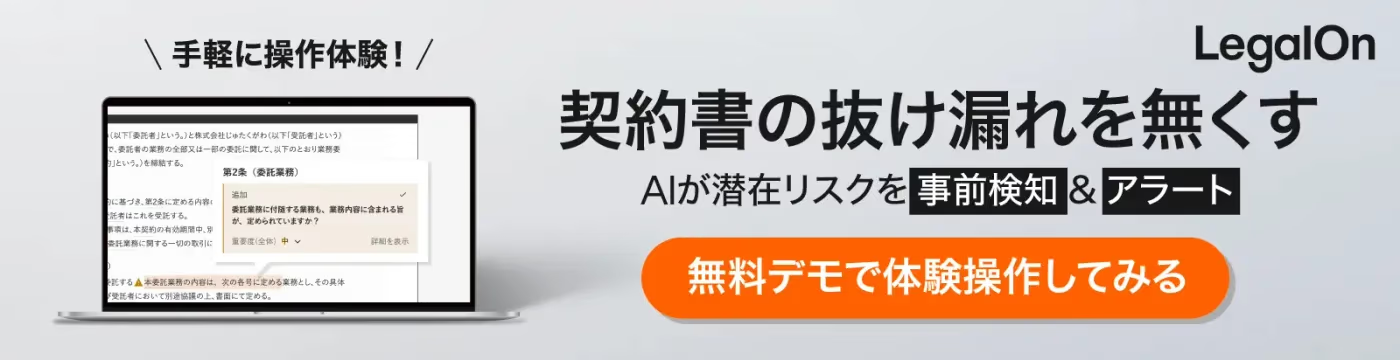リーガルテックとは「法律と技術を組み合わせた言葉」
リーガルテックとは、「法律(Legal)」と「技術(Technology)」を組み合わせた言葉です。法律業務や手続きにIT技術を活用し、新たな価値や仕組みを提供する言葉です。リーガルテックは元々米国で生まれたもので、電子署名サービス・特許情報サービス・法廷での証拠開示手続きを支援する「eDiscovery」サービスなどが開発され、2000年代初頭のインターネットの大幅な普及とともに広がりました。
近年、日本でもリーガルテックへの関心が高まっています。少子高齢化による人材不足や、コロナ禍による働き方の変化を背景に、電子契約やAI契約レビュー、契約書管理の自動化などのリーガルテックが広く導入され始めています。
リーガルテックは現在法律業務の幅広い分野で普及しており、例として以下の領域に活用されています。
- 契約作成・締結・管理
- 登記・登録
- 法律相談
- 知的財産
- 証拠・不正調査
- 集団訴訟
- 法令・判例検索
リーガルテックサービス一覧
日本国内において、リーガルテックにはどんなサービスがあるのか、まずはサービス一覧から全体像を把握しておきましょう。
電子契約
- クラウドサイン
- Docusign
- 電子印鑑GMOサイン
- LegalOn Cloud
- freeeサイン
- WAN-Sign
- ベクターサイン
- 契約大臣
- マネーフォワード クラウド契約
- Adobe Acrobat Sign
契約書レビュー支援
- LegalOn Cloud(LegalForceの進化版)
- LAWGUE
- OLGA
- MNTSQ
- LeCHECK
- LawFlow
契約書管理
- LegalOn Cloud (LegalForceキャビネの進化版)
- Docusign CLM
- ContractS CLM
- 楽々Document Plus
- OPTiM Contract
- Hubble
案件管理
- LegalOn Cloud
- OLGA
- Hubble
- HighQ
- ContractS CLM
リーガルリサーチサービス
- Legalscape
- LEGAL LIBRARY
- Westlaw Japan
知財業務支援サービス
- AI Samurai
- AQX 知財総合管理ソリューション
- DIAMS iQ
- IPfolio
- 知財管理システムAktes
リーガルテックの市場規模(2025年最新レポート)
これまでのリーガルテック市場
2016年以降日本で市場規模が成長しているリーガルテック。
矢野経済研究所の調べでは、2016年には184億円であったリーガルテック市場は、2023年には350億円にものぼると予測されています。
矢野経済研究所「リーガルテック市場に関する調査を実施(2019年)」2019年08月27日発刊
日本国内でリーガルテックが注目される背景には、社会構造や経済環境の変化、そして新型コロナウイルスの影響が大きく関係しています。
新型コロナウイルスの影響やそれに伴う法改正や規制の見直しにより、リモートワークや業務のデジタル化が急速に進みました。その結果、法務業務にもオンラインで契約を締結する電子契約サービスや、AIを活用した契約書レビューといった技術が積極的に導入されるようになりました。
さらに日本では少子高齢化による労働人口の減少が深刻化しており、限られた人材で高い生産性を確保することが求められています。特に法律業務は、契約書の作成やレビュー、法令リサーチなど工数と専門性を要する非効率な作業が多く、時間やコストの負担が大きい分野です。企業にとって、こうした業務を効率化し、コストを削減しながら迅速で的確な法的対応を実現することは競争力の強化につながります。
リーガルテックは、これらの課題に対する解決策として、ITやAIを活用して法務業務の自動化や効率化を実現します。これにより、企業は契約書の締結や管理のプロセスをデジタル化するだけでなく、リモートワークの導入を促進し、グローバル競争の中でも迅速に対応できる体制を構築することが可能になります。
時代の変化とともに、法務の現場ではリーガルテックが欠かせない存在となりつつあり、その市場は今後も拡大し続けると予想されています。
リーガルテックサービスの導入率
現在、さまざまな企業がリーガルテックテックサービスを提供しています。日本経済新聞の調査によると、最も多く導入されているリーガルテックは「電子契約」で約8割が導入しており、すでに多くの企業にリーガルテックサービスが普及していることがうかがえます。
参考:日本経済新聞|リーガルテック、コロナ下で加速 電子契約導入8割に
2025年~2035年:リーガルテック市場規模の展望
イギリスの調査会社Future Market Insightsが2025年3月に発表したレポートによると、世界のリーガルテック市場は2025年に約354億米ドルに達し、2035年には725億米ドルにまで拡大する見通しです。これは、年平均成長率(CAGR)7.6%という安定した成長を示しており、法務業界のデジタル化がますます進むことを裏付けています。
引用:LegalTech Market Trends & Growth | Key Insights 2035
日本のリーガルテック市場は、今後10年間で着実な成長が見込まれており、2025年から2035年にかけての年平均成長率(CAGR)はドイツ(7.8%)やその他の先進国を上回る水準である8.6%と予測されています。リーガル分野のデジタル化において日本が積極的な動きを見せていることを示しています。
特に契約書レビュー、法務ドキュメントの検索・管理(ナレッジマネジメント)、コンプライアンス対応などの業務において、AIや自然言語処理技術を活用したリーガルテックソリューションの導入が進んでいます。今後は、単なる業務効率化だけでなく、法務部門が経営戦略に寄与する「攻めの法務」へと進化する中で、リーガルテックの役割はますます重要になると見込まれます。
リーガルテックサービスの種類
リーガルテックと呼ばれるサービスにはさまざまなものがあります。以下でいくつか例を紹介するので、参考にしてみてください。
- 電子契約サービス
- 文書管理サービス
- 契約書レビューサービス
- 申請出願サービス
- 紛争・訴訟サービス
- 検索サービス
- 法律事務所向けサービス
それぞれ詳しく解説します。
電子契約サービス:契約がクラウド上で行える
電子契約サービスは、クラウド上で契約を完結できるサービスです。
紙の契約書を作成する負担がなくなり、契約書の作成・電子署名・送付まですべてサービス上で完結できるので、リモートワーク下でも問題なく契約事務を進められます。
電子契約サービスに契約書保管用のサーバを組み合わせた主流のサービスでは、電子契約の作成から保管管理までをシームレスに進められます。さらに、契約書の整理ができるほか、分類をAIで自動で行えること、本文の検索機能やレビュー機能など、サービス・機能ともに豊富に展開されています。
電子署名と保管のみといったシンプルなものから最新鋭の多機能のものまで、業態・契約書の数、管理の方法にあわせたサービスを選べます。日本語・英語双方の契約書に対応できるサービスもあるうえ自動化も進んでいるため、契約管理事務の手間が大きく軽減できます。
電子契約の導入を検討する際には、契約業務全体との整合性や連携のしやすさが重要な評価基準となります。LegalOn Cloud サインなら、電子契約の締結はもちろん、契約書レビューや、 締結済み契約書管理、法務相談案件管理まで、企業法務のすべてのプロセスを他のツールを介さずに一元的に完結できます。
以下の記事では、電子契約サービスの基礎知識から、関連する法律への対応、導入のメリットや注意点、選定のコツについて詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>電子契約とは?導入メリットや関連した法律などについて徹底解説
文書管理サービス:書類をデータ化してサーバーで管理する
契約書をはじめ、業務上使用する書類をサーバ上で管理するサービスです。スキャンした書類をデジタルデータ化し、サーバ上で管理します。
文書の整理や分類、本文検索など、電子契約サービスの保管機能と同様に多機能で、他のシステムやサービスとの連携もよく見られます。中でもOCR-AIと連携できるサービスでは、過去の紙文書のスキャンデータ作成から、文書のデジタルデータ化まで自動で進められるのが特徴です。
また2022年4月に施行された改正電子帳簿保存法の保存要件を満たすサービスを提供するものもあり、改正法に対応できます。
LegalOn Cloudは、最新の電子帳簿保存法に対応し、最先端のAI技術を活用して書類管理を効率化するクラウドサービスです。書類をアップロードするだけで、自動で分類・項目抽出を行い、管理台帳を自動作成します。また、電帳法対応に必要な保存要件をAIが自動でチェックでき、不足している要件がある場合はアラートを出し、確実な法令対応をサポートします。電子帳簿や契約書など、面倒な書類管理が手間をかけることなく、適切に管理することができます。
まずは以下の体験型無料デモから、契約書管理がどれほどラクになるのか、実際の操作を通じてぜひお確かめください。
さらに、契約締結前の作成段階から締結後の更新や期限管理まで、契約のライフサイクル全体を一元的にサポートするサービス「契約ライフサイクルマネジメントサービス(CLM:Contract Lifecycle Management)」にも注目が集まっています。
以下の記事では、契約ライフサイクルマネジメントサービス(CLM)について詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>CLM(契約ライフサイクルマネジメント)とは?意味や解決できる課題を解説
契約書レビューサービス:作成した契約書の内容をチェックする
リーガルテックによる契約書レビューサービスとは、専門的な法律知識に基づいて契約書の内容をチェックし、法的リスクや不利な条項の有無、修正提案などを行うサービスです。さらに、ひな形との違いや過去に締結した契約書文言との差分比較など、従来は手間のかかった作業を効率的に行うことが可能です。高度なAI技術を活用することで、多くの契約書を短時間かつ高精度でレビューでき、契約業務の標準化と大幅な効率化を実現します。
<関連記事>契約書チェックをAIで効率化する方法を解説!
代表的なサービスの一つに、LegalForceから進化した新サービス「LegalOn Cloud」があります。
非定型的なカスタムメイドの契約書や、特に難易度が高い契約書などの場合、弁護士・法務部員によるチェックや対案の提示などが必要になることもあります。LegalOn Cloudなら、有名弁護士事務所が過去の契約書を元にシステムを監修しているため、プロの目線を取り入れた実務的かつ信頼性の高いチェックが実現でき、安心してご利用いただけます。
まずは以下の体験型無料デモから、契約書のリーガルチェックがどれほどラクになるのか、実際の操作を通じてぜひお確かめください。
申請出願サービス:登記や商標の申請を支援する
申請出願サービスは、登記・商標・特許などの申請や出願を支援するサービスです。
申請や出願は、定型的な手順と文書によって行う業務であるほか、電子上で行うことが可能であるため、定型化・標準化・効率化になじみやすい業務です。定型的な申請・出願手順に沿った書面作成や、出願データの送信支援をPC上で提供してくれるため、ユーザーはサービス画面に沿って簡単に作業を進められます。
手入力は定型化・簡素化されるので、入力ミスも最小限にとどめられます。過去の申請書類の内容を正確に引用したり、編集によりカスタマイズしたりできるので、業務の効率化や質の向上などが期待できます。
代表的なサービスは、「Toreru 商標登録」、「Cotobox」、「すまるか」などがあります。
紛争・訴訟サービス:訴訟への対処や解決支援を行う
紛争・訴訟サービスは、訴訟への対処や解決支援を行うサービスです。証拠の収集や保全、書面の作成サービスを主に提供しています。
弁護士や企業などの事業者向けのものと個人向けのものがあり、提供しているサービス内容は以下の通りです。
- 不正検出・検知サービス:デジタルフォレンジックサービスとも呼ばれ、企業が主に内部での不正の検出・証拠収集・紛争予防または解決のために利用します。
- 証拠収集・保全支援サービス:米国でのDiscovery(証拠開示)へ備えるためのものや、弁護士事務所が訴訟提出書面や業務記録の作成・管理に使うものなどがあります。
- 法廷等への提出書面の作成支援:訴訟での準備書面、会社更生や破産など倒産手続きのための書面作成支援サービスです。
- 本人訴訟支援サービス:法律資格のない個人でも、本人だけで訴訟を起こす場合に特化した書面作成等を支援するサービスです。
多くの書面が必要となる、訴訟に特化した文書の作成・保管・管理をサービス上で行うことで手作業を減らせます。これにより、訴訟準備にかかる時間の短縮や、訴訟自体の手間を減らすことが期待できるでしょう。
検索サービス:法律に関する資料の閲覧を可能にする
検索サービスとは、法令、判例、契約書、特許、商標、登記情報など、法律実務に関わる多様な法情報を、キーワード検索や構造化されたフィルターを通じて迅速かつ効率的に調べることができるサービスです。
業者が提供する有料サービスだけでなく、官公庁や海外の大学が提供する無料のサービスもあるのが特徴です。よく企業で使われる検索サービスには、次のようなものがあります。
- 法令検索サービス
- 知財検索サービス(日本での特許電子図書館・海外の官公庁提供特許情報検索システム・民間業者の検索サービスなど)
- 判例検索サービス
- 登記情報・会社情報提供サービス(民事法務協会の登記情報提供サービス、会社情報検索サービス、信用情報・制裁情報提供サービスなど)
AI法務プラットフォーム:法務業務全体をサポート
法務業務すべてをサポートするAI法務プラットフォームも登場しています。法務案件管理から、契約書の作成・審査、電子契約の締結、契約書管理など、多岐にわたるリーガルテックサービスが業務ごとに分断されているという課題を解消するために、法務担当者が担うさまざまな業務に対応するサービスを一つのプロダクトに搭載します。
AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」の資料より
対応する領域は、契約のマネジメント(CLM)にとどまらず、法務業務領域全体に拡大する予定です。これにより、法務担当者は一つのプロダクトで業務をすべて完了できるようになります。
法律事務所向けサービス:法律事務所の業務をサポートする
法律事務所向けのサービスとは、大量の書類の取り扱いや、案件・進捗・業務の管理といった、法律事務所特有の業務手順や慣行を支援するためのサービスです。
サービスを通じて、情報の一元管理・経費管理・人員のアサイン管理・記録管理などをできるほか、他の文書管理や押印などの電子契約サービスなどと連携した利用もできます。
ダッシュボード機能により視覚的にも全体の案件進捗情報が見やすいことや、提出書類のチェックリストがすぐ見られることなど、情報の集約にも優れたサービスが登場しています。
リーガルテックを導入するメリット
リーガルテックを導入するメリットは、次の通りです。
- あらゆる手間が省けて作業が効率化できる
- 担当者による業務品質のバラつきが防げる
- 書類が安全かつ効率的に管理できる
- 膨大な情報や細かい情報がすぐに収集できる
それぞれ詳しく解説します。
メリット①あらゆる手間が省けて作業が効率化できる
自動で書面を整理・デジタルデータ化すること、AIによるチェックや修正案の提示をすることなどにより手作業が省け、作業が大幅に効率化できます。電子契約であれば契約書を送る手間や持っていく手間なども省けて、時間の短縮効果は絶大です。
その結果、法務担当者はより重要な判断業務に集中でき、残業時間の短縮にも繋がります。
手間や時間などの人件費だけでなく、事務用品・保管場所・プリンタ・印紙代などのコストも削減できます。
メリット②担当者による業務品質のバラつきが防げる
AIによって自動で書面をチェックしたり入力できたりすると、人為的なミスが削減できるほか、担当者による業務品質のばらつきが防げます。
クセや性格、熟練度によって差が出てしまうような業務でも、AIが行えば一定の基準からぶれることはないため、業務品質の向上や標準化を狙うことができます。
メリット③書類が安全かつ効率的に管理できる
リーガルテックのターゲットとなる業務は、書類を管理・保管することを伴う業務がほとんどです。リーガルテックを利用し書類をクラウドサーバで保管できれば、最新のセキュリティ体制のもと書類は安全に保管され、効率的に管理できます。
電子データ化されサーバに保管された書類は検索性にも優れているので、必要な書類がすぐに探し出せるのも魅力です。保管場所も取らず、管理コストもかかりません。
メリット④膨大な情報や細かい情報がすぐに収集できる
何らかの手続きが必要になったとき、知識や情報を紙で逐一探すことには膨大な時間がかかります。
リーガルテックがあれば、ほしい「あの時」の「あの書類」が高度な検索機能のもとですぐに見つけられます。締結済み契約書情報・契約書ひな形・判例・書面による証拠となる情報・統計による数字のデータなど、情報を一元化して共有することもまた簡単に行えます。
リーガルテックを導入するデメリット
リーガルテックを導入することで得られるメリットは多いですが、デメリットもあります。なかでも、企業で電子契約の導入を行う場合には、以下のデメリットに注意することが必要です。
- 電子契約等が認められない契約書もある
- 取引先に理解してもらう必要がある
- トラブル時の対策を練っておく必要がある
リーガルテック導入時のデメリットについて詳しく解説します。
デメリット①電子契約等が認められないこともある
電子契約は、効率化とコストダウンが期待できるものですが、電子契約やその他の交付書面には法令上紙での作成が必要なものがあります。以下のような書面に関しては、電子契約ではなく、紙を用いて締結・交付することが必要です。
- 定期借地・定期建物賃貸借契約(借地借家法第22条、第38条第1項)
- 宅地建物売買等媒介契約(宅地建物取引業法第34条の2)
- 不動産売買における重要事項説明書(宅地建物取引業法第35条)
- 投資信託契約の約款(投資信託及び投資法人に関する法律第5条)
- 訪問販売等特定商取引における交付書面(特定商取引法第4条)
紙での作成書面が多い業種や業態では、電子契約を中心とするリーガルテックの導入をしても、かえって管理が煩雑で所期の効果が得られないこともあります。
上記のような書類を多く取り扱う場合は、電子契約が認められるようになってから導入するのもひとつの手です。また、電子契約と紙の契約の割合を考え、試験的に一部の契約書だけに導入して混乱が起きないようにするなどの対応も検討してみてください。
また、2022年5月から一部重要事項説明書も電子交付が可能になるなど、状況が変化することにも注意しておきましょう。
<関連記事>【弁護士監修】電子帳簿保存法の対象書類や改正点とその保管期間を解説! 保存時の注意点とスムーズな導入方法も
デメリット②取引先に理解してもらう必要がある
電子契約の場合、取引先によってはIT技術に苦手意識を持っていたり、会社として導入が認められなかったりすることがあります。取引先の多くが電子契約を拒否した場合は、せっかくサービスを導入してもあまり役に立ちません。
むしろ、電子契約と紙の契約が取引先によって入り乱れてしまうと、かえって業務負担が増えることにもつながります。
JIPDEC・ITRによりリリースされた「IT-REPORT 2021 Spring」によると、電子契約の普及率は67.2%と高い割合であり、今後さらにこの割合が高くなることも考えられますが、まだまだ電子契約に対応していない企業が多くあるのも事実です。
自社の取引先がどのくらい電子契約に前向きになってくれるかを把握したうえで、メリットとデメリットを比較してから導入の可否を検討してみてください。
参照|JIPDEC「IT-REPORT|JIPDEC」2021年5月発刊
デメリット③トラブル時の対策を練っておく必要がある
リーガルテックを利用すれば、人為的なミスを減らすことができます。しかし、AIならまったく間違いが発生しないとは言い切れません。設定ミスなどが起こることもあるほか、クラウドサービスであればサービスそのものがダウンすることもあります。
トラブルが生じた場合の責任の所在をケースごとに明確にしておくこと、サービスがダウンした場合のバックアップについてプランを持っておくことなど、トラブルの対策を十分に練ることが必要です。
リーガルテックを導入する際のポイント
以下では、リーガルテックサービスを導入するうえでのコツやポイントについて解説します。
- リーガルテックを導入する目的を明確化する
- 導入前にトライアルを活用する
- 業務や部門の範囲を決めて段階的に導入する
- 他社の事例を参考にする
それぞれ詳しく解説します。
ポイント①リーガルテックを導入する目的を明確化する
リーガルテックを導入する際には、まず目的を明確化しておくことが重要です。自社の課題を見つけたうえで、リーガルテックにどういう課題を解決してほしいのかを具体的に考えておきましょう。目的が曖昧だと、せっかく導入しても費用に見合った効果が得られません。
導入することでどのくらいの時間を短縮できるのかや、どのくらいコストカットができるのかなど、具体的な試算をしてから導入の可否や導入サービスの種類を決めることが重要です。
ポイント②導入前にトライアルを活用する
リーガルテックのサービスを導入する際には、無計画に導入するべきではありません。まず、目的を明確にした後、自社の目的に合致しているかを確認する必要があります。そのためにも、リーガルテック導入の前にトライアルを活用してみましょう。
導入時には、運用コストや導入コストを気にしてしまいがちです。しかし、使いやすさや、本当に自社の課題が解決できそうかなどを確認するには、サービス画面に触れてみるのが確実。ほとんどのサービスでトライアルやセミナーでのサービス体験が提供されているので、ぜひ活用してみてください。
ポイント③業務や部門の範囲を決めて段階的に導入する
いきなり大規模な範囲でリーガルテックを導入するのは、あまりおすすめできません。実際にツールを使用してこそわかる課題があるため、一部の部署で試験運用するなど、スモールスタートでの導入をおすすめします。
運用上の問題点などを特定の業務範囲から洗い出し、本格的に利用するかどうかを決めた方が無駄がありません。問題点が見つかることで、より自社に合ったサービスを見つけることにもつながります。
LegalOn Cloud であれば、必要な機能やアカウント数だけを最初に導入し、業務に合わせて後から柔軟に拡張することができます。そのため初期導入のハードルが低く、段階的に運用範囲を広げていくことが可能です。
こうした柔軟性は、法務業務の変化に対応しながら、無駄なくテクノロジーを活用する上で大きなメリットとなります。
ポイント④他社の事例を参考にする
リーガルテックを導入することにより、自社の業務にどのような変化が起きるのかを想像しづらいという方も多いでしょう。
そのような場合には、業務内容や企業の規模が近い他社の導入事例を探すことがおすすめです。リーガルテックを提供しているサービスのホームページなどを見てみると、導入実績として事例が記載されている場合も多いです。
事例を確認することで、実際にリーガルテックを導入し、活用した際のビジョンをイメージできるようになるでしょう。
リーガルテックを導入しても業務が効率化しない理由
さまざまなリーガルテックを紹介してきましたが、個々の業務を支援するリーガルテック選びには注意点があります。
上記で述べたように、現状でさまざまな企業がリーガルテックテックサービスを提供しています。しかしサービスを導入していても、課題は依然として残っている、というケースも存在しています。業務の効率化ができていない、人手不足が解消できていない、業務の属人化が解消できていない、という課題が解決できていないという法務組織もあります。
では、なぜ法務が抱える課題は残っているのでしょうか。考えられる原因は三つです。
- 法務組織が対応する業務領域の広さ
- ナレッジが分散していること
- 知っていることしか気づけないこと
それぞれ解説します。
法務組織が対応する業務領域の広さ
法務担当者は、契約書レビューや、契約の締結、契約管理といった契約書のマネジメント業務だけでなく、コンプライアンスや法務相談、コーポレートガバナンス、これらに付随したリサーチなど、さまざまな業務を担当しています。そしてどの業務も難易度がとても高く、対応するには時間、知識、経験が必要です。
これら法務担当者が抱える業務のそれぞれに、各社がサービスを提供しています。
しかし、サービスは提供者が別々なので業務ごとに分断されています。担当者は、複数のサービスを契約してその間を行き来し、手作業で情報をサービス間で連携する必要があります。せっかくサービスを契約しているのに、根本的な業務効率は上がりません。
ナレッジが分散
また、法務業務に関わるナレッジが分散していることも課題です。ナレッジを活用するためには、単に締結した契約書を保管しているだけでは意味がありません。
関係部署や法務組織内のやりとり、顧問弁護士とのやりとりや修正履歴、参考にした過去の契約書やリサーチしたさまざまな資料、これらすべての関連情報は、紐づけて管理する必要があります。
しかし、例えばメールはメールサーバー、契約書のドラフトはファイルのサーバー、締結済みの契約書は場合によっては紙の状態で書棚にある、など複数の場所に保存してあるケースがほとんど。仮にこれらが一つの場所に集約されていても、物理的に一か所にあるだけで関連情報がうまく紐づいていない場合がほとんどです。
そのため、情報は断片化してナレッジ化できておらず、必要だと思ったときにかんたんに探し出せません。「どこだろう」と探すのに多くの時間を費やしたり、そもそも活用できる情報があること自体に気付けないという事態になってしまいます。
知っていることにしか気づけない
3つ目として、法務担当者が案件の論点を洗い出すためには、各所への確認や調査をしないといけませんが、その前提として案件についての周辺知識を持っていることが必要です。つまり、「調べるためにも知識が必要だ」ということです。
先ほど述べたように、法務担当者の業務は多岐にわたっていますが、いままでの経験で分かっている範囲内でしか、確認・調査をすることができません。
検索技術の発展、大規模言語モデル(LLM)の登場によって、必要な情報を探しやすくなりました。しかし適切な回答を得るためには、質問の意図を正確に伝えたり、回答に必要な情報を与えたり、といった「聞く力」が求められます。このため、必要な情報を調べようとしても、すべて収集するということは困難です。
「LegalOn」でリーガルテック導入のお悩みを解決
LegalOnは、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲かつ総合的に支援する次世代のリーガルテックプラットフォームです。あらゆる法務業務をAIがカバーできるほか、機能モジュールを選んでスモールスタートできるため、初めてリーガルテックの導入を検討する方にもおすすめです。
すべての法務業務を1つのツールで完結
LegalOnの特長は、法務業務すべてをサポートすることです。さまざまなリーガルテックサービスが業務ごとに分断されているという課題を解消するために、LegalOn Cloudは一つのプロダクトで法務業務全般を支援します。
具体的には、案件管理、契約書レビュー、電子契約の締結、契約書管理など、法務担当者が担うさまざまな業務に対応するサービスを一つのプロダクトに搭載します。
まずは以下の体験型無料デモから、契約まわりの業務がどれほどラクになるのか、実際の操作を通じてぜひお確かめください。



(1).webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
.webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)