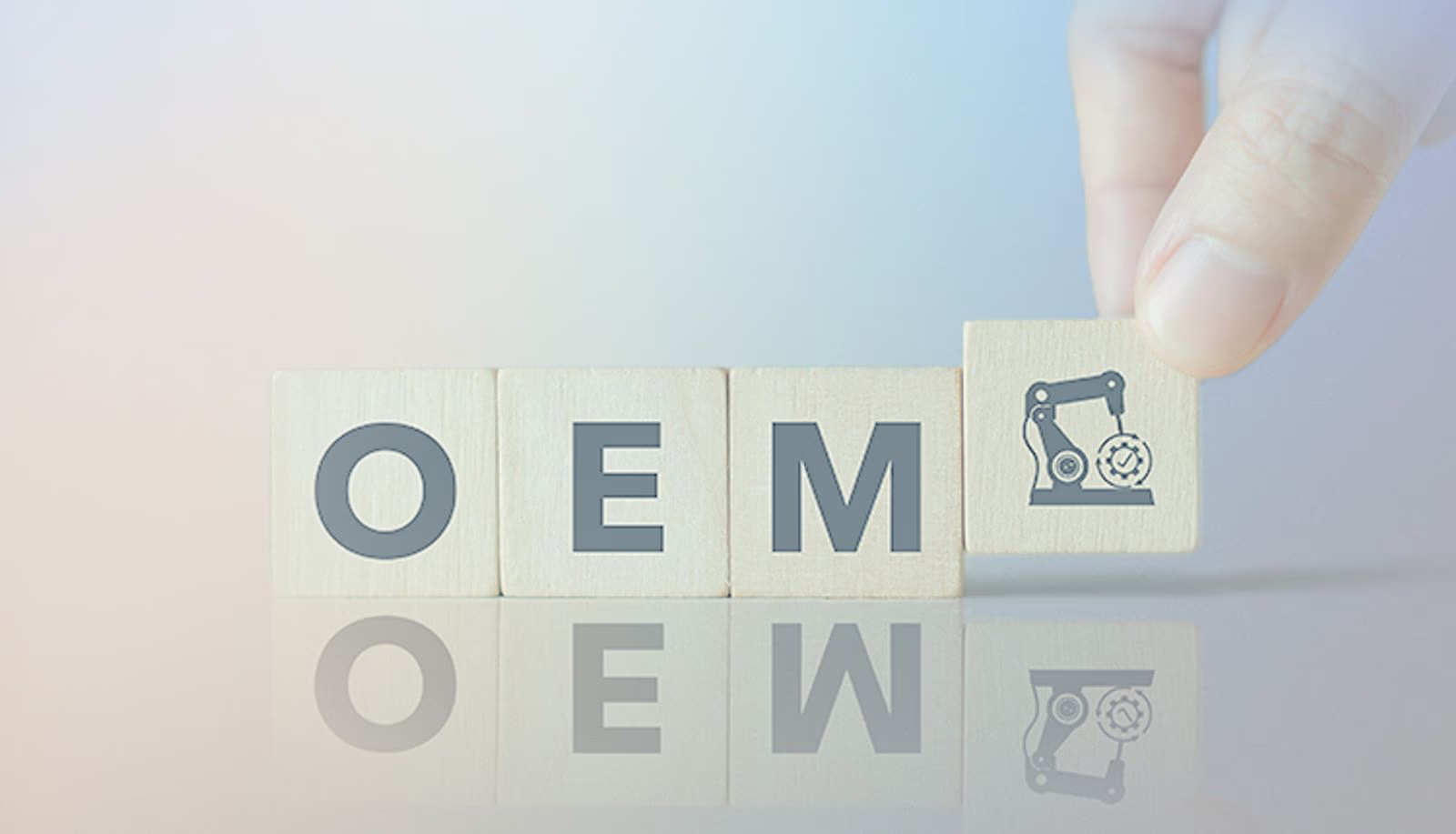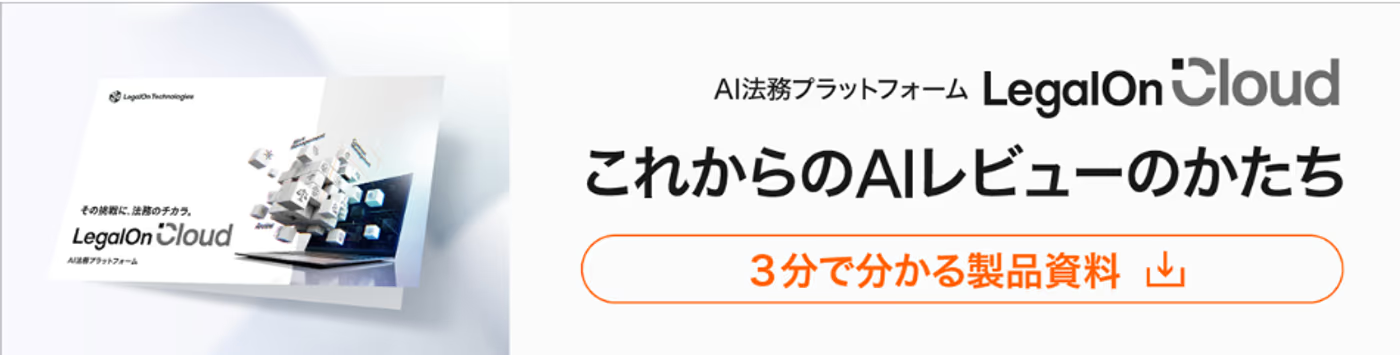OEM契約とは
OEMは「Original Equipment Manufacturing」の略で、OEM契約とは、自社ブランドの製品の製造を他社に委託する契約です。一般的には、自社の商標を付した商品の製造を委託する場合をいいます。
委託するのは製造のみで、製造した製品の販売は含みません。
OEM契約は、委託する側にとっては、製品の製造のコストを下げたり、新たな設備投資や技術開発を行わずに新製品を販売できたりするメリットがあります。
一方、受託する側にとっても、自社の製造技術や余剰のキャパシティを活用できる、販売管理や販売コストを考えずに製造することができるというメリットがあります。
使い勝手のよい取引形態ですが、商標の利用の問題など、契約書作成においては注意することも多い契約書です。
ライセンス契約との違い
OEM契約と類似する契約にライセンス契約があります。
OEM契約とライセンス契約の違いは、OEM契約が製造することがメインであるのに対し、ライセンス契約は製品の特許や商標等の知的財産権を利用させることがメインという点です。
つまり、OEM契約の場合は、受託者は製品の製造のみ行い、委託者はその製品の供給を受けるということになります。
一方、ライセンス契約の場合は、ライセンサー(ライセンスを許諾する側)がライセンシー(許諾を受ける側)に対して、製造の許可に加え、販売についても許可する場合がほとんどです。
また、ライセンスの期間や販売できるエリア・年数を限定することがあります。
製造委託契約との違い
製造委託契約とは、委託者が受託者に対して、製品の製造を委託する契約の全般を指します。
つまり、OEM契約は、製造委託契約の一種になります。
なお、製造委託契約の中には、ODM契約(Original Design Manufacturing)と呼ばれるものもあります。
これは、製品の製造のみを委託するOEM契約と違い、製品の企画・開発から委託するもので、なかには製品の販売に関するマーケティング戦略の立案まで委託するケースもあります。
製造委託契約の内容は、現在、単なる製造にとどまらないものに進化しています。
OEM契約を結ぶメリット
OEM契約は、自社ブランド力がある委託者と、製造能力がある受託者が、それぞれの得意なことを活かして行う取引ですので、両者にとってメリットがあります。
委託者は自社ブランドの商品の製造コストを下げて供給量を増やすことができ、受託者は安定した収益が見込めます。
委託者のメリット
OEM契約における委託者のメリットとしては、下記の3点があげられます。
- 製品の供給量を拡大できる
製造能力がある会社に製造を委託することにより、自社で製造するよりも多くの製品の製造が可能になります。
また、新たに設備投資や人員増員をする時間をかけず、短期間で供給量が拡大できることもメリットです。 - 製造にかかるコストを削減できる
すでに製造能力がある会社に依頼すれば、自社で新たに設備投資や人員増員をする必要がないので、その分のコストが削減できます。
また大量に発注することによって、一つ一つの製造単価を下げることも可能です。 - 製造以外の業務に注力できる
製造以外の業務、例えば、自社ブランドの広報や価値向上、マーケティング、販売網の拡充などの業務に注力することができます。
受託者のメリット
OEM契約における受託者のメリットとしては、下記の3点があげられます。
- 収益を安定して得られる
OEM契約では継続した一定期間、一定の量の受発注を約束することが多いため、受託者としては、収益を安定して得られるというメリットがあります。 - 技術力の向上が見込める
委託者の指定する技術や方法により製品を製造するので、製品の製造に関する技術力を向上させて、経験を蓄積することができます。 - 販売のコストを下げることができる
市場で販売するコストを委託者が負担するので、受託者自身は販売に関するコストを下げて製造することができます。
OEM契約を結ぶデメリット
OEM契約のデメリットは、双方ともに自社の技術やノウハウが流出するおそれがあるほか、委託者は製品の品質が落ちるリスクがあり、受託者は良い製品を作っても自社の製品として販売できない等のリスクがあります。
委託者のデメリット
OEM契約における委託者のデメリットとしては、下記の3点があげられます。
- 製品の品質が落ちるリスクがある
製造過程のすべてを委託者が監視できないため、不具合のある製品が多発する、適切な製造方法に基づかない製品が製造される等、品質が落ちるリスクがあります。 - 製造ノウハウが流出するリスクがある
OEM契約には、技術情報の漏洩や他目的の利用を禁止する条項を入れますが、それが守られずに受託者が製造ノウハウ等を使用して他社製品や自社製品を製造したり、情報を流出させたりするリスクがあります。 - 自社の技術力が向上しない・低下する
自社で製造を行わなくなるために、自社の技術力が向上しない、または低下するというリスクがあります。
受託者のデメリット
OEM契約における受託者のデメリットとしては、下記の3点があげられます。
- 自社の製品として販売できない
OEM契約では製造した製品は、委託者の製品として販売します。自社の製品として販売はできません。 - 委託者に製造技術が流出するリスクがある
製品の製造過程において、受託者の製造技術を利用する場合、その技術が委託者に流出するリスクがあります。 - 委託者との力関係が不均衡になりやすい
自社で製造量を決めることができず、収益を委託者に頼ることが多くなるため、委託者と対等ではない力関係になることがあります。
OEM契約書の記載事項
OEM契約書には、製造する物品の内容や仕様、納期や検査方法、また、委託者の商標の内容や製品への表示方法など最低限記載すべき事項だけでも多々あります。記載漏れがある場合には後々にトラブルとなりますので、取引において必要な事項をしっかり入れることが大切です。
契約書のひな型はインターネット上でも入手できますが、OEM契約の内容は個々の取引において違います。
自社の事情を担当部署からしっかりと聞き込み、それを漏れなく落とし込み、適宜修正していくようにするのがいいでしょう。
取引の内容
最も重要な条項です。
OEM契約で製造する製品の内容、サイズ、材料、製造方法などの取引の内容を記載します。
仕様が複雑な場合や、複数の製品を製造する場合には、個々の製品について別途仕様書に詳細を記載する例が多くみられます。
途中で仕様を変更する場合には協議によるとしたり、仕様書に疑義が生じた場合には受託者がその内容を指摘する義務を定めたりする場合もあります。
商標の表示
こちらもOEM契約において重要な条文です。
OEM契約では、委託者の商標を付した製品を製造しますが、これは商標法の定める「使用」に該当します。
そのため、商標を付けることができる旨定めたうえ、使用する商標を特定すること、使用する方法を指定すること等を定めます。
また、商標を他の製品に使用してはならないことや、商標を付した製品を受託者が第三者に譲渡や販売、貸与できないことも記載します。
発注の期日
発注については、契約段階で発注日が明確に決まっていれば記載することが多いですが、継続的な委託で都度発注する場合には、「別途発注日を個別契約で定める」と記載することが多いです。
最低発注数
OEM契約のうち、1回の発注ではなく、継続して発注を予定している契約の場合は、最低発注数を定める例がほとんどです。
なぜなら、OEM契約では、大量に受注することで、資材や部品をまとめて確保しコストダウンするという特色があるためです。一定量以上の発注がないとコストが増え、それを受託者が負担することになってしまいます。
また、製造ラインを確保しておくこともあるため、最低発注数が見込まれないと、人件費などのコストも余計にかかります。
納入の期日
製造した製品の納入期日を定めることは必須です。
ただ、継続的な契約の場合には、納入期日を個別契約書や発注書に記載する例がほとんどです。
納入期日の記載がなければ、委託者としては、必要なときに製品が手元にない、ということになりかねません。
受入検査の方法
契約書には、納品された製品の受入検査の方法も記載します。
複雑な検査が必要な場合にはその方法を別途定めることもあります。
大量かつ均一的な製品の場合には、抜き取って検査する場合や、外装検査のみとする場合もあります。
検査の方法以外に、納入されてから検査が完了するまでの期間、検査結果の通知方法、通知がない場合に合格とみなすこと、検査に不合格だった場合の受託者の対応方法についても決めておきます。
これは製造する製品の性質に沿って適切な内容にすることが大切です。
代金の支払い方法
代金の支払い方法についても契約書に記載します。
別途個別契約に記載するとする場合もあれば、契約書には請求書の発行日や請求書発行月の末日など一般的な支払日を記載するだけの場合がほとんどです。
細かいところでは、振込手数料をどちらが記載するのかについても記載したほうがよいでしょう。
なお、下請法が適用される場合は、納入日から60日以内に支払う必要がありますのでご注意ください。
品質保証・契約不適合責任
製造した製品に不具合がある場合の対処方法についても、契約書で定めておく必要があります。
受入検査で不合格が出たとき、追加で納入する、代品を納入するなど、どのように対処するのかを定めます。追加納入や代品の納入以外に、代金の減額や損害賠償を請求できると定める場合もあります。
また、不合格品を受託者が引き取ると定めたり、引き取る場合の代金をどちらが負担するのかを決めたりすることもあります。
検査時には発見できなかった不具合が後に発見された場合にも、同様に契約不適合の問題が生じます。
この場合は、契約不適合への対応を行う期間を民法と同様に発見時から1年とするのか、納品日や検収終了時を基準として考えるのか、期間をどの程度にするのか、という点で、委託者と受託者でかけひきが生じます。
不具合のある製品でも、委託者が認めた場合は納入できるとすることもあります。
なお、下請法の適用がある場合は、返品が認められるのは6か月以内に限られますので、ご注意ください。
秘密保持
委託者・受託者それぞれがもつ技術やノウハウをともに利用するのがOEM契約です。
そのため秘密保持契約は必須ですし、その内容についても、細かくしっかりと定めることが大切です。
秘密情報の定義については、委託者及び受託者ですりあわせることになりますが、重大な情報を提供する側は、より慎重に内容を吟味しなければなりません。
そのほか、秘密情報の開示を認めないこと、漏洩しないこと、目的外使用を禁止すること、漏洩した場合の対処法や損害賠償についても定めます。
契約解除事由
契約解除事由はOEM契約に限らず、基本的にあらゆる契約書に記載される項目です。
多くは手形の不渡りや破産申立をしたとき等、信用不安の場合を記載します。
そのほか、契約違反があり是正されないとき、重大な背信行為があったとき、反社会的勢力の排除条項に反したときなどについて定めます。
また、任意解除として、一方からの申し出により解除できる旨を定めることもあります。
この場合は、解除を希望する日の3か月から6か月前などに通知する必要があると定めることがほとんどです。
期限の利益喪失の責任
期限の利益喪失とは、支払期限が先になっている債務を、すぐに支払わなければならなくなる、という条項です。
期限の利益を喪失させられる条件としては、破産や差し押さえなど、解除条項と重なる内容を定めることが多くみられます。
期限の利益喪失も、OEMに限らず他の契約書でも入れられる条項です。
契約の有効期間
OEM契約が1回の発注で終わらず、継続的な取引となる場合には、契約期間を記載します。
1年から3年というのが通常よくみる例です。
契約期間満了後も取引が継続する可能性があるならば、自動更新についても記載しておくべきです。
その場合、自動更新しない場合の通知を書面に限定するか、通知の期限をいつまでにするかがポイントになります。
OEM契約は、委託者は販売を見据えて、受託者は資材や材料の購入を見据えて取引しているので、継続しない場合にはあらかじめ調整する事項が多々あるからです。
再委託の可否
再委託とは、受託者がOEMの業務の全部又は一部を、第三者にさらに委託することをいいます。
委託者としては、再委託をされると監視監督が難しくなるため、事前に許可が必要としたり、再委託先がどこかを通知させたりすることがほとんどです。
一方、受託者としては、再委託によってコストが安くなる場合や、特定の作業について再委託先が高い技術を持っているような場合には、再委託をするほうがベターとなります。
再委託先が起こした問題は、受託者が一切の責任を負う、という内容も盛り込むべきです。
OEM契約締結における注意点
OEM契約においては、まずは、製造する製品の仕様や条件をしっかり定めることが重要です。
また、商標の使用方法についても、もれなく定める必要があります。
そのほか、OEM契約は委託者と受託者の立場が不均衡になりやすい、という注意点があります。委託者側は、取引に下請法が適用される場合には、契約内容が下請法に違反していないか確認しましょう。
また、継続的に取引する場合、取引内容が変わり、契約書と一致しなくなることもありますので、随時契約内容の修正がないかを気にしておくことも大切です。
「LegalOn Cloud」でAI契約書レビューは次のステージへ
LegalOn Cloudは、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲かつ総合的に支援する次世代のリーガルテックプラットフォームです。あらゆる法務業務をAIがカバーできるほか、サービスを選んで導入できるため、初めてリーガルテックの導入を検討する方にもおすすめです。
<関連記事> 法務が抱える三つの課題と、AI法務プラットフォームが示す解決策
【新任~若手法務の方へ】
そもそも契約とは何か、なぜ契約書を作成するのか、正しく答えられますか? 以下の無料資料をダウンロードして、契約の基本を網羅的に理解しましょう。