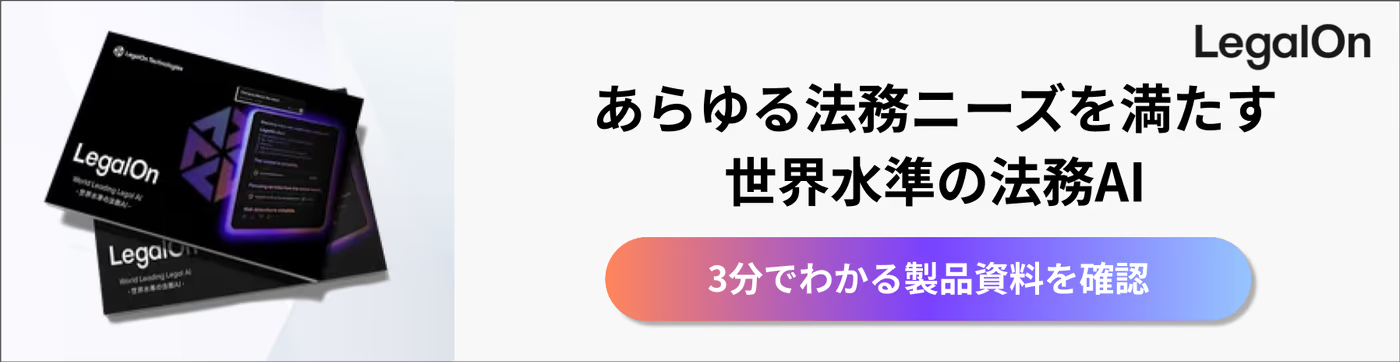登記簿謄本(登記事項証明書)とは?
「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は実質同一の書類
登記簿謄本と登記事項証明書は、現在では実質的に同一の書類です。以前は紙の登記簿を複写したものを「登記簿謄本」と呼んでいましたが、登記情報の電子化に伴い、コンピューターシステムで記録された事項を証明したものが「登記事項証明書」として提供されるようになりました。そのため、現在では「登記事項証明書」が正式な名称となっていますが、一般的には「登記簿謄本」という呼称も広く使われています。
そもそも登記簿とは?
登記簿は、会社や不動産の情報を記録した公的な書類です。登記とは、権利関係を明確にするために公の記録として情報を登録し、一般に公開する制度を指します。これにより、権利の保護や取引時の予期せぬ損害を防ぐことができます。登記には、「商業・法人登記」と「不動産登記」の2種類があります。次章ではこの2種類の登記簿謄本について詳しく解説します。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法
不動産の登記事項証明書も法人の登記事項証明書も、いずれも取得方法は同じです。法務局の窓口や郵送、オンラインなどの方法で取得できます。特にオンライン申請システムを利用すれば、法務局に出向くことなく登記事項証明書を取得でき、手数料も窓口での請求より安くなるためおすすめです。
必要なもの
登記事項証明書の取得に際して必要なのは、①交付請求(申請)書の記入と提出、②手数料の支払いです。原則として、その他の書類は不要です。委任状や実印、身分証明証なども準備しなくて大丈夫です。
不動産の登記事項証明書は土地建物の所有者でなくても誰でも取得可能。法人の登記事項証明書も法人の関係者でなくても取得できます。
それでは、各取得方法の詳細を確認していきましょう。
オンラインでの取得方法と手数料
登記事項証明書は、法務局のオンラインサービスを利用することで、自宅やオフィスにいながら簡単に取得できます。受け取り方法は法務局の窓口での受領と、指定住所への郵送から選択できます。手続きはシンプルで、クレジットカード決済も可能です。手順は次のとおりです。
【STEP 1】利用者情報の登録
- 法務局「登記情報提供サービス」にアクセス
・登記事項証明書(会社・法人) を取得したい方はこちら
・登記事項証明書(土地・建物)を取得したい方はこちら - 「申請者情報の登録」画面で必要情報を入力
・申請者ID
・パスワード
・氏名
・住所
・電話番号
・メールアドレス など - 認証メールを確認して本登録を完了
登録したメールアドレスに届いた認証情報をもとにログインします。
【STEP 2】ログインと証明書の選択
- 「登記・供託オンライン申請システム」にログイン
トップページから「かんたん証明書請求」をクリックする。 - 必要な登記事項証明書の種類を選択
判断に迷う場合は、事前に関係者あるいは不動産会社に確認しておきましょう。
【STEP 3】交付方法と手数料の支払い
- 交付方法を選択
・書面請求(手数料:600円)
・オンライン請求・送付(手数料:520円)
・オンライン請求・窓口交付(手数料:490円) - 手数料の支払い
・支払い方法:クレジットカード、インターネットバンキング、Pay-easy対応ATM
法務局の窓口・郵送での取得方法と手数料
登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
取得に必要な「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書」、「登記事項証明書・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書」は窓口に置いてありますが、あらかじめ法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。
なお、窓口で登記事項証明書を申請・取得する場合の手数料は1通につき600円となっています。また、郵送で申請・取得する場合には、住所・氏名を書き、切手を貼った返信用封筒を用意する必要があります。
登記簿謄本(登記事項証明書)の種類
「商業・法人登記」の登記事項証明書の種類
登記簿に記録される事項を証明した書面を登記事項証明書といいます。法人登記の登記事項証明書には以下の種類があります。
- 現在事項証明書
請求日現在の法人に関する登記情報が載っている(商号・本店・目的・発行済株式の総数・資本金・役員など) - 履歴事項全部証明書
請求日現在の登記情報と「交付請求日の3年前の1月1日以降」の登記情報が載っている - 閉鎖事項全部証明書
履歴事項全部証明書に記載されていない抹消・閉鎖された古い登記事項などが載っている - 代表者事項証明書
会社の代表者の代表権に関する事項が載っている
法人登記の登記事項証明書が必要となるタイミング
- 金融機関での法人口座開設時:会社の実在性や基本情報を確認するために提出が求められます。
- 融資の申し込み時:会社の信用力や財務状況を確認するため、登記事項証明書の提出が必要です。
- 補助金・助成金の申請時:申請内容と会社情報の整合性を確認するために使用されます。
- 新規取引先との契約時:相手企業の信用調査や与信チェックの際に利用されることがあります。
- オフィスの賃貸契約時:会社の代表者や資本金などの確認のため、提出が求められることがあります。
- 特定の許認可手続き時:業種によっては、許認可申請の際に必要となる場合があります。
- 登記内容の変更時:本店移転や役員変更などの際、現在の登記内容を確認するために取得します。
- 決算申告時:税理士が資本金などの会社情報を確認する際に、登記事項証明書が必要となることがあります。
- 外部からの出資やM&A時:デューデリジェンスの一環として、会社情報の確認のために提出が求められます。
これらの場面で、法人の登記事項証明書は会社の基本情報や権利関係を確認する重要な書類として使用されます。
<関連記事>
【法律用語解説】定款とは? 作成から認証、記載事項や管理・保管まで徹底解説
「不動産登記」の登記事項証明書の種類
不動産登記の登記事項証明書には主に以下の種類があります。
- 全部事項証明書
登記簿に記載されている権利変動などの履歴が全て載っている(閉鎖登記簿除く) - 現在事項証明書
請求日現在効力の登記情報が載っている(閉鎖登記簿除く) - 一部事項証明書
一部の事項のみ載っている(閉鎖登記簿除く)(全部事項証明書を取得すると膨大になるときなどに利用する) - 閉鎖事項全部証明書
コンピューター化された以前の記録や滅失した建物などの記録が載っている
主に土地や建物の所在地、面積、所有者、権利関係など、不動産に関する重要な情報が記載されています。
<関連記事>
【弁護士監修】全部事項証明書とは? 取得方法や登記事項証明書との違いを解説
登記事項証明書が必要になるタイミング
- 不動産の売買契約時:売主と買主が不動産の所有権や権利関係を確認するために必要です。
- 不動産の賃貸契約時:貸主と借主が所有権や権利関係を確認する際に使用されます。
- 不動産を担保に融資を受ける際:金融機関が担保物件の所有権や既存の権利関係を確認するために求められます。
- 不動産の権利関係を調査する際:取引先や投資先の不動産の権利状況を確認する場合に利用されます。
- 新規取引先との契約時:取引先の不動産の権利状況を確認する場合に利用されます。
- M&Aの際:対象企業の不動産資産の権利関係を確認するために必要です。
これらの場面で、不動産の登記事項証明書は不動産の正確な情報を把握し、取引の安全性を確保するために重要な役割を果たします。
交付請求(申請)書の書き方
不動産の登記事項証明書の交付請求書を「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書」、会社法人の登記事項証明書の交付申請書を「登記事項証明書 登記簿謄本抄本 概要記録事項証明書 交付申請書」と呼びます。
まず不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)の交付を申請する場合の書き方を説明しましょう。
画像引用元:法務局|登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書 [PDF]
- 申請者の住所・氏名を記載する
- 種別、群・市・区、町・村、丁目・大字・字、地番、家屋番号又は所有者を記載する
- 請求通数を記載する
- 土地・建物の場合は、財団/船舶/その他は記載しなくていい
- 共同担保目録の要否を記載する(債権の担保として複数の不動産に抵当権が設定されており、それらをまとめて記載した目録が必要な場合に記載する項目)
- 「登記事項証明書・謄本(土地・建物) 専有部分の登記事項証明書・抄本」にチェックを入れる(マンションの場合は名称を記載する)
続いて、法人の登記事項証明書の交付を申請する場合の書き方は以下の通りです。
画像引用元:法務局|登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書
- 申請者の住所・名前を記載する
- 取得したい会社の商号を記載する
- 会社の本店所在地を記載する
- 法人番号を記載する(わかる場合)
- 請求事項、通数に印を付ける
参考:法務省|「登記・供託に関するオンライン申請について」、法務局:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
登記簿謄本(登記事項証明書)情報はオンラインで閲覧できる
不動産や企業に関する公的な情報を確認したい場合、必ずしも登記事項証明書を入手する必要はありません。より効率的で経済的な方法として、オンラインでアクセス可能な「登記情報提供サービス」が存在します。
このサービスを利用すれば、インターネットを通じて不動産や法人に関する登記データ、さらには関連する地図や図面なども閲覧することができます。単に情報を確認するだけであれば、この方法が時間とコストの面で優れています。
特に、複数の物件や企業について調べる必要がある場合や、急ぎの確認が必要な際には、このオンラインサービスの利便性が際立ちます。ただし、正式な書類として提出が求められる場合などは、登記事項証明書の取得が必要となる点に注意が必要です。
閲覧申し込みの注意事項
申し込みの手続きに法人は1か月程度かかることには注意しましょう。
利用時間
- 平日:8:30~23:00
- 土日祝日:8:30~18:00※地図・図面情報は平日8:30~21:00
料金
- 登記事項証明書(全部事項証明書):331円/1件
登録費用
- 法人:740円
- 国、地方公共団体等:560円
支払い方法
- 法人:口座引き落とし
登記簿謄本(登記事項証明書)の記載事項と見方
登記の記載事項と見方を説明します。ここでは不動産の登記事項証明書を取り上げます。
※ 以下は土地の全部事項証明書の見本です。
画像引用元:法務省|登記事項証明書(不動産登記)の見本(土地・PDF形式)
不動産登記は、大きく分けて「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」と言う4つの部門で構成されており、それぞれの見方は以下の通りです。
表題部
表題部は対象不動産の基本情報が記載されている部分です。土地と建物で記載事項が一部異なります。
土地の場合
- 所在:土地の場所が市/町/村/字まで記載されている
- 地番:不動産登記する際に土地に付与される番号
- 地目:土地の用途
- 登記の日付:登記の日付(登記された年月日と原因)
建物の場合
- 所在:市町村字および地番まで記載されている
- 家屋番号:不動産登記する際に建物に付与された番号
- 種類:建物の用途により区分された種類
- 構造:建物の構造を「構成材料 + 屋根の種類 + 階数」で表す
- 床面積:建物の床面積で、階数ごとに表示される
- 登記の日付:登記された日と原因を記載
権利部(甲区)
権利部(甲区)は不動産の所有者に関する情報が記載された場所です。以下のような項目が記載されています。
- 順位番号:登記された順番
- 登記の目的:所有権に関する事項
- 受付年月日・受付番号:登記された日と受付番号
- 権利者その他の事項:所有者等の住所/氏名や原因
権利部(乙区)
権利部(乙区)には、甲区以外の権利、つまり所有権以外の権利が記載されています。記載項目は以下の通りです。
- 順位番号:乙区で登記された順番
- 登記の目的:所有権以外の権利に関する事項
- 受付年月日・受付番号:所有権以外の権利の登記が行われた日と受付番号
- 権利者その他の事項:権利者の住所/氏名や原因
共同担保目録
共同担保目録は、同一の債権を担保するために複数の不動産に担保権を設定した場合(共同担保)の関係性を明らかにするために作成するものをいいます。
共同担保目録を見る場合は、権利部(乙区)と照らし合わせなければいけません。例を挙げてみましょう。
住宅ローンを組んで戸建て住宅を購入したとします。普通は、この場合、土地と建物の両方を担保に提供し、同じ抵当権を設定するでしょう。
この場合、両方の登記事項証明書を確認すると、共同担保目録に両方の記載があるので、土地も建物も抵当権が設定されていると分かります。
共同担保目録の記載事項は以下の通りです。
- 番号:不動産に割り振られた通し番号
- 担保の目的である権利の表示:抵当権等担保権が設定されている不動産の所在/地番/家屋番号
- 順位番号:抵当権等担保権の順位
まとめ
ビジネスシーンで欠かせない登記事項証明書。従来の法務局での取得は時間と手間がかかりますが、近年ではオンライン申請で、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用し、自宅やオフィスから手続きが可能です。法人登記、不動産登記のどちらも取得できます。
また、民間サービスも便利です。オンラインで閲覧できるサービスなどがあります。これらのサービスは、法務局に行く時間がない場合や、大量の登記事項証明書を取得する必要がある場合に特に役立ちます。
取得した登記事項証明書は、ファイル保管やデータベース化で管理効率を上げましょう。
これらの方法を組み合わせることで、登記事項証明書の取得にかかる時間と手間を大幅に削減できます。ぜひ、ご自身の状況に合わせて最適な方法を試してみてください。
登記簿謄本(登記事項証明書)のよくある質問
委任状は必要?誰でも請求できる?
結論:委任状は原則不要で、だれでも請求できます。
登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は「公示」を目的とした公的情報です。不動産・法人いずれも、請求者が所有者や会社関係者でなくても取得できます。窓口・郵送・オンラインのいずれでも、交付請求書(申請書)と手数料があれば足ります。本人確認書類や実印は通常不要です。
例外的に、窓口で第三者の代理受領に制限や確認が入る運用があるため、確実性を求める場合は管轄法務局の案内を事前確認しましょう。プライバシー配慮の観点から、目的外の大量取得は避けるのが実務上のマナーです。
即日発行の可否/オンラインの所要時間は?
結論:窓口なら多くのケースで即日交付、オンラインは受取方法で所要が変わります。
法務局窓口に申請すれば、混雑状況にもよりますが当日中に交付されるのが一般的です。オンラインは二通りあり、①オンライン申請→窓口受領なら、受領指定の法務局で当日または指定日時に受取、②オンライン申請→郵送交付なら、投函から到着まで数日を見込みます(郵便事情や地域で増減)。 急ぐ場合は窓口交付かオンライン申請+窓口受領を選び、複数通は事前に必要通数を明記すると受取がスムーズです。
履歴事項“全部”と“現在”の違いは?
結論:「履歴事項全部証明書」は“現在+過去の変更履歴”を含み、「現在事項証明書」は“現在有効な内容のみ”です。
法人登記で、与信・取引審査・M&Aなど変遷の把握が必要な場面は履歴事項全部証明書を選びます。役員の就退任、本店移転、目的変更、増減資などの変更履歴が読み取れます。 一方、口座開設や許認可等で現時点の登記内容の確認のみ求められる場合は現在事項証明書が指定されることがあります。提出先の要件が明確なときは、その指示に従うのが最短です。
「証明書」が必要な場面/必要でない場面は?
結論:調査・下見は“閲覧”で十分、提出・証明は「証明書」が必要です。
オンラインの登記情報提供サービスでは、不動産・法人の登記情報を画面上で閲覧できます。社内の事前調査、物件・相手先の一次チェック、地番・家屋番号の確認などは閲覧が最速・低コストです。 ただし、金融機関への提出、官公庁の許認可、契約・登記申請の添付資料など、「公式な証明」が必要な手続では登記事項証明書(原本または原本相当)が求められます。閲覧画面の印刷は原則として提出資料の代替になりません。用途を見極めて選択しましょう。
初めてのリーガルテックなら「LegalOn」
LegalOnは、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲かつ総合的に支援する次世代のリーガルテックプラットフォームです。あらゆる法務業務をAIがカバーできるほか、サービスを選んで導入できるため、初めてリーガルテックの導入を検討する方にもおすすめです。
<関連記事>