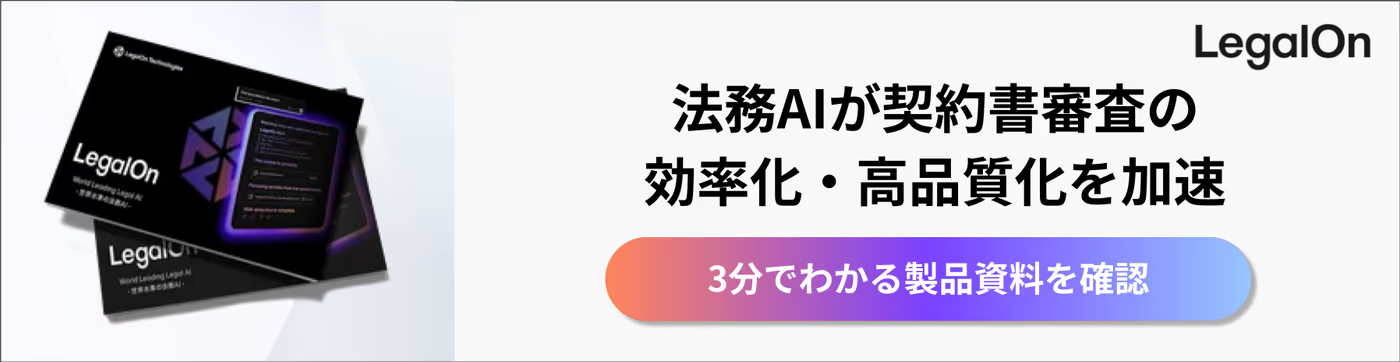日本の国力予測とAIの必然性
いま日本は、世界の中で実質GDP第4位という地位を保っています。しかし、日本経済研究センター(JCER)の予測では、この順位は徐々に低下し、2075年には11位まで後退する可能性があるとされています。

※出典:日本経済研究センター「長期経済予測:2075年BRICS経済圏が米国の1.4倍に拡大」をもとに編集部作成
一方で、AIを積極的に活用し生産性を高めれば、人口減少という避けられない課題を抱えながらも、今の国力を維持できるとも示されています。AIは単なる業務効率化のITシステムではなく、日本の構造的な制約を補い、未来の競争力を支える「必然」であり、同時に「希望」でもあるのです。この構造は企業にも当てはまり、人材不足や業務量の増大に直面する中で、AI活用が成長の鍵となります。
経営を再定義するインパクト:2026年「1人ユニコーン」の可能性
生成AIは、企業のDXを推進するキーテクノロジーとしてあらゆる領域に組み込まれ、急速に浸透しています。その主たる理由は、人間の生産性を飛躍的に高めるからにほかなりません。
こうした流れを象徴的に表すのが、AnthropicのCEOダリオ・アモデイ氏の発言です。AIの進化によって「2026年には1人で10億ドル規模の企業を経営できる可能性がある」というものです(Benzinga,2025)。誇張に聞こえるかもしれませんが、これは経営の形そのものを再定義せざるを得ない未来を示しています。
少人数でも巨大な価値を生み出す時代は目前に迫っています。経営がAIを取り込んで加速する以上、法務や総務などの管理部門も同じ速度で動けなければ、経営の信頼を得ることはできません。
経営者の頭脳を拡張するAI
一見突飛に思える“1人ユニコーン”が、なぜ今リアルな可能性として語られるのでしょうか。その背景には、生成AIによる戦略立案の自動化があります。例えば、経営者が新規事業の戦略を考える場面を想像してみてください。私自身、生成AIにこう指示を出したことがあります。
「あなたは経営戦略の専門家でありスタートアップのCEOです。AIの普及に伴い世界の電力需要がひっ迫するという課題を解決するために、最先端テクノロジーを活用した次世代エネルギー事業を展開し、2031年3月末までの5年半で売上300億円を達成する戦略を立案してください。」
ディープリサーチを用いると、核融合や小型モジュール炉といった最新技術の選択肢や、市場規模や需要予測、投資規制や競合状況が整理され、さらにKPIに分解した数値計画やマイルストーン、Go-to-Market戦略まで提示してくれます。前提の曖昧さやハルシネーションはあるため追加検証は不可欠ですが、従来ならコンサルタントが数週間かけて作成していた戦略レポートが、今や数分で生成できるのです。
時代は生成AIから「AIエージェント」へ
OpenAIは、AIの進化を段階的に整理しており、一部では2025年を「エージェント元年」と位置づける見方もあります。
2022年のLLMによるテキスト生成(レベル1)、推論モデルの登場(レベル2)を経て、現在のレベル3では自律的に計画・実行できるエージェントが業務を代替し始めています。今後はレベル4:イノベーター、レベル5:組織体へと進化し、AGIへの道が拓かれると見られています。

※出典:Bloomberg(2024年7月12日報道)を参考に、編集部で翻訳・再構成
こうした存在が普及すれば、数週間かけていた戦略立案が一瞬で可能となり、競争環境は激変し、事業構造そのものが変わっていくでしょう。これは効率化というレベルではなく、オフィスワークにおける産業革命に匹敵する経営インパクトです。私たちは、まさに「革命前夜」に立っているのです。
戦略の均質化と遂行の時代へ
重要なのは、こうして戦略の素案がAIによって均質化していくという事実です。従来であれば、情報収集力や分析力、戦略構想力そのものが企業の競争優位を支える源泉でした。しかしAIが瞬時に最適解を提示する時代には、企画段階の優位性は急速に縮小していきます。
つまり「戦略の差」そのものが縮まり、誰もが似たような戦略を持ち得る世界が訪れるのです。差がつくのは、誰も思いつかないようなアイディアを思いつけるか否か、その戦略をいかに素早く、確実に遂行できるかという実行力になります。戦略を描くことから、それを組織としてどのように実現していくかへと、競争の主戦場が移っていくと考えます。
この変化は、事業の立ち上げや新規市場への参入だけでなく、法務・総務・管理といったコーポレート部門の在り方にも直結します。AIによる戦略立案のスピードと精度に合わせ、契約やリスク管理、ガバナンスの仕組みをいかに迅速に整えられるかが、経営全体の成果を左右する時代へと入ろうとしています。
法務への示唆:“守り”を超えて、経営を動かす戦略パートナーへ
このようなAI時代において、経営から本当に頼られる法務・総務・管理部門に求められる条件は、以下の5つだと考えます。
- 経営方針の理解者であること管理部門が経営方針を正しく理解していることは、経営陣と同じ目標を共有しながら建設的な議論を行うことができ、経営判断の質を高めることができる。経営の意図や背景を汲まずに、法務や管理部門の理屈だけを押し出すと、結果的に経営の推進力を削ぎ、信頼を損なうリスクが生じます。したがって、常に最新の経営方針とその背景を理解したうえで、助言や判断を行う姿勢が重要です。
- 業務推進の支援者であること法務や管理部門の本質的な使命は、事業推進を支えることです。経営陣から「事業推進の支援者」として認識され、信頼を得ることができれば、たとえ経営方針に異議や修正意見を唱える場面でも、その発言は重みを持ちます。逆に、支援の姿勢を欠いた部門の意見は、単なる“制約要因”と見なされがちです。経営の目指す方向を理解しつつ、その歩みを支える姿勢を持つことが、法務・管理部門の存在価値を高めます。
- 攻めと守りのバランスに優れていること経営者が必ずしも法的知識を十分に持っているわけではないため、法務・管理部門の判断が事実上の最終判断となるケースは少なくありません。過度に守りに寄れば事業機会を逸失し、攻めすぎれば致命的なリスクを負う可能性があります。そのため「攻守のバランス」をとる感覚が不可欠です。このバランス感覚を養うには、「自分が経営者であればどのように判断するか」という視点を持つことが有効です。経営目線を持ってリスクと機会を天秤にかけることこそ、戦略パートナーに求められる役割です。
- 迅速であることAIをはじめとした技術の進展により、経営スピードは加速度的に増しています。その中で、契約審査や法務相談といったチェック機能が経営のスピードを阻害するようでは、「法務や管理はブレーキ役だ」という不名誉な評価を招きかねません。求められるのは、経営が期待するスピードに応える迅速さです。チェックやリスク管理の質を維持しながらも、いかにリードタイムを短縮し、経営のスピードに追随できるか。その機動力が、信頼される管理部門か否かを分ける鍵となります。
- 胆力があること法務や管理部門は、経営判断に関わる場面や日々のリスク判断において、避けて通れない選択を迫られます。「リスクがあります」と警告するだけでなく、「私ならこう判断します」と責任を持って提言できる胆力が重要です。リスクを回避するだけなら外部アドバイザーでも可能ですが、自らリスクを引き受ける覚悟を示すことで、経営にとって代替不可能なパートナーとなります。その胆力こそが、経営にとって“頼れる存在”と映り、長期的な信頼の礎となるのです。
実装を支える3要素
この5条件を実現するために必要なのが、次の3つの要素です。
- 知識・経験・判断法務やコーポレートの専門知識を高めるだけでなく、それを経営判断に資する“提案力”へと昇華させることが重要です。単にリスクを列挙するのではなく、「この状況ならこう進めるべきだ」と代替案を示せる力が、経営の信頼を得る分かれ目になります。
- マインドセット経営方針や事業戦略を理解しようとする姿勢は、誰にでも身につけられる要素です。ただの規制順守の立場ではなく、事業を前進させる支援者として動く意識が、日々の判断に大きな違いを生みます。
- リソース経営スピードに応えるには、人材や仕組みといったリソースが不可欠です。採用や育成に加え、AIを活用して不足を補うことで、ルーティンを効率化し、限られた人材を高度な判断に集中させることが可能になります。
法務を支えるAIエージェント開発の最前線
当社の主力製品であるLegalOnをはじめとして、当社グループのサービスは現在、グローバルで7,500社以上、日本国内では1,200社超の上場企業にご利用いただいています。直近では70億円超の資金調達を行い、累計調達額は286億円となりました。この資金をAIエージェントの開発に投資しています。
さらに、世界で最も広く使われている生成AIを開発するOpenAIとの戦略的連携を通じて最新の大規模言語モデル群(OpenAIモデルを含む)を法務領域に応用し、現場で自律的に業務を行うAIを実現する取り組みを進めています。
開発中のエージェント例
- ドラフティングエージェント:依頼内容をヒアリングし、最適なひな形から契約書を自動作成。
- レビューエージェント:契約書をアップロードすると、リスクチェックや修正案を提示。
- マターマネジメントエージェント:法務案件を自動取り込み、過去事例や法令データベースを活用して初期回答を作成。
- コントラクトマネジメントエージェント:条件に合う契約書を一覧化し、リスクや課題を可視化。
これらの法務エージェントは、Human-in-the-loop(AIが進めつつ要所で人が確認する仕組み)を前提に設計されており、最終判断は人が担いながらも、AIが横で自律的に仕事を進めます。その結果、経営や事業の速度が2〜3倍に高まっても、法務が遅れず対応できる体制を実現します。
まとめ
AIは日本の国力を左右する必然であり、生成AIからAIエージェントへの進化は経営のスピードを飛躍的に引き上げています。戦略は均質化し、差がつくのは遂行の力です。この変化に対応するには、法務・総務・管理部門も「守り」にとどまらず、経営をともに動かす戦略パートナーへと進化することが求められます。
ここで示した5条件と3要素は、単なる理論ではなく、実際に実装できる実務指針です。契約審査を短縮し、法務相談に即応し、AIを活用して人材不足を補うことで、経営の加速に遅れず伴走する体制を築けます。
LegalOn Technologiesは、法務に特化したAIエージェントを通じて、こうした進化を現場で支えます。管理部門が経営から揺るぎない信頼を得て、事業に貢献し、未来の競争環境を勝ち抜く。その実現を、テクノロジーと共に後押ししてまいります。