契約交渉は問題解決のプロセス
契約交渉は単なる条件調整ではなく、双方の利害を整理して最適な合意点を見いだすためのプロセスです。特に業務委託契約は、成果物の性質や権利関係の違いから紛争に発展するリスクが高い領域です。契約不適合責任や成果物の著作権の帰属など、典型的に利害が対立しやすい論点が数多くあります。こうした争点の交渉では、生成AIを活用して論点を整理し、依頼部門への説明や相手方に提示するコメントを作成することで、業務を効率化する余地が多分にあります。
3つのラウンドで整理する交渉フレームワーク
契約交渉を「3つのラウンド」で捉えると、全体の流れを俯瞰しやすくなります。
第1ラウンド:自社の書式で主導権を握る
契約交渉の出発点は、「どちらの当事者の書式をベースにするか」です。非常に基礎的なことではありますが、自社ひな形を提示できれば、交渉の土台を自社に有利な条件に設定できるため、重要な視点です。
自社書式を提示する際のチェックポイント
- 条項が取引の実態に即しているか
- 表現が明確で、相手方にも理解しやすいか
- 自社に有利すぎる内容となっていないか
- 関係法令に違反するおそれがないか
もっとも、あらかじめ重要な論点を精査した自社書式を整備していても、現場で十分に活用されていない企業も少なくありません。そのため、依頼部門を含めた全社でその重要性を理解し、積極的に自社書式を提示する運用を徹底することが望ましいでしょう。
第2ラウンド:交渉の着眼点を見極める
自社に不利益となる全ての条項について交渉を行うことは、実際上難しいことが多いです。案件の重要性や相手方との力関係を踏まえ、交渉に向けて追記や修正を提案する条項を見極めることが大切です。
個々の契約において交渉対象の優先度を見極める際には、成果物の性質や取引規模、リスクの発生可能性といった観点が役立ちますが、一般論としては以下のような整理が可能です。
一般的に優先度の高い項目
- 自社のリスクに直結する条項 (例:知的財産、契約不適合責任)
- 法令対応が必須となる条項 (例:下請法)
- 将来の事業展開に影響する条項 (例:競業避止義務)
優先度が相対的に低い項目
- 一般条項や定型的な手続きに関する条項
- 業界慣行に従った標準的な条項
- 相手方の合理的な要求
例えば、システム開発委託契約のように成果物に形がなく、当事者間で認識の齟齬が生じやすい案件では、成果物の定義や納期、それらが変更となる場合の手続きについて慎重に審査し、交渉することが考えられます。
こうした案件の内容に即した重要度の高い条項に重点を置く一方で、契約書の形式面や些末な表現については、必要最低限の修正にとどめることが有効な場面も多いです。限られた労力を効率的に配分し、優先順位を意識して審査や交渉を進めることが有効です。
第3ラウンド:誰に、何を、どう伝えるかを整理する
交渉を合意に導くには、内容だけでなく「伝え方」が重要です。依頼部門と相手方のそれぞれについて、ポイントを説明します。
誰に伝えるか?
依頼部門を通して契約書の修正内容を伝える場合、依頼者(依頼部門の担当者)の契約への理解度や交渉経験を踏まえて、交渉に向けた進め方を変えることが有効です。依頼者が契約交渉に明るい場合には、修正のポイントについて分かりやすく伝えたうえで、依頼者を通じて取引の相手方と交渉を進めることが一般的です。。
逆に、依頼者の習熟度が高くない場合や論点が法律論となる場合には、法務側で相手方向けのコメントを用意するのが効果的です。
何をどう伝えるか?
取引の相手方に向けてコメントをする場合には、相手方が理解しやすい表現で、説得力のある形でコメントを準備する必要があります。交渉で納得感を高めるための視点としては次のようなものがあります。
- 実務上、自社にどのような影響があるのかを具体的に示す
- 相手方が修正後の条件を受け入れても支障が小さい理由を示す
- 民法や商法といった適用法令のデフォルトルールとの比較を提示する
- 自社だけに不利益が及ぶ片務的な条項であることを示す
- 不明瞭な条項を具体化することを提示する
相手方の交渉力が強い場合はどうすればよいか?
相手の交渉力が強いと、自社の要望が通らないと感じることもあるでしょう。ただし、合理性のある要望であれば、相手方に受け入れられる可能性は十分にあります。大切なのは要望の伝え方と準備です。交渉力に差がある場面におけるポイントは、次のとおりです。
- 譲れないポイントを絞り、論点を明確にする
- 修正理由を説得力のある形で示す(合理的な要望は受け入れられることも多い)
- 相手方の負担を減らす工夫をする(例:相手方に条項の修正をさせるのではなく、自社で修正文案や覚書を作成し、確認しやすい形にして提示する)
紛争に発展しやすい二大論点
業務委託契約について、実務で特に対立が起こりやすいのが、契約不適合責任と成果物の権利(著作権)の2点です。業務委託契約ではほぼ必ず議論になるテーマなので、ここで基本的な考え方と交渉の着眼点を整理しておきましょう。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、成果物に問題があった場合に、受託者が負う責任の範囲(責任の内容や期間)を定める条文です。業務の委託側としては責任を広く長く設定したいと考える一方で、受託側は責任を限定し期間も短くしたいと考えるという利害の対立があります。
成果物の権利(著作権)帰属
成果物の権利(著作権)の帰属は、業務委託契約に基づく業務によって作成された成果物の著作権を、委託者と受託者のどちらに帰属させるかを定める条文です。委託側は成果物の著作権を取得したいと考える一方で、受託者は契約の締結前から保有する自社や第三者の資産の権利は委託者に移転せずに留めておきたいと考えるという利害の対立があります。
交渉にあたっては、この立場の違いを前提に、合理的な妥協点を探ることが重要です。
AI活用で交渉準備を効率化する
依頼者に向けた修正箇所の説明や、取引の相手方に向けた交渉用コメントを作成する際に、生成AIは補助ツールとして有効に活用できます。※以下のプロンプトの出力例と、実際の交渉に活用する際のブラッシュアップのポイントは、弊社のお役立ち情報で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。
【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と生成AI活用術(業務委託契約編)
- 依頼者向けの説明コメントや、取引の相手方向けの交渉用コメントを出力する際のプロンプト例
- #役割:あなたはベテランの契約審査担当者です。
#前提
対象となる契約の種類:【契約種類(例:業務委託契約)】
自社の立場:【自社の立場(例:委託者/受託者)】
【修正前】
修正前の条文を入力
【修正後】
修正後の条文を入力
#タスク
以下の2つのコメントを作成してください。
① 依頼部門向けコメント:なぜこの修正を行ったのかを、契約に詳しくない依頼部門でも理解できるように簡潔に説明すること。
② 相手方向けコメント:相手方に修正点を納得してもらうための交渉用コメントを作成すること。法的根拠や合理性を示すこと。
※ご注意:AIの出力結果は参考情報です。必ず専門家によるレビューと、事案に応じた修正を行ってください。また、機密情報を入力する場合は情報漏洩のリスクにも十分配慮してください。
ぜひこのプロンプトを活用して、依頼部門向けの説明や、相手方への交渉コメントのたたき台の作成を試してみてください。
まとめ
業務委託契約の交渉は、日常的に発生しますが、契約不適合責任や成果物の権利の帰属など重要な条項も多く、慎重な対応が欠かせません。本稿では、書式の主導権を握ること、交渉の着眼点を見極めること、そして依頼部門や取引の相手方への伝え方を整理することを「3つのラウンド」として紹介しました。これらを踏まえることで、難しく考えがちな契約交渉も、全体像を把握しながら進めやすくなります。
さらに、生成AIを補助的に活用することで、修正理由や交渉コメントを効率的に整理できます。属人的な経験だけに頼らず、基本的な考え方とAIを組み合わせて合理的に交渉を進めることは、組織全体にとって有益です。
契約交渉において、法務が案件や関係者に応じて柔軟に対応していくことで、事業成長への貢献を確かなものにしていきましょう。




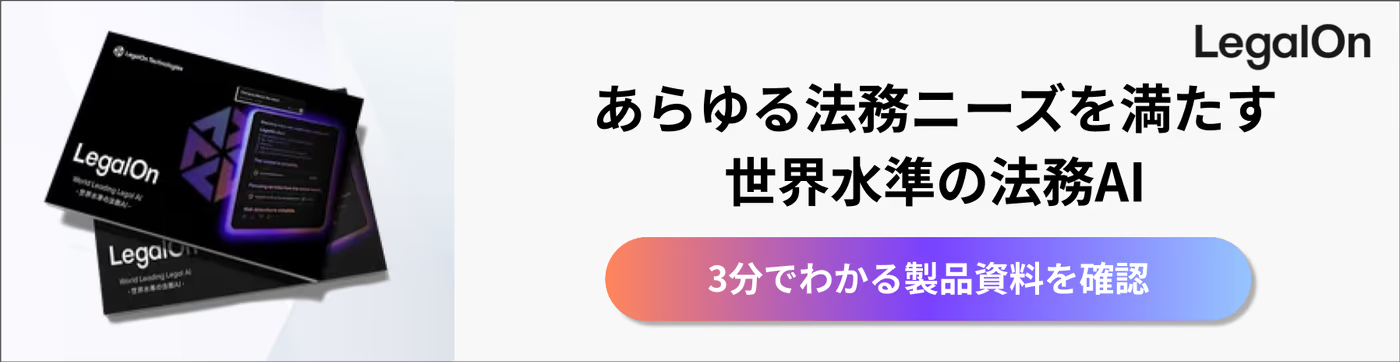
.png?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
