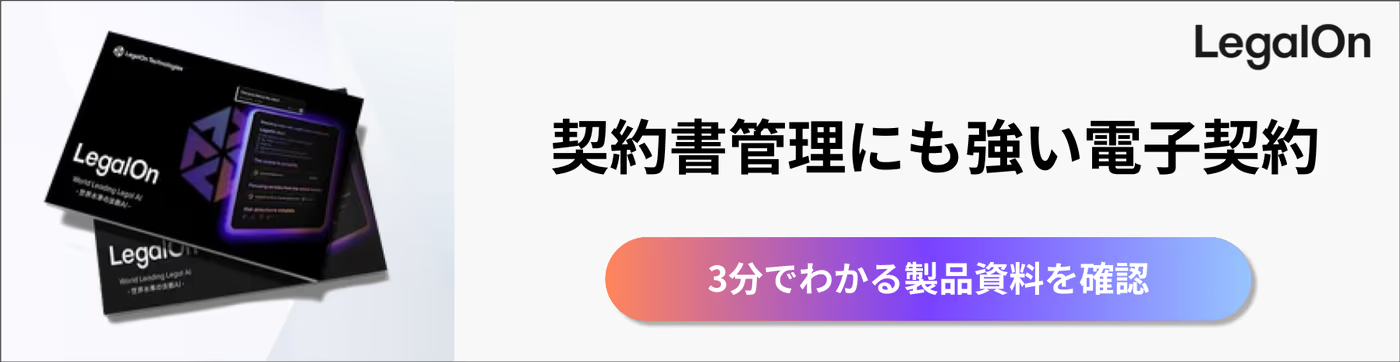電子契約とは?基本を解説
電子契約とは、契約書の一連の契約業務をオンライン上で完結できる仕組みのことです。本章では、電子契約の基本的な仕組みや流れ、立会人型と当事者型の2つの契約方式の違いについて、わかりやすく解説します。
電子契約とは
電子契約とは、契約書の作成から署名、送付、保管までをすべてオンラインで完結できる仕組みです。紙の契約書や印鑑は不要で、ファイル形式の契約書をWeb上でやり取りしながら、時間や場所に縛られずに契約が締結できます。
電子契約は、以下のような課題を一気に解決します。
- 契約書の印刷・郵送コストを削減できる
- 押印や書類管理の手間がなくなる
- オンライン上で契約が完了するため、業務のスピードが向上
- 電子署名によって、書面契約と同等の法的効力がある
電子契約は紙の契約書よりも速く・簡単で・安全に契約業務を進められる手段です。近年では中小企業から大手まで、業種を問わず広く導入が進んでいます。
電子契約の仕組みと流れ
電子契約は、紙の契約書のように郵送や押印が不要で、スピーディかつ確実にやり取りできます。契約書は、Web上で共有・署名され、正式な契約として成立します。
電子契約の流れは、以下の通りです。
- 契約書を作成し、電子契約システムにアップロード
- 取引先に送信し、内容を確認のうえ署名・承認
- 双方の合意により契約成立、締結済み書類がメールで自動配信
- タイムスタンプなどの非改ざん性保証機能で締結日時を証明
- データはクラウドに保管され、いつでも確認可能
上記のように、紙の契約書と同等の管理・運用が実現可能です。電子契約は手間のかかる紙の契約手続きを大幅に簡素化し、業務のスピードと安全性を向上させてくれるでしょう。
<関連記事>電子署名とは?ビジネスにおけるメリットや仕組み、注意点を解説
電子契約の種類|立会人型と当事者型の違い
電子契約サービスには「立会人型」と「当事者型」の2種類があります。契約の署名者や電子署名の方式により、証拠力や信頼性、対応できる契約書の種類が異なるためです。
それぞれの特徴は以下の通りです。
立会人型(電子サイン方式)
- 電子契約サービス事業者が「第三者」として署名をサポート
- 一般的な業務委託契約やNDAなど、日常業務で使いやすい
当事者型(電子署名方式)
- 契約当事者がそれぞれ電子証明書を持ち署名をおこなう
- 実印相当の証拠力が求められる契約(例:不動産、M&A)向け
自社の契約内容やリスクレベルに応じて、どちらの方式が適しているかを見極めることが、電子契約サービス選びの第一歩です。
電子契約システムの選び方|8つの比較ポイント
電子契約システムは、契約業務を効率化し、ペーパーレス化を進めるための有力なツールです。
しかし、サービスごとに機能や料金体系、対応範囲が大きく異なるため、「どれを選べばいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
本章では、自社に合った電子契約システムを選ぶために押さえておきたい8つの比較ポイントを詳しく解説します。
- 機能の充実度
- コスト構造(初期費用・月額・従量課金)
- 操作性
- サポート体制
- セキュリティと法的対応
- 導入実績と対応業種
- 取引先の対応状況
- 契約書管理などの付加価値
1.機能の充実度
電子契約システムは、自社に必要な機能が備わっているかを基準に選ぶのが重要です。
搭載されている機能はシステムごとに異なるため、目的に合わないツールを導入してしまうと、逆にコストや手間が増えてしまう可能性があります。
例えば、以下のようなニーズごとにおすすめの機能が異なります。
- ニース:法的効力を担保したい
おすすめの機能例:電子署名、タイムスタンプ、改ざん防止機能 - ニーズ:業務効率を重視したい
おすすめの機能例:契約テンプレート登録、自動通知機能、ワークフロー設定 - ニーズ:契約書を一元管理したい
おすすめの機能例:クラウド保存、検索機能、フォルダ分類、アクセス権設定 - ニーズ:社内の承認フローを簡素化したい
おすすめの機能例:多段階承認、通知・リマインド機能、履歴ログの可視化
導入前に、自社の業務に必要な機能を整理したうえで、比較サイトや公式サイトで各サービスの機能詳細を確認し、最適な電子契約システムを選定しましょう。
2.コスト構造(初期費用・月額・従量課金)
電子契約システムを選ぶ際は、自社の契約件数や予算に合わせて最適な料金体系を選ぶことが重要です。多くの電子契約サービスでは、月額基本料+従量課金型や定額制(月額固定型)などの料金体系が用意されています。
契約書の送信数やユーザー数によって料金が変動するため、導入前にコスト構造をしっかり比較・確認しておく必要があります。
例えば、月額5,000円〜1万円前後の基本料金に加え、1通あたり100〜200円の送信料金が発生するプランが一般的です。一方で、契約件数が少ない企業向けに、無料プランや初期費用0円で始められるサービスも登場しており、コストを抑えながらスモールスタートすることも可能です。
契約業務の規模や頻度に応じて、無理のない料金プランを選ぶことが、電子契約システムの導入成功に直結します。まずは月額費用・従量課金・無料プランの有無を整理し、自社に最適なサービスを選定しましょう。
3.操作性
電子契約システムを選ぶ際は、誰でも迷わず使える操作性が重要です。いくら機能が充実していても、操作が複雑だと現場では使いこなせず、導入の効果が薄れてしまいます。特に、PC操作に不慣れな従業員がいる場合、操作性は選定時の重要な比較ポイントです。
操作性を見極めるポイントは、以下の通りです。
- 画面がシンプルで、直感的に操作できるインターフェース
- 契約書のアップロードや送信が少ないステップで完結する設計
- 操作ミスを防ぐナビゲーションやアラート表示
- 操作マニュアルやオンラインサポートが整っている
- 利用者が複数でも、混乱せずに使える権限設定やUI設計
導入前に無料トライアルやデモ利用で実際に操作してみると、ユーザー目線での使いやすさを確認できます。
4.対応言語とサポート体制
電子契約システムを選ぶ際は、対応言語やサポート体制にも注目しましょう。操作中に困ったときや、不具合が発生したときにすぐに問い合わせできるかどうかは、システムの使いやすさや定着率に大きく影響します。また、海外企業との契約がある場合は、英語など多言語対応がされていないと、実務に支障が出る場合もあるでしょう。
チェックしておきたいポイントは、以下の通りです。
- 英語など、取引先の使用言語に対応しているか
- サポート窓口が整っているか(電話・メール・チャットなど)
- 対応時間帯やサポート品質が自社に合っているか
- ヘルプページやマニュアルが充実しているか
ソフト面の対応が整っているシステムを選ぶと、導入後も安心して運用できます。
5.セキュリティの強度と管理体制
契約書を電子で管理するうえで、セキュリティは最も重要な検討ポイントのひとつです。電子契約では、氏名・住所・金融情報などの個人情報や、企業の営業機密を含む契約書を扱います。これらが漏えい・改ざんされると、信用失墜や損害賠償といった重大なリスクにつながりかねません。
以下のようなセキュリティ対策が備わっているシステムを選ぶのが重要です。
- 通信内容の暗号化(SSL/TLS)
- 契約ファイルのクラウド保管時のデータ暗号化
- ユーザーごとのアクセス制御とログイン管理
- 操作ログの保存と監査対応
- タイムスタンプや電子署名による改ざん防止
加えて、ISO27001やSOC2などの第三者認証の取得状況も、セキュリティ体制の信頼性を測る指標になります。現場のIT担当者や情報管理責任者とも連携し、導入候補のセキュリティ機能を細かく比較しておきましょう。
6. 法的対応(電子署名法・電子帳簿保存法など)
電子契約を法的に有効なものとするには、国内法や規制に対応しているかどうかの確認が欠かせません。電子契約に関係する主な法令は以下の2つです。
電子署名法
- 電子署名が「本人によるもの」であると認められる要件を規定。署名の真正性を担保する根拠になる
電子帳簿保存法
- 税務調査などに備え、契約書等の電子データ保存に関する保存要件・検索性・改ざん防止などの基準を定めた法律
上記の法令に対応していないサービスを選んでしまうと、契約が無効になるリスクや、税務調査で証拠と認められないリスクが発生します。
導入を検討する際は、以下をチェックしましょう。
- 電子署名法に準拠した署名機能(本人性を担保)
- 電子帳簿保存法に対応したデータ保存・検索機能
- JIIMA認証など、第三者機関の法的適合認証の有無
契約の証拠力を重視する法務部門や管理部門にとって、法的対応は導入判断の大きな基準となります。
7.導入実績と対応業種
電子契約システムを選ぶ際は、導入実績と対応業種をチェックすると、自社に合ったサービスを見つけやすくなります。他社の導入事例は、システムの信頼性や汎用性を示す大きな指標です。特に自社と同業種・同規模の企業が利用している場合は、業務にフィットしやすい可能性が高まります。
例えば、次のような観点を確認しましょう。
- 同じ業種(例:IT、製造、小売など)での導入事例の有無
- 企業規模に応じた対応実績(中小企業〜大手まで)
- 対応業界に特化した機能(例:不動産、金融、士業など)
- 公式サイトに掲載されている導入企業一覧や利用インタビュー
選定前には、公式サイトや比較サービスで「導入実績」「業種対応」「活用シーン」の詳細を確認し、自社と近いケースの有無をしっかりチェックしましょう。
8.取引先の対応状況
電子契約システムを導入する際は、自社だけでなく取引先が無理なく対応できるかも重要です。電子契約は、契約当事者双方の合意によって成立します。自社にとって利便性の高いサービスであっても、相手先の環境や運用フローに合わなければ、導入後に利用が進まない可能性があります。
特に注意すべきポイントは、以下の通りです。
- 相手側にアカウント登録や初期費用が必要な場合、負担に感じられることがある
- 電子契約に不慣れな企業では、操作が複雑だと受け入れられにくい
- 紙での締結を前提とした社内ルールが残っている企業もある
取引先の登録が不要なサービスや、直感的に操作できるUIを備えたツールを選ぶといいでしょう。導入実績が豊富で認知度の高いサービスであれば、取引先にも安心感を持ってもらいやすくなります。
9.契約書管理などの付加価値
電子契約システムを選ぶ際は、契約書管理などの付加価値があるかどうかも確認しておくと良いでしょう。契約締結後の書類管理まで一貫して対応できるシステムであれば、別途文書管理ツールを用意する必要がなくなり、業務効率が大きく向上します。
例えば、以下のような機能が搭載されていると、契約業務全体の負担が軽減されます。
- 締結済み契約書のクラウド保存・一元管理
- 契約書の検索機能やフォルダ分け
- アクセス権限の設定や閲覧履歴の確認
- 契約期限の通知・アラート機能
付加価値機能があれば、契約の作成から保管・管理までを一元化でき、入力や確認の手間を大幅に削減できます。特にBtoB間で契約業務を効率化したい企業は、管理機能の役割や導入後の使い方、オプション機能の有無なども含めて徹底的に確認しておくと安心です。
<関連記事>契約書管理システムの魅力・選び方を解説
シンプルで使いやすさこだわりの電子契約システム3選
電子契約システムは、業務効率化やコスト削減に役立つ一方で、操作に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本章では、シンプルで使いやすさにこだわりのある電子契約システムを厳選してご紹介します。
- LegalOn Cloudサイン
- freeeサイン
- GMOサイン
1.LegalOn Cloudサイン
LegalOn Cloudサインは、操作ミスや契約トラブルを防ぎたい企業にとって、安心・安全な電子契約ツールです。直感的な操作性とミスを未然に防ぐ機能が充実しており、初めての方でも安心して使える設計です。
以下の機能や特徴が、契約業務をスムーズかつ確実に進めるうえで役立ちます。
- 差分比較機能
送信前に契約書の変更点を自動でチェック可能 - シンプルなUI
シンプルな画面で誰でもすぐに操作できる - テンプレート連携
自社の契約書ひな形を活用し作成から締結まで一気通貫で対応可能 - プロセスの可視化
締結フローを見える化し、進行状況の把握や漏れの防止に効果的 - アクセス管理
社内の編集・閲覧権限を柔軟に設定でき、情報漏洩リスクを低減 - バージョン管理
契約書の修正経緯を締結後も確認でき、透明性の高い運用が可能 - 自動フォルダ分け
書類は自動で分類され、検索や管理がラクになる
LegalOn Cloudサインは、実務に即した機能とシンプルな使いやすさを兼ね備えた、電子契約の導入・定着を支援する頼れる選択肢です。
2. freeeサイン
freeeサインは、契約業務の送信・締結だけでなく、作成・保管まで対応できる、オールインワン型の電子契約サービスです。シンプルな操作性に加え、他サービスとの連携など企業の実務に即した機能が揃っています。
freeeサインの代表的な機能と特徴は、以下の通りです。
- Wordテンプレート
対応Google Docsで作成・登録でき、美しい文書を簡単に作成 - コンプライアンス強化
上長承認・権限管理・閲覧制限で社内統制と個人情報保護をサポート - 文書の一括保管
紙の契約書も電子ファイルとして保存・管理が可能 - 多彩な送信手段
メール・SMS・URL送信に対応 - 他サービスとの連携
Salesforce・kintone・他freee製品と連携し、業務を自動化 - 対面契約対応
タブレット1台で店舗や現場でもその場で契約が完結
参考:freeeサイン
freeeサインは、あらゆる業種・現場にフィットし、かんたん操作と高機能のバランスに優れた使い勝手のいい電子契約システムです。
3. GMOサイン
GMOサインは、法的信頼性とセキュリティ性に優れた電子契約システムです。特に手手書きサインや対面での署名が必要な企業におすすめです。
GMOサインの代表的な機能は、以下の通りです。
- 実印レベルの電子署名
電子認証局による本人確認済みの署名で、法人実印に相当する法的効力がある - タイムスタンプ
電子文書の証拠力を強めるタイムスタンプを付与可能 - アクセス制限・SSO連携
IP制限や認証連携などで社内統制を強化 - OR署名
三者以上の契約や複数署名者への柔軟な送信設定に対応 - 拡張機能(決済・対面署名)
手書きサインや契約と同時の請求処理に対応
参考:GMOサイン
GMOサインは、契約の正確性・安全性を何より重視したい企業にとって、使いやすくて信頼できる選択肢のひとつといえるでしょう。
【比較表付きまとめ】電子契約システムおすすめ10選
電子契約システムは、契約業務の効率化やコスト削減に大きく貢献しますが、サービスによって料金体系や機能、導入のしやすさは大きく異なります。本章では、電子契約システムの中でも特に評価の高い10サービスを厳選してご紹介します。
料金・機能・対応範囲・セキュリティなどのポイントを比較しながら、自社にぴったりのサービスを見つけていただけるような構成です。まずは、各サービスの主なスペックを比較表でご確認ください。

1. クラウドサイン|国内シェアNo.1の定番ツール
クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する立会人型の電子契約システムで、国内導入実績250万社以上、累計契約送信件数1,000万件超の実績を誇ります。
月額11,000円(税込)〜で利用可能で、契約書の送信件数に応じた従量課金も採用されています。法務リスクが高い業界や、法務部門を持つ中〜大規模企業に特におすすめです。
クラウドサインの主な特徴
- 弁護士監修&電子署名法準拠で、証拠力・法的効力を高水準で担保
- タイムスタンプ付きの電子署名で改ざん防止と本人確認が可能
- 操作性が高く、マニュアル不要で誰でも簡単に使える
- IP制限・2段階認証・アクセス権設定など法人向けセキュリティも充実
- SlackやSalesforceなどとのAPI連携で業務効率化にも貢献
サービス詳細
- 提供会社:弁護士ドットコム株式会社
- 月額料金(税込):月額10,000円〜
- 従量課金:あり(1通あたり220円)
- 電子署名型:立会人型
- 主な機能:契約テンプレ、一括送信、API連携、承認権限など
- 法的対応:電子署名法、電子帳簿保存法
- セキュリティ:ISO27001・SOC2、2段階認証、IP制限、暗号化通信、監査ログ対応
- 無料プラン:あり(月3件・1ユーザー)
参考:クラウドサイン
2. freeeサイン|契約業務をまるごと効率化
freeeサインは、電子契約の送信・締結だけでなく、文書の作成・AIレビュー・保管まで、契約業務全体をカバーできる統合型の電子契約サービスです。
ひな形機能やSalesforceなどとの外部連携、法務対応にも配慮したセキュリティ機能が充実しており、契約管理の効率化に貢献します。freeeサインは、月間契約数が限られている企業や、既存の業務システムと連携させたい企業におすすめです。
freeeサインの主な特徴
- 送信・締結・保管・管理までを1つのサービスで完結
- ひな形作成やAIレビューなど、契約業務の工数削減を支援
- Salesforceやkintoneなど他ツールとの柔軟な連携が可能
- 月額5,980円(税込)〜の手頃な料金体系+無料サイン枠あり
- 顧問契約、雇用契約、業務委託契約など多様な業種・業務に対応
サービス詳細
- 提供会社:freee株式会社
- 月額料金(税込):月額5,980円〜(Starterプラン)
- 従量課金:あり(1通あたり100円〜)
- 電子署名型:立会人型
- 主な機能:テンプレート登録、外部連携(Salesforce、kintone)など
- 法的対応:電子署名法、電子帳簿保存法に準拠
- セキュリティ:暗号化通信、アクセス制限、ログ管理
- 無料プラン:あり(Starter:月50通・ユーザー1名まで)
参考:freeeサイン
3. GMOサイン|コストを抑えたい中小企業に最適
GMOサインは、GMOグローバルサインが提供する電子契約サービスで、導入企業数350万社以上、累計送信件数4,000万件超を誇る国内有数の実績を持ちます。
月額無料のフリープランから、立会人型・当事者型の電子署名が選べる有料プランまで幅広く用意されており、1件あたり100円の送信料で使える圧倒的なコストパフォーマンスが魅力です。法的対応・セキュリティ体制・導入コストのバランスを重視したい中小企業や、送信件数が限られる個人事業主におすすめです。
GMOサインの主な特徴
- 1件100円(税込)の従量課金で導入しやすく、送信数が多くてもコストを抑えやすい
- 権限管理やテンプレート作成、検索・保管機能など、充実した基本機能を標準搭載
- フリープランあり(月5件まで送信無料)、中小企業・個人事業主にも人気
- 立会人型/当事者型/マイナンバー実印など、用途に応じた署名方法が選択可能
- ISO27001・SOC2などの国際基準に準拠したセキュリティ体制
サービス詳細
- 提供会社:GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
- 月額料金(税込): 有料プラン:月額9,680円〜
- 従量課金:あり(立会人型:110円/件、当事者型:330円/件)
- 電子署名型:立会人型、当事者型、マイナンバー
- 主な機能:テンプレート、一括送信、押印・閲覧権限、検索・保管、スマホ対応、外部連携
- 法的対応:電子署名法準拠、JIIMA認証
- セキュリティ:ISO27001、SOC2 Type2、IP制限、暗号化通信など
- 無料プラン:あり(月5件・1ユーザー)
参考:GMOサイン
4.Docusign(ドキュサイン)|グローバル対応・世界シェアNo.1
Docusignは、180ヵ国以上・44言語対応という圧倒的な国際対応力を誇る、世界シェアNo.1の電子署名サービスです。
契約の作成・署名・管理にとどまらず、ワークフローの自動化や本人確認、契約分析まで対応できるため、グローバル展開企業に多く採用されています。Docusignは、グローバル対応やセキュリティ重視、外部ツール連携を求める企業におすすめです。
Docusignの主な特徴
- 世界中で1,600,000社以上に導入され、1日数百万件の取引をサポート
- SalesforceやGoogle Workspaceなど900以上の外部サービスと連携可能
- ISO 27001、SOC2 Type2などの国際的なセキュリティ認証を取得
- スマホやタブレット対応で、直感的な操作が可能
- 英語・日本語など14言語での送信と、44言語での署名に対応
サービス詳細
- 提供会社:Docusign Inc.
- 月額料金(税込):月額1,333円〜
- 従量課金:年間送信数上限あり(例:100通/年)※超過時の課金有
- 電子署名型:立会人型、当事者型
- 主な機能:テンプレート、契約管理、ワークフロー自動化、API連携など
- 法的対応:電子署名法対応(日本含む180以上の国・地域で適法)
- セキュリティ:ISO27001、SOC2 Type2など
- 無料プラン:30日間トライアルあり
参考:Docusign
5.Adobe Acrobat Sign|PDF契約書との相性が抜群
Adobe Acrobat Signは、Adobe社が提供する電子契約サービスで、既存のAcrobat製品との高い連携性が特徴です。PDFをベースにした契約フローをワンストップで管理でき、電子サイン・編集・共有・追跡を一括で行えます。
PDF文書の電子契約に特化しているため、契約書のやり取りが多い企業や、Adobe製品をすでに活用している法人におすすめです。
Acrobat Signの主な特徴
- Acrobat PDFとのシームレスな統合。電子契約から編集・共有・追跡まで一元管理
- Microsoft 365・Salesforce・Boxなど、主要アプリとの連携がスムーズ
- フォームのテンプレート保存や進捗トラッキングなど、実務的な機能が充実
- 高度なコンプライアンス対応(HIPAA、GLBA、FDA CFR 21など)
- Adobeブランドの信頼性とサポート体制あり
サービス詳細
- 提供会社:Adobe Inc.
- 月額料金(税込):月額1,848円〜
- 従量課金:なし(送信回数制限ありプランあり)
- 電子署名型:立会人型、当事者型
- 主な機能:PDF編集・作成、電子サイン、署名追跡、テンプレート、アプリ連携など
- 法的対応:日本を含む各国の電子署名法に準拠(HIPAA・GLBA・FDA規制などにも対応)
- セキュリティ:ISO 27001、SOC2、21CFR、Part11など
- 無料プラン:14日間の無料体験あり
参考:Acrobat Sign
6.マネーフォワード クラウド契約|経理・会計クラウドとの連携に強み
マネーフォワード クラウド契約は、会計・経費・勤怠などのクラウド型業務支援ツールを多数展開するマネーフォワード社が提供する電子契約サービスです。
契約書の作成からワークフロー、締結、管理までをワンストップで提供し、バックオフィス全体の業務効率化が図れます。
送信・保管にかかる追加費用がない定額制で、契約件数が多い企業やコスト管理を重視したい中小企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド契約の主な特徴
- 契約送信・保管料が0円。件数無制限で定額利用が可能
- 他社電子契約・紙契約のデータも含めた一元管理に対応(※特許取得済)
- 契約の進捗状況や社内承認の履歴を可視化でき、内部統制にも有効
- マネーフォワード会計・経費精算などとの連携でバックオフィス全体を最適化
- Slack・Salesforceなどの外部サービスともAPI連携可能
サービス詳細
- 提供会社:株式会社マネーフォワード
- 月額料金(税込):月額2,980円〜
- 従量課金:なし(送信・保管件数無制限)
- 電子署名型:立会人型
- 主な機能:テンプレート作成、申請・承認ワークフロー、一元管理、期限アラートなど
- 法的対応:電子帳簿保存法対応
- セキュリティ:IPアドレス制限、履歴管理、アクセス権設定
- 無料プラン:要問い合わせ
7.WAN-Sign|紙の契約書も一元管理できるハイブリッド型
WAN-Signは、NXワンビシアーカイブズが提供する電子契約サービスで、紙と電子の契約書を一元管理できるハイブリッド型が大きな特長です。
契約締結・管理・保管・内部統制を1つのシステムで完結させ、初期費用・月額費用0円から導入可能なコストパフォーマンスに優れたサービスです。社内に紙文化が残る企業や、電子契約導入のハードルを下げたい中堅・大企業に特におすすめです。
WAN-Signの主な特徴
- 紙・電子の契約書を一元管理可能(特許取得済)
- 無料プランでも実用的:認印版10件・実印版3件まで毎月無料
- 電子契約・管理・セキュリティ機能を追加費用なしで標準搭載
- 外部サービスとのAPI連携やIPアドレス制限も対応
- 情報管理のプロであるNXワンビシアーカイブズによる安心のサポート体制
サービス詳細
- 提供会社:NXワンビシアーカイブズ株式会社
- 月額料金(税込): 0円〜(プランにより異なる)
- 従量課金:あり(例:認印版100円/件、実印版300円/件)※無料枠あり
- 電子署名型:立会人型、当事者型
- 主な機能:書類テンプレート、送信・締結、一元管理、ユーザー権限管理など
- 法的対応:電子帳簿保存法、電子署名法
- セキュリティ:暗号化、IP制限、権限設定、ISMS取得済み
- 無料プラン:あり(月10件の認印送信、3件の実印締結、10件の文書管理が可能)
参考:WAN-Sign
8.契約大臣|とにかく低コストで始めたい企業向け
契約大臣は、月額4,000円台から始められるコスト重視型の電子契約サービスです。初期費用ゼロ・送信相手の登録不要・テンプレート完備と、電子契約が初めての企業にもやさしい設計が特徴です。契約書の送信数が月50件以下の中小企業・士業事務所に特におすすめです。
契約大臣の主な特徴
- 月額4,400円(税込)から利用可能な低価格設計
- 契約書の送信数に応じたシンプルな従量課金制
- ベーシックプラン以上はユーザー数無制限
- 受信側は登録不要で相手に負担をかけない運用が可能
- 見たまま操作の直感UIと、契約テンプレート完備
- 電子帳簿保存法・電子署名法に準拠し、法的安心性も◎
サービス詳細
- 提供会社:株式会社インフォマート
- 月額料金(税込):月額4,400円〜
- 従量課金:あり(電子サイン無料、電子署名220円/件)(プランにより変動)
- 電子署名型:立会人型
- 主な機能:テンプレート、グループ管理、2要素認証、契約書保管など
- 法的対応:電子署名法、電子帳簿保存法
- セキュリティ:暗号化通信、ファイアウォール、セキュリティ診断
- 無料プラン:あり(送信5件まで・1ユーザー)
参考:契約大臣
9.ベクターサイン|シンプル操作&国産クラウド
ベクターサインは、初期費用・基本料金が一切不要で利用できる国産クラウド型の電子契約サービスです。
画面の案内に沿ってクリックするだけの簡単操作で、相手先にアカウント登録や負担をかけずに契約を締結できます。まずは使ってみたい企業や、書類のやり取り頻度が少ない事業者に特におすすめのシンプル型電子契約サービスです。
ベクターサインの主な特徴
- 初期費用・基本料金0円で導入ハードルが低い
- 電子署名・タイムスタンプをワンクリックで付与可能
- 他社で締結した文書もまとめて管理・保管OK
- 文書保管数・ユーザー数は完全無制限
- 使った分だけ支払う従量課金制(440円/通)
- 年間プラン・月間プランなど柔軟な選択肢
サービス詳細
- 提供会社:株式会社ベクター
- 月額料金(税込): 0円(基本料)
- 従量課金:あり(送信料:400円/通+税)
- 電子署名型:立会人型
- 主な機能:電子署名、タイムスタンプ、外部文書の一元管理など
- 法的対応:電子署名法、電子帳簿保存法
- セキュリティ:通信暗号化、アクセス制限、改ざん防止機能を標準搭載
- 無料プラン:基本料金0円、初期費用なし
参考:ベクターサイン
10.LegalOn Cloud|AIで契約審査までカバー
LegalOn Cloudは、契約書の審査・締結・管理だけでなく、法務相談や法改正対応までを一気通貫で行えるAI搭載の法務プラットフォームです。
LegalOn Cloudは電子契約システムを搭載したAI法務クラウドであり、単体の電子契約サービスとは異なり、締結予定の契約書と審査完了後の契約書の差分比較や、締結済み契約書の一元管理まで、すべて同一システム上で対応可能です。
契約リスクの抽出、条文比較・修正、ひな形管理など、法務のあらゆる業務を効率化・高度化できます。契約審査の精度とスピードを両立させたい企業に特におすすめです。
LegalOn Cloudの主な特徴
- 契約審査・管理・リスクチェックを1つのシステムで完結
- AIが条文差分やリスクを自動抽出、修正文案も提案
- 締結済み契約書の一元管理、更新通知、法改正対応も標準搭載
- 他社ひな形・自社テンプレートとの条文比較機能も充実
- 外部電子契約サービス(クラウドサイン、GMOサイン等)と連携可能
- 高度な非改ざん性を保証機能とセキュリティ対策(Google Cloud、ISMS、SSO、IP制限等)
サービス詳細
- 提供会社:LegalOn Technologies株式会社
- 月額料金(税込):月額11,000円〜
- 従量課金:アカウントごとに220円〜330円(機能モジュールにより変動)
- 電子署名型:立会人型(サインモジュールで利用可能)
- 主な機能:電子サイン、バージョン管理、契約書比較、契約審査AI、契約管理、テンプレ利用、リスクチェック、更新期限アラート
- 法的対応:電子帳簿保存法対応(JIIMA認証)、法令順守チェック機能あり
- セキュリティ:ISMS、SSO、アクセス制限、改ざん防止機能を標準搭載、脆弱性診断実施済み
電子契約システム導入時に見落としがちな3つの注意点
電子契約システムの導入は、業務効率やコスト削減に大きく貢献しますが、導入前に確認すべき注意点も存在します。制度上の制約や法令対応、相手先との調整を怠ると、思わぬトラブルや手戻りにつながる可能性があるためです。
ここでは、見落とされがちな3つのポイントについてわかりやすく解説します。
契約書の種類によっては電子化できないケースがある
電子契約は便利な一方、すべての契約書に適用できるわけではありません。一部の契約は、法律上、紙での締結が義務付けられています。
電子契約の有効性は「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」により認められていますが、一部の契約は法令で「書面(紙)かつ公正証書」での締結が必要と明記されています。
出典:デジタル庁|電子署名
本人の意思確認や公的証明が特に重視される契約であり、電子化が制限されているのです。現在、電子化が認められていない契約書の例は以下の通りです。
- 事業用定期借地契約(借地借家法第23条)
- 任意後見契約(任意後見契約に関する法律第3条)
- 企業担保権の設定契約(登記実務上、書面提出が必要)
- その他、公正証書での締結が義務付けられた契約
電子契約システムを導入する前に、自社で扱う契約書の種類と電子化の可否を必ず確認しましょう。電子契約と紙契約の併用が必要になるケースもあるため、法務や関連部署と連携した事前チェックが欠かせません。
電子署名法・電子帳簿保存法などの法令対応が必要
電子契約を導入する際は、電子署名法や電子帳簿保存法など、関連法令への対応が欠かせません。これらの法令に準拠することで、契約の法的効力や保存データの信頼性が担保されます。
例えば、以下のような観点からの対応が求められます。
- 電子署名法第3条に基づき、本人による電子署名があれば「真正に成立した」と推定される
- 電子帳簿保存法により、契約書などの電子データは改ざん防止・検索性の確保などの要件を満たして保存する必要がある
- 税務調査時などにおいて、電子保存された契約書が証拠資料として認められるかどうかに関わる
電子契約システムを選ぶ際は、導入後の契約管理・法令対応まで視野に入れて検討するのが重要です。
導入には相手先の合意と協力が必要
電子契約の導入を円滑に進めるには、契約相手の理解と協力が欠かせません。電子契約は一方的に締結できる仕組みではなく、相手先が電子契約に対応できる体制を整えていることが前提のためです。
具体的には、以下のようなケースが想定されます。
- 相手企業の承認フローが紙ベースに限定されている
- 法務部の判断で「電子契約は不可」としている企業がある
- 海外企業など、電子署名の有効性に慎重な取引先がある
- 中小企業で電子契約ツールそのものを導入していない
- 契約相手が「原本返送」など慣習的なやり取りを重視している
導入前には、主要な取引先の運用状況を確認し、必要に応じて説明や調整を進めながら合意形成を図ることが重要です。
「電子契約の導入効果を最大化するポイント~業務改善を成功させる契約管理フロー」
電子契約システムの導入手順|5つのステップで解説
電子契約システムは、業務の効率化やコスト削減に大きく大きく役立ちますが、導入を成功させるには手順が重要です。十分な準備や比較検討をせずに導入してしまうと、運用面でのトラブルや、現場での混乱を招く恐れがあります。
本章では、電子契約システムをスムーズに導入・定着させるための5つのステップをわかりやすく解説します。初めて導入を検討している方も、すでに比較段階に入っている方も、ぜひ参考にしてください。
ステップ1:導入目的を明確にする
電子契約システムの導入を成功させるには、最初に「なぜ導入するのか?」という目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、社内での調整もうまく進まず、最悪の場合は導入自体が立ち消えになるリスクがあるためです。
以下のように、自社の課題や改善したい業務を整理することで、導入の目的がクリアになります。
- 印紙税のコストを削減したい
- 契約書の保管・検索を効率化したい
- 契約締結までのスピードを上げたい
- 遠隔地とのやり取りをオンラインで完結させたい
- 紙の契約書の管理に限界を感じている
まずは、導入の背景や解決したい課題を明確化し、関係者と共通認識を持つことから始めましょう。
ステップ2:複数サービスを比較・選定する
電子契約システムを選ぶときは、導入目的に合ったものを比較しながら選びましょう。サービスごとに「料金」「機能」「対応範囲」に違いがあるため、目的に合わないものを選ぶと、使いにくさや無駄なコストにつながります。
具体的に比較すべきポイントは、以下の通りです。
- 初期費用・月額費用の有無(定額・従量課金など)
- 無料トライアルの有無
- セキュリティ対応(電子署名法、電子帳簿保存法など)
- 連携できる他システムの種類(会計、ワークフロー等)
- 紙契約・他社システムで締結した契約書の取り込み可否
3〜4社を候補に絞って、比較表などで整理しながら選ぶのが効果的です。
ステップ3:関係部署と調整し、ルールを整備する
電子契約をスムーズに導入・運用するには、関係部署と事前に調整し、ルールを整えておくことが重要です。紙からデジタルに変わることで、承認フローや役割分担に変化が生じるためです。ルールが曖昧だと、現場で混乱を招くおそれがあります。
決めておくべきルールの例は、以下の通りです。
- 誰が契約書を作成・送信するのか
- どの種類の契約に電子契約を使うか
- 締結後の保存・管理方法(保管場所・アクセス権限など)
- 紙契約と電子契約の使い分けルール
法務・総務・営業など、関係部署と連携しながら全社で使える体制を整えましょう。
ステップ4:トライアル導入〜本稼働
電子契約システムは、いきなり全社展開するのではなく、まずはトライアル導入から始めるのがおすすめです。実際に使ってみることで、操作性や社内フローとの相性など、事前には見えなかった課題に気づけます。
例えば、以下のような進め方が効果的です。
- 一部の部署でパイロット導入を実施
- 利用者から使用感や不便な点をヒアリング
- フローや運用ルールを改善してから全社展開
本格導入の前に段階を踏んで検証することで、混乱を防ぎ、社内定着もしやすくなります。導入後は、管理者の選定や権限設定、保存ルールの整備などもあわせて行いましょう。
ステップ5:社内浸透と取引先へのフォローアップを行う
電子契約を社内に定着させ、社外とも円滑に運用するためには、導入後のサポート体制をしっかり整えることが重要です。社内・社外問わず、利用者の理解と納得がないまま導入を進めると、定着せず形骸化してしまう恐れがあります。
社内・社外で取り組むべきフォローアップ施策は、以下の通りです。
社内向け
- 操作マニュアルや利用フローを配布して社員の理解を促進
- 経理・営業・人事など契約業務の多い部署には講習会を実施
- サービス提供会社の導入支援(初期設定・操作説明会)を活用
- 社内ポータルやチャットに「よくある質問集」や問い合わせ先を設置
取引先向け
- 電子契約の概要や操作方法をまとめた説明資料を事前に送付
- 相手にアカウント登録を求めないサービスを選ぶことで負担を軽減
- 初回はトライアル契約などで操作感を確認してもらう
- 紙文化が根強い企業には、移行期間や併用ルールの明示も検討
導入後の社内定着と取引先の理解を丁寧に進めることで、電子契約のメリットを最大限に活かせる体制を築きましょう。
電子契約システムに関するよくある質問
本章では、実際によく寄せられる質問をピックアップし、わかりやすく解説しています。導入前の不安を解消し、スムーズな活用につなげるために、ぜひ参考にしてください。
電子印鑑と電子署名の違いは?
電子署名は法的効力を持つ認証手段である一方、電子印鑑は見た目の印影を示すだけで、法律上の効力はありません。
電子署名は、電子署名法に基づいて「本人性」や「改ざんされていないこと」を保証する仕組みです。認定された第三者(認定認証局)によって発行される電子証明書を用いるため、契約時の証拠力があります。
一方、電子印鑑はスタンプ画像などによる視覚的な確認印であり、本人確認や改ざん防止の機能はありません。社内文書や簡易なやり取りに用いられるケースが中心です。
電子署名が使われる場面
- NDA(秘密保持契約)
- 業務委託契約書
- 雇用契約書など、対外的な契約
電子印鑑が使われる場面
- 稟議書への承認印
- 社内回覧文書
- 見積書や発注書への印影の挿入など
対外的な契約や法的な証拠力が求められる文書には電子署名を、社内の承認や簡易な確認には電子印鑑を活用しましょう。
スマホやタブレットでも電子契約はできますか?
スマホやタブレットでも問題なく電子契約が可能です。
多くの電子契約システムは、クラウド型で提供されており、Webブラウザや専用アプリからスマートデバイスで操作できるよう設計されています。
近年はテレワークの普及により、マルチデバイス対応が標準機能となることが多いです。
スマホやタブレット対応の電子契約システムを使えば、インターネット環境さえあれば、どこにいても契約業務をスムーズに進められます。
紙の契約書やスキャンした書類も一緒に管理できますか?
電子契約システムによっては、紙の契約書やスキャンしたPDFなども一元管理できます。
電子契約の導入によって契約書のデジタル化が進んでいますが、過去に締結された紙の契約書や、電子契約以外で取り交わした契約書も業務上は重要な文書です。分けて管理していると、検索性や更新管理の面で手間やミスが発生しやすくなります。
例えば、LegalOn Cloudでは、電子契約書とあわせて紙の契約書のスキャンデータ(PDFなど)もアップロードして一元管理することが可能です。契約内容に関するメタデータ(契約日・更新期限など)を登録すれば、更新通知や検索も電子契約書と同様に行えます。
電子契約システムを選ぶ際は、紙の契約書や他社で締結したファイルもまとめて管理できる機能があるかを確認すると、より実務に即した運用が可能になります。
電子契約は本当に印紙税がかからないの?
電子契約で作成された契約書には、基本的に印紙税はかかりません。
印紙税は、紙の文書に対して課税されるものであり、電子データでやり取りされる契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当しないためです。
印紙税法第2条および第3条では、別表第1に掲げる文書を作成した場合に印紙税を課すと定められており、これはあくまで紙の文書が対象となっています。
以下のような紙の契約書には本来、印紙税が必要です。
- 2号文書:請負契約書
- 7号文書:業務委託契約書や代理店契約書などの基本契約書
- 17号文書:領収書など売上代金の受取書
電子契約で締結すれば、紙の文書を作成していないことになるため、印紙税を納める義務がなくなります。印紙税のコストを削減したい企業は、電子契約を導入することで確実に効果が得られます。
しかし、運用にあたっては契約書を紙に出力しない運用を徹底することが大切です。社内ルールや取引先との調整も含めて、電子契約への移行を進めましょう。
法務のデジタル化を成功させる第一歩は、電子契約システムの選定から
本記事では、電子契約システムの選び方やおすすめのサービスについて詳しく解説しました。電子契約を導入すると、契約締結までのスピードが格段に向上し、印紙税や郵送コストの削減、管理工数の軽減など、多くの業務改善効果が期待できます。
導入の際は、自社の業務に本当に必要な機能やコスト感、契約書管理の有無、導入実績などをしっかり比較検討するのが大切です。また、契約業務のデジタル化をきっかけに、法務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めていく視点も重要です。
闇雲にリーガルテックを導入するのではなく、効果的に業務を支援してくれるツールを選びましょう。LegalOn Cloudは、AIによる契約審査から管理・法改正対応までを一貫してサポートする、次世代型の法務支援プラットフォームです。豊富な機能を必要に応じて柔軟に導入できるため、はじめてリーガルテックに取り組む企業にも最適です。法務業務を効率化し、リスクを最小限に抑えるためにも、ぜひ導入を検討してみてください。
<関連記事>
電子契約とは?導入するメリットや注意点、関係する法律を詳しく解説
電子契約のやり方を解説!メリットやデメリット、システム導入や選定方法がわかる
契約書を電子化するメリットとは?電子契約システムの導入方法や注意点を解説