労働者派遣法の基礎知識
はじめに、労働者派遣法とはどのような法律か、制定された目的や適用対象などを解説します。
労働者派遣法とは
労働者派遣法とは、派遣労働者の権利保護、労働者派遣事業の適切な運営を実現するべく、1985年に制定され1986年に施行された法律です。正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
法の目的と基本理念
労働者派遣法1条では、法制定の目的について次のように記されています。
労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。(労働者派遣法1条)
まとめると、目的は以下の3点となります。
- 派遣労働者が安心して働けるように、派遣労働者の権利保護を強化する
- 労働者派遣事業における、派遣労働者の不当な対応を防止し、適正な運営を確保する
- 派遣労働者の待遇改善、雇用の安定を実現する
上記の目的のもと、派遣労働者の働き方を守るために労働者派遣法は機能しています。
適用範囲と対象者
労働者派遣法は、派遣労働者・派遣元企業・派遣先企業の3者に適用されます。しかし、労働者の派遣が禁止されている業務については適用されません。
派遣禁止業務として定められている業務は、以下の通りです。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
また、次の業務に関しては各業務の関連法令に基づき派遣禁止とされています。
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
- 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除く)
- 建築士事務所の管理建築士の業務
- 人事労務管理関係のうち、派遣先における労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
- 同盟罷業(ストライキ)・作業所閉鎖(ロックアウト)中、あるいは争議行為が発生している事業所への新たな労働者派遣
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の労働者派遣
(参照:厚生労働省|労働者派遣事業を行うことができない業務は・・・)
労働者派遣法が制定されるまでの背景
1985年に労働者派遣法が制定されるまで、労働者派遣は法律違反とされていました。労働者と企業との間に第三者が介入することで、強制労働や中間搾取などの問題が発生したためです。
しかし、高度経済成長に伴う労働力の需要増加、働き方の多様化などにあわせて、人材派遣の必要性が高まり、労働者派遣法の制定・施行へと至りました。
当初は派遣可能な業務が限られていましたが、繰り返される改正によって規制緩和が進み、今では幅広い業務において労働者派遣が可能です。
労働者派遣法の改正年度と主な改正内容
労働者派遣法は、雇用形態の多様化や社会情勢の変化に伴って、改正が度々繰り返されています。これまでの主な法改正の流れと変更点は以下の通りです。
- 1996年:適用対象業務が16業務から26業務に。無許可事業主からの派遣受入等に対する派遣先への勧告・公表について制度化。
- 1999年:適用対象業務が自由化されたほか、派遣労働者の直接雇用の努力義務が発生。新たに対象となった26業務以外の業務は派遣受入期間を最長1年の期間制限に。
- 2000年:派遣先企業に直接雇用されることを前提とした「紹介予定派遣」が解禁。物の製造業務へ労働者派遣が解禁されたほか、派遣労働者への契約の申込義務が発生。26業務以外も最長3年の期間制限に。
- 2012年:派遣労働者の保護・待遇改善を強化し、日雇い派遣は原則禁止に。
- 2015年:労働者派遣事業を許可制へ一本化したほか、雇用安定措置、キャリアアップ措置を義務化し、均衡待遇を強化。派遣期間規制を3年に見直し。
- 2020年:待遇差を解消するための規定が整備されたほか、派遣労働者の待遇について説明義務を強化。
- 2021年:マージン率等のインターネットによる開示や、雇用安定措置に関する希望聴取を義務化。
上記の通り、派遣労働者の保護や不当評価の是正をするべく、時代の流れに合わせて改正されています。
(参照:厚生労働省|労働者派遣制度の概要及び改正経緯について)
50個以上のテンプレをExcelでプレゼント!人事・労務部門ですぐに使えるChatGPTプロンプト集
労働者派遣法改正の背景と目的
労働者派遣法が改正されてきた背景には、労働市場の変化があります。ここからは、労働者派遣法が改正されてきた背景についてより詳細に解説します。
労働市場の変化と改正の必要性
労働者派遣法は、労働市場におけるさまざまな変化に応じて改正されています。なかでも大きな方向転換へとつながったのは、2008年のリーマンショックです。経済不況の影響により、派遣切り・雇止めなどが社会問題となりました。その後の2012年からは、派遣労働者の権利保護強化に向けて、派遣法改正の議論は大きく舵を切ります。
この時派遣法は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」という名称から、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」という名称に変更されました。労働者を保護する法律であることに、よりいっそう重きが置かれたのです。
その後、2020年の改正では、正社員と非正規社員の待遇格差を是正すべく「同一労働同一賃金」の実現を目指すなど、働きやすい労働環境を整えるために改正が重ねられています。
改正が目指す企業と労働者の関係改善
労働者派遣法の改正は、企業と派遣労働者の関係をより公平かつ安定したものとするために実施されています。そのため、改正内容には待遇の均等化・説明義務の強化・福利厚生の提供・雇用安定措置・無期雇用への転換促進といった内容が含まれてきました。
今後の改正においても、待遇の改善や雇用の安定化などが強化されていくと予想されます。
労働者派遣法の最新の改正ポイント
2021年4月に施行された労働者派遣法の最新の改正では、次の二点について変更が加えられました。
- 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取
- マージン率等のインターネットでの提供
詳しく解説します。
新たに導入された規定と条文の変更点
2021年4月の改正では、以下の条文が追加されました。
派遣元事業主は、法第30条1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による措置を講ずるに当たつては、特定有期雇用派遣労働者等(同条第1項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する当該措置の内容を聴取しなければならない。(労働者派遣法施行規則第25条の2第3項)
つまり、有期雇用派遣労働者が継続就業を希望する場合、あらかじめ希望する措置内容を聴取することが義務付けられたのです。
派遣元事業者は労働者に対し、派遣先への直接雇用を希望するのか、派遣元での無期雇用を望むのかなど、どういった雇用安定措置を求めるのかを確認しなければなりません。
また、希望内容について聴取した際には、その内容の派遣元管理台帳への記載も義務付けられています。
また、数ある派遣元事業者から適切な企業を選べるように、マージン率の開示についても義務付けられました。追加された条文は以下の通りです。
法第23条第5項の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。(労働者派遣法施行規則第18条の2第1項)
この改正では、事業所ごとの派遣労働者数や派遣先数、労使協定の締結の有無など、マージン率以外の情報についてもインターネットにおける開示が義務付けられています。
改正内容が実務に与える影響
2021年4月の改正により、希望する雇用安定措置内容の聴取と記録、マージン率などのインターネットにおける情報開示が義務付けられました。
派遣元企業は、継続して1年以上の派遣就業見込がある等一定の要件に該当する労働者へ以下のどれを希望するか聴取し、実施する必要があるため注意してください。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供
- 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
- その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(雇用維持中の教育訓練等)
また、マージン率等も漏れなく開示する必要があります。「マージン率等」とは、具体的には以下の情報です。
- 事業所毎の派遣労働者の数
- 事業所毎の派遣先の数
- 教育訓練
- マージン率(労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合)
- 労使協定を締結しているか否かの別等
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
なお、インターネット以外で開示している情報も含め、インターネット上ですべて公開することが義務付けられています。事業年度が変わり次第、前年度の情報を速やかに更新することが必要です。
労働者派遣の制度的な仕組みと流れ
労働者派遣制度を正確に理解するには、契約構造や指揮命令権の所在、就業までのフローを明確に把握する必要があります。関係者間の役割が曖昧である場合、法的リスクを抱えるおそれがあるため、法令や運用ルールを前提とした体制整備が不可欠です。
ここでは、制度の枠組みと基本的な流れ、周辺制度との違いについて整理します。
派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係
労働者派遣制度は、派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係を基盤としています。雇用契約の当事者は派遣元であり、業務の指揮命令を行うのは派遣先となります。
労働者は雇用された企業以外の場所で指示を受けながら働く構造であるため、契約内容と実態が一致しているかを確認する姿勢が重要です。三者の役割を整理することで責任の所在を明確化し、違法派遣や偽装請負などのリスクを未然に防止できます。
労働者派遣と請負の違い
労働者派遣と請負は、業務の委託方法として混同されやすい制度ですが、指揮命令を行う主体が異なっています。派遣は派遣先が直接労働者に指示を出しますが、請負では受託側が業務管理を行うのが特徴です。
現場での指示権限や責任範囲が交錯している場合、契約形態と実態の乖離が発生し、違法な労働関係と判断される可能性があります。制度を適切に選択し、契約書や運用体制にも整合性を持たせることが重要です。
労働者派遣の基本的な流れ
労働者派遣の基本的な流れは、以下の通りです。
- 派遣元と労働者の間で雇用契約を締結
- 派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結
- 派遣元が派遣労働者へ業務内容や就業条件を説明
- 派遣先での就業が開始され、業務指示は派遣先が実施
- 就業期間の終了時に契約更新や雇用安定措置を検討
労働者派遣では派遣元と労働者の雇用契約に基づき、派遣先で業務に従事する体制がとられます。契約は二重構造であり、派遣元と派遣先の間では業務委託としての契約を別途締結します。
就業開始後は、労働者が派遣先の指示を受けて働きますが、労務管理や給与支払などは雇用主である派遣元が担当するのが一般的です。就業期間終了時には、派遣先による直接雇用の打診や他の雇用安定措置が検討されます。
労働契約・派遣契約・指揮命令系統の違い
派遣制度においては、契約や命令系統の違いを明確に理解することが欠かせません。労働契約は派遣元と労働者の間で締結され、賃金や社会保険の管理が発生します。
派遣契約は派遣元と派遣先の間で交わされ、業務の範囲や期間が記載されます。指揮命令は派遣先が担当し、実務の指導や評価を行います。役割ごとの責任が曖昧になると違法行為とみなされる危険があるため、構造の理解と管理の徹底が重要です。
紹介予定派遣の制度概要
紹介予定派遣は、派遣労働者を一定期間派遣就業させた後、派遣先での直接雇用を前提とする制度です。業務適性の見極めや企業との相性確認を目的とし、正規雇用とのミスマッチを防ぐ手段として活用されています。
導入時には、紹介予定であることを明示し、事前選考の有無や契約期間を明確にする必要があります。厚生労働省が定める指針に従い、適切な運用を行わなければ職業紹介事業違反に該当するおそれがあるため、慎重な運用が求められます
労働者派遣に関する禁止事項と例外規定
派遣業務の中には、法律により禁止されている業務や、厳格な要件を満たす必要がある業務が存在します。業務範囲の誤認や対応ミスは、重大な法令違反につながるため、各種ガイドラインや関連法令を踏まえた判断が不可欠です。
以下では、禁止対象となる業務や規制の背景、例外措置や違反時のリスクについて解説します。
派遣が禁止されている業務の種類
労働者派遣が認められていない業務には、以下が含まれます。
- 建設
- 港湾運送
- 警備
- 医療
- 弁護士や税理士などの士業
上記は高い公共性・安全性・専門性を伴っているため、派遣による一時的な労働力では対応が困難とされます。派遣元と派遣先は契約締結前に業務内容を正確に分類し、対象業務に該当しないかの確認を怠ってはなりません。
派遣禁止の理由と背景
禁止業務に指定されている分野では、安全や倫理、社会的信頼性の確保が求められるため、派遣による業務遂行では要件を満たせないと判断されています。
たとえば、警備業務では施設や人の保護といった公共性が強く、継続的な信頼構築が不可欠です。医療関連の職務は、患者の生命に直接関わるため、継続的な教育と現場の連携が前提です。
これらの背景を踏まえて派遣形態が不適切とされ、法律により制限が設けられています。
業務ごとの例外措置と適用要件
一部の禁止業務では、法令に基づき限定的な条件のもとで派遣が認められる場合があります。たとえば、医療業務の中でも看護師による健診補助など、医師の直接指導下で行われる業務は例外に該当することがあります。
また、港湾運送業務においては、港湾荷役の周辺作業が請負と明確に区別されていれば、派遣が可能です。例外の適用には、厚生労働省の通知や通達に基づく正確な運用が求められます。
違反した場合のリスクと処分
禁止業務への労働者派遣を実施した場合、以下のような重大な処分を受けるおそれがあります。
- 行政指導
- 事業停止命令
- 許可取消
違法性が高い場合は派遣元だけでなく、派遣先にも責任が及ぶことがあります。さらに、名義貸しや不正な業務契約が認定された場合には、刑事罰の対象となるケースもあります。
リスク回避には契約段階での職種確認と、現場での業務実態の継続的なモニタリングが欠かせません。
派遣可能業務の範囲の見極め方
派遣が可能な業務かどうか見極めるには、業務内容の詳細な棚卸しと、各職務の位置付けに関する法的な評価が必要です。職種名だけで判断することは避け、作業内容・就業形態・指揮命令系統を含めた実態確認を行う必要があります。
さらに、労働局や厚生労働省のガイドライン、公的通達なども活用しながら、判断根拠を明確にしておくことが推奨されます。必要に応じて、弁護士や社労士など専門家への相談も有効です。
労働者派遣法の違反例
労働者派遣法に違反すると、派遣元・派遣先の双方が行政処分や罰則の対象となり、企業の信用にも大きな影響を及ぼします。以下では、特に重要で違反リスクが高い事例を厳選して解説します。
1. 無許可での派遣事業
労働者派遣事業には厚生労働大臣の許可が必要です(法第5条)。許可を得ずに派遣を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
例:許可を取得していない会社が派遣契約を結んで労働者を派遣した。
2. 禁止業務への派遣
港湾運送、建設、警備、医療(例外を除く)、士業など、法律で派遣が禁止されている業務に派遣労働者を従事させることは違法です(法第4条等)。
例:無資格の派遣労働者を医療行為に従事させた。
3. 偽装請負
請負契約の形をとりながら、実態として派遣先が直接指揮命令している場合は違法です。職業安定法にも抵触します。
例:業務委託契約の形式だが、派遣先の社員が日々業務指示を行っている。
4. 二重派遣
派遣された労働者を、派遣先がさらに別の企業に派遣する行為は原則禁止されています(法第24条の2)。
例:派遣先企業が、派遣労働者をグループ会社の現場に派遣して働かせた。
5. 派遣期間制限(3年ルール)違反
同一の派遣先・同一の組織単位で同じ派遣労働者を受け入れられる期間は原則3年までです(法第40条の2)。超過すると違法になります。
例:同じ部署で同じ派遣労働者を4年間継続して就業させた。
6. 就業条件明示義務違反
派遣元は、業務内容・就業場所・賃金・契約期間などを派遣労働者に事前に書面や電子で明示する必要があります(法第35条)。
例:書面を交付せず、口頭説明のみで就業を開始させた。
7. 均等待遇・均衡待遇の不履行
派遣先の同種業務の労働者と比較して、不合理な待遇差を設けることは禁止されています(法第30条の3〜第30条の5)。
例:同じ業務をしているのに、派遣労働者だけ賞与や通勤手当がない。
事業者が注意すべき労働者派遣法のポイント
ここからは、事業者が押さえておくべき労働者派遣法のポイントを解説します。
企業全体でのコンプライアンス強化
労働者派遣法を遵守するために、派遣先企業・派遣元企業はともにコンプライアンスを強化する必要があります。
とくに派遣先企業は、労働者派遣法について適切に理解するのに加え、労働基準法についても注意しなければなりません。派遣労働者に対しては、労働時間や賃金、休暇といった基本的な条件を正規従業員同等に提供することが求められます。
正規・非正規にかかわらず同等の待遇を提供することで、法令に則った対応となるだけでなく、派遣社員のエンゲージメントやモチベーション向上、企業のイメージアップにもつながります。
内部統制とリスク管理の実践例
労働者派遣法を遵守するためには、徹底した内部統制やリスク管理が欠かせません。例えば、次のような対策が求められます。
- 法令遵守のための社内規程を作成する
- コンプライアンス違反の内部通報窓口を設置し、不正行為を報告できる体制を整える
法令遵守のための社内規定作成では、労働者派遣法に基づいた契約書の作成方法・管理方法について記すことをおすすめします。法令に沿った形で派遣業務を実施するためにも、契約書作成・管理は重要なポイントとなるでしょう。
また、万が一コンプライアンス違反が見られる場合に早期に発見できるよう、内部通報窓口の設置が必要です。不正行為を臆することなく報告できる体制を整えることで、内部統制とリスク対策の強化につながります。
主な法律違反リスクとその対応策
労働者派遣法における違反行為や、それに対する罰則はさまざまです。また、罰則だけでなく行政処分が下される場合もあります。
ここからは、労働者派遣法違反となった場合の罰則や行政処分の内容、違反を防ぐための対策について解説します。
違反時の行政処分や罰則の概要
労働者派遣法で違反とされる行為には、次のような例があげられます。
- 労働者派遣が禁止されている業務への派遣
- 無許可での労働者派遣
- 偽りや不正行為により労働者派遣事業者の許可・期限更新を受けた場合
- 労働者派遣事業主の名義貸しによって行われた派遣
- 派遣可能期間の制限を超えた派遣
- 当該派遣労働者に就業条件などの明示を行わなかった場合
なかでも禁止業務への派遣や無許可派遣、虚偽・不正行為による申請、名義貸しは罰則が重く、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。その他の違反行為は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、あるいは30万円以下の罰金となります。
また、行政処分には以下のパターンがあげられます。
- 改善命令
- 事業停止命令
- 許可の取り消し
- 事業廃止命令
一般労働派遣事業の許可条件に反している場合や、職業安定法への違反が見られた場合、もっとも重い処分である許可の取り消しとなる場合があるため注意が必要です。
社員研修と教育プログラム
労働者派遣法における違反を防止するには、労働者派遣業務について適切に理解する必要があります。そのため、労働者派遣とは何か・派遣先や派遣元が講ずべき措置とは何か・具体的にはどのような実務対応が必要かなど、労働者派遣に関する社員研修を実施することが効果的です。
eラーニングや外部のセミナーなどを活用し、労働者派遣法についての理解を深めておくことが推奨されます。
派遣元と派遣先が実務上考慮すべきポイント
最後に、派遣元企業・派遣先企業が実務上で考慮すべきポイントを解説します。派遣労働者が安心して働くことのできる環境とするために、以下の点に注意してください。
派遣元企業の実務上の注意点
派遣元企業が注意すべき点は、以下の2つです。
- 派遣労働者の適切に管理・サポートできる体制を整える
- 労働条件の明確化と定期的な見直しを欠かさない
派遣労働者を適切に管理・サポートできる体制を整える
派遣元企業は、派遣労働者に対して適切な管理とサポート体制を整えることが重要です。派遣労働者のスキルや経験を分析して適切な職務を割り当て、業務に必要とされる研修やトレーニングなども提供してください。
また、派遣労働者が派遣先で安心して働けるように、定期的なコミュニケーションを心がけることも重要です。トラブルが発生した際にも、迅速に対応できる体制とすることが求められます。
労働条件の明確化と定期的な見直しを欠かさない
派遣労働者を適切に管理・サポートするには、労働条件の明確化と定期的な見直しが欠かせません。派遣労働者の労働時間・賃金・休暇といった基本的な労働条件を把握し、派遣先企業と共有してください。
また、労働条件が遵守されているかを定期的に確認し、改善すべき点はないか見直しを行うことも重要です。
公正かつ安心して働ける環境か定期的にチェックすることは、派遣労働者の満足度を向上させ、長期的なパートナーシップを構築へとつながるでしょう。
派遣先企業の実務上の注意点
派遣先企業では、次の2点に注意が必要です。
- 契約内容を明確化し責任範囲を整理する
- 派遣労働者の労働環境整備と安全管理を徹底する
契約内容を明確化し責任範囲を整理する
派遣先企業が実務上注意すべき重要な点の一つは、契約内容の明確化と責任範囲の整理です。
派遣契約の目的や派遣料金、派遣期間・就業日などの基本的な情報に加えて、派遣労働者から苦情が寄せられた場合の対応方法、契約解除要件についてなど、労働者派遣契約書に記載する内容について明確に定める必要があります。
内容に誤りはないか確認するだけでなく、不利益を被る条項がないか確認することも忘れないでください。
また、労働時間の管理や職場環境の整備、管理台帳の作成や派遣元への報告など、派遣先企業が担う実務と責任範囲も整理しておくことが重要です。
派遣元・派遣先それぞれの責任範囲を把握し、協力することを心がけてください。
派遣労働者の労働環境整備と安全管理を徹底する
派遣労働者の労働環境整備と安全管理を徹底することは、派遣先企業に与えられた重要な役割です。
就業環境や福利厚生は適切か、教育訓練は十分に行われているかなどを定期的に把握し、派遣労働者を含む従業員が働きやすい環境を整備してください。
また、就業場所の定期巡回、安全教育の提供などを通じ、安全管理を隈なく行うことも欠かせません。安全衛生教育を行った際には、実施内容と結果を派遣元に報告してください。
安全教育を派遣元に依頼する場合は、教育カリキュラムの作成支援や講師の紹介や派遣といった形での協力を受けることも有効です。
まとめ
本記事では、労働者派遣法の概要や改正の流れのほか、派遣元・派遣先企業が実務で注意すべきポイントまで解説しました。
1986年に施行された労働者派遣法は、社会や労働環境の変化に合わせて何度も改正が繰り返されています。派遣元・派遣先企業は、最新の改正内容について常に把握し、法令遵守を徹底できるように心がけてください。
法令対応を着実に行うためには、日々の法務業務の効率化も欠かせません。高品質で効率的な法務サービスの提供には、法務DXは必須です。一方で、ただ闇雲にリーガルテックを導入するだけではコストに見合う成果は得られません。LegalOnは、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲かつ総合的に支援する次世代のリーガルテックプラットフォームです。あらゆる法務業務をAIがカバーできるほか、サービスを選んで導入できるため、初めてリーガルテックの導入を検討する方にもおすすめです。
<関連記事>




(1).webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
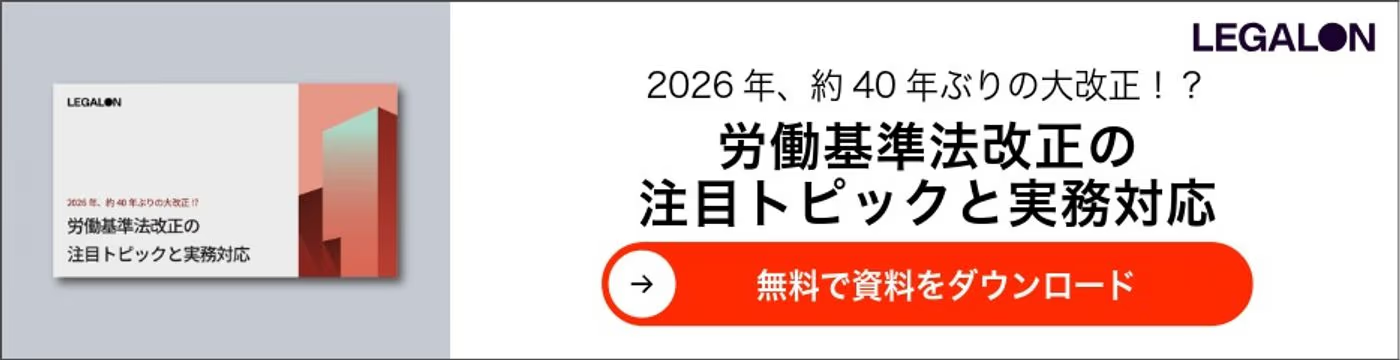
(1).webp?width=1400&fit=cover&quality=60&format=auto)
