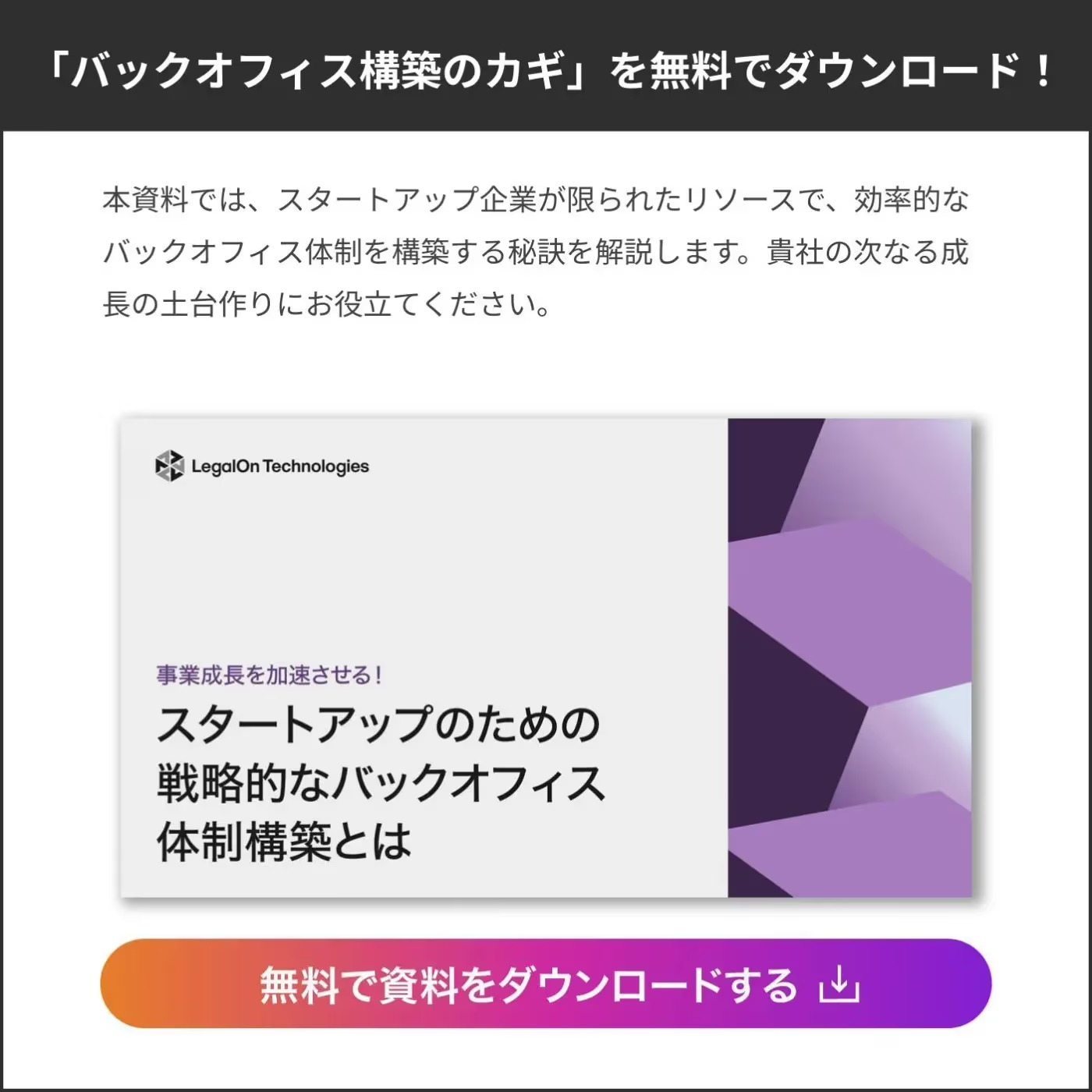36協定の前提となる「労働時間の原則」
36協定を詳しく知るうえでは、その前提となる「労働時間の原則」を理解することが必要です。
労働基準法の第32条では、使用者が労働者に対して「1日8時間、1週間について40時間以内」を超えて労働させてはいけないと定めています。この括弧内の時間は、法定労働時間と呼ばれるものです。
また、労働基準法の第35条では、労働者の休日に関して「毎週少なくとも1回の休日を与えること」を定めています。ただし、使用者が4週間を通じて4日以上の休日を与える場合、このルールは適用されません。
参考:令和6年4月からは、36協定のない残業は、違法です!(愛知県豊田市)
36(サブロク)協定とは
36協定の正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定書」です。労働基準法の第36条に根拠が書かれていることから、一般的には「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
ここでは、以下の流れで36協定の概要を見ていきましょう。
- 36協定の目的と背景
- 36協定締結と残業時間の上限
36協定の目的と背景
企業が経済活動をするうえでは、労働者に残業や休日勤務をしてもらう必要が生じます。たとえば、「駅の自動改札システムが停止した。」や「アルバイトがコロナ感染でシフトをキャンセルした。」などのトラブルが生じた場合、規制内での労働をしていたのでは、社会や経済がまわらなくなることもあるでしょう。
そこで労働基準法では、以下2つの手続きを行った場合に、先述の法定労働時間「1日8時間、週40時間以内」を超えた時間外労働(残業)と休日勤務を認めることにしています。
- 労働基準法に基づき労使協定(36協定)の締結
- 所轄労働基準監督署長への届出
この労使間の合意が、36協定と呼ばれるものです。36協定を締結しない場合、使用者は労働者に対して法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせることができません。
36協定を締結したら残業時間の上限はどうなる?
労務管理をする企業側としては、36協定の締結で時間外労働(残業)の上限がどうなるかも気になるところだと思います。ここでは、以下の流れで36協定と残業時間上限のルールを見ていきましょう。
- 36協定と時間外労働の上限規制
- 時間外労働の上限規制が猶予されていた職種
36協定と時間外労働の上限規制
2019年(平成31年)4月より、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられるようになりました。いわゆる限度時間と呼ばれる上限は「月45時間・年360時間」です。臨時的で特別な事情がない限り、この数字を超えることはできません。この限度時間を超える場合に適用されるのが、『特別条項付き36協定』です。
ただし、臨時的で特別な事情に労使が合意していても、「年720時間、複数月の平均80時間以内(休日労働を含む)」と「月100時間未満(休日労働を含む)」を超えることはできません。また、月45時間を超えることが可能となるのは、「年間6ヵ月まで」とされています。
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針(厚生労働省)
参考:令和6年4月からは、36協定のない残業は、違法です!(愛知県豊田市)
時間外労働の上限規制が猶予されていた職種
時間外労働の上限規制は、ビジネス環境でも注目された「2024年問題」との関連性も高いものです。時間外労働の上限規制では、以下の業種について、仕事の特性や取引慣行の影響で長時間労働にならざるを得ない背景があることから、制度の適用を5年間猶予していました。
- 工作物の建設の事業
- 自動車運転の業務
- 医業に従事する医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
「2024年問題」とは、これらの業種に対する猶予期間が終了することで生じる問題を指すトピックでした。しかし、2024年(令和6年)以降は、一部の特例を除き時間外労働の上限規制の適用が完了しています。
参考:建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)(厚生労働省)
36協定が必要なケース
36協定は、労働者の働き方が以下に該当するときに締結が必要となります。各ケースのポイントを見ていきましょう。
- 法定労働時間を超える残業(時間外労働)を課す場合
- 法定休日に休日労働(休日出勤)を課す場合
法定労働時間を超える残業(時間外労働)を課す場合
「残業時間が法定労働時間を超えた場合」は、重要ポイントです。
たとえば、勤務時間および休憩時間を「9時始業~17時終業、12時~13時までは1時間の休憩」と就業規則で定めていた場合、1日の労働時間は7時間となります。企業側が独自に定める時間は「所定労働時間」と呼ばれるものであり、法定労働時間を超えた設定にはできません。
仮にそこで、17時~18時に1時間の残業が発生したと仮定します。
この場合、「通常勤務が7時間+残業1時間⇒8時間」となることから、残業を課しても法定労働時間は超えません。さらに、この会社の従業員が月〜金まで週5日の勤務である場合、1時間の残業を毎日行っても法定労働時間の「週40時間」は超えない形です。それはつまり、法定労働時間の「1日8時間、週40時間」を超過しないことから、36協定の対象外になります。
一方で、この会社の従業員が「毎日1時間以上の残業」をしていたと仮定します。その場合、「通常勤務が7時間+残業1時間以上」で法定労働時間の「1日8時間、週40時間」を超えることになりますから、36協定の締結が必要になるでしょう。
法定休日に休日労働(休日出勤)を課す場合
休日については、まず労働基準法第35条で定める以下の要件を遵守できない場合、36協定の締結が求められます。たとえば、「毎週1回、日曜日の休日」が設定されているにも関わらず、何らかの理由でこの法定休日に労働を求める場合、36協定の締結と届出が必要になるイメージです。
- 「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」
スタートアップ企業などが、これから36協定の締結を経て従業員の勤務時間や休日を設定する場合、先述の法定労働時間と休日労働の両方で条件をクリアしているかどうかを見る必要があります。注意しましょう。
36協定を締結する相手
36協定は、以下いずれかの相手と締結する必要があります。各要件を見ていきましょう。
- 過半数組合がある場合(過半数組合と締結)
- 過半数組合がない場合(過半数代表者と締結)
過半数組合がある場合(過半数組合と締結)
過半数組合とは、事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する労働組合のことです。その労働組合は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数で組織する必要があります。
過半数組合がない場合(過半数代表者と締結)
過半数の労働者で構成される労働組合がない場合、過半数代表者と36協定の手続きを進めていきます。過半数代表者とは、労働者の過半数を代表している人のことです。
先述の労働組合と同様に、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数を代表する人でなければなりません。また、過半数代表者は、「36協定を締結するための過半数代表者であること」を明らかにしたうえで、投票や挙手などで選出する必要があります。
そこで以下のようなケースに該当した場合は、「36協定の締結目的で選出された過半数代表者」ではないことから、締結した協定も無効となるでしょう。
- 過半数代表者を使用者が指名した
- 社員親睦会の幹事などを自動的に選任した など
また、労働基準法第41条第2号で定めた管理監督者も、過半数代表者にはなれません。注意しましょう。
36協定が適用除外となるケース
36協定には、適用できない一部の例外があります。以下の流れで、適用除外に該当するケースを見ていきましょう。
- 36協定を締結できない労働者
- 36協定の適用除外となる業務
36協定を締結できない労働者
以下に該当する労働者は、そもそも時間外労働が認められていません。したがって、以下の労働者については36協定も締結できないことになります。各労働者の就労に関するポイントを簡単に見ていきましょう。
- 18歳未満の年少者
- 育児・介護中の労働者
- 妊産婦の労働者
- 管理監督者
18歳未満の年少者
18歳未満の年少者は、時間外労働および休日労働をさせることができません。また、36協定とは直接的な関係がありませんが、午後10時~翌日午前5時までの深夜時間帯の使用もNGです。
参考:高校生等を使用する事業主の皆さんへ~ 年少者にも労働基準法等が適用されます! ~(厚生労働省)
育児・介護中の労働者
以下の労働者から請求があった場合、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、「1ヵ月に24時間、1年に150時間」を超える時間外労働をさせることができなくなります。
- 小学校就学までの子を養育する労働者
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者
時間外労働が制限されるのは、1回につき1ヵ月以上1年以内のなかで、労働者が請求した期間です。この請求は、何度でも行えます。
この制度は、期間を定めて雇用される労働者も利用可能です。一方で以下の労働者は対象外になります。
- 日々雇用される労働者
- 勤続年数が1年未満の労働者
- 週の所定労働時間が2日以下の労働者
上記の要介護状態と対象家族の定義には、細かな注意点があります。制度の詳細を含めたポイントは、以下のページを確認してください。
参考:Q12.従業員が育児・介護のため時間外労働の制限を希望する場合 (厚生労働省)
妊産婦の労働者
妊産婦が請求した場合、以下の3つをさせることができなくなります。
- 時間外労働
- 休日労働
- 深夜業(午後10時~午前5時まで)
36協定とは直接的な関係はないですが、妊婦の労働者についても多くの特例があります。詳細は、以下の資料を確認してください。
管理監督者
管理監督者とは、労働条件の決定やその他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある人のことです。管理監督者の場合、労働基準法で定められた労働時間・休日・休憩の制限を受けません。
管理監督者かどうかは、その人の仕事内容や責任・権限、勤務態様の実態などから総合的に判断する必要があります。厚生労働省の資料で示されている以下のチェックポイントを確認するとよいでしょう。
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
現実の勤務様態も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
引用:管理監督者の範囲の適正化のために|管理職はみんな「管理監督者」?(厚生労働省)
36協定の適用除外となる業務
新技術・新商品等の研究開発業務は、上限規制の適用が除外されています。したがって、36協定も締結できません。
ただし、労働安全衛生法の改正によって、「1週間当たり40時間を超えて労働した時間が、⽉100時間を超えた労働者」に対して、医師の面接指導が義務付けられるようになりました。対象労働者に医師による面接指導を行わない場合、罰則が科せられます。36協定は不要ですが、注意しましょう。
36協定で留意すべき事項
36協定を締結する際には、厚生労働省が定める事項について留意する必要があります。ここでは、8つのポイントを簡単に紹介していきましょう。
- 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる
- 労働者の安全に配慮する
- 時間外労働・休日労働を行う業務を明確にする
- 特別な事情以外で限度時間を超えない
- 短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない
- 休日労働をできる限り少なくする
- 労働者の健康・福祉を確保する
- 限度時間が適用除外されている業務でも健康・福祉を確保するよう努める
1.時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる
時間外労働や休日労働は、労働者の負担になるものです。仮に36協定を締結していたとしても、最小限に留めることが求められます。
2.労働者の安全に配慮する
厚生労働省労働基準局長の通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」では、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなればなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まることが示されています。
さらにいえば、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6ヵ月月平均で80時間を超えた場合も、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強くなるようです。
上記の内容は、労働時間が長くなればばるほど、過労死との関連性が強まることを意味します。
企業側は、36協定を締結した場合も、労働契約法第5条で定める安全配慮義務を負っていることに留意し、過労死などを防ぐために労働時間の調整などを行う必要があるでしょう。
3.時間外労働・休日労働を行う業務を明確にする
36協定の締結で法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働をさせる際には、業務の区分を細分化したうえで、業務範囲を明確にすることが求められます。
4.特別な事情以外で限度時間を超えない
限度時間(月45時間・年360時間)を超えることができるのは、「臨時的な特別な事情があるときのみ」です。「業務上やむを得ない場合」や「業務の都合上必要な場合」などのように、恒常的な長時間労働を招くおそれがある理由は認められません。
したがって、36協定で限度時間を超えた労働をさせることができる場合を定めるときには、通常予見できる業務量の大幅な増加等にともない、臨時的に限度時間を超過して労働させる必要があるケースを可能な限り具体的に定める必要があります。
また、そもそも時間外労働は、限度時間を超えないことが原則です。仮に限度時間を超えることがある場合、以下の2つを限度時間に近づける努力が必要となります。
- 1ヵ月の時間外労働および休日労働の時間
- 1年の時間外労働時間
労働者に時間外労働をさせた場合は、25%を超える割増賃金率を適用することも必要です。
5.短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない
1ヵ月未満の期間で働く労働者の時間外労働は、以下の目安時間を超えないように努める必要があります。
- 【1週間の場合】15時間
- 【2週間の場合】27時間
- 【4週間の場合】43時間
6.休日労働をできる限り少なくする
繰り返しますが、休日労働は労働者の負担になるものです。事業者には、休日労働が発生する場合、日数および時間数を可能な限り少なくする配慮も求められます。
7.労働者の健康・福祉を確保する
限度時間を超えた労働を求める場合、労働者の健康・福祉を確保する目的から、以下のなかから協定することが望ましい点に留意する必要があります。
- 医師による面接指導
- 深夜業の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心とからだの相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
8.限度時間が適用除外されている業務でも健康・福祉を確保するよう努める
新技術・新商品の研究開発業務は、限度時間が適用除外されています。しかしそれでも、限度時間の勘案が望ましいことに留意しなければなりません。
また、新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者が「月45時間・年360時間」を超えて時間外労働をする場合、上記で紹介した健康・福祉を確保するための措置(9項目)を協定するように努める必要があります。
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針(厚生労働省)
36協定に違反した場合の罰則
以下のいずれかに該当する場合、労働基準法第32条の違反により6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、36協定を締結して時間外労働を行わせる場合は、時間数の上限にも注意が必要です。以下のいずれかに該当した場合、36協定で定めた時間数に関わらず、労働基準法第36条第6項の違反によって、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
- 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上の場合
- 時間外労働と休日労働の合計時間について、2~6ヵ月の平均のいずれかが80時間を超えた場合
なお、法律違反になるケースの例は、以下資料の21ページで詳しく解説されています。ぜひチェックしてください。
参考:時間外労働の上限規制わかりやすい解説(厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
36協定における締結・届出の流れ
36協定の締結・届出は、以下の流れで行います。ここでは、各作業のポイントを解説しましょう。
- 労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定を締結する
- 36協定の内容を36協定届に記入する
- 36協定届を労働基準監督署に届け出る
- 36協定の内容を労働者に周知する
1.労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定を締結する
使用者(事業主)と労働者代表が合意できる内容で、労使協定(36協定)を締結します。ここでいう労働者代表は、以下のいずれかに該当する人のことです。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
- 労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する人
管理監督者は労働者代表になれません。また、労働者の過半数を代表する人は、「36協定のための選出であること」を明らかにしたうえで、民主的な方法で選ばれている必要があります。
なお、36協定は、本社・支店・営業所といった「事業場ごと」の締結が必要です。また、36協定の内容は、「労働時間の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」に適合している必要があります。この資料はチェックリストとしても使えるようになっています。ぜひ活用してください。
2.36協定の内容を36協定届に記入する
労働者代表との協定で決まった内容を、36協定届(様式第9号等)に記入します。具体的には、以下の7種類から自社の用途に合うものを選択する形です。
引用:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
なお、2021年4月から様式が新しくなりました。新様式では、以下の点が変更になっています。
- 36協定届における押印・署名の廃止
- 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定届の様式は、以下のページからダウンロード可能です。書き方や記載例もぜひ参考にしてください。
参考:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)(東京労働局)
3.36協定届を労働基準監督署に届け出る
36協定で定めた時間外労働・休日労働は、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出てはじめて労働者に行わせられるようになります。36協定の届出方法は、以下の3つです。各方法のポイントを見ていきましょう。
- 窓口で届け出る
- 郵送で届け出る
- e-Govで電子申請する
窓口で届け出る
以下2つの書類について、原本と写しの2部を提出します。正本(原本)は労働基準監督署の届出用、写し(副本)は会社控え用として返される形です。
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
- 時間外労働・休日労働に関する協定書(労使協定)
参考:届出方法について(36 協定届)-窓口または郵送で届け出る場合-(福井労働局参考資料)
郵送で届け出る
郵送で届出をする場合は、上記の2つ(36協定届+労使協定)に加えて、以下を添えて提出します。
- 返送用の切手及び封筒(封筒に切手を貼り付け、返送先を記入)
- 送付状(内容物と数量を適切に確認する目的)
郵便事故による個人情報の漏洩などを防ぐために、いわゆるレターパックや特定記録などの「記録付き郵便」で送る必要があります。提出内容に問題がなければ、労働基準監督署に到着した日に受理される形です。
参考:届出方法について(36 協定届)-窓口または郵送で届け出る場合-(福井労働局参考資料)
e-Govで電子申請する
e-Govによる電子申請には、以下4つのメリットがあります。
- 24時間いつでも届出可能
- とこからでも申請可能
- マイページから状況を確認可能
- パソコン上だけで手続き完了
厚生労働省の資料で示されている電子申請の流れは、以下のとおりです。
引用:「36協定届」や「就業規則(変更)届」など労働基準法などの電子申請がさらに便利になりました!(厚生労働省)
アプリの操作方法なども、詳しく解説されています。電子申請を選択する際は、ぜひ厚生労働省の資料を見ながら作業を進めてみてください。
4.36協定の内容を労働者に周知する
労働基準監督署長への届出を行った36協定は、作業場の見やすい場所への備え付け・掲示、書面の交付などの方法で労働者に周知する必要があります。
36協定の上限を遵守するための施策
時間外労働および休日労働は、時間数や回数が多ければ労働者の身体に負担をかけてしまうものです。そのため、労働者に時間外労働や休日労働を行わせる目的で36協定を締結する場合は、上限を遵守し労働者の負担を減らす工夫や施策を実施していく必要があります。
ここでは、多くの企業が実践する施策の一例を紹介しましょう。
- 労働者の勤怠を正確に管理・把握する
- 生産性が上がる仕組みを考える
- 勤務形態や働き方の制度を見直す
- 経営層や管理職の意識を変革する
労働者の勤怠を正確に管理・把握する
36協定で取り決めた上限を超えないようにするためには、労働者の勤怠を正確かつリアルタイムに監視・管理できる仕組みが必要です。
たとえば、労務管理に特化したクラウドシステムのなかには、36協定に対応したものが多くあります。36協定のアラート機能を使うと、自社が設定した上限時間に近づいたときに通知されるイメージです。こうしたシステムを活用すると、残業時間の多さなども早い段階で気づきやすくなるでしょう。
労働者の負担を減らすためのリソースおよびスケジュールの調整なども、正確な勤怠管理の仕組みがあってこそ実現できるものとなります。
生産性が上がる仕組みを考える
労働者の時間外労働や休日労働を減らすことには、人件費を抑える目的もあります。具体的な施策は業種・職種によって異なるものの、以下のような方法で業務効率化や生産性の向上が実現すると、残業時間の大幅な削減も可能になるかもしれません。
- 作業分析を行い、ムダな仕事を排除する
- ハイパフォーマーのやり方をメンバー全員に共有する
- 業務の属人化をやめる
- 優先度の判断基準を明確化する など
- 一部業務のDX化を進める など
勤務形態や働き方の制度を見直す
労働者の時間外労働などを減らすためには、職種やプロジェクトの特徴に合った働き方や休み方の制度を取り入れることも大切です。以下のような制度の導入で働き方の柔軟性が高まると、労働者の負担も軽減しやすくなるでしょう。
フレックスタイム制
コアタイム(全員に出勤義務がある時間帯)さえ出勤していれば、フレキシブルタイムでは自由に出社・退社できる制度。
フリーアドレス制
各自が固定席を持たずに、自由に席を選んで働くスタイル。生産性向上なども期待できる。
ノー残業デー
残業なしの定時退社を促す日のこと。仕事にメリハリが生まれやすくなる。
リモートワーク
勤務先オフィスに出社せず、自宅などの離れた場所で仕事ができるもの。通勤にかかる時間を削減することで、心身の負担軽減が可能になることも。
リフレッシュ休暇
従業員の気分転換や疲労回復などを目的に、任意で制度を設けるのも一つ。
経営層や管理職の意識を変革する
時間外労働が多くなりがちな組織には、以下のような企業風土が残っている可能性もあります。
- 残業が当たり前である
- 毎日遅くまで残業した人を高く評価する
- 成果を出すためには休日出勤も厭わない
- プライベートよりも仕事が優先 など
自社の組織に上記の傾向がある場合、まずは経営層に時間外労働および休日労働を抑制することの大切さを理解してもらう必要があります。そのうえで、経営層が自ら風土改革に向けたメッセージを発信することが大切でしょう。また、研修などを通じて現場の管理職の意識を変えることも必要となります。
なお、必要以上の時間外労働を減らすためには、人事評価制度を見直すなどの方法もあります。ただし、新たな評価制度の運用を通じて残業を減らすうえでは、経営層および管理職の意識改革がやはり必要です。
また、先述の「リフレッシュ休暇」や「ノー残業デー」などの制度を浸透させ、労働者の負担が少ない労働環境をつくるなかでも、経営層および管理職の意識を変える必要があるでしょう。
36協定の概要とポイントを解説しました
従業員に法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働をさせる際には、一部の例外を除き、労働者代表との36協定の締結と労働基準監督署長への届出が必要です。
また、労働者の時間外労働を抑えるためには、業務効率化による生産性の向上や、経営層・管理職の意識改革なども必要となります。36協定の締結・届出後は、労働者の負担を減らし健康を守るうえでも、自社に導入できる施策から実践していきましょう。