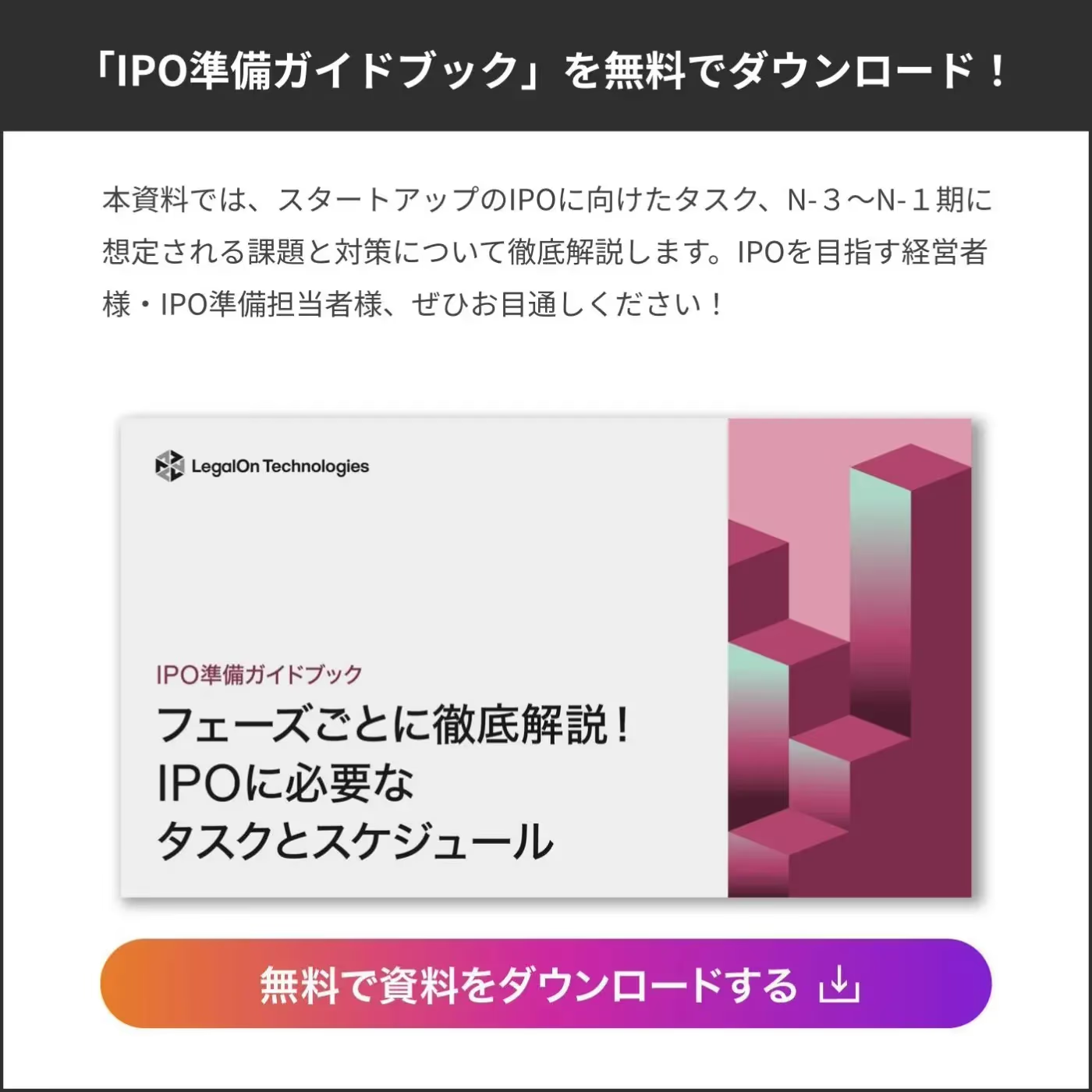監査とは
監査とは、企業経営の健全性と透明性を確保するために、取締役などの職務執行状況を監視し、適切に評価することです。取締役が会社の方針や法律、規則に従って職務を遂行しているかどうかを確認し、不適切な点があれば是正措置を促します。
また監査の結果を株主に報告し、経営状況を正確に把握できるようにします。
監査役会とは
監査役会とは、企業の経営や業務執行の適正性を確保するために設置される監査機関のことです。
コンプライアンスの徹底とコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的に、一定以上の規模を持つ会社への設置が義務付けられています。
監査役会の主な目的は、企業活動が株主やその他のステークホルダーの利益を損なうことなく適正に行われるよう監督し、経営の透明性と信頼性を高めることです。
企業の規模が拡大するにつれて、業務の複雑化や組織構造の多様化が進み、監査の対象となる範囲も広がります。その結果、単独の監査役では十分な監査を行うことが難しくなるため、複数の監査役による組織的な対応が必要です。
監査役会の役割や職務内容、構成人員などについて詳しく見ていきましょう。
監査役会の役割
監査役会の役割は下記のとおりです。
- 監査方針や監査方法の決定
- 代表取締役が遂行する業務のリスク評価
- 法令・社内規程の遵守確認(コンプライアンス監査)
- 経営意思決定プロセスの監視
- 内部統制の評価
- 監査報告書の作成
- 不正行為の発見
- 会社資産の保護
通常、監査対象となる部門には事前に通知され、監査のために必要な資料の提出が求められます。しかし不正の疑いがある場合や緊急性の高い案件については、事前通知なしで監査を実施することもあります。
監査役会の職務内容
監査役会は、経営組織から独立して監査権限を行使することで、公正かつ客観的な視点から企業の業務運営を監視する役割を担います。各監査役が「独任制」のもとで独自の判断に基づいて職務を遂行するため、監査役会自体が個々の監査役の活動を制限することはできません。
必要に応じて取締役や経営陣に対して事業報告の提出を求めることができ、会社の財務状況や経営の実態について詳細な調査を行う権限を持ちます。また、一定の条件下では子会社に対しても報告を求めることが可能であり、グループ全体のガバナンス強化にも寄与します。ただし、監査役会は定款や監査役会規則で定められた範囲を超えて権限を行使することは許されず、個々の監査役の調査権限を不当に制限できません。
監査役会の主な職務内容は以下のとおりです。
常勤監査役の選定および解職
- 説明:監査役の中から常勤監査役を選定し、必要に応じて解職する権限を有します。常勤監査役は、会社の営業時間中に職務に専念します。
- 関連する条文:会社法390条3項
監査方針、業務および財産状況の調査方法の決定
監査報告の作成
- 説明:各監査役の報告に基づいて監査報告を作成します。意見の不一致がある場合、個々の監査役が自らの意見を付記することができます。
- 関連する条文:会社法施行規則130条、130条2項、3項
構成人員
監査役会は少なくとも3名以上の監査役で構成され、そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。これは、企業内部だけでなく外部の視点を取り入れることで、監査の独立性と客観性を確保するためです。
さらに、監査役会には常勤監査役を少なくとも1名以上置くことが義務付けられています。常勤監査役は、企業の日常業務に密接に関与し、継続的な監査活動を通じて経営の実態を把握します。
監査役の任期は原則として4年です。
監査役会の設置状況
日本の株式会社では、会社法に基づき、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれかを設置する必要があります。このうち、最も多く採用されているのが監査役会設置会社です。
上場企業においては、監査役会設置会社を採用している企業が多数を占めており、監査役を3名任命している企業は全体の50%以上といわれています。さらに4名の監査役を任命している企業も含めると、全体の約90%に達するとされています。
一方で、近年ではコーポレートガバナンスの多様化が進んでおり、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社を採用する企業も増加傾向です。
監査役会設置のための手続き
監査役会を設置する際は、会社法に基づいて以下の手順を踏む必要があります。
1. 定款変更決議
- 内容:株主総会で監査役会設置に関する定款変更を決議する。特別決議が必要で、3分の2以上の賛成が必要
- ポイント:株主の十分な理解と支持が重要
2. 監査役の選任決議
- 内容:3名以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)を選任する。株主総会での決議により正式に任命される
- ポイント:事前に適切な候補者を確保しておくとスムーズ
3. 監査役の就任承諾
- 内容:選任された監査役から書面による正式な就任承諾を得る
- ポイント:就任承諾書の取得が必須
4. 登記申請
- 内容:承認効力発生日から2週間以内に法務局へ登記申請を行います。
- ポイント:期限内に申請しないと法的リスクが生じる可能性があります。
登記申請には、下記の書類が必要です。
- 株主総会議事録
- 定款
- 株主リスト
- 新任監査役の就任承諾書および本人確認証明書
なお取締役や監査役を変更した際にも、登記申請を行う必要があります。
監査役会と他の会の違い
監査役会と他の会の違いについて詳しく見ていきましょう。
取締役会との違い
取締役会と監査役会の違いは役割と機能です。
取締役会は会社の経営方針や重要な業務執行に関する意思決定を行う機関であり、企業戦略の策定や予算の承認、人事などの経営全般に関わる重要事項を決定する役割を担っています。
一方、監査役会はその取締役会による意思決定や業務執行が法令遵守やコンプライアンスの観点から適正であるかどうかを監査・監督する機関です。
指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社との違い
指名委員会等設置会社は「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」を設置することが義務付けられています。指名委員会と報酬委員会は取締役の人事や報酬決定を担います。
また各委員会は3人以上の取締役で、その過半数は社外取締役であることが必須です。そのため、経営判断の透明性と客観性に優れています。しかし日本企業では、社外取締役に人事や報酬決定の権限を与えることへの抵抗感があり、導入企業は少数派です。
監査等委員会設置会社は、指名委員会等設置会社と監査役会設置会社の中間的な位置づけにある制度です。取締役会内に「監査等委員会」を設置し、取締役の業務執行を監督します。特徴的なのは、監査等委員会のメンバーが取締役として取締役会で議決権を持つ点です。
指名委員会等設置会社と異なり、取締役の人事や報酬に直接関与することはありません。
監査役会の設置義務がある企業(監査役会設置会社)
監査役会の設置はすべての企業に義務付けられているわけではありません。しかし、社会的な影響力が大きいとされる一定の企業には、会社法により設置義務があります。対象となるのは、以下の2種類の企業です。
- 公開会社
- 大会社
公開会社とは、株式の譲渡に制限が設けられていない企業を指し、株主間で自由に株式を売買できます。不特定多数の株主を持つことが多く、株主の利益保護や経営の透明性確保が重要とされるため、監査役会の設置が義務付けられています。
次に、大会社です。大会社とは、資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の企業を指します。規模が大きく経済全体への影響力も大きいため、内部統制やガバナンス体制の強化が求められます。
必ずしも上場している必要はなく、未上場企業であっても資本金や負債額の基準を満たしていれば、監査役会の設置が必要です。
たとえば、創業10年未満の未上場企業であっても、評価額が10億ドルを超えるようなユニコーン企業が存在します。このような企業は上場会社ではないものの、資本金が5億円以上、または負債が200億円以上であれば、大会社として監査役会の設置義務が生じます。
監査役会の運営方法
監査役会の運営方法について詳しく見ていきましょう。
召集方法
監査役会を開催する際には、すべての監査役が出席できるように調整が必要です。これは、監査役会が企業の重要な意思決定や監督機能を担うことで、全員の意見を反映した議論と決議が必要であるためです。
召集にあたっては、事前に日時、場所、議題、関連資料を明確に通知します。通常、書面や電子メールで行い、議題に関連する資料も併せて送付することで、各監査役が事前に内容を把握し、効果的な議論が行えるようにします。
決議
決議は各監査役が1人につき1つの議決権を有し、過半数の賛成によって可否が決定されます。代理人による議決権の行使は認められていません。すべての議題が決議を必要とするわけではなく、監査役会で扱う事項は大きく3つに分類され、それぞれ異なる性質を持っています。
決議事項
- 概要:監査役の過半数によって可否を決定する事項
- 具体的な特徴:重要な監査方針の決定など、監査役会全体の同意が求められる場合に適用される
協議事項
- 概要:監査役間で意見交換が求められる事項
- 具体的な特徴:監査役の職務や権限行使に関する議題など、必ずしも監査役会としての決定を求められるものではない
同意事項
- 概要:各監査役が個別に同意か否かを意思表示するべき事項
- 具体的な特徴:監査役会の決議を必要としないが、十分な協議に基づいた妥当性が求められる
議事録
監査役会の議事録は、会議の内容や決定事項を公式に記録する文書です。議事録には、出席した監査役の署名または記名押印が必要であり、正式な手続きを経たうえで、会社の本店に10年間保管することが法的に定められています。
議事録の保管が求められる理由として、株主や会社債権者による閲覧請求が挙げられます。株主は裁判所の許可を得ることで、監査役会議事録の閲覧を請求することが可能です。また、会社債権者が役員の責任追及を行う際にも、裁判所の許可を得て議事録を確認できます。
さらに、親会社の株主が子会社の議事録の閲覧を請求するケースも存在しますが、裁判所が閲覧によって親会社または子会社に損害が生じる恐れがあると認めた場合には、請求が却下されることもあります。
議事録は、監査役会での決定事項だけでなく、会議中に出された反対意見や異論の記録も必須です。これは、全会一致で決議されなかった場合でも、少数意見を尊重し、その記録を残すことで、後日その意見が重要な意味を持つ可能性があるためです。
また監査役会の監査報告書においても、異論がある場合には個人の見解を付記します。
監査役会のメリットとデメリット
監査役会を設置するメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット
監査役会を設置するメリットは次のとおりです。
導入しやすい
監査役会制度は、日本企業において長年親しまれてきた伝統的な機関設計であり、すでに多くの企業で運用されているため、導入が比較的容易であることがメリットです。
登記や各種手続きに関する法的枠組みやシステムも成熟しており、初めて導入する企業でもスムーズに体制を構築できます。
監査の実効性と機動性に優れている
監査役会は各監査役が個別に独立した立場で監査権限を行使できる制度であり、この独立性が監査の徹底と機動性を高める要因となっています。監査役会には常勤監査役を設置することが一般的ですが、常勤監査役は取締役として通常の業務執行に関与することがないため、監査業務に専念することが可能です。
社会的信用が向上する
監査役会を設置することで、企業は対外的に適切なガバナンス体制を整備していることを示せるため、社会的信用の向上が期待できます。特に上場企業や大企業においては、監査役会が存在することで株主や投資家、取引先、金融機関などのステークホルダーに対して信頼性の高い経営が行われていることのアピールが可能です。
コスト効率が良い
指名委員会等設置会社と比較すると、監査役会設置会社は必要な役員数が少なくて済むため、役員報酬や運営コストを抑えることができます。委員会設置型の組織では、多くの社外取締役や委員会メンバーが必要となり、これに伴う人件費や管理コストが増加します。一方、監査役会設置会社はよりコンパクトな体制でありながらも効果的なガバナンスを維持できるため、コストパフォーマンスの高い組織運営が可能です。
デメリット
監査役会を設置するデメリットは次のとおりです。
取締役に対する権限の制約がある
監査役会は取締役の業務執行を監査・監督する役割を担っていますが、その権限はあくまで「監視」に限定されており、取締役の選任や解任、報酬決定といった経営の根幹に関わる意思決定に直接関与できません。
これに対して、欧米のガバナンスモデルでは、独立した監査委員会が取締役の選任や報酬に対して強い影響力を持つことで、監査の実効性を高めています。そのためグローバル展開を目指す企業にとっては、海外の投資家や企業からの理解を得にくいという課題が生じます。
監査役会の形骸化のリスクがある
形式的には監査役会が設置されていても、実質的な機能が果たされないケースが存在します。特に問題となるのは、任期を終えた取締役がそのまま「横滑り」的に監査役に就任するケースです。このような人事では、元取締役が現経営陣と強い人的関係を維持している場合が多く、独立した立場での監査が難しくなる可能性があります。
監査役会について解説しました
監査役会は、企業経営における健全性と透明性を確保するための機関です。監査役会の設置は単なる形式的なものではなく、実効性のある監査機能を果たすことが求められます。
そのためには、独立性の高い監査役の選任、適切な議事運営、意思決定プロセスの構築が不可欠です。また、企業の成長や事業環境の変化に応じて、監査役会の体制や運営方法を継続的に見直すことも重要です。
経営の質を高めるための重要なパートナーとして位置付け、実効性のある監査体制を維持・強化していきましょう。