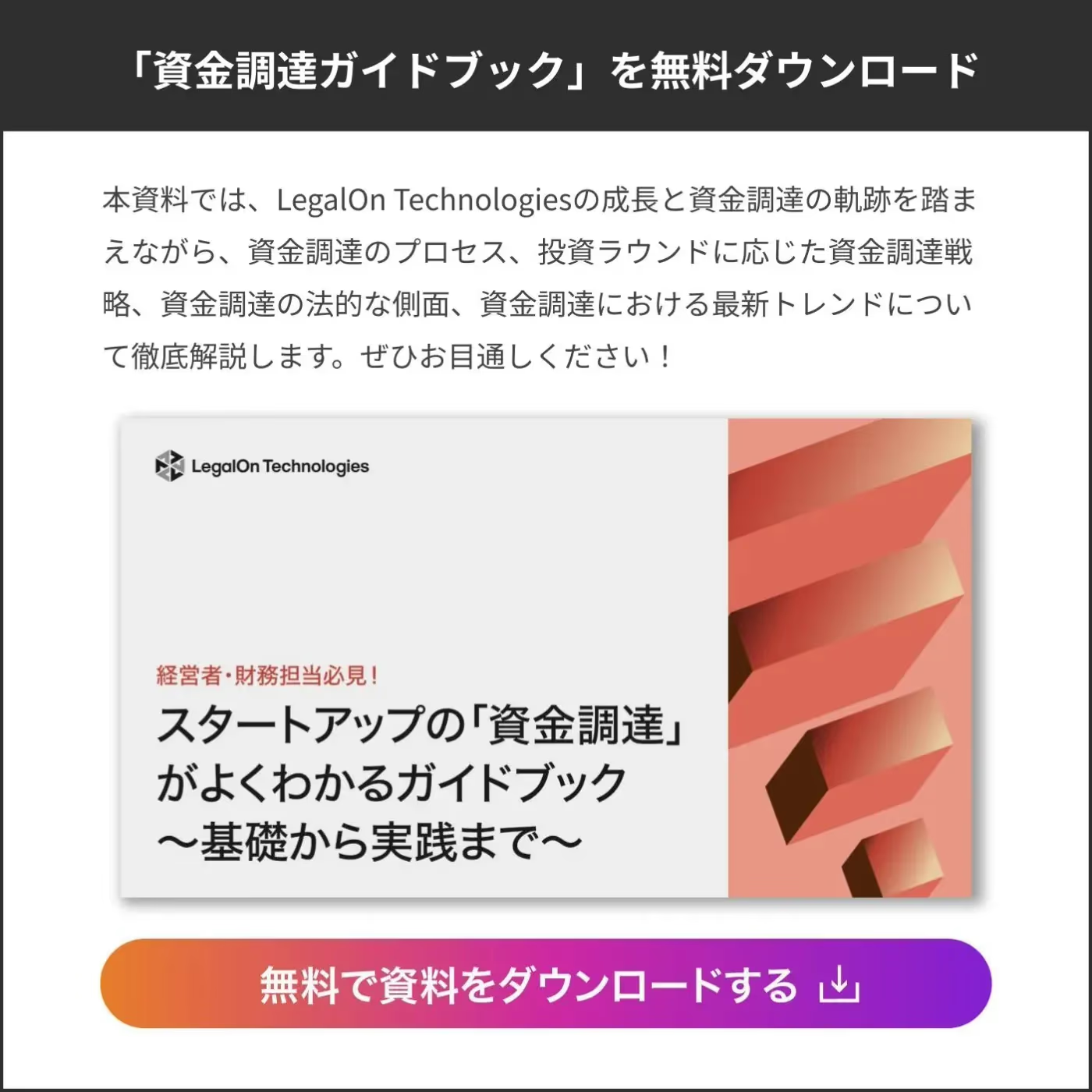キャッシュフロー(CF)とは?
キャッシュフロー(CF)とは、企業における現金の出入りによる流れを表します。特に企業に入ってくる現金を「キャッシュインフロー」、出ていく現金を「キャッシュアウトフロー」と呼び、これらをまとめたものがキャッシュフローとされています。
ここでいう「キャッシュ」は現金を意味するため、売掛金など将来的に企業に払われる金額は含まれていません。現金やすぐに現金化できる預金の他に、3か月以内に満期になる定期預金や一部の投資信託なども含まれますが、基本的には現金のみです。
そのため企業のキャッシュフローを確認することは、実際に手元にある現金の額や出入りの状況の把握につながります。
キャッシュフローと資金繰りの違い
キャッシュフローと類似する言葉として、資金繰りという概念があります。どちらも企業の資金の流れに関連していますが、それぞれの意味は異なります。
企業における現金の出入りによる流れを表すキャッシュフローに対し、資金繰りは企業が日々の運営を行うために必要な資金をどう調達し、どう使うかを管理する活動を指します。
つまり、キャッシュフローは企業の現金の流れそのものに焦点を当て、資金繰りはその現金の流れを日々調整・管理していく活動と言えます。
以下の記事では、資金繰りについて詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>資金繰りとは?悪化の原因や改善方法、資金繰り表のフォーマット・作り方をわかりやすく解説
キャッシュフローの種類とそれぞれの読み方・考え方
キャッシュフローは、以下に示す「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」「フリーキャッシュフロー」の4つに分類されます。それぞれにキャッシュフロー計算書に記載されるプラスやマイナスがどのような意味になるのか、読み方を詳しく見ていきましょう。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフローは、企業が行う本業=主要事業によって生じる収入と支出をまとめた項目です。例えば、収入なら本業の利益や売掛金の回収、支出なら原材料費や従業員への給与支払いなどがここに含まれます。
この項目がプラスになっている場合、本業が黒字になっていて順調であることがわかります。逆にマイナスになっていれば、本業が赤字を出していることがわかるため、早急に資金繰りや収支のバランス改善が必要です。
マイナスになっていること=赤字と同義であり、一般的にプラスになっていることが望ましい項目です。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフローは、設備投資で固定資産を購入した場合や、別事業への投資で株式や債券を取得した場合などの収支をまとめた項目です。不動産の取得・売却や、有価証券の取得・売却などが含まれています。
この項目がプラスになっていれば、この期間内に固定資産や有価証券といった企業の資産を売却したことで、現金を得たことがわかります。一方でマイナスとなっている場合は、将来的な投資として固定資産や有価証券を購入したと考えることが可能です。実際に何を購入したかは、貸借対照表を前期と比較することで確認できる場合があります。
営業活動によるキャッシュフローと異なり、マイナスになっているからといって悪い状況というわけではありません。企業が将来的に利益を生み出す投資を行っていれば、マイナスである方が良い場合もあるためです。プラスになっていても、資金繰りに困って現金不足を解消する方法として、資産を売却した可能性もあります。単純なプラスマイナスを考えるだけでなく、購入・売却の内容まで確認するようにしましょう。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフローは、金融機関などとの取引により現金の不足をどのように補ったかをまとめた項目です。金融機関からの借入や返済、新規株式発行によって得られた収入、配当金の支払いなどが含まれます。
この項目がプラスになっている場合は、借入金や社債といった貸借対照表(B/S)上で負債になる資金調達があったことを表します。その逆にマイナスの場合は、それらの負債の返済が進んだと考えることが可能です。
財務活動によるキャッシュフローについては、企業がその時点でどのような状況かによってプラスとマイナスが変化します。一概にどちらの方が状況が良いという項目ではないため、実際のプラス、マイナスの理由を元に検討する必要があります。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、上記のキャッシュフローのうち「営業活動によるキャッシュフロー」から「投資活動によるキャッシュフロー」を差し引いた金額です。事業活動や設備投資に用いる資金を全て差し引いて、企業が自由に使える金額を指しています。
フリーキャッシュフローは、キャッシュフロー計算書には記載されていないケースもありますが、返済能力や投資能力を図るひとつの指標です。そのため、プラスになっているほど企業価値が高く、投資家や金融機関からの評価につながります。
マイナスになっている場合、投下資金の回収率の低さや投資力・事業成長力が無いと捉えられてしまう可能性がある点に注意しましょう。
キャッシュフロー計算書とは
キャッシュフローを書類として確認できるようにまとめたのが、キャッシュフロー計算書です。貸借対照表(B/S)および損益計算書(P/L)とともに、企業の経営状況や売上を表す「財務三表」に数えられています。一定の会計期間を通じて、どのように企業の現金が動いたかを確認できる書類です。
基本的なキャッシュフロー計算書は、以下のような表で表されます。
キャッシュフロー計算書の例

中小企業庁「キャッシュフロー計算書の様式例を活用したい方へ」元に作成
キャッシュフロー計算書の作り方
企業がキャッシュフロー計算書を作成するのは決算期に必要となるためです。とはいえ、決算書類として作成が義務付けられているのは上場企業のみで、それ以外の企業や個人事業主には義務がありません。しかし、前述の通り金融機関から融資の際に提出が求められるため、融資を受ける可能性がある企業は上場に関係なく作成している場合があります。
今後の財務諸表のひとつとして作成を考えている企業の方は、その作り方も把握しておくとよいでしょう。キャッシュフロー計算書は貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)を元に作成しますが、営業活動によるキャッシュフローについては以下に示す2種類の算出方法があります。
直接法
直接法は営業収入や原材料、仕入れによる支出など、主要な取引ごとに総額を表示する方法です。営業活動ごとに現金の増減を確認でき、詳細がわかる点がメリットに挙げられ、国際会計基準で推奨されています。しかし、取引ごとのデータが必要になるため作成に手間がかかることがデメリットです。
また「投資活動によるキャッシュフロー」と「財務活動によるキャッシュフロー」は、直接法によって算出することも、覚えておきましょう。
間接法
間接法は損益計算書(P/L)を用いて、税引前当期純利益から営業活動に関係していない利益や費用を差し引いて算出する方法です。直接法に比べて各取引のデータを必要としない分だけ手間が少なく、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)があれば作成できます。その一方で、直接法で作成した場合ほど細かな収支の流れが確認できないため、やや全体を把握しづらいことが欠点です。
財務における手間が少なく、多くの企業でこの間接法が採用されています。
貸借対照表・損益計算書との違い
ここまでに述べてきた内容に多く登場した財務諸表に「財務三表」があります。本記事で解説する「キャッシュフロー計算書(C/F)」と「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」の3つが「財務三表」です。ここからはキャッシュフローとその他の2つの文書の違いについて、解説していきます。
決算にあたり必要となる財務関連書類について、キャッシュフロー計算書を起点に整理しておきましょう。
貸借対照表との違い
貸借対照表(B/S)は、決算日時点の資産・負債・純資産などによって企業の財政状態を表しています。その時点で企業が持つ資産と負債の状況や、資金の調達手段と利用法を確認することが可能です。
キャッシュフロー計算書も、企業の経営成績や財政状態を確認できる書類ですが、貸借対照表と異なり、確認できるのは一定期間の現金の流れに限られます。一方でどのような理由でどのくらいの金額が流出入したかは、貸借対照表ではわかりません。
出入りした金額や理由がわかるキャッシュフロー計算書と決算日時点の状況がひと目で分かる貸借対照表を照らし合わせることで、企業の財務状況をより詳しく知ることができます。
損益計算書との違い
損益計算書(P/L)は、会計期間の収益と費用による損益を表しています。これを確認することで、売上に対してどのくらいの費用が発生したか、費用を差し引いた利益がどの程度だったかといった損益を確認することができます。
キャッシュフロー計算書と異なる点は、掛取引を計算に含んでいる点です。キャッシュフロー計算書は掛取引が含まれず、現金の流れのみを表しています。損益計算書で収益として計上されていても、実際の金銭は回収されていない場合があるため、キャッシュフロー計算書と照らし合わせることで、売掛金の回収漏れを防ぐことが可能です。
キャッシュフローを把握するメリット
キャッシュフローを把握することで、企業は手元にある現金の額を把握することができます。しかしそれだけでなく、キャッシュフローを把握することには企業にとっていくつかのメリットがあります。ここからは企業がキャッシュフローを正確に把握するメリットを見ていきましょう。
資金ショートを防止できる
企業がビジネスを行う過程で、利益と手元にある現金にズレが発生することはよくあります。なぜなら経費や売掛金といった、掛取引による「将来的に払う、または受け取るお金」が生まれるためです。売上では十分な金額が手元にあるように見えて、実際に入金されるのは1〜2か月先という場合があります。こういった掛取引によるズレを正確に把握できていないと手元に現金がなくなってしまい、資金ショートが起こります。
資金ショートとは、手元の現金が不足して必要な支払いができない状態です。手持ちの現金が足りず支払いが滞ることで、最悪の場合は倒産の危険性があります。
キャッシュフローを正確に把握しておくことで、資金の状況が見えるようになるため、資金ショートのリスクを低減できます。
以下の記事では資金ショートについて詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>資金ショートとは?原因や予防・対処法、資金繰りの基本を解説
金融機関からの信用を得られる
金融機関から資金調達を行う場合に、キャッシュフローを確認されます。キャッシュフローの状態が良くなければ、資金繰りがうまくいっていないと判断されるため、希望した融資を受けられない可能性があります。普段からキャッシュフローを確認して、問題点を解決し必要な対策を講じておくことで、金融機関からの信用を得られるようにしましょう。
キャッシュフローを把握して資金繰りが良好になっていれば、大規模な設備導入や新規事業立ち上げの際に、金融機関からの資金調達が円滑に行えるようになります。
経営の選択肢が増える
企業の経営判断には、設備や人員への投資が欠かせません。しかし、資金を確保できなければ、選択肢は狭まってしまうでしょう。
キャッシュフローを正確に把握することで、金融機関からの融資を受けやすくなるだけでなく、資金に余裕があるタイミングを判断できます。そのタイミングで人員や設備、開発費用などに適切に投資すれば、企業の成長につながります。このように経営としての選択肢が増えることも、キャッシュフローを正確に把握するメリットです。
キャッシュフローの重要性と活用方法について解説しました
キャッシュフローは企業の手元にある現金の流れを表しています。キャッシュフローを正確に把握することで、貸借対照表や損益計算書だけではわからない、企業の資金繰りを安定させるための情報が得られます。計算書を作成する場合は、それぞれの項目の見方にも注意して、活用していきましょう。
この記事ではキャッシュフローの概要と把握するメリット、キャッシュフロー計算書について、キャッシュフロー計算書の読み方と作り方、貸借対照表・損益計算書との違いを解説してきました。決算や資金繰り改善に向けて、貸借対照表と損益計算書だけでなくキャッシュフローを利用したいと考えている方の参考になれば幸いです。