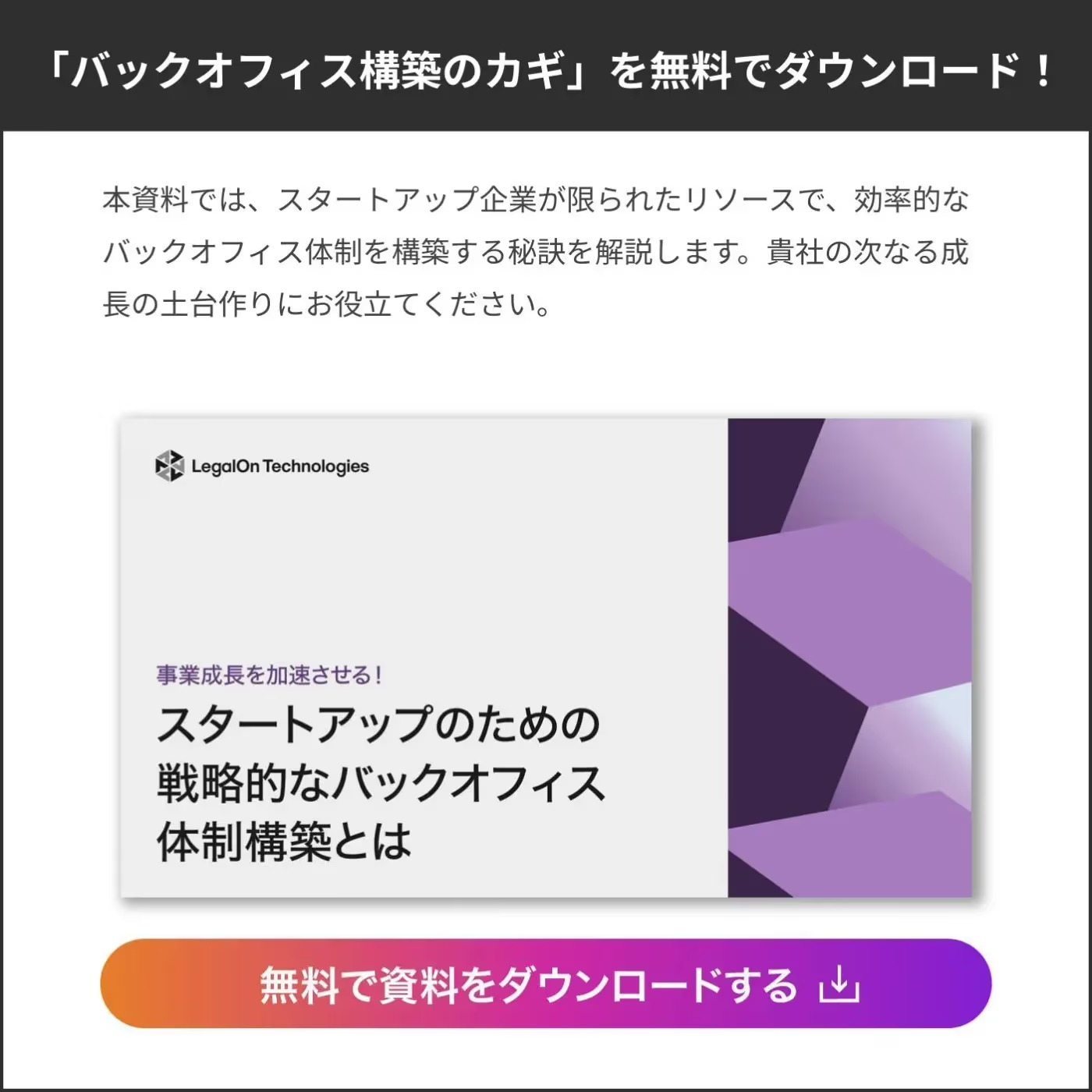報酬制度とは
報酬制度は人材を活かし、組織を成長させるために欠かせない制度です。求職者にとっては、企業を決める際の重要な項目のひとつになります。
まずは報酬制度の目的や役割、基本的な主命について見ていきましょう。
報酬制は労働対価を決定・管理するための仕組み
報酬制度とは従業員の労働に対して支払われる対価を決定・管理するための、体系的な仕組みです。単なる給与計算の仕組みではなく、企業の理念や目標を反映し、従業員の成長と組織の発展を支える重要な経営基盤となります。
報酬制度は給与や賞与といった金銭的な対価に留まりません。福利厚生などの非金銭的な報酬も含めた、総合的な制度です。企業と従業員の双方にとって、価値のある関係性を築くための土台となります。
適切に設計された報酬制度は企業の競争力を高め、優秀な人材の採用や定着にも大きく貢献します。
目的・役割
報酬制度の主な目的は、以下の3つです。
- 企業と従業員の持続的な成長を実現する
- 経営戦略の実現を支援する
- 多様な働き方の受け入れにつながる
報酬制度は企業にとっても、従業員にとっても重要な項目です。
従業員の貢献に対して適切な対価を提供することは、仕事への意欲を高め、個々人の能力開発を促進します。また明確な評価基準に基づく公平な処遇は、職場の信頼関係を醸成し、組織の一体感を高めるためにも重要です。
さらに企業にとっては、報酬制度は経営戦略の実現を支援する重要なツールとしても機能します。目標達成への動機付けを明確にし、高度な技術を持つ人材の確保につながるからです。また適切なコスト管理にも貢献します。
特に近年は多様な働き方への対応や、グローバル競争に対応した制度設計の必要性が高まっています。さまざまな働き方に対して正当な評価と報酬を提示することは、対外的な信用度の向上にも貢献する要素です。
社会の変化にともなって、報酬制度の重要性はますます大きくなっていると言えるでしょう。
報酬制度の種類
現代の企業で採用されている報酬制度には、大きく以下の4つがあります。
1.年功制度
勤続年数や年齢に応じて報酬が上昇する伝統的な制度です。技術や役職が向上するにつれて報酬も上がるという考え方ですが、転職したり、中途採用されたりした場合に正当な評価を得られにくく、特に新しい企業ではあまり採用されない傾向にあります。
2.成果主義制度
個人や部門の業績に基づいて報酬を決定する制度です。明確な成果に対する評価を重視します。成功させるためには、適切な評価制度の設定が必要です。
3.職務等級制度
職務の価値や責任に応じて報酬を設定する制度で、グローバルスタンダードとして広く採用されています。同じ仕事をしていれば同じ報酬が得られるので、従業員の納得感が得られやすいのが特徴です。
4.職能資格制
従業員の保有する能力や技能に応じて報酬を決定する制度です。報酬アップに向けたスキルの向上が期待されやすく、個々人のモチベーションを高めやすい制度です。
企業の規模や業態、経営方針によって最適な制度は異なりますが、重要なのは自社の経営戦略と整合性のとれた制度を構築し、継続的に改善していくことです。
なお近年では、これらの制度を組み合わせたハイブリッド型の報酬制度を採用する企業も増加しているほか、長期的なインセンティブ制度としてストックオプションや譲渡制限付株式などが採用されるケースもあります。
報酬制度の管理方法のポイント
報酬制度の管理には、評価制度との連動と適切なシステム運用が不可欠です。人事評価の結果を報酬に反映させるため、総合的な評価システムを構築しましょう。
不公正な評価制度によって最低賃金を下回る報酬水準や、労働条件の不当な格差が生じた場合、従業員のモチベーション低下につながるだけでなく、最低賃金法や労働基準法の規定に違反する可能性があります。同一労働同一賃金を原則とし、明確な評価基準を提示することで、従業員にとってもわかりやすい報酬制度を設定することが重要です。
また企業の成長にあわせた報酬制度の見直しも大切です。近年、社会的な賃上げへの要請が活発化しています。賃上げは経済全体の動きも左右する大きな要素です。
企業とともに従業員も成長を実感できるような、流動的な報酬制度が求められます。
企業における6つの「報酬」
いわゆる「報酬」は、複数の給与項目を組み合わせて構成されています。ここではそれぞれの役割と、特徴をまとめました。
基本給
基本給は従業員に対して、毎月支払われる固定的な給与の中心部分です。従業員にとっては生活の基盤となります。
また補助金等の公的な支援を活用する際には、基本給を基本として支給額が算出されることもあります。求職者にとっても就職後の収入を判断する基準となる、基本的な数字です。
基本給の金額は、年齢や勤続年数、職務遂行能力などを考慮して決定されます。また多くの企業では、基本給額は賞与や退職金の算定基礎にもなる金額です。近年は職務や成果に応じて基本給を決定する企業も増えてきました。
従来の要素に加えて、より柔軟な設計が求められています。
能力給
能力給は従業員が保有する技能や知識、資格などの職務遂行能力に応じて支給される給与です。職能資格制度と連動して運用されることも多く、能力の向上に応じて段階的に昇給する仕組みとなっています。
評価基準には業務知識や専門スキルのほか、問題解決力やリーダーシップ能力などが含まれ、定期的な能力評価を通じて支給額が見直されます。従業員の成長意欲を引き出し、キャリア開発を促進する効果のある報酬制度です。
ただし評価の客観性や公平性の確保が課題となるため、明確な評価基準の設定が重要となります。
職務給
担当する職務の価値や責任の大きさに応じて決定される給与です。職務分析に基づいて各職務の格付けを行い、その等級に応じた給与額を設定します。広義では役職手当等が含まれることもあります。
職務給はグローバルスタンダードとして、多くの企業で採用される報酬制度のひとつです。同一職務であれば同一賃金が原則となります。
職務と報酬の関係が明確になる一方で、柔軟な職務変更や育成的な配置転換との調整が課題となることもあります。導入時には職務記述書の作成や、等級制度の整備が不可欠です。
賞与(ボーナス)
賞与は企業の業績や個人の成果に応じて、定期的に支給される臨時的な給与です。通常、年2回(夏季・冬季)支給されることが多く、一般的には「基本給の数ヶ月分」として算出されます。
企業の収益状況や個人の目標達成度、部門の業績などが支給額に反映され、従業員の労働意欲向上と業績向上への貢献を促す重要な報酬のひとつです。近年は固定的な支給から変動型の成果主義的な運用へと移行する企業も増加し、より明確な評価基準と透明性の高い算定方法が求められるようになりました。
従業員の生活設計にも大きな影響を与えるため、安定性との両立が重要です。
インセンティブ
インセンティブとは特定の成果や行動を促進するために設定される報奨金制度で、いわゆる「出来高制」です。営業職の販売手数料やプロジェクト達成報酬、特許報奨金などが代表例として挙げられます。
目標達成度に応じて明確に金額が決定され、即時的な評価と還元が特徴です。成果の定量化が容易な職種や部門で特に効果を発揮し、短期的な業績向上や革新的な取り組みの促進に寄与します。
ただしインセンティブは過度な競争や、短期的な成果偏重を招く可能性もある要素です。チームワークや長期的な成長を阻害しないよう、慎重に制度設計を行いましょう。
諸手当
従業員の様々な状況や負担に応じて支給される、補助的な給与です。主に以下のものがあります。
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当などの生活関連手当
- 役職手当
- 資格手当
- 職務関連手当
従業員の生活支援や特定の役割に対する処遇として機能し、基本給を補完する重要な役割を果たす制度です。
近年は同一労働同一賃金への対応や制度の簡素化の観点から、手当の見直しや整理統合が進んでいます。新設する際は支給目的の明確化と、公平性・透明性の確保がポイントです。
報酬制度設計の流れ
賃金制度を設計することは、企業経営における重要な意思決定のひとつです。制度設計の手順を理解し、計画的に進めていきましょう。
効果的な報酬制度を構築するための流れをまとめました。
①現状を分析・把握する
報酬制度を設計するには、まず現状分析を行います。現在の従業員の年齢構成や給与水準、職種別の人員配置、人件費の総額などの基礎データを収集し、目標に対して変更すべき点を洗い出します。経営課題や人材戦略との整合性を確認し、新しい制度に求められる要件を明確にしましょう。
同業他社の報酬水準や制度設計についても調査を行い、市場での競争力を意識した制度設計の方向性を定めると良いでしょう。
また人材の採用・定着に関する課題や、従業員の満足度調査の結果なども参考になります。
データに基づいた綿密な分析を行い、新制度に求められる要素を特定することが、後の制度設計の成否を左右する重要な基盤となります。
②評価制度との整合性を確認する
報酬制度を設計する上で、評価制度との整合性確保は極めて重要です。評価の要素として業績、能力、行動などをどのように組み合わせるか、それぞれの評価結果をどのような比重で報酬に反映させるかを決定する段階です。評価項目や評価基準、評価の頻度が新しい報酬制度と適切にリンクするよう設計しましょう。
評価者訓練や評価の標準化など、運用面での課題も併せて検討が必要です。特に評価結果のフィードバック方法や、評価に対する異議申し立ての手続きを明確にし、制度の信頼性を確保するための仕組みづくりも重要です。
実際に評価を行う担当者にもヒアリングし、運用に支障がないか確認しながら作業を行いましょう。
③報酬体系を定める
具体的な報酬体系の設計では各給与項目の構成や、それぞれの金額の決定方法を定めます。職種や職位による違い、昇給・昇格の基準、賞与の算定方法など、細部にわたる設計が必要です。
その際には法令を遵守することはもちろん、制度の公平性や分かりやすさ、運用のしやすさも重要な要素となります。
また人件費予算との整合性を図りながら、将来的な制度の見直しや改定にも柔軟に対応できる設計とすることが求められます。事業特性にあわせた報酬制度を導入し、従業員のロイヤリティを高める工夫も大切です。
制度の持続可能性を考慮し、段階的な導入や移行措置についても検討しましょう。
④基本給を設定する
基本給の設計では職務や職能、年齢などの要素をどのように組み合わせるかを決定します。職種ごとの給与テーブルや昇給基準、初任給の水準なども含めて検討しましょう。
ただし既存の従業員の処遇に大きな影響を与える部分であるので、急激な変化は避けなくてはいけません。必要に応じて、移行時の激変緩和措置も考慮に入れてください。
また雇用形態による不合理な待遇差や、市場競争力のある水準にも注意が必要です。企業の支払能力との整合性を図りながら、適切な金額を設定しましょう。
制度導入後の運用コストも考慮し、シンプルで分かりやすい仕組みを目指します。
⑤報酬・賞与を決める
報酬や賞与テーブルは、基本給と連動する形で設計します。等級や号俸の数、昇給幅、賞与の支給月数などを算出し、シミュレーションしながら、具体的な金額を算出します。
業績連動部分がある場合は、その変動幅や評価反映方法も明確にしましょう。また各職位や職種における市場相場との比較も行い、適切な水準を設定します。
将来的な人件費の増加も見据えて、長期的な視点での持続可能性を確保することが重要です。テーブルの改定方法や、物価上昇への対応なども含めて検討し、柔軟性のある設計を行いましょう。
⑥運用のシミュレーションを行う
新制度の導入前には、必ず運用シミュレーションを実施します。実際の従業員データを用いて、新制度導入後の給与水準や人件費総額の変化を確認してください。
昇進・昇格のモデルケースや評価結果による変動、世代間の給与バランスなど、多様なパターンでの検証を行います。想定外の影響や課題を洗い出し、必要に応じて制度の微調整を行いましょう。
また人事システムでの運用面での課題、人事部門の業務負担、経理処理の変更点なども確認が必要です。円滑な制度運用の準備を整えるために、シミュレーションと修正を重ねましょう。
⑦従業員へ周知
新しい報酬制度の導入には、従業員の理解と納得が不可欠です。説明会や研修を通じて、丁寧に説明します。
特に評価方法や昇給・昇格の基準については、具体例を示しながら分かりやすく伝えることが重要です。また労働組合がある場合は事前協議を行い、合意形成を図ります。
従業員からの質問や懸念に対応する相談窓口を設置するなど、導入後のフォロー体制も整備する必要があるでしょう。
透明性の高い説明と十分な準備期間の確保が、新制度への円滑な移行につながります。
報酬制度の事例
最後に企業の報酬制度改革の具体例を、公表されている情報から見ていきましょう。
ブルドックソース株式会社
ブルドックソース株式会社では、物価上昇に対応し、従業員の生活の安定を目的として基本給のアップを行いました。さらにパート社員を含む全従業員に、一律5万円の特別賞与を支給しています。また2021年4月からは新しい人事制度として、シニア社員制度が導入されました。これは60歳の定年退職を迎えた後、70歳までの10年間を継続して雇用するものです。査定昇給や賞与支給のための業績評価も行われ、社員のモチベーション向上につなげています。
セコム株式会社
2022年4月の3,000円のベースアップ実施に加え、2022年の秋からは改定を一部前倒しする形で2,000円のベースアップを決定しました。セコムと同じ給与体系を持つグループ会社もこれに追随しています。同社では労使の協議体として、社長をはじめとした人事・業務の担当役員・責任者と労働組合(セコムライブリィーユニオン)が参加する「セコム社員中央審議会」が設置されています。同会は春季労使交渉での追加開催分を含めると、年14回の開催です。物価高への迅速な対応としてのベースアップも、従業員の声に耳を傾け、直ちに課題を解決するという姿勢の一例とされています。
報酬制度について解説しました
報酬制度は企業と従業員をつなぐ重要な制度です。適切な制度設計と運用によって従業員の成長意欲を引き出すことは、企業の競争力強化にもつながります。
報酬制度の設計で重要なのは、以下の3つのポイントです。
- 自社の経営戦略や目標と整合性のとれた制度設計を行うこと
- 評価制度と綿密に連動すること
- 継続的に制度を見直し、改善すること
報酬制度は社会環境の変化や企業の成長に合わせて、柔軟に制度を改定していく必要があります。従業員の声が届き、ともに成長を実感できる報酬制度の設計は、企業成長にとっても不可欠な仕組みです。