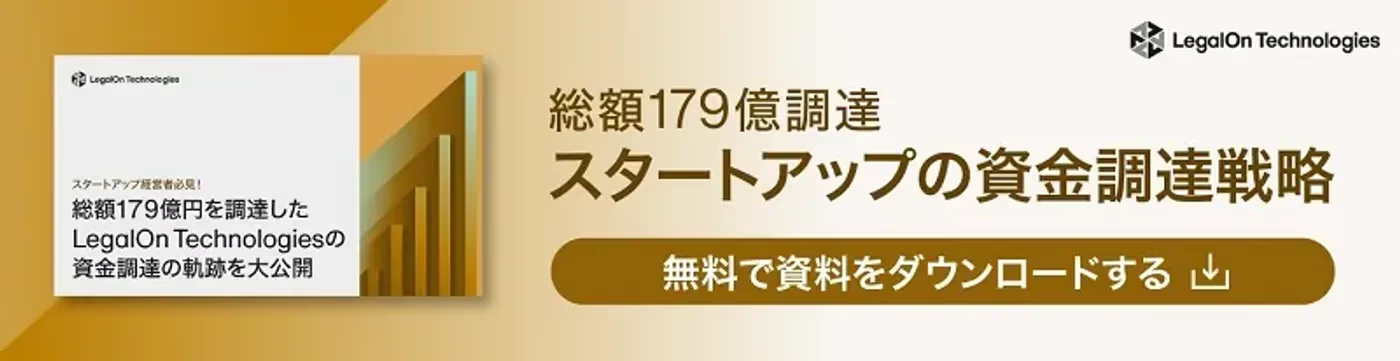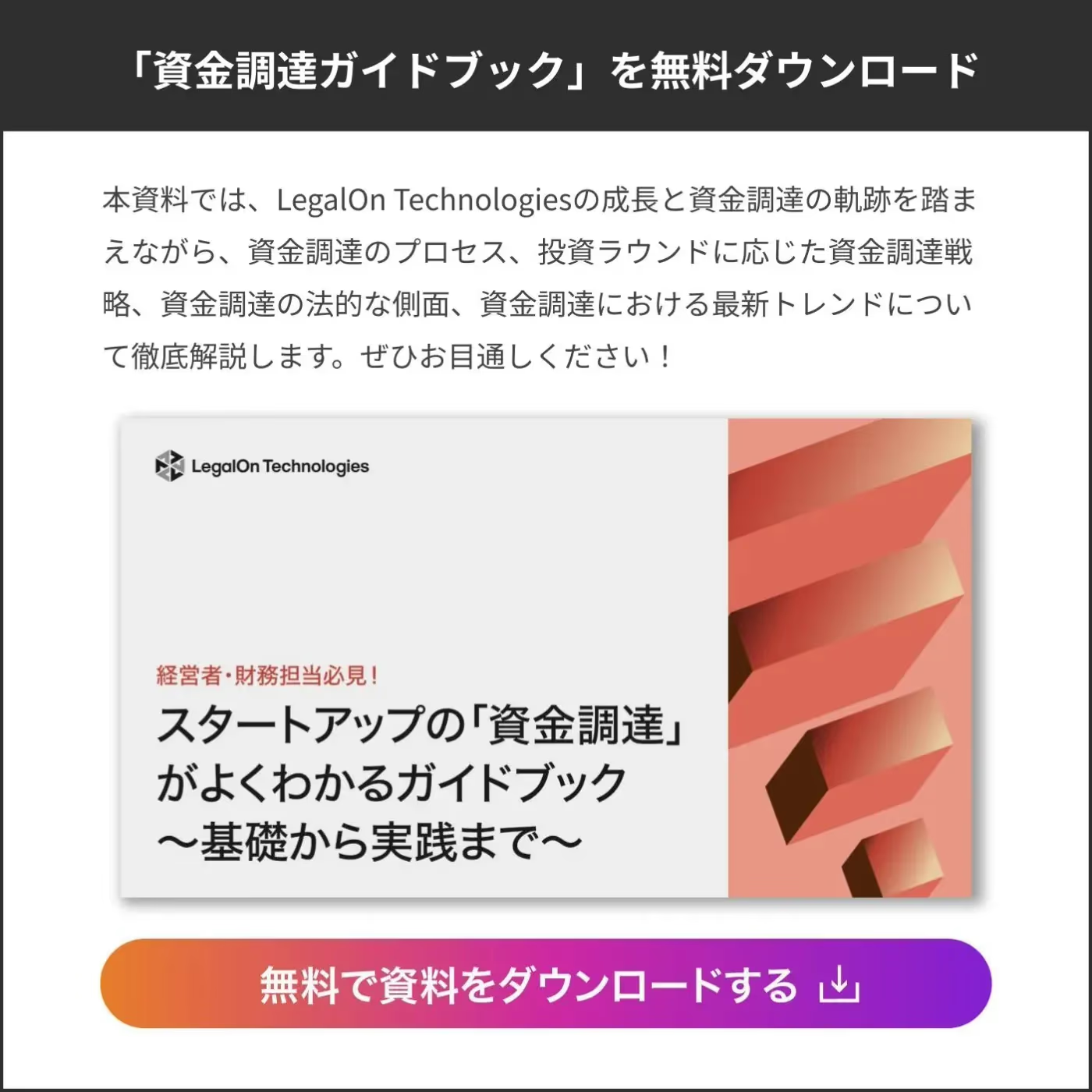CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?
CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは、特定の事業会社が自社の資金を用いて組成した、スタートアップ企業やベンチャー企業など未上場の新興企業に出資や支援を行う活動組織です。ここでいう事業会社は投資企業ではなく、その他の業種を本業としています。自社の事業に何かしら関係性のある企業に投資することで、本業とのシナジーを生むことが主な目的です。CVCによる出資は1社単独で行われる場合と、複数の事業会社が共同でファンドを組成して出資する場合があります。
CVCとVCの違い
CVCと頻繁に比較される事業体に、VC(ベンチャーキャピタル)があります。VC(ベンチャーキャピタル)は、CVCと同様に新興企業に資金を出資・支援する機関です。
CVCとVCの主な違いは、出資を行う目的です。前述した通り、CVCは事業会社が自社の本業に関係のある新興企業に投資することで、本業とのシナジーで利益をもたらすことを目的としています。これに対して、VCは出資で新興企業の株式を取得し、数年後にその企業の株式価値向上によってキャピタルゲインを得ることが目的です。
こういった目的の違いもあって、出資対象の企業の選定基準も異なります。VCでは業種に関係なく企業の成長性を重視しますが、CVCは本業との相乗効果への期待がより重視されます。
CVCとM&Aの違い
CVCの「関係性のある企業に投資する」という内容は、一面でM&Aによる買収と近いと捉えられる場合があります。いずれの場合も投資する側の企業が、自社のビジネス拡大を目的として投資する点で共通点がみられます。
一方で、CVCとM&Aで異なるのが「必要となる金額」と「対象企業への影響力の強さ」です。
M&Aは合併・買収を意味し、買収された企業の経営権は吸収・買収する側に移ります。ただし、経営権を獲得するためには対象企業の株式を一定以上取得しなくてはならず、必要となる金額は莫大です。
これに対してCVCは、対象企業の経営方針や判断に一定の影響力があるものの、支配しているわけではありません。そのため支援やアドバイス、要望といったレベルの影響力にとどまります。その分少ない投資で経営権は対象企業のままであり、投資が結果失敗に終わってもM&Aほどの損失はありません。
M&Aの方がよりリスクがあり、先々に回収できるリターンが大きい場合に取られる方法であることを覚えておきましょう。
4つのCVC投資スキーム
CVCからの投資を受ける際は、出資元のスキームによって得られるメリットや関係性が大きく変わります。CVC投資は主に以下の4つのスキームに分類されます。
- 事業会社本体による直接投資
- 事業会社がCVC子会社・関連会社を設立して投資
- 事業会社が自社専用ファンドを既存VCと連携して組成し投資(二人組合)
- 事業会社が既存ファンドにLP(有限責任組合員)として参加して投資
事業会社本体からの直接投資は、投資判断が迅速で、事業連携がスピーディに進む一方、経営判断や戦略方針への影響力が強まるリスクがあります。
CVC子会社・関連会社を通じた投資は、投資専門人材による成長支援が受けられ、親会社との適度な距離感を保ちながら柔軟な事業連携が可能です。
二人組合スキームのCVC投資では、既存VCの介入により資金調達プロセスは一定の透明性と効率性が確保されます。一方でVCのネットワークを活かしながら事業会社との連携機会も得られますが、交渉はやや間接的になります。
既存ファンドへのLP出資による投資は、本体の事業会社との直接的な連携は期待しにくい点に注意が必要です。一方で広く資金調達の選択肢を持っておきたい場合や、市場動向を把握するために一定の接点を持っておきたい場合には有効的な選択肢です。
出資の背後にある意図を正しく読み解き、自社にとって本当に価値のあるパートナーシップを築くことが重要です。
スタートアップ企業がCVCから投資を受けるメリット
CVCはスタートアップ企業の資金調達手段として、上場前の資金調達ラウンドでは代表的な出資元のひとつとなっています。ではスタートアップ企業がCVCから出資を受ける場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは代表的な3つのメリットを解説していきます。
事業会社の本業と連携できる
CVCにおける出資元である事業会社は、自社の本業と関係し利益をもたらすビジネスを行うスタートアップ企業へ投資します。スタートアップ企業が成功すれば事業会社の事業拡大にもつながるため、経営ノウハウや販路、人材などのリソース提供を受けられることが大きなメリットです。スタートアップ企業にとって、出資元企業は自社よりも圧倒的に規模が大きく、その事業会社の本業と連携することで、自社ビジネスの拡大が期待できます。
また出資元の事業会社が、スタートアップ企業の技術やビジネスを自社のプロダクトに組み込むケースもあります。この場合、スタートアップ企業が収益基盤を大きく強化することが可能です。
企業の社会的信用や認知度が向上する
CVCによって規模や影響力の大きな企業から出資を受けることができれば、その影響で投資を受けたスタートアップ企業の社会的信用が向上します。創業したてで金融機関などから融資を受けづらいスタートアップ企業にとって、社会的信用の向上で融資や出資を受けやすくなるのは大きなメリットといえるでしょう。
また、CVCによる出資を受ける際にプレスリリースが発行される場合があります。大企業から発信された出資の情報を目にする関係者は多く、ここに社名が掲載されることで認知度も向上します。成長段階での認知度の向上は、追加の資金調達や上場に好影響を及ぼすため、スタートアップ企業にとって見逃せない利点です。
返済義務が無い資金調達ができる
スタートアップの資金調達には出資と融資があります。融資は返済義務と利息負担が伴い、事業成長が停滞した際には資金繰りを圧迫するリスクがあります。
それに対してCVCによる出資は返済義務がなく、資金繰りの負担を軽減できます。精神的なプレッシャーも少なく、事業成長に集中しやすい点はスタートアップにとって大きなメリットです。
CVC選定時の注意点
CVCからの投資は、スタートアップ企業にとって多くのメリットがあります。しかしメリットだけでなく、CVCの性質から来る注意点もあることを知っておかなくてはなりません。成長段階で利用する資金調達手段としてCVCを考えている場合は、以下に示す注意点を踏まえてCVCを選定してみましょう。
①親会社の事業領域とシナジーの有無
まずはCVCの親会社の事業領域と、自社の事業や技術との親和性があるかを確認しましょう。親会社の事業領域が同業界または隣接業界であれば、将来的に業務提携や販売チャネルの共有など、実務的なシナジーが期待できる可能性が高いです。
例えばSaaS系スタートアップであればIT系大企業のCVC、ヘルスケア領域であれば製薬会社や医療機器メーカーのCVCが親和性が高いでしょう。
チェックポイント
- 同業界または隣接業界であるか?
- 提携事例があるか?
②投資目的の確認(財務リターン vs 戦略リターン)
CVCによって投資の目的は大きく異なり、純粋に財務的なリターンを重視している場合もあれば、将来的な戦略的提携やM&Aを前提とした投資を行う場合もあります。自社が求めているのが単なる資金調達なのか、あるいは販路拡大や技術開発支援など成長支援まで含めた関係構築なのかを明確にした上で、相手の投資スタンスを見極める必要があります。
チェックポイント
- CVCの投資ポリシーは公開されているか?
- これまでの投資実績のイグジット状況は?
イグジットとは、創業者や投資家が株式を売却して投資資金を回収する手法です。主なにIPOとM&Aに分けられます。以下の記事ではそれぞれの詳細について解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
③投資後の関与レベル
CVCによっては、出資後にどの程度経営に関与してくるかに大きな違いがあります。CVCから取締役を派遣して経営をサポートするなど、経営方針への影響力を強めるケースも見られます。スタートアップとしては、成長戦略に支障が出ない範囲での適切な関与かどうかを事前に確認しておくことが必要です。
チェックポイント
- CVCが取締役席の取得を求めているか?
- 取締役派遣がある場合、議決権比率にどのような影響があるか?
- 派遣される取締役との相性や意思疎通のしやすさを事前に見極める。
CVCから投資を受けた企業の事例
ここからは実際にCVCから投資を受けた企業の実例を紹介していきます。
出資元の事業会社や出資を受けた企業を知っていれば、よりCVCの効果やイメージが湧きやすくなります。今後、CVCによる資金調達を検討しているなら、参考にしてみましょう。
株式会社AIメディカルサービス
株式会社AIメディカルサービスは、内視鏡画像による診断を支援するAIを開発しているAIベンチャー企業です。2019年10月に行われた第三者割当増資で、約46億円を調達したと発表しました。VCであるグロービス・キャピタル・パートナーズなどの他、ソニーイノベーションファンドや日本郵政キャピタル、アフラックなどのCVCが出資を行いました。
調達された資金は、AIメディカルサービスが開発するAI製品の医療機器としての承認に向けた臨床試験の費用として利用すると発表されています。
参考:日本経済新聞「AIメディカルサービス、内視鏡AI開発に46億円調達」
株式会社エネコートテクノロジーズ
株式会社エネコートテクノロジーズは、次世代型の折れ曲がる太陽電池として期待されている「ペロブスカイト太陽電池」を開発する京都大学発のスタートアップ企業です。2024年7月の出資で、55億円を調達しました。CVCとして出資したのは、トヨタ自動車や日揮グループ傘下のCVCです。調達された55億円は「ペロブスカイト太陽電池」の量産工場稼働開始に向けた資金として利用することが発表されています。
また日揮グループによると、エネコートテクノロジーズへの出資が2022年に続けて追加出資となっていることから、期待度の高さ次第で追加支援が受けられることがわかる事例です。
参考:日本経済新聞「曲がる太陽電池、EV向け量産 京大発にトヨタ系など出資」
日揮ホールディングス株式会社公式HP - 2024ニュースリリース「CVCファンドを通じて、次世代太陽電池を開発するエネコートテクノロジーズに追加出資」
日本のCVC3選(投資方針・実績付き)
三菱UFJキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)に属し、成長企業への投資を通じて持続可能な社会の実現に貢献してきました。
投資傾向
- 長期的視点での支援:
企業の初期段階から成長段階に至るまで、持続可能な成長を支援します。 - ESGへの配慮:
環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への配慮を重視した投資を行い、持続可能な社会の実現を目指します。 - 多様な業界への投資:
ライフサイエンスやテクノロジー分野を中心に、幅広い業界への投資実績があります。
投資実績(一部)
- 株式会社LegalOn Technologies【IT(B to B)】:
AI法務プラットフォームLegalOn Cloud(リーガルオンクラウド)の開発・運営など - 株式会社ヤマップ【IT(B to C)】:
登山アウトドア向け Web サービス・スマートフォンアプリ「YAMAP」の開発・運営など - テンセグリティファーマ株式会社【ライフサイエンス】:
戦略上開発中止となった治療薬候補を独自の創薬視点で評価・回収し、グローバルでの臨床開発を通じてPOCの取得を目指す - 株式会社REJECT【サービス】:
プロeスポーツチーム「REJECT」の運営及びeスポーツ選手のマネジメント・プロモーション事業 - 株式会社3DC【製造業】:
バッテリーの長寿命化、高容量化を実現する新炭素材料GMSの開発/製造
三菱UFJキャピタル株式会社からの資金調達を実現した株式会社LegalOn Technologiesの事例について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の参考資料もご覧ください。
KDDI株式会社
KDDI株式会社は、スタートアップとの共創を目的としたCVC「KDDI Open Innovation Fund」を運営しています。同ファンドは、KDDIグループの技術やビジネス知見を活用し、AIやDeepTechなどの先端分野において有望なスタートアップへの投資を通じて、新たな事業の創出を目指しています。
投資傾向
- 幅広い投資領域:
AI、DeepTech、モビリティ、ロボティクスなど、多岐にわたる分野への投資を行います。 - ファンドの多様性:
複数のファンドを運用し、各ファンドごとに異なる投資対象や運用期間を設定しています。 - 国内外への投資:
国内外のスタートアップ企業に対して、積極的な投資を実施しています。
投資実績(一部)
- Sakana AI株式会社【 IoT/AI 】:
生成AI領域における基盤モデルの研究開発 - 株式会社 QunaSys【 DX 】:
量子コンピュータを用いたソフトウエア開発 - 株式会社ギフティ【 Consumer 】:
スマートフォンからメールやLINEなどでギフトを贈れる、ソーシャルギフトサービス「giftee」の運営。 - Chemix, Inc. (US)【 IoT/AI 】:
生成AIによる次世代バッテリー開発 - SHANGHAI YOGO ROBOT Co., Ltd. (China)【 IoT/AI 】:
自動で複数用途に機能を切り替え、エレベータなどビル設備と連携する屋内向け多機能配送ロボット開発
HENNGE株式会社
HENNGE株式会社は、クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」を中心に、BtoB向けITソリューションを提供するSaaS企業です。同社はテクノロジーと現実のギャップを埋めることを理念とし、スタートアップ企業への投資を通じて新たな価値創出を目指しています。
投資方針
事業領域:
BtoBのITサービス(SaaS, IoT, AI等)を提供しているスタートアップ
HENNGEとのシナジー:
HENNGEの事業や将来の事業に対してシナジーのある、独⾃の要素、技術を保持しているスタートアップ
事業ステージ:
シード、アーリー、シリーズA中⼼対象地域⽇本・海外
引用:スタートアップ向け投資支援 | HENNGEとは | HENNGE株式会社(へんげ)
投資実績(一部)
- 株式会社kickflow【IT(B to B)】:
ワークフローツールkickflow(キックフロー)の開発・運営 - DIGGLE株式会社【IT(B to B)】:
予実管理クラウドDIGGLEの開発・運営 - SecureNavi株式会社【IT(B to B)】:
企業の情報セキュリティ対策を支援するソフトウェアSecureNaviの開発・運営
CVCについて解説しました
CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)は、事業会社が本業と関係性のある新興企業(スタートアップ企業やベンチャー企業)に出資・支援を行う投資ファンドです。スタートアップ企業がCVCによる投資を有効活用できれば、返済義務の無い資金調達手段として大幅な事業拡大や企業成長が期待できます。CVCの母体となる事業会社から受ける影響などの注意点を踏まえて、スタートアップビジネスの拡大に役立てましょう。
この記事ではCVCの概要、VCとの違い、投資を受けるメリット、投資を受ける場合の注意点、CVCから投資を受けた事例を解説してきました。
CVCの利用はスタートアップの資金調達ラウンドに密接な関係がある、代表的な資金調達方法です。これを読んだスタートアップ企業の経営者の方が、どのようにCVCによる資金調達を行うかの参考となれば幸いです。