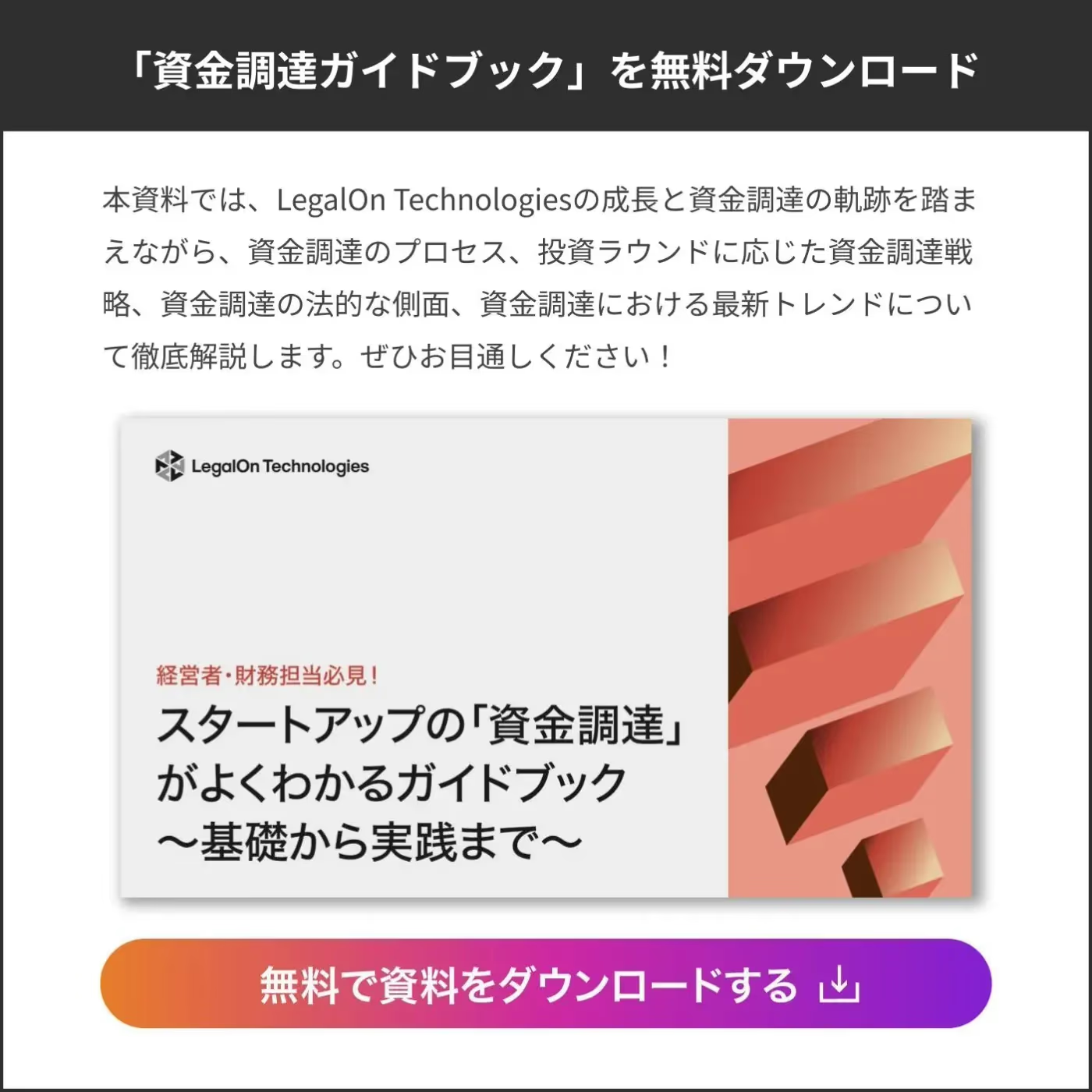赤字決算とは
赤字決算とは、法人の会計期間において収益よりも費用が上回り、最終的な利益がマイナスになる状態のことです。
個人事業主においても同様に、1月1日から12月31日までの収入から必要経費を引いた際に収支がマイナスになった状態を赤字決算といいます。
赤字決算は、事業の継続不可能を意味するわけではありません。例えば、一時的な設備投資や景気の影響による売上減少などが原因で赤字になっている場合、適切な経営判断や資金調達を行うことで持ち直すことが可能です。
しかし赤字が続くと経営の健全性が損なわれ、企業の資金繰りが厳しくなります。運転資金の確保が難しくなり資金ショートを起こすと、事業継続が困難になるため早期の対処が重要です。
赤字決算と債務超過、資金ショート、黒字倒産の違いについて詳しく見ていきましょう。
債務超過との違い
債務超過は、企業が所有する総資産よりも負債のほうが多くなり、純資産がマイナスの状態になることです。
赤字決算は一時的なものとして経営改善によって立て直せる可能性がありますが、債務超過に陥ると、企業がすべての資産を売却して現金化しても負債を完済することができず、経営の継続が困難になります。
債務超過の状態が続くと金融機関からの融資を受けにくくなり、資金調達の手段が限られるため、企業存続の危機に直面する可能性が高まります。
資金ショートとの違い
資金ショートは、企業の運転資金が枯渇し、支払いや仕入れができなくなる状態です。赤字決算であっても、十分なキャッシュフローを確保できていれば、経営を継続することは可能です。しかし黒字決算で利益が出ている場合でも、売掛金の回収が遅れたり、予期せぬ大きな支出が発生したりすると、手元資金が不足し資金ショートを起こすことがあります。
資金ショートは、取引先への支払いや従業員の給与支払いが滞るなど、企業の信用を大きく損なう要因となるため、黒字倒産につながるリスクがあります。
以下の記事では資金ショートについて詳しく解説しています。ぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>資金ショートとは?原因や予防・対処法、資金繰りの基本を解説
黒字倒産との違い
黒字倒産とは、会計上は黒字であるにもかかわらず、資金繰りが悪化して倒産することです。赤字決算は収益が費用を下回る状態ですが、手元資金が十分に確保されている場合、事業の継続は可能です。しかし黒字倒産の場合は、利益が出ていたとしても資金繰りが悪化し、債務の返済や取引先への支払いができなくなることで経営が立ち行かなくなります。
黒字倒産の主な原因は、売掛金の回収遅延や過剰な在庫の抱え込み、大規模な設備投資などです。売上が好調で利益が出ていても、現金化できる資産がなければ、運転資金を確保することが難しくなります。
赤字の種類
赤字には、次の種類があります。
売上総利益の赤字
売上総利益は、売上高から売上原価を差し引いた金額であり、これがマイナスになっている場合、仕入れや製造にかかるコストが売上を上回っていることを意味します。
計算式は下記のとおりです。
- 売上総利益=売上高-売上原価
例えば、1万円で仕入れた商品を6,000円で販売すると、事業として成立しません。売上が増えても利益を得られず、経営が成り立たなくなるため、コスト削減や価格設定の見直しが必要です。
営業利益の赤字
営業利益は、売上総利益から販売費や一般管理費(販管費)を差し引いた金額のことで、赤字になっている場合は広告費や人件費、家賃などの固定費がかかりすぎている可能性があります。
計算式は下記のとおりです。
- 営業利益=売上総利益-販管費(販売費及び一般管理費)
売上総利益が黒字であっても、販管費が過剰であると営業利益は赤字となり、経営を圧迫します。不要な経費を見直し、効率的な運営を目指すことが重要です。
経常利益の赤字
経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いた金額です。借入金の利息負担が大きすぎる場合や、不採算な投資による損失が発生している場合に赤字になります。
計算式は下記のとおりです。
- 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
本業の収益が安定していても、財務管理が適切でなければ利益は圧迫されてしまいます。利息負担の軽減や財務戦略の見直しを行い、経常利益の改善を図ることが必要です。
当期純利益の赤字
当期純利益は、経常利益に特別利益を加え、特別損失を差し引いて算出する企業の最終的な業績を示す金額です。固定資産の売却損や一時的な損失によって赤字になることがあります。
計算式は下記のとおりです。
- 当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失
一時的な要因による赤字であれば、翌年度に改善できる可能性がありますが、継続的な赤字が続く場合は、事業全体の収益構造の見直しが必要です。
創業赤字
創業赤字は、新しく事業を立ち上げた際に生じる赤字です。創業時はオフィスの契約費用や設備投資、採用費などの初期コストが発生します。事業が軌道に乗るまでの間は売上が安定しないことから、赤字になりやすい傾向にあります。
創業赤字自体は問題ではありませんが、資金繰りを適切に管理し、早期に黒字化するための計画を立てることが重要です。
恒常赤字
恒常赤字は、長期間にわたって赤字が続く状態のことです。売上が伸び悩み、経費がかさむことで収益を確保できない場合、企業の存続が危ぶまれます。
市場の競争激化や外部環境の変化によって事業の成長が見込めない場合は、事業の再編や不採算事業の撤退を検討することが必要です。
臨時的な赤字
臨時的な赤字は、突発的な出来事による一時的な損失が原因で発生する赤字です。例えば、設備の故障や自然災害、訴訟費用の発生などが該当します。多額の損失が発生すると資金繰りが悪化し、企業の経営に支障をきたす可能性があります。事業継続のためには、適切なリスク管理や資金計画の見直しが必要です。
赤字決算のメリット
赤字決算には、次のメリットがあります。
税金が一部免除される
法人税は原則として課税所得に対して課されるため、決算で赤字が確定し、課税所得がゼロまたはマイナスとなれば、法人税を支払う必要はありません。同様に法人事業税も課税所得に基づき、赤字決算の場合は納税義務がなくなります。
ただし赤字であってもすべての税金が免除されるわけではなく、消費税や法人住民税の均等割は支払いが必要です。また、会計上の利益と法人税法上の課税所得は必ずしも一致しないため、税務調整の結果によっては、赤字決算であっても法人税や法人事業税が発生する場合があります。
赤字(欠損金)が繰り越せる
法人が赤字決算となった場合、損失を翌期以降の課税所得と相殺できる「繰越欠損金控除」を利用できます。赤字で発生した欠損金を将来の黒字決算時に控除することで、法人税の軽減が可能です。繰越可能な期間は最長10年間です。
控除を受けるためには、赤字が生じた会計年度において青色申告法人として確定申告を提出している必要があります。また、翌年以降も継続して確定申告を行うことも条件です。
適用範囲は、資本金1億円未満の中小企業であれば赤字分を全額控除できますが、資本金が1億円を超える法人は、課税所得額の50%が上限です。
赤字(欠損金)の繰り戻し還付が受けられる
赤字決算となった場合でも、前期が黒字で法人税を納めていれば、「欠損金の繰戻し還付」を利用することで、前期に納付した法人税の一部を取り戻すことができます。
当期の赤字額と前期の黒字額を通算することで、前期分の法人税を軽減し、その差額を還付金として受け取ることが可能です。
適用されるのは、資本金1億円以下の青色申告法人に限られており、資本金5億円以上の法人の100%子会社は対象外です。また、繰戻し還付の対象となるのは前期に納付した法人税のみで、それ以前の年度に支払った法人税の還付は受けられません。
赤字決算のデメリット
赤字決算には、次のデメリットがあります。
金融機関の債務者区分が引き下げられる
赤字決算が続くと、金融機関が行う信用格付けに影響を及ぼし、債務者区分が引き下げられる可能性があります。金融機関は、企業の財務状況や返済能力をもとに、正常先・要注意先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先といった区分を設けています。
赤字が慢性的に続く企業は「要注意先」と判断されやすく、融資の審査が厳しくなることが通常です。一方で創業時の赤字や一時的な赤字であれば、企業の将来性が評価され、信用格付けに大きな影響を与えない場合もあります。
既存の融資先からの信用が低下する
金融機関は貸し倒れのリスクを最小限に抑えるため、赤字が常態化している企業の信用力を厳しく評価する傾向があります。その結果、追加融資の審査が厳しくなるだけでなく、既存の融資条件が見直される可能性も生じます。
経営の健全性を維持するためにも、財務状況を早期に改善し、金融機関からの信頼を損なわないようにすることが重要です。
債務超過や倒産リスクが高まる
赤字決算が長期間続くと、企業の資金繰りは徐々に悪化し、債務超過に陥る可能性が高まります。債務超過によって運転資金の確保ができなくなり、取引先への支払いや従業員の給与支払いが滞る可能性が生じます。
最悪の場合、資金ショートを起こし、倒産することになりかねません。
従業員のモチベーションが下がる
企業の財務状況が悪化し、赤字決算が続くと、従業員の間でも不安が広がります。特に給与の遅延やボーナスの減額、人員削減の可能性が生じると、社員のモチベーションが低下します。また、優秀な人材の流出につながるため、ますます利益が下がることになりかねません。
税務調査が入る可能性が高まる
法人税は企業の利益に対して課される税であり、赤字であれば法人税の支払い義務が発生しません。この仕組みを悪用し、意図的に赤字を計上して法人税を逃れようとする企業がいるため、税務署は赤字が続く企業に対して不正の可能性を疑うことがあります。
適正な会計処理を行っていれば問題はありませんが、不正を疑われた場合は、税務調査が実施される可能性があります。日頃から正確な帳簿管理と適切な会計処理を心がけることが大切です。
資金調達時に経営者保証が必須になる
中小企業が金融機関から融資を受ける際、多くの場合「経営者保証」が求められます。一定の利益を維持し、健全なキャッシュフローを確保していれば、保証なしで融資を受けられる可能性もあります。
しかし赤字決算の状態では、会社の経営リスクが高いと見なされ、金融機関は貸し倒れリスクを回避するため、経営者保証を求められることが通常です。
経営者保証を付帯すると、事業が失敗した場合でも経営者自身が負債を背負い、個人資産を差し押さえられるリスクが発生し、再起が困難になることもあります。
赤字でも直ちに問題が起きるわけではないケース
次のようなケースでは、赤字でもすぐに債務超過や資金ショートに陥ることはないでしょう。
原価率の上昇が一時的な場合
売上総利益が赤字になった場合でも、一時的な原価率の悪化が原因であれば、経営に深刻な影響を与えるとは限りません。
例えば原材料やエネルギー価格の高騰が一時的なものであり、今後コストが下がる見込みがある場合は、長期的には売上総利益の改善が期待できます。
また新商品の発売前に、市場競争力を高めるために一時的に値引きを行うケースもあります。このような場合、短期的には赤字になっていても、新商品が軌道に乗れば利益率が向上し、最終的に業績は回復するでしょう。そのため、一時的なコスト増加による赤字は、将来的な収益向上を見据えた戦略の一環として捉えることができます。
減価償却費が赤字の要因になっている場合
会社が固定資産を購入すると、その支出は耐用年数にわたって減価償却費として計上します。減価償却は会計上の処理であり、実際に現金が流出するわけではありません。そのため、減価償却費の影響で赤字になっている場合でも、企業のキャッシュフローが健全であれば、経営上の問題は少ないといえます。
本業以外の支出が原因で赤字になっている場合
営業活動以外の支出が一時的に増加することで赤字になることがあります。例えば、借入金の利息負担や為替変動による損失、有価証券の売却損などが該当します。本業の収益とは直接関係がないため、一時的な要因であれば翌期以降の業績には大きな影響を与えないことが通常です。
特別損失が赤字の原因である場合
特別損失とは、通常の事業活動の中では発生しない特別な損失のことです。固定資産の売却損や資産価値の減損処理などが該当します。
企業が経営方針の転換や事業整理を進める際、不要な資産を売却することで一時的に損失が発生することがありますが、これは企業の経営基盤を強化するための戦略的な判断によるものです。
このような損失が要因で赤字となった場合、翌期以降は特別損失が発生しない可能性が高く、経営全体に与える影響は限定的でしょう。
赤字から脱却する方法
赤字から脱却するために、次の方法を検討しましょう。
キャッシュフローを健全化する
赤字からの脱却には、キャッシュ・フローの管理が必要です。事業の収入と支出のバランスが崩れると、売上が立っていたとしても資金が不足し、運営が立ち行かなくなる可能性があります。
そのため、売上債権の回収を早めることや、取引先への支払い条件を調整することで、資金の流れをスムーズにしましょう。
以下の記事ではキャッシュフローについて詳しく解説しています。ぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>キャッシュフローとは?計算書の読み方・作り方をわかりやすく解説!
商品の価値を高めて売上の拡大を図る
赤字を解消するためには、売上を伸ばすことが最も効果的です。しかし、単に販売数を増やすだけではなく、商品やサービスの付加価値を高めて顧客単価を向上させることも大切です。
例えば、オプションサービスを追加してアップセルを促したり、関連商品を提案してクロスセルを実施したりすることで、既存顧客の購買単価を引き上げられます。
過剰な在庫を圧縮する
在庫の管理が適切でないと、保管コストが増大し、キャッシュフローの悪化を招きます。
定期的な在庫整理を行い、売れ行きが悪い商品や、長期間動きがない商品、過剰な在庫を抱えないようにすることが重要です。売れ残りの商品は、在庫処分セールや値引き販売を実施することで、できるだけ早く現金化しましょう。
収益性の低い事業を削減する
複数の事業を展開している場合、不採算部門が赤字の要因になっているケースがあります。利益を生み出していない事業は、思い切って撤退することで経営の効率化を図ることができます。
収益性の高い事業に集中し、経営全体の収益を向上させましょう。
仕入れコストの最適化で利益率を改善する
赤字の解消には、コスト削減の取り組みも欠かせません。取引先と価格交渉を行い、より良い条件で仕入れができるよう調整したり、複数の仕入れ先から見積もりを取り、最適な業者を選定したりしましょう。
また、広告宣伝費やオフィスの維持費など、固定費を削減することで、経営の安定化につながります。
金融機関と交渉し、返済スケジュールを調整する
融資を受けている企業の場合、資金繰りが厳しいときはリスケジュール(返済条件の変更)について相談しましょう。
毎月の返済額を減額したり返済期間を延長したりすることで、キャッシュフローの改善につながります。金融機関も、取引先企業の経営が破綻することを避けたいと考えているため、誠実な対応をすれば柔軟に応じてもらえる可能性があります。
赤字決算の仕組みと対策について解説しました
赤字決算が続くと、企業の存続そのものが危ぶまれる可能性が高くなります。しかし、経営の課題を正確に把握し、適切な改善策を講じることで、黒字転換を図ることは十分可能です。
赤字決算のリスクを最小限に抑え、持続可能な経営を実現するためには、短期的な対策だけでなく、中長期的な視点を持つことが不可欠です。
財務状況を定期的にチェックし、適切な経営戦略を策定することで、安定した事業運営を目指しましょう。