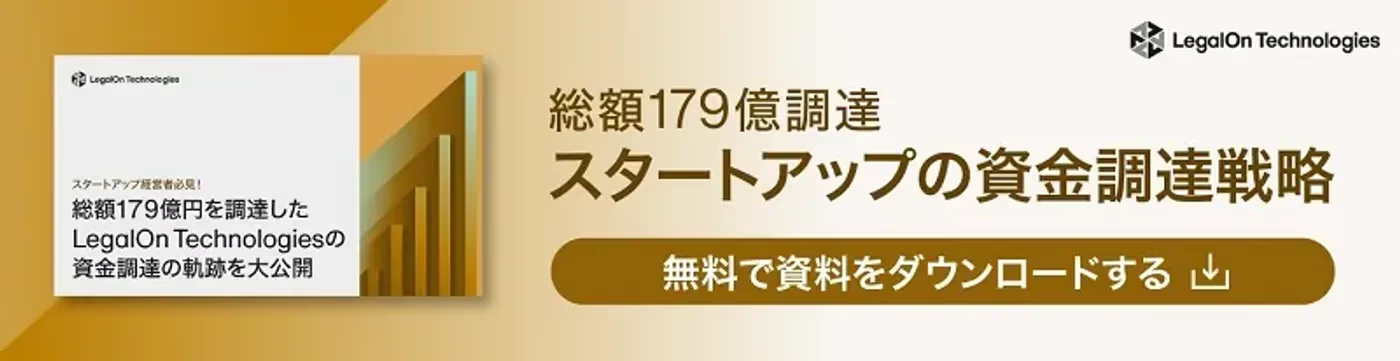設備資金とは
設備資金とは、事業者がビジネスの創業や運営に必要な設備の拡充・更新に伴う支出に充てるための資金です。設備資金の投入は自己資金で行われるのはもちろん、銀行からの融資によって賄われるケースもあります。またリース契約を締結することで支出を抑え、最小限の設備資金の確保で賄うというのも可能です。
事業の規模にもよりますが、設備資金として確保すべき金額は大きくなる傾向にあります。そのため、自己資金だけで設備資金を賄うことが難しく、多くの事業者は銀行からの融資を頼るのが一般的です。
あとで詳しく解説しますが、設備資金を借り入れる場合にはその使い道なども正しく把握しておく必要があります。なので、何が設備資金に含まれるのか、他の資金とはどのような違いがあるのかを理解し、円滑な融資に繋げましょう。
設備資金の主な項目
設備資金として含まれる主な項目には、以下が挙げられます。
物件の敷金・礼金
物件の敷金・礼金は、金融機関や用途により設備資金として扱われる場合があります(運転資金として扱われる場合もあります)。家賃の支払いとは別途一括で支払いが必要なので、まとまった資金の用意が欠かせません。
物件の内装工事費
内装工事費も、敷金や礼金同様に必ずといって良いほど発生する支出です。居抜き物件を契約するのであれば、費用は小さく抑えられるものの、それでもある程度の工事費は免れません。
十分な設備資金を確保して、満足のいく内装工事を実現することが大切です。
備品購入費用
業務に必要な店舗什器やOA機器などは、備品購入費用に含まれます。設備資金によって備品購入費用を賄い、開業や事業の継続性を確保することが大切です。
業務に必要なソフト導入費用
上で紹介した費用はハードウェアのものが大半を占めますが、ソフトウェアの導入費用も設備資金で賄います。会計システムや勤怠管理システムなど、事業運営に必要なソフトの購入もまとまった資金が必要です。あらかじめ計上して、資金として確保することが求められます。
近年はあらゆる領域でDXが進んでいるため、ソフト導入にかける予算は潤沢に確保しておきたいところです。
Webサイト作成費用
店舗の公式サイトや予約サイトなどを設置する際に発生する費用も、設備資金で賄います。インターネットを使った集客や情報発信は重要性が高く、デザイナーを入れるなどして丁寧に作るのが良いでしょう。
設備資金と運転資金の違い
このように、設備資金の範囲で賄うべき支出は多岐に渡ります。一方、設備資金と似たような概念としてあるのが、運転資金です。設備資金と運転資金はどちらも事業に必要なお金である一方、異なる役割を果たします。
設備資金と運転資金の主な違いを、以下の表にまとめました。
設備資金
- 使い道:事業に必要なものの購入資金など
- 借りやすさ:借りにくい
- 返済期間:長め
運転資金
- 使い道:事業を継続するための資金
- 借りやすさ:借りやすい
- 返済期間:短め
設備資金と運転資金では、まず使い道に大きな違いがあります。設備資金の場合、事業に必要なものを購入するのに必要な資金として使用します。
一方で運転資金は、事業を継続するための資金として確保が必要なお金です。従業員に支払う給料や、光熱費などは運転資金として扱います。
設備資金と運転資金では、借りやすさにも違いがあるのが特徴です。具体的な条件については後ほど解説しますが、一般的に運転資金よりも設備資金の方が条件が厳しいとされています。審査内容が厳密で、正確な説明を金融機関に行わなければなりません。
返済期間についても、設備資金と運転資金で違いが現れやすいと言えます。審査が厳密なぶん、設備資金の場合は長期的な返済計画を策定し、それを実行しなければなりません。運転資金は審査基準が比較的ゆるく、返済期間も短期で設定の上融資を受けることが可能です。
資金調達の際、設備資金と運転資金では上述のような違いがあることを理解しておけば、事前準備を効率よく進められるでしょう。
設備資金の融資金額はどれくらい?
設備資金の融資を受けたいと考えている場合、個人や中小企業であればまず頼りたいのが日本政策金融公庫(日本公庫)の貸付です。日本公庫では、設備資金の融資を受ける場合
- 一般貸付
- 新規開業資金
の2つの選択肢があります。
一般貸付の場合、日本公庫が貸し付けてくれる限度額は4,800万円です。返済期間は10年以内と定められており、うち2年間は据置期間とされます。据置期間とは、元金の返済はせずに利息のみを支払う期間のことです。
新規開業資金、つまり新たに創業する際に利用できる融資枠では、設備資金と運転資金を合わせた総額で7,200万円までとなっています。そのうち、設備資金として借入れたものについては返済期間が20年、運転資金の枠が10年以内と決まっているのが特徴です。なお、据置期間についてはいずれも5年以内となっています。
最終的にどれくらいの金額を融資してもらえるのかについては、事業内容や必要な資金によって細かく変動します。詳細について把握したい場合、直接日本公庫に相談してみることが大切です。
設備資金の融資金額に影響を与えるもの
設備資金の融資金額がどれくらい借入れられるのかについては、借入の際の状況に応じて異なります。これはケースバイケースであるため、具体的な金額は実際に手続きを進めないとわかりません。ただ、大きな影響を与える要素としては以下が挙げられます。
- 業種
- 自己資金
- 設立年月
最もわかりやすい要素が、業種です。どのような事業を営んでいるかによって、一定期間当たりの営業利益率や、計上利益率は大きく異なるからです。
自己資金をどれだけ持っているかというのも、実際に融資できる金額に大きな影響を与えます。自己資金額を大きく上回る融資は条件が厳しくなるため、少ない元手で大きなビジネスを始めるのは難しいと考えるべきでしょう。
おおむねして、実際に融資を期待できる金額としては自己資金額の3倍程度までと言われています。多くの融資を必要とする場合、何らかの形で自己資金をある程度増やしておくことが必要です。
会社の設立年月は、事業の信用度にも直結します。設立年月が若い会社だと事業の信頼度も低く、受けられる融資も限られます。ある程度年月を重ねている会社の場合や、返済経験が豊富な会社の場合は金融機関からの信頼も厚いものです。ある程度自己資金を上回るような多額の融資であっても、承認が得やすいという強みが期待できるでしょう。
設備資金の融資が通るかどうかの審査基準
設備資金の融資が通るかどうかは、以下の3つのポイントから総合的に判断されます。
- 融資の必要性
- 返済源
- 返済期間
融資が通るかどうかは、そもそもその設備資金の確保のために融資が必要かどうかの判断に委ねられます。設備資金の使途が不透明であったり、その設備投資によってどんな問題を解決できるのかが不明だったりすると、融資が通りづらくなるでしょう。
融資で得た設備資金をもとに、どうやって返済のあてを作っていくかの計画性も、注意深く確認されます。設備投資の必要性が具体的に説明されていても、将来的な返済計画までが見通せていないと、融資は通りません。
設備資金の融資を受ける場合、注意したいのが返済期間です。投資が必要な設備の、減価償却における償還年数以内に返済期間が設定されていないと、融資を受けることは困難になります。
投資を検討している設備の償還年数が何年になるのかを踏まえた上で、返済計画を事前に立てることが重要です。
スタートアップの資金調達についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下のお役立ち資料も併せて確認してみてください。
設備資金の融資を受けるのに必要な準備
設備資金の融資を受ける上では、以下の3つの書類をあらかじめ用意しておくことが必要です。上でも紹介した通り、設備資金を借入れる場合、運転資金の調達よりも審査が厳格になります。前もって計画を具体的に組み立てておくことで、円滑な資金調達を実現しましょう。
見積書・領収書
ここで言う見積書とは、設備資金を何に使うのか、どの設備にどれくらいの支出が発生するのかを見込んだ見積書のことです。何にどれくらいのお金がかかるのかという情報を示すのに加え、それぞれの設備はどのように事業に役立てるのか、という説明ができるところまで準備しておくのが良いでしょう。
また、見積書で提示している見積もり金額が妥当なものであるかどうかは、こちらから相見積もりをとった上で金融機関に提示することで対応することが重要です。特に高価な機材などを購入する場合、用途や代替品の価格について厳しく言及される可能性があります。なぜその機材が良いのか、他の設備では換えが効かないのかを説明できるよう、備えておきましょう。なお、設備の購入後は領収書を保存しておくことも大切です。領収書を残しておけば、適切に資金を使用したことを証明することができます。
予算計画書
予算計画書とは、設備資金を受けて設備を拡充した結果、どれくらいのリターンが得られるのかについての見込みをまとめた書類です。
何となくプラスに働きそうだから設備投資を行う、ということでは金融機関を納得させることはできません。その設備を導入した結果、どんな利益が、いつまでに達成される見込みなのかといった、具体的な将来性を示すことが求められます。
金融機関に対して、設備資金の融資を行う価値が高いプロジェクトであることを示しましょう。
資金繰り表などの資料
融資を行った結果、この会社から正しく返済を受けられるのかどうかという判断は、資金繰り表なども参考に行います。行ってしまえば、万が一設備資金の融資が計画通りに進まなくとも、返済できる見込みが高いかどうかを判断するための資料です。
この際に用いられるのは資金繰り表に加え、試算表や決算表といったものになります。借り手側には優れた返済能力が元々備わっているということを、正しく示せる資料を用意しましょう。
<関連記事>資金繰りとは?悪化の原因や改善方法、資金繰り表の作成までわかりやすく解説
設備資金の融資を受ける際の注意点
設備資金の融資を受ける場合、自己資金とは異なりその運用についてはある程度の制約が課されます。以下の2つの注意点については、必ず把握しておくことが必要です。
使い道を後から変えることはできない(資金使途違反のおそれ)
設備資金として金融機関より融資を受けた場合、後から運転資金として運用するような変更は認められていません。設備資金として融資を受けた際には、必ず事前の計画通りに設備投資を行うことが条件です。
使い道を後から変えたことが金融機関に明らかになると、今後追加融資が必要になった場合などで、融資を受けることが難しくなるリスクが発生します。余計な経営リスクを背負わないようにするためにも、計画的な資金調達と運用を実現しましょう。
また、設備資金を正しく運用しているか調査が入った場合に備え、領収書などを残しておくことも大切です。
ちなみに、設備資金を運転資金として使用した場合、資金使途違反に問われてしまいます。ひどい場合には、一括返済のペナルティが課されるおそれもあるので、必ず計画的な資金運用を遵守しましょう。
ある程度ゆとりを持った資金の運用を行いたい場合には、設備資金ではなく運転資金として融資を受けることをおすすめします。運転資金であれば返済期間こそ設備資金の調達より短くなりますが、比較的カジュアルに資金を運用しやすくなるでしょう。
事業に関係ない費用は含められない
設備資金は、あくまで事業に関係する設備の導入にのみ使用することを前提とした資金です。例えば店舗兼住居の住居部分にかかる費用や、法人設立に伴う資本金に組み込むなどは、設備資金として使えない点に注しなければなりません。
これらの費用は、設備資金とは別に調達することが求められます。
余裕を持った返済計画を検討する
減価償却の期間内に返済を行わないといけないからといって、実際のニーズよりも短く返済期間を設定するのはおすすめできません。融資の返済に追われ、事業の継続性が失われるリスクが出てくるからです。
融資を申し込む段階で、融資を受けることが目的になってしまうと、無理のある事業計画で話が進んでしまうこともあります。しかし、ここではあくまで事業の成長がゴールであり、融資は手段の一つに過ぎません。安定した事業の成長とリターンが得られるよう、確実なプランを優先することを心がけましょう。
設備資金について解説しました
この記事では、設備資金とは何か、資金調達を融資で行う場合、どのような条件が発生するのかなどについて解説しました。
設備資金は創業時はもちろん、事業の持続可能性を高める上で欠かせない元手です。自己資金で賄うのが難しい場合、金融機関からの融資を頼ると良いでしょう。
ただ、設備資金の融資は運転資金のそれよりも、条件が厳しくなります。計画的な返済と事業の成長の両立につながるよう、あらかじめ周到な準備を進めておくことが大切です。