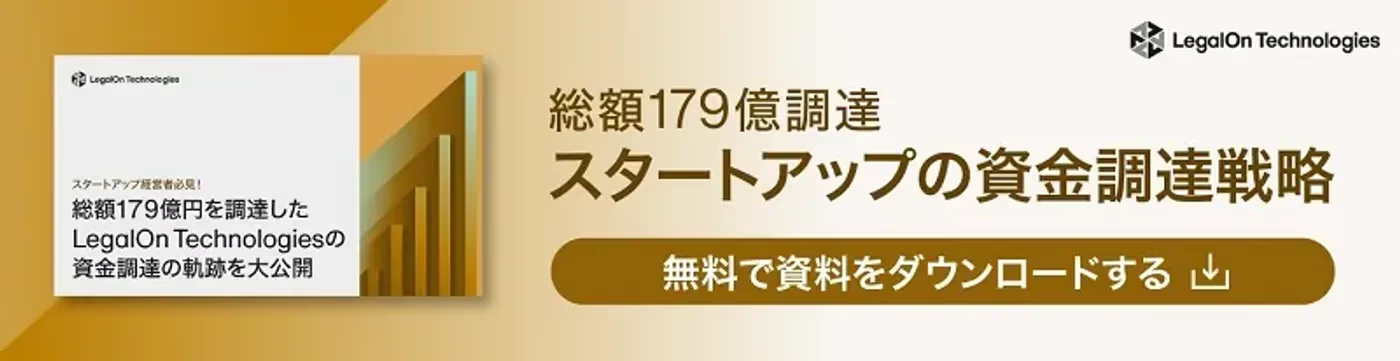IPOによる資金調達とは
IPOは「Initial Public Offering」の略称で企業が新規に株式を発行し、証券取引所に上場することを指します。IPOによる資金調達とは、IPOを通じて企業は自社株式を市場で売買できるようになり、株式を売却して得た資金を事業資金に充てることです。不特定多数の投資家に株式を販売することで、未公開時よりもはるかに大きな額の資金調達を行いやすいのが特徴です。
IPOに際して、株式の価格には「公募価格」と「売出価格」が設定されます。公募価格は、IPOによって新たに発行される株式の価格です。一方、既存株主が保有する株式を市場に売り出す際に設定されるのが、売出価格と呼ばれます。基本的に売出価格は、公募価格と差が設けられることはありません。
これらの価格設定には、引受証券会社や主幹事証券会社が関与しています。企業の資金調達目標や、市場の需給動向を考慮の上、IPOのたびに価格が設定されるのが特徴です。
IPOと上場の違い
IPOと同義的に紹介されるのが、「上場」です。IPOも上場も、未公開だった株式を新たに市場へ公開するという点では変わりません。ただ、IPOは上場に際し、新たに株式を公開するという点で単なる上場とは違いがあります。
IPOを行う企業のほとんどは、会社のさらなる成長を目指して増資を行います。そのため上場に際して株式を新たに発行し、より多くの投資家を集めることで、資金調達を実現する必要があります。
そのため、会社が上場を実現する際には、ほぼ確実に新規株式の発行を行うことから、IPOと上場が同じような意味で使われます。
IPOにおける資本政策とは
後ほど解説しますが、IPOの実施にはコストが発生するだけでなく、IPOを行えば必ず成功するとは限りません。IPOによる資金調達の効果を最大化するには、相応の計画と事前準備が必要です。
この際に考えなければならないのが、資本政策です。資本政策では、IPOに向けた資金調達の方法や、株主構成の比率などを計画し、増資を実現するかを検討します。
なぜ資本政策を実施するのか?
資本政策を実施する最大の目的は、円滑な資金調達の実現です。資本政策によって計画的にIPOを行わないと、IPOによって得られる利益が期待するようなものにならない可能性を高めてしまいます。最悪の場合、会社が別の組織に買収されるリスクを高めてしまうかもしれません。
このような問題を回避する上で、資本政策を通じた計画的なIPOの実現が必要です。株主構成は無理が生じないような比率を保ち、IPO後の安定経営に繋げられます。
資本政策の方法や実施ステップ
資本政策の方法は多岐にわたり、主に以下の10種類が考えられます。
- 種類株式の発行
- 株主割当増資
- 第三者割当増資
- 従業員持株会
- ストックオプション
- 株式移動
- 株式分割
- 自己株式の取得
- 自己株式の処分(売却)
- 新株予約権付社債
以下の記事では、各資本政策の詳細や、資本政策の実施タイミング・実施ステップから、成功させるポイントや失敗パターンについて詳しく解説していますので、気になる方は併せて確認してみてください。
<関連記事>【資本政策とは?】目的や実施ステップを中小企業目線で解説
IPOによる資金調達のメリット
計画的なIPOの実現は、資金調達において多くのメリットをもたらしてくれます。以下のメリットへの理解を深めることは、施策の意味を最大化する上で重要です。
返済義務が発生しない
IPOの最大のメリットは、返済義務が発生しないことです。株式を売却して得たお金は、借入金ではありません。金融機関を介さず、利子もなしに市場から直接資金調達を実施できるので、極めて柔軟性の高い手法と言えます。
もちろん、株式を購入した投資家に対しての責任は発生するため、成長し続けるプレッシャーは小さくありません。しかし金融機関から資金調達を行うことの経済的負担などを踏まえると、IPOは実に効率的な手法です。
会社の信用力が向上する
IPOによって市場に広く株式を公開することは、会社の信用力を大きく育む上でも重要な取り組みです。会社の信用力が高まると、様々な恩恵が期待できます。
例えば、銀行からの借入能力に直接良い影響を与えるメリットです。上場していない会社に比べて社会的信用があるので、より多くの金額を借り入れることができたり、債券の発行により資金調達ができたりします。
また、商品やサービスのブランド価値が向上し、より多くの顧客を獲得できるチャンスにも恵まれるでしょう。知名度が上昇して新しい投資家を集めることができたり、新規事業の創出チャンスが得られるかもしれません。
優秀な人材の確保や、離職率の改善、モチベーションの向上などもIPOのメリットです。会社の既存メンバーに「やりがい」をもたらしたり、外部の転職希望者に「この会社で働きたい」と感じてもらえたりします。
組織の管理能力が改善する
後述しますが、IPOに際して企業は上場審査を受ける必要があり、クリアのためには厳しい水準を超えていなければなりません。
その過程では経営や社内環境において高度に管理が行き届いていることが求められます。結果、上場に向けた準備を通じて、組織体制の健全化が実現するわけです。
IPOを無事迎えることができた際には、優れた組織運営を実現できている可能性が高いことも、メリットと言えます。
キャピタルゲインが期待できる
会社の創業者、および創業に際して資金面で援助を行ってくれた投資家やファンドに対して、キャピタルゲインをもたらすことが可能です。
株式が市場に公開されると、ほぼ確実に非上場時と比べて株式価格は高騰します。公開前に株式を取得していた人たちに対して大きな株式の売却益を生み出し、会社を支えてくれた恩返しができるわけです。
IPOによる資金調達のデメリット
IPOによる資金調達には、上述したメリット以外にも警戒すべきデメリットがあります。以下の問題については、事前に把握の上対処することが必要です。
上場そのものに時間とコストがかかる
そもそもIPOは、手続きの負担が大きいため気軽に行えるものではありません。最低でも創業から3年以上の期間を必要とすることから、短期間で資金調達を行うのには適していないアプローチです。
また、創業から年数が経過しているからといって、必ずIPOができるとも限りません。監査法人から監査を受けたり、証券会社からの審査を受けたりした上で、問題がないと判断された時に初めて上場できます。
そのため、IPOを迎えるにはまず短期的な資金調達を実施したり、事業を軌道に乗せたりと、多くのハードルをクリアする必要があるわけです。
上場維持のための負担が大きい
IPOを実現するまでの道のりが困難なだけでなく、上場後も企業は相応のプレッシャーにさらされ続けることとなります。
上場後も定期的に監査を受けたり、株主総会を開いたりといった、上場企業としての義務と責任を果たさなければなりません。投資家から株式を通じて多額の資金を調達できる一方、その仕組みを維持するための運営コストも大きくなることを知っておきましょう。
近年は組織の財政健全化に向けて、上場を取りやめる企業も見られます。IPOが、全ての企業にとって必ずベストなアプローチであるとは限りません。
株主や株価に会社が振り回されやすい
IPOによる株式上場は、会社が株主の意向に振り回されてしまうリスクもはらんでいます。上場していない企業の場合、組織の意思決定は経営層が100%手綱を握って行うのが当たり前でした。しかし株式を上場することで、株主からの要求に応えられないと、会社が資金調達どころではなくなってしまうこともあります。
また、短期的な株価の上下に大きく組織や企業価値が左右され、意思決定が複雑になってしまうリスクが出てくるかもしれません。IPOによる資金調達は、会社の規模が大きくなるだけで、結果的にやりたいことが実現できない問題をもたらす恐れがあります。
買収リスクが増加する
上場会社の株式は、市場原理に基づき極めて自由に取引が行われます。そのため理論上、少数の投資家によって株式の過半数が取得され、経営権を失ってしまうリスクもあるわけです。
意図しない株式の買い占め、例えば競争力の低下を目的としたライバル会社による株式買い占めなどに対し、対策が求められます。
スタートアップの資金調達についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下のお役立ち資料も併せて確認してみてください。
IPOによる資金調達の際の公募価格決定方法
IPOによる資金調達を検討している場合、IPO株の公募価格を決める必要があります。株式の価格は、以下の2つの方式によって決定されるのが特徴です。
ブックビルディング方式
ブックビルディング方式は、大口の投資家のニーズを参考に価格を決定する方法です。最初に大口投資家へIPOの通知をして、意見をまず把握します。その後一般の投資家にも通知し、全体の需要を参考にした上で公募価格を設定する方法です。
市場のニーズに基づいた価格決定方式のため、需要と供給のバランスがとりやすいメリットが期待できます。
入札方式
入札方式は、一定期間の間に投資家から公募価格の入札を行い、その結果に基づき価格を設定する方法です。企業に有利な公募価格を設定しやすく、以前はこの入札方式が唯一の公募価格設定方法とされてきました。
ただ、入札方式では公募価格が市場のニーズよりも価格が高めに設定されやすい問題を抱えます。投資家による短期的な売却の結果、価格が暴騰する恐れがある点に、注意が必要です。
IPOの資金調達額の計算方法
IPOによって実施する資金調達額は、以下の計算方法に基づき算出します。
- 公募価格×発行株式数=資金調達額
極端に言えば、発行株式数が多いほど、あるいは公募価格が高いほど多くの資金を調達できる仕組みです。ただ、これらのバランスは市場のニーズを踏まえて調整する必要があります。市場のトレンドを踏まえた株式発行や公募価格設定でないと、極端に企業の価値を損ねる恐れもあるからです。
投資家にとって魅力的な上場企業となるためには、需給バランスへの注目も必要になるでしょう。
IPOを行う株式市場と上場審査基準
IPOを行う株式市場は、大きく分けて以下の3つです。
- プライム市場
- スタンダード市場
- グロース市場
それぞれのマーケットによって、コンセプトや上場の基準、そして上場維持の基準が微妙に異なるため、整理しておきましょう。
プライム市場
- 市場のコンセプト:高水準のガバナンスと流動性
- 主な新規上場基準:株主数800人以上、流通株式比率35%以上 など
- 主な上場維持基準:平均売買代金0.2億円以上 など
スタンダード市場
- 市場のコンセプト:株式投資に足るガバナンス
- 主な新規上場基準:株主数400人以上、流通株式比率25%以上 など
- 主な上場維持基準:売買高の月平均10単位以上 など
グロース市場
- 市場のコンセプト:ポテンシャル重視
- 主な新規上場基準:株主数150人以上、流通株式数1,000単位以上 など
- 主な上場維持基準:時価総額が上場10年経過後40億円以上 など
プライム市場
機関投資家から注目されるのが、プライム市場です。高水準のガバナンスと、優れた流動性を備えた企業が上場を果たすマーケットで、上場後も高い基準を満たし続けることが求められます。
以下の記事ではプライム市場について詳しく紹介しています。気になる方は併せて確認してみてください。
<関連記事>東証プライムとは?1記事でわかる上場のメリットや基準、他市場との違い
スタンダード市場
スタンダード市場では、株式投資に足る水準の時価総額を備えた企業が上場しています。プライムほどではないものの、優れた水準のガバナンスを求められる市場です。
以下の記事ではスタンダード市場について詳しく紹介しています。気になる方は併せて確認してみてください。
<関連記事>スタートアップの経営者必見!スタンダード市場の特徴と上場に必要な知識を徹底ガイド!
グロース市場
グロース市場には、ポテンシャルとリスクの両方が高い水準にある企業が上場しています。上記2つの市場に比べ株主数などの水準がゆるく、今後の成長可能性を重視する投機的な株式投資家からの注目を集める市場です。
以下の記事ではグロース市場について詳しく紹介しています。気になる方は併せて確認してみてください。
<関連記事>東証グロースに上場するためには?審査基準やメリット、費用を大解説
IPOによる資金調達の進め方
IPOによって資金調達を進めたいと考えている場合、以下のステップにしたがって計画を策定します。
- 上場希望先への申請・承認
- 株式の仮条件の決定
- 発行価格の決定
- 抽選の実施
IPOに際しては、どの上場先を選ぶにせよ上場希望先から承認を得る必要があります。書面審査やヒアリングなど、厳しい審査が行われるため、このハードルを乗り越えるのが最も困難です。
申請が承認された場合、株式の仮条件を決定します。上で紹介した公募価格の設定方法を用いて、株式の価格が大まかに決定されるステップです。
最終的な発行価格は、IPOを引き受ける証券会社によって示される売出し結果によって判明します。発行価格は高すぎても安すぎてもリスクがあることから、その中間をうまく掴めるかどうかがポイントです。
IPO株を発行すると、投資家から多くの注文が入ります。その際株式を購入する権利を抽選によって投資家に配分し、株の配分が完了した時点で、上場を行うのが一通りの手順です。
IPOで資金調達を目指す企業に求められるポイント
IPOで資金調達を実施する際、まず知っておきたいのがIPOはゴールではないことです。IPOは実現までに時間がかかる上、手続きも複雑なものとして知られます。経営者の中には、IPOをいったんのゴールに設定する人もいるものです。
しかし、IPOはあくまで資金調達を実施するための手段にすぎません。IPOによって何を成し遂げたいのか、整理しておくことが大切です。なぜリスクをとってまでIPOをするのかというビジョンがないと、この機会を有効活用できないでしょう。
以下の記事では「なぜ上場ゴールは悪いのか?」について詳しく解説しています。上場ゴールがもたらすリスクや、上場ゴールを避けるためのネクストアクションについて気になる方はぜひ併せてご確認ください。
<関連記事>上場ゴールはなぜ悪いのか?セルフチェックリスト&今すぐできること
IPOによる資金調達について解説しました
この記事では、IPOで資金調達を目指すメリットや、IPOに際して知っておきたい注意点を解説しました。IPOは莫大な資金調達を行える魅力的なアプローチですが、長期的には企業をリスクにさらす恐れもあることから、慎重な判断が必要です。
IPOの仕組みや、そのプロセスで何が必要なのかを把握した上で、計画的に取り組みましょう。