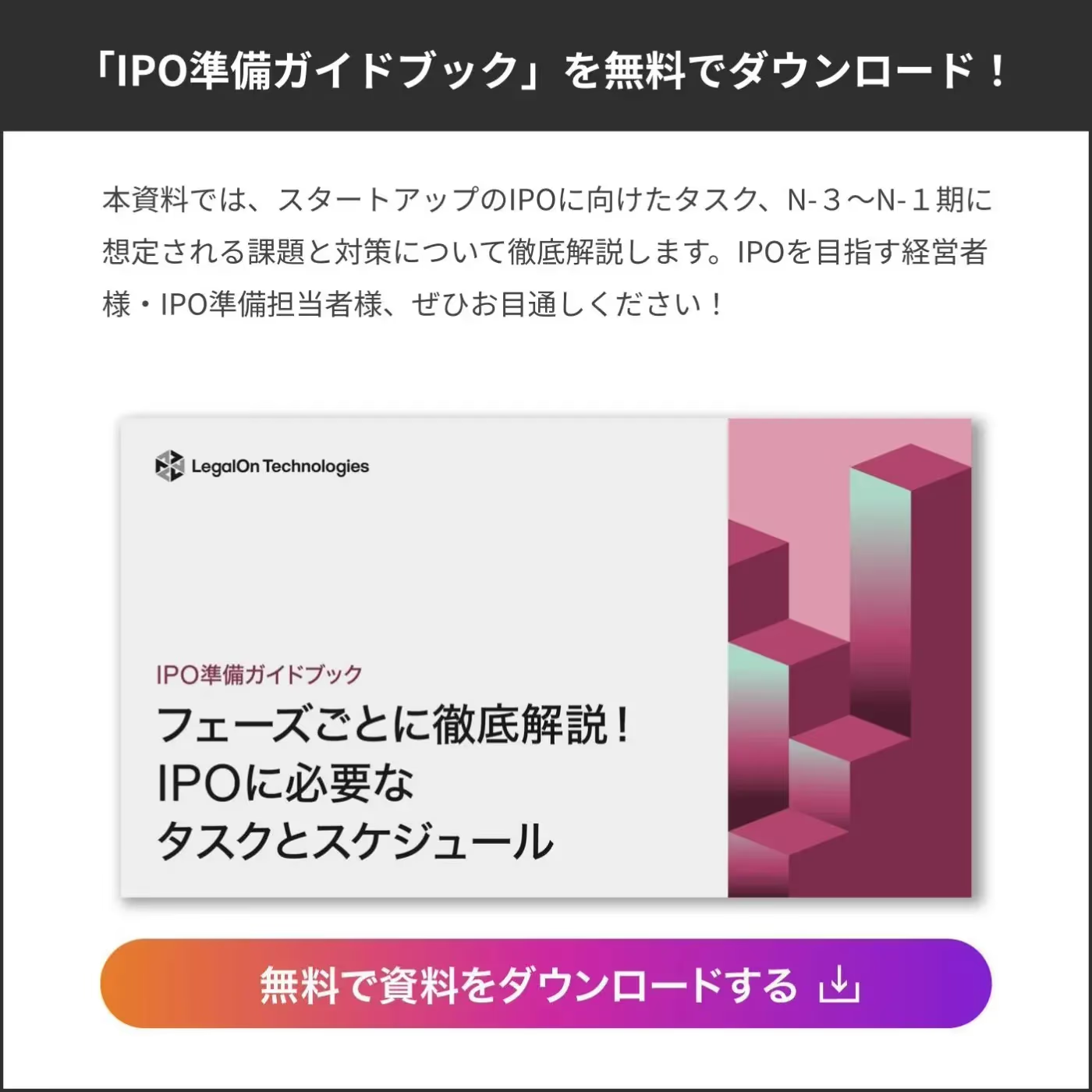税制非適格ストックオプションとは?
税制非適格ストックオプションは、数あるストックオプション制度の中の一つです。まずは同制度の基本について、押さえておきましょう。
ストックオプションの基本的な仕組み
ストックオプションとは、あらかじめ決められた価格(行使価格)で、自社株を取得できる権利です。企業はこれを従業員や役員に付与し、株価の上昇を利益につなげる報酬制度として活用します。
権利を行使すると、市場価格より低い価格で株を取得できる可能性があります。その後、売却時の差額が利益となる仕組みです。この制度は、企業の成長と従業員の利益が連動するため、モチベーション向上の手段としても有効です。
下図のように、ストックオプションには有償ストックオプションと無償ストックオプションの2種類があります。さらに無償ストックオプションには、税制適格と税制非適格の2種類に分かれます。それぞれ課税方法が異なるため、適切な選択が必要です。両者の違いについては、後ほど解説します。
税制非適格ストックオプションの概要と特徴
税制非適格ストックオプションは、税制適格の要件を満たさないストックオプションを指します。そのため、税制優遇措置を受けられない点に注意しなければなりません。
最大の特徴は、権利行使時に給与所得として課税される点です。株を取得した時点で、市場価格と行使価格の差額に課税されます。さらに、株式売却時には譲渡所得税も発生することから、税負担のリスクに備えなければなりません。
その一方、同制度は設計の自由度が高いことがメリットです。税制適格ストックオプションでは付与対象が限定されますが、税制非適格では社外取締役や業務委託先にも付与可能です。この柔軟性により、企業は経営戦略に応じた多様な活用ができます。
税制非適格ストックオプションの活用例
税制非適格ストックオプションの主な活用シーンは、以下の2つです。
- 現役役員・業務委託先の報酬の代替
- 役員退職慰労金の代替
株価の上昇によって、大きな売却益を得られる機会を提供できます。そのため、会社への貢献度の高い人物に対し、大きなモチベーションを創出可能です。
税制非適格ストックオプションは、役員退職慰労金の代わりとしても活用されています。直接金銭を支払うわけではないので、キャッシュフローの悪化を回避可能です。それでいて、金銭と同等、それ以上のインセンティブとなるのが他にない強みと言えます。
税制非適格ストックオプションと税制適格ストックオプションの違い
税制適格ストックオプションとの違いについて、さらに掘り下げていきましょう。
税制適格ストックオプションは、一定の要件を満たすことで税制優遇を受けられる制度です。権利行使時には課税されず、売却時に譲渡所得税が適用されます。そのため、税負担が比較的軽くなるメリットがあります。
ただし、行使価格を発行時の時価以上に設定することや付与対象が取締役・従業員に限られることなど、厳格な条件を満たすことが必要です。
一方税制非適格ストックオプションは設計の自由度が高く、社外取締役や業務委託先にも付与できます。ただ権利行使時には給与所得として課税され、その税率は最大55%になることもあるのが懸念点です。さらに売却時には譲渡所得税もかかるため、税負担のリスクが生じます。
企業は税務負担や付与対象の違いを考慮し、目的に応じて最適な制度を選択することが重要です。
税制非適格ストックオプションの税金と計算方法
税制非適格ストックオプションは、どのように税金が発生する制度なのでしょうか。ここで簡単に課税タイミングや計算方法について、確認しておきましょう。
課税のタイミング
税制非適格ストックオプションの課税タイミングは、以下の通りです。権利行使時と売却時の2回にわたり課税が発生します。
- 権利行使時:市場価格と行使価格の差額が給与所得として課税される。
- 売却時:売却価格と取得価格の差額が譲渡所得として課税される。
上述の通り、税負担のリスクが発生していることから、手元に残る所得は小さくなることを想定しておきましょう。
税率と税負担の違い
また、権利行使時と売却時においては発生する税率も異なります。以下の表は、それぞれの負担の違いをまとめたものです。
給与所得(権利行使時)
- 税率:最大55%
- 課税のタイミング:株式取得時
譲渡所得(売却時)
- 税率:約20.315%
- 課税のタイミング:株式売却時
まずは株式取得時のケースです。ここでは給与所得に対する累進課税が適用されるため、 高額所得者ほど税負担が大きくなる点に注意しなければなりません。
譲渡所得時については累進課税になりません。ただ税の差引があるため負担が発生する点は懸念すべきことと言えるでしょう。
具体的な税額計算のシミュレーション
上述の課税ルールをもとに、簡単なシミュレーションを行ってみましょう。以下の例を確認してみてください。
例:1株1,000円の行使価格で、時価5,000円の株式を100株取得し、8,000円で売却した場合
1.権利行使時の課税(給与所得)
(5,000円 - 1,000円)× 100株 = 400,000円
所得税(仮に30%とする)= 120,000円
2.売却時の課税(譲渡所得)
(8,000円 - 5,000円)× 100株 = 300,000円
譲渡所得税(20.315%)= 60,945円
合計課税額:約180,945円
このように、税制非適格ストックオプションでは、売却前に高額な税負担が発生します。そのため、あらかじめキャッシュフローの計画を丁寧に考えておくべきです。
税制非適格ストックオプションのメリット
税制非適格ストックオプションを有効活用できれば、以下のメリットが期待できます。
柔軟な設計が可能
税制非適格ストックオプションは、税制適格ストックオプションの厳格な要件を満たす必要がありません。そのため、企業のニーズに応じた柔軟な設計が可能です。
例えば、行使価格を市場価格より低く設定することも認められています。これにより、従業員や役員にとって魅力的なインセンティブ設計がしやすくなるでしょう。
また権利行使期間や売却制限を自由に設定できるため、企業の成長戦略に応じたカスタマイズが可能です。また株価が急上昇した場合でも、行使価格を適切に調整することで、従業員が利益を最大化できる仕組みを作ることができます。
広い対象範囲で付与できる
税制適格ストックオプションは、「取締役・従業員」のみが付与対象です。一方、税制非適格ストックオプションにはこの制限がなく、社外取締役や業務委託先にも付与可能です。
この特徴を活かし、企業は外部の専門家やアドバイザーにストックオプションを提供できます。特にスタートアップ企業では、資金の制約がある中で優秀な人材を確保する手段として活用されています。
現金報酬の代わりにストックオプションを活用することで、資金繰りを圧迫せずにインセンティブを提供できる点も大きな利点です。
企業側の導入ハードルが低い
税制非適格ストックオプションは、法的な制約が少ないため、企業の導入ハードルが低い点が特徴です。
税制適格ストックオプションを導入するには、厳格な要件が求められます。行使価格を発行時の時価以上に設定することや、付与後2年以上経過しなければ行使できないなどです。
しかし税制非適格ストックオプションではこれらの要件が不要なため、制度構築が簡単に行えます。必要な書類や手続きも比較的簡素化されており、企業は短期間でストックオプション制度を整備できるでしょう。
税制非適格ストックオプションのデメリット
税制非適格ストックオプションの活用には、一方でデメリットもあります。どのような対策が必要なのか、あらかじめ把握しておきましょう。
従業員の税負担が高くなる可能性
税制非適格ストックオプションの最大のデメリットは、税負担の大きさです。税制適格ストックオプションでは、株式売却時にのみ譲渡所得税が課税されます。一方税制非適格ストックオプションは、権利行使時に給与所得として課税されるのが懸念点です。
上述の通り、この税率は最大55%に達することもあり、想定以上の税負担が発生する可能性があります。
その結果従業員は高額な税金を支払うケースがあり、制度の魅力が低下するかもしれません。企業はこの税負担を考慮し、従業員に十分な説明を行うことが求められます。
キャッシュフローの問題
税制非適格ストックオプションでは、株式売却前に税金が発生するため、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。
通常、ストックオプションは株価上昇後に権利を行使し、利益を得ることが目的です。しかし、この制度では権利行使時に給与所得として課税されます。そのため、現金収入を得る前に税金を支払うリスクも出てくるわけです。
特に未上場企業の株式を取得した場合は、注意が必要です。売却が制限されているため、納税資金を確保できない可能性があります。企業はこのリスクを従業員に説明し、無理なく権利を行使できる仕組みを整えることが重要です。
税務リスクや手続きの煩雑さ
税制非適格ストックオプションは、税務処理の負担が大きい点もデメリットです。権利行使時の課税が給与所得として扱われるため、企業は給与支払報告書の作成や源泉徴収の手続きを適切に行う必要があります。従業員ごとに異なる所得税率を考慮しながら、正確に計算・申告しなければなりません。
また税務署による監査の対象となる可能性もあります。そのため適切な記録管理と報告が不可欠です。制度を導入する際は、専門家の助言を受け、税務リスクを最小限に抑える体制を構築することが求められます。
税制非適格ストックオプションの活用例
信託型ストックオプションとは
信託型ストックオプションとは、信託を活用してストックオプションを管理・運用する制度です。従来のストックオプションと異なり、企業が信託会社を通じて株式を預託し、権利行使のタイミングを調整できる点が特徴です。
この仕組みを用いることで、従業員が権利行使時の税負担を軽減できる可能性があります。また企業にとってもキャッシュフローの影響を抑えつつ、柔軟な報酬制度を設計できる点がメリットです。
通常のストックオプションとの違い
通常のストックオプションでは、企業が直接従業員へ権利を付与します。そのため、権利行使時に給与所得として課税され、税負担が大きくなる可能性に備えなければなりません。
一方、信託型ストックオプションでは、企業が株式を信託に預け、一定の条件を満たした従業員が取得できる仕組みです。この方法により、給与所得課税を回避し、売却時に譲渡所得として課税される可能性が高くなります。
また信託を活用することで、株価変動リスクを分散し、より安定したインセンティブ設計が可能です。うまく使うことができれば、企業と従業員の双方にとって有利な運用が期待できるでしょう。
信託型ストックオプションは増税対象?
信託型ストックオプションの課税方法は、税制適格ストックオプションとは異なり、税制改正の影響を受けやすい点に注意が必要です。
2024年以降、信託型ストックオプションの課税強化が議論されており、一定の条件を満たさない場合、給与所得として課税される可能性があります。これにより、従業員の税負担が増加するリスクが出てくるでしょう。
企業は今後の税制改正を注視し、専門家のアドバイスを受けながら最適な設計を行うことが求められます。制度のメリットを最大限活かすため、最新の税務動向を確認しながら慎重に運用することが重要です。
税制非適格ストックオプションについて解説しました
税制非適格ストックオプションは、柔軟な設計が可能で、幅広い対象者に付与できる点が魅力です。しかし、税負担の大きさやキャッシュフローの課題には十分注意しなければなりません。
企業が導入を検討する際は、税務リスクや従業員への影響を考慮し、適切な設計を行うことが不可欠です。特に、権利行使時の課税タイミングや資金計画を明確にし、従業員に丁寧な説明を行うことが求められます。
企業側も税務処理や源泉徴収の義務を正しく理解し、管理体制を整備することが重要です。適切な運用を行うことで、企業と従業員の双方がメリットを享受できる仕組みを構築できるでしょう。