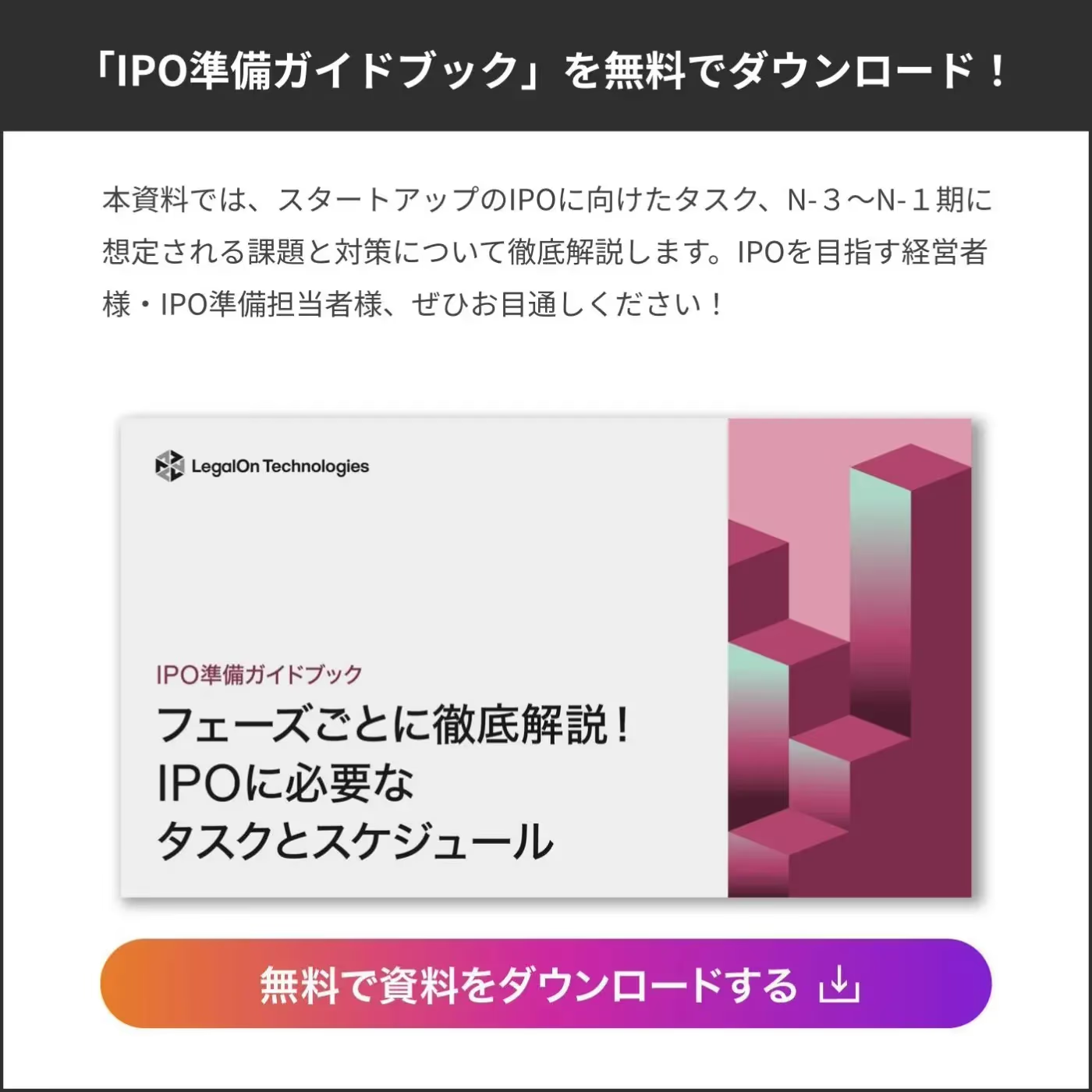ストックオプションとは
そもそもストックオプション制度は、従業員や役員があらかじめ決められた価額で自社株式を購入できる制度です。
株式は一度市場で公開されると、会社の成長に伴いどんどんその価値は高くなっていきます。そこで株式上場を目指す企業は、あらかじめ安価な価額で自社株式を社内向けに購入できるよう制度を整備し、上場を目指してパフォーマンスを発揮できるよう促すわけです。
ストックオプション制度の導入は、特に資本金が乏しい企業にとって魅力的と言えます。給与支払いのための現金の代わりに、安価な株式によって従業員にインセンティブを与えられるからです。
また、ストックオプション制度により自社株式を購入してもらうことで、会社が十分に成長するまで組織にとどまってもらえる効果も期待できます。従業員にとっては自分が高いパフォーマンスを発揮するほど、将来受け取れる株式の売却益が大きくなるからです。
<関連記事>IPOを目指す企業必見! ストックオプション徹底解説と法務戦略の重要性
ストックオプションの種類
ストックオプションには大きく分けて、以下の2つの種類があります。
- 有償ストックオプション
- 無償ストックオプション
有償ストックオプションは、従業員や役員が自社株式を入手する際に、あらかじめ定められた発行価額を支払う必要がある制度です。市場に公開する時よりもはるかに安く株式を手に入れることはできるものの、入手のためには購入分の発行価額を支払わなければなりません。
一方の無償ストックオプションは、金銭の支払いをすることなく従業員や役員が株式を入手できる制度です。また、無償ストックオプションの場合は特定の条件を満たすことで、給与課税が免除されます。
簡単に言えば、両者の違いはストックオプションの利用に際して従業員に金銭的な負担を強いるのか、そうでないのかの違いです。細かな説明については今回は省くものの、両者の違いについても、制度の導入時には知っておくのが大切です。
ストックオプションの権利行使価額について
ストックオプションの権利行使価額とは、ストックオプションの権利を行使する際にの価格です。ストックオプション制度によって手に入れた株式を売却し、利益をあげたい時は、自社株式の価格が権利行使価額を上回ったタイミングを待ちます。
ストックオプションの権利を行使するタイミングは、一般的に権利を行使する従業員や役員に委ねられているものです。ただ注意点として、ストックオプションの権利行使には期間が定められています。
ストックオプションの権利行使期間は、会社によって条件が異なるものです。税法や会社の都合を踏まえて、ストックオプションの権利行使のタイミングを図ることが、従業員には求められます。
1円ストックオプションとは
ストックオプション制度の導入方法は、会社によってさまざまです。最近では、権利行使価額を1円に設定する、いわゆる1円ストックオプションを採用する企業も増えてきました。
1円ストックオプションとは、簡単に言えば自社株式を1株1円で購入できる制度です。権利を行使する際、株価との差引はマイナス1円となるため、ほぼ株価と同額の売却益を得ることができます。
株式報酬型ストックオプションとも呼ばれるこの制度は、無償税制非適格ストックオプションの一種です。つまり、権利を行使する人は有償ストックオプションのように金銭を支払う必要がないのと同等の扱いを受けられます。ストックオプションの権利行使価額1円の場合、実質無償として扱われることは重要なポイントです。
税法上の1円ストックオプションの扱い方
上でも触れているように、1円ストックオプションは無償税制非適格ストックオプションに分類されます。税務上の取扱いとしては以下の3つの段階において、特定のルールが適用される点に注意が必要です。
権利付与時の扱い
新株予約権が無償で付与される場合、付与時点では受贈者に課税関係は生じません。これが無償ストックオプションの特徴ですが、1円ストックオプションの場合も同様です。
権利行使時の扱い
ただし、1円ストックオプションは全くの非課税制度というわけではありません。権利行使時には取得した株式の時価と権利行使価格(1円)との差額が、経済的利益とみなされます。
そのため、権利行使時にははじめて給与所得として課税される点に注意が必要です。この際、会社は源泉徴収の義務を負うので、この手続きを忘れずに行わなければなりません。例えば、権利行使時の株価が1,001円の場合、1株あたり1,000円の給与所得が発生するような計算方法です。
株式売却後の扱い
取得した株式を売却した際は、その売却益が譲渡所得として課税されます。売却時の株価が権利行使時の株価を上回っていれば、その差額が譲渡所得となるため、これもその都度計算が必要です。
(番外)従業員側の節税効果について
1円ストックオプションは、従業員にとっても一定の節税効果が期待できる取り組みです。同制度の権利行使時に得られる利益は、退職時に行使することによって、税法上は退職所得として課税されます。
給与課税の場合、税率は最大55%です。一方で退職所得の場合は税率が45%となるため、差引額はその分小さくなることが期待できます。
1円ストックオプションを導入する際には、この点も社内で広く共有することで、同制度への理解の促進や利用の促進を促せるでしょう。
1円ストックオプションのメリット
1円ストックオプションの導入によって、企業や従業員は以下のメリットを期待できます。1円ストックオプションの導入効果を最大化するためにも、利点を事前に把握しておきましょう。
従業員のモチベーション向上
1円ストックオプションの導入は、従業員のモチベーション向上において非常に効果的な取り組みです。
ストックオプションの制度は、いずれもモチベーションに良い影響を与えるとされています。中でも1円ストックオプションの場合は、株価がほぼそのまま売却益となるのは大きな魅力と言えるでしょう。
ストックオプションの制度があろうとなかろうと、会社の成長は従業員のモチベーションやパフォーマンス次第で大きく左右されるものです。しかし同制度を導入することで、従業員は高い成果を残せば残すほど、将来得られる利益が大きくなると期待できます。
所属する会社でしっかりと成果を残したいと考える人にとっては、魅力的な制度と言えるでしょう。近年はストックオプション制度の知名度も高まっており、これから優秀な人材を集めたいと考えている企業にとっても、有力なアピールポイントとなるでしょう。
損金算入による節税効果
1円ストックオプションは、給与への損金算入ができるため節税効果が見込めます。従業員が1円ストックオプションを行使する場合、発生する権利行使価額は全て損金として計上可能です。
損金として計上するタイミングは権利行使時で、その時に発生する「株式の時価」と「権利行使価格(1円)」の差額が給与として扱われます。権利付与時点では損金算入ができない点に、注意が必要です。
従業員の権利行使負担の低減
1円ストックオプションは、従業員の権利行使負担が小さいというのもメリットの1つと言えます。例えば有償のストックオプションを導入する場合、たとえ将来の市場価格よりも安価に株式を取得できるとは言っても、それなりの元手資金が必要です。
そのため、あまり普段の給与や貯蓄に余裕のない従業員にとっては、ストックオプションの制度を有効活用できない問題が出てくるかもしれません。一方で1円ストックオプションは、わずか1円で株式を取得できるので、気軽に権利を行使することができます。
ストックオプション制度を気軽に、広く活用してほしいと考えている場合、魅力的な制度と言えるでしょう。
1円ストックオプションのデメリット
1円ストックオプションは、一方で無視できないデメリットをもたらす懸念も残ります。制度理解を深め、以下のリスクを最小限に抑えるべきでしょう。
インセンティブの低下
1円ストックオプションは、思っているほど従業員のモチベーションに寄与しない可能性があります。
一般的なストックオプションの場合、権利行使価額は市場価格に近い金額に設定されます。そのため、従業員はある程度成果を出して会社を成長に導かないと、大きな売却益を得ることができません。
一方で1円ストックオプションは、市場価格から大きく乖離した金額で権利を行使できます。そのため、権利を行使した時点でそれなりの売却益を得られることがほぼ確定しており、従業員のモチベーションを高めるには物足りないことがあるからです。
「棚からぼた餅」程度の扱いとなってしまわないよう、制度導入の際にはこれを考慮して設計することが求められます。
権利行使時の税負担の発生
1円ストックオプションの制度は、上述の通り権利行使時に給与所得課税が発生します。
退職金として売却益を含む場合には、退職課税として計上できるので、給与課税よりも税率を安く抑えることが可能です。しかし退職前に権利を行使して売却益を得る場合には、その分給与として課税対象となるため、税負担が退職時よりも大きくなってしまいます。
課税分については、従業員が現金で税の支払いを行わなければなりません。そのため、手元資金に余裕のない人にとっては、期待しているような利益を得られないことになることもあるでしょう。
ストックオプション制度には常に課税のリスクが伴います。利益を最大化するためには、制度上の工夫が求められるわけです。
利害対立の発生
1円ストックオプションの導入が、利害対立をもたらすおそれがあることも覚えておくべきでしょう。特に、有償ストックオプションを以前から導入していた企業にとってはこのリスクが大きくなります。
1円ストックオプションは、基本的に従業員にとってデメリットはほぼ無い制度です。課税による利益圧縮のリスクはあるものの、それでも受け取れる利益がゼロになるリスクは無いと言えます。
一方で市場価格と近い価額でのストックオプションの権利行使を求められてきた従業員にとっては、不公平感があるかもしれません。彼らは1円ストックオプションよりも大きなリスク、つまり自身の持ち出し額が大きく、それでいて売却益も小さくなります。結果、そのギャップや待遇の違いに不満が募るわけです。
このことから、1円ストックオプションをこのような条件下で設ける場合、待遇のギャップが大きくならないよう、制度設計を行わなければなりません。
1円ストックオプションを導入すべき企業は?
1円ストックオプションの導入は上述の税制やメリット・デメリットを踏まえると、以下の企業にとって成果が期待できます。
- 成長余地の大きい企業
- 優秀人材の獲得を推進したい企業
- 長期的な人材育成を検討する企業
おおむねして、1円ストックオプションに適した企業は成長のポテンシャルに優れる企業にとって魅力的な制度です。従業員一人一人の生産性を高め、少数精鋭でIPOを目指す企業や、外部から優秀人材を獲得し、スケールアップを目指している企業が挙げられます。
また、人材の流出を回避したり、終身雇用に近い制度の設立で従業員に安心感を与えたりしたい場合も、1円ストックオプションが役に立つでしょう。
他のストックオプション制度とも比較の上、最適な制度導入を検討するべきです。
1円ストックオプションについて解説しました
この記事では、1円ストックオプションとはどのような制度か、メリットやデメリットについて触れながら紹介しました。ストックオプション制度の中でも気軽に権利を行使しやすいこの制度は、中長期的に人材を育成し、離職を回避したい際に役立ちます。
ただ他の制度と同様に課税面での制約があることや、他のストックオプション制度と衝突してしまうデメリットもあるため、導入に際しては注意しなければなりません。
1円ストックオプション制度への理解を深め、従業員の育成や生産性向上、そして優秀人材の確保に努めましょう。