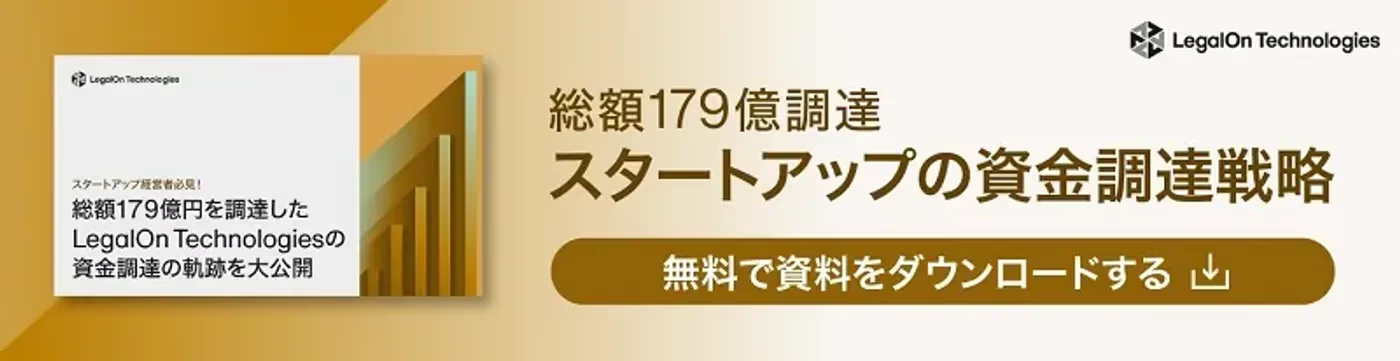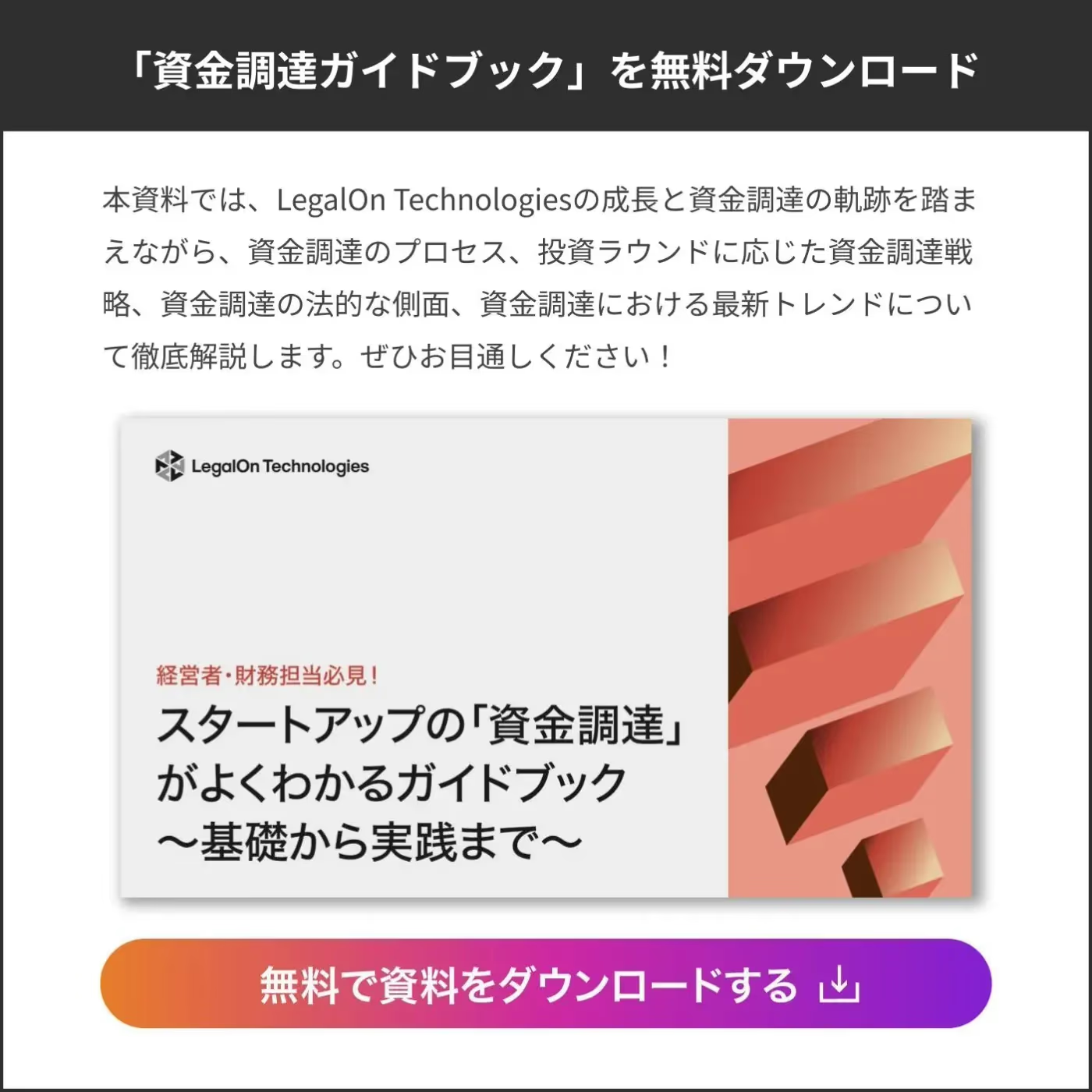プライベートエクイティ(PE)とは
プライベートエクイティ(Private Equity)とは、未上場企業や経営再建を必要とする企業に対して資本を提供し、経営支援を行う投資手法を指します。一般的な株式市場で取引される上場企業とは異なり、非公開の企業株式を対象とする点が特徴です。
プライベートエクイティの目的は、対象企業の価値を向上させた上で株式を売却し、投資リターンを得ることにあります。投資先は、成長から成熟期企業、事業承継に課題を抱える企業まで幅広くあるのもポイントです。日本においては、後継者不足に直面する中小企業へのM&A支援が増えてきました。
またプライベートエクイティは単なる資金提供にとどまりません。経営戦略の策定、人材強化、業務改善など、多面的な支援を通じて企業価値を向上させる役割を果たします。そのため、資本政策や成長戦略を検討する経営者にとって、有力な選択肢の一つとなり得るでしょう。
ベンチャーキャピタル(VC)との違い
プライベートエクイティ投資は、広い意味では未上場企業の株式を取得すること全般を指し、ベンチャーキャピタル投資もその一部です。ただし厳密的には、ベンチャーキャピタル投資は新しく立ち上がった企業に対して小規模の投資を行うことを指し、プライベートエクイティ投資は、成長期や成熟期にある企業に対して、より大きな資金を提供したり、株主に売却のチャンスを提供する投資方法です。
またプライベートエクイティ投資では、企業の過半数の株式を取得して経営に関与することが多いため、これを「バイアウト投資」と呼ぶこともあります。
プライベートエクイティが注目の理由
近年プライベートエクイティへの注目が急速に高まっており、その背景にはさまざまな要因が影響しています。ここでは、プライベートエクイティが注目される主な理由について詳しく解説します。
事業承継問題の解決策としてのPE
日本では少子高齢化により、多くの中小企業が後継者不足に直面しています。従来は親族や社内幹部が継承するのが一般的でしたが、近年は適切な後継者が見つからず廃業する企業も増えています。
こうした中、PEファンドが後継者が見つからない企業を買収し、経営の安定化や成長戦略の策定を支援するケースが目立ってきました。プライベートエクイティを活用することで、従業員の雇用を維持しつつ、企業価値を高めることが可能です。そのため、事業承継問題の解決策として有力な選択肢となっています。
経営改革・成長支援のパートナーとしてのPE
プライベートエクイティファンドは、単なる資金提供者ではありません。多くのファンドは豊富な経営ノウハウや業界ネットワークを持ち、投資先の企業が成長できるよう積極的に支援を行います。
例えば業務の効率化、営業力の強化、新市場への進出などです。企業の成長戦略を立案し、実行を支援します。
経営資源が限られている中小企業にとって、プライベートエクイティファンドとの連携は大きなチャンスとなります。自社だけでは実現が難しい事業拡大や新規事業への進出を、スムーズに実現できる可能性が高まるアプローチです。
株式市場の変化と未上場企業の魅力
近年、株式市場では上場企業に対する規制が強化され、経営の自由度が制限されるケースが増えています。株価の変動リスクや短期的な業績へのプレッシャーから、上場を目指さずに未上場のまま成長を続ける企業も増えてきました。
このような環境の変化に伴い、未上場企業への投資が魅力的な選択肢として注目されています。プライベートエクイティファンドは、上場企業と異なり、短期的な株価の変動にとらわれず、中長期的な視点で企業価値を高めることに注力できます。これにより、企業と投資家の双方にとって、より持続的な成長が可能となるのです。
プライベートエクイティ(PE)ファンドとは
プライベートエクイティファンド(以降、PEファンド)とは、未上場企業や経営改革が必要な企業に対して投資を行い、株式を売却する投資ファンドです。一般的に、機関投資家や富裕層から資金を集め、数年から十数年の運用期間を設けて投資を行います。
PEファンドの投資手法
PEファンドは、企業の経営支援を積極的に行う点が特徴です。単なる資金提供にとどまらず、経営戦略の見直し、業務の効率化、新規市場への展開など、多角的なサポートを提供します。また、投資対象となる企業の状況に応じて、成長資金の提供、事業再生、M&Aなど、さまざまなアプローチを実施するファンドです。
PEファンドの役割
PEファンドは、企業にとって単なる出資者ではなく、成長戦略のパートナーとして機能します。そのメリットは、経営資源が限られる中小企業にとっては、資金調達だけでなく、経営の高度化や事業拡大の支援を受けられる点です。そのため、多くの企業がPEファンドとの連携を検討するようになってきました。
スタートアップの資金調達についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下のお役立ち資料も併せて確認してみてください。
PEファンドの種類
プライベートエクイティファンドには、投資対象や戦略の違いによってさまざまな種類があります。それぞれのファンドが異なる目的やリスク許容度を持ち、企業の成長フェーズや経営課題に応じて活用するのがポイントです。ここでは、代表的なプライベートエクイティファンドの種類について解説します。
1. バイアウトファンド
バイアウトファンド(Buyout Fund)は、成熟した企業を買収し、経営改革を通じて企業価値を高めた後に売却することを目的とするファンドです。企業の成長戦略の見直しやコスト削減、新たな市場開拓などを支援し、数年後のエグジット(売却)を目指します。
バイアウトファンドには、以下のような種類があります。
- レバレッジド・バイアウト(LBO)ファンド:レバレッジ(借入金)を活用して企業を買収し、買収後に経営改善を進める手法です。企業の自己資本だけでなく、銀行融資などを活用することで、大規模な企業買収が可能になります。
- マネジメント・バイアウト(MBO)ファンド:企業の経営陣が主導して、PEファンドと協力しながら自社を買収する手法です。オーナー企業の事業承継や、上場企業の非公開化(上場廃止)に用いられることが多く、経営の自由度を高める狙いがあります。
以下の記事ではバイアウトについて詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>バイアウトとは?手法と成功させるポイントや注意点を徹底解説
2. グロースキャピタル
グロースキャピタル(Growth Capital)は、すでに一定の成長を遂げている企業に対し、さらなる拡大のための資金を提供するファンドです。投資対象は、ある程度の事業基盤が確立されているものの、新規市場開拓や設備投資などに資金を必要とする企業が中心となります。
グロースキャピタルは、経営の主体を企業側に残しつつ、少数株主として関与するケースが多いです。そのため、経営権を譲渡せずに資本を調達したい企業にとって、有効な選択肢となります。
3. ディストレストファンド
ディストレスト(Distressed)ファンドは、経営危機に陥った企業や、財務的に困難な状況にある企業を対象に投資を行うファンドです。企業再生や事業再建を通じて業績を回復させた後、売却によって利益を得ることを目的としています。
このファンドは金融機関からの借入金が多く、経営再建が求められる企業をターゲットとすることが一般的です。買収後は、財務の立て直しや事業の再構築を進め、企業価値を回復させていきます。
リスクは高いものの、適切な再建策が機能すれば、大きなリターンを得ることができます。
4. セカンダリーファンド
セカンダリーファンド(Secondary Fund)は、他のプライベートエクイティファンドが保有する投資案件を引き継ぎ、運用を継続するファンドです。
通常プライベートエクイティファンドは一定の運用期間を持ちます。セカンダリーファンドは、その期間内に売却が難しい案件や、運用継続が必要な案件を引き受ける役割を担います。
この手法により、投資家は早期に資金を回収することができ、PE市場全体の流動性が向上するというメリットがあります。また、投資対象がすでにある程度の成長を遂げている企業であるため、リスクを抑えながら安定的なリターンを狙うことが可能です。
プライベートエクイティ活用のメリット
投資を受ける側のメリット
プライベートエクイティを活用することで、企業は資金調達だけでなく、経営の高度化や成長加速といった多くのメリットを享受できます。特に、経営資源が限られる中小企業や、事業承継に課題を抱える企業にとっては、魅力的な選択肢と言えるでしょう。
1. 資本調達による成長加速
PEファンドからの投資を受けることで、銀行融資に頼らずにまとまった資本を調達できます。これにより、新規事業の立ち上げ、設備投資、M&Aなど、成長戦略を迅速に実行可能です。
上場企業のように短期的な株価変動を気にせず、中長期的な視点で企業価値向上を目指せます。
2. 経営ノウハウとネットワークの活用
PEファンドは、単なる資金提供者ではなく、豊富な経営ノウハウや業界ネットワークを活用して企業の成長を支援します。例えば事業戦略の見直しやコスト削減、営業強化など、経営のあらゆる側面に関与し、企業の競争力を高めるサポートを行います。
また、PEファンドのネットワークを活用することで、新たな取引先の開拓や海外展開の足がかりを得ることも可能です。
3. 事業承継の解決策
後継者不足に悩む企業にとって、PEファンドは有力な事業承継の選択肢となります。創業者が退任する際に、PEファンドが経営を引き継ぎ、企業の安定した成長を支援することで、従業員や取引先の信頼を維持しながら、円滑な事業承継を実現可能です。
4. 上場の代替手段
上場には多くのコストや規制が伴うため、必ずしもすべての企業にとって最適な選択肢ではありません。一方、PEファンドを活用することで、経営の自由度を維持しながら資本を調達し、事業拡大を進めることができます。
上場のプレッシャーから解放されることで、経営の長期的な視点を持ちやすくなる点は、大きなメリットです。
投資をする側のメリット
プライベートエクイティは、投資をする側にとってもメリットのあるアプローチです。
最大のメリットは、やはりリターンの大きさでしょう。安価に未上場の株式を取得し、企業価値が高まった段階で売却を行えば、大きな利益をあげられます。
またプライベートエクイティをポートフォリオに組み込み、リスクを分散することも可能です。株式や債権、金などに加えることで、バリエーションをもたらすことができます。
プライベートエクイティ活用のデメリット・注意点
投資を受ける側のデメリット・注意点
プライベートエクイティを活用することで、企業の成長や経営改革を加速できる一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらを事前に理解し、適切な対応を取ることが重要です。
1. 経営の自由度が制限される
プライベートエクイティファンドからの投資を受ける場合、ファンドが一定の経営権を持つことが一般的です。そのため、経営者の意思決定が制限される可能性があります。
短期間での企業価値向上を重視するファンドの場合、経営方針の調整が求められるケースもあるでしょう。
2. 投資期間の制約
プライベートエクイティファンドは、一般的に5〜10年程度の運用期間を持ちます。その間に企業価値を高めた上で、株式を売却することが目的です。
そのため長期的な経営戦略を描くことが難しく、ファンド側の意向に沿った成長計画が求められることになります。
3. ファンドとの相性が重要
PEファンドにも、それぞれ投資方針や得意分野があります。自社の経営スタイルや成長ビジョンと合致しないファンドを選んでしまうと、期待した効果が得られないこともあるかもしれません。
事前にファンドの投資スタンスや過去の支援実績を十分に確認し、自社に適したファンドを選定することが不可欠です。
投資をする側のデメリット・注意点
投資をする側であっても、プライベートエクイティにはデメリットがつきまといます。
まず大きなリターンが期待できる反面、リスクが大きいです。成長途上の企業や、経営危機に陥った企業への投資となるため、企業経営がうまくいかなかった場合はリターンが得られなくなります。
また上場企業より、未上場企業の組織の透明性が低く、精度のある意思決定がしづらいのも課題です。
長期での投資となるため、短期的な売却益を期待できない点もあらかじめ知っておくべきでしょう。
プライベートエクイティ(PE)ファンドの投資判断材料
プライベートエクイティ投資は、未上場企業を対象とするため、上場企業の株式投資とは異なる評価基準が求められます。ファンドが投資判断を行う際には、企業の成長性や収益性、財務健全性などを総合的に分析し、投資リスクとリターンを慎重に見極めます。
ここでは、プライベートエクイティ投資における代表的な評価方法を解説します。
1. 企業価値の評価
プライベートエクイティ投資では、企業価値の算出が重要なプロセスとなります。企業価値の計算方法いくつかありますが、以下の3つをピックアップして紹介します。
DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法
企業が将来的に生み出すキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法です。成長性や収益予測を考慮できる点が強みですが、前提条件の設定によって結果が変わるため、慎重な分析が求められます。
マルチプル法(類似企業比較法)
同業界の類似企業の株価収益率(PER)やEBITDA倍率(EV/EBITDA)などを基準に、対象企業の価値を算出する方法です。市場環境の影響を受けやすいものの、比較的シンプルな計算で評価できるため、多くのPEファンドで活用されています。
収益還元法
企業が将来得られる収益を現在の価値に換算して、企業の価値を評価する方法です。具体的には「平均収益 ÷ 資本還元率」によって企業価値を算出します。資本還元率は、企業の資本コストや長期国債の利回りを基に、会社の経営状態や規模などのリスク要因を加味したものです。
以下の記事では、企業価値の算定方法について詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>株価算定とは?スタートアップが押さえるべき基本と成功の秘訣を徹底ガイド
2. 財務健全性の分析
PE投資では、企業の財務状況も重要な判断材料となります。以下の指標は、その代表的な判断材料です。
- EBITDA(利払い・税引き・減価償却前利益):企業の本業による収益力を測る指標で、PEファンドが投資先の収益力を評価する際に広く使用されます。
- 負債比率(Debt-to-Equity Ratio):負債の割合が高すぎる企業は財務リスクが大きいため、借入金の適正水準が保たれているかがチェックされます。
3. 経営力・成長ポテンシャルの評価
財務指標だけでなく、企業の成長戦略や経営陣の能力も重要な評価ポイントです。プライベートエクイティファンドは、以下の要素を分析し、投資リスクを判断します。
- 市場の成長性:対象企業が属する市場の規模や成長性を分析し、将来的な収益拡大の可能性を見極めます。
- 経営チームの実力:経営陣のリーダーシップや戦略実行能力が、企業成長に直結するため、経験や過去の実績が重視されます。
- 競争優位性:事業モデルや技術、ブランド力など、競争力の源泉を明確にし、持続的な成長が可能かを検討します。
プライベートエクイティ投資による企業のM&A事例
プライベートエクイティ投資によるM&Aの事例は、近年よく見られます。以下の事例は、その代表的なケースです。
住友ベークライト、素材・化学分野特化のベンチャーキャピタルに出資
住友ベークライト株式会社は、素材・化学産業分野への投資に特化したベンチャーキャピタルへの出資を決定しました。「ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社(UMI)」が組成する、UMI3号投資事業有限責任組合への出資です。
この出資により、同社は次世代有望素材や革新的生産技術を持つスタートアップ企業の事業化をうながします。ICT、モビリティ、ヘルスケアの3領域での新技術探索の強化です。今回の出資を通じて、SDGsに即した機能性化学品の開発を推進し、社会課題の解決に貢献することを目指します。
参考:住友ベークライト株式会社|素材・化学産業分野に特化したベンチャーキャピタルへの出資のお知らせ
CLSAキャピタルパートナーズ、タスク・フォースへの資本参加
CLSAキャピタルパートナーズがアドバイザーを務めるSunrise Capital IVは、株式会社タスク・フォースへの資本参加を完了しました。
タスク・フォースは、企業主導型保育園や事業所内保育所を全国で約120施設運営しています。Sunrise Capital IVは、同社の高品質な保育サービスを高く評価し、経営基盤の強化を通じて社会貢献の継続を支援する方針です。
なお、今回の資本参加に伴い、タスク・フォースの経営体制やブランド名に変更はありません。
参考:CLSAキャピタルパートナーズ|株式会社タスク・フォースへの資本参加について
TKPと識学、インターステラテクノロジズに共同投資
株式会社TKPと株式会社識学が連携して組成した「新進気鋭スタートアップ投資事業有限責任組合」は、インターステラテクノロジズ株式会社への投資を実行しました。
インターステラテクノロジズは、民間企業としてロケットの開発・製造・打ち上げを行い、小型で低コストなロケット「ZERO」の開発を進めています。
今回の投資により、同社の組織運営の強化と企業成長の加速が期待されています。
参考:PR TIMES|TKPが株式会社識学と連携し組成した「新進気鋭スタートアップ投資事業有限責任組合」インターステラテクノロジズ株式会社に投資を実行
プライベートエクイティについて解説しました
プライベートエクイティは、資金調達の手段にとどまらず、企業の成長支援や経営改革のパートナーとしても大きな役割を果たします。事業承継やM&A、経営改善を検討する企業にとって、PEファンドの活用は有力な選択肢となるでしょう。
一方で、経営の自由度や投資期間の制約といったデメリットも見逃せません。ファンドの投資方針や自社の経営戦略を、あらかじめしっかりと見極めることが重要です。
状況に応じてプライベートエクイティを適切に活用し、企業価値の最大化を目指しましょう。