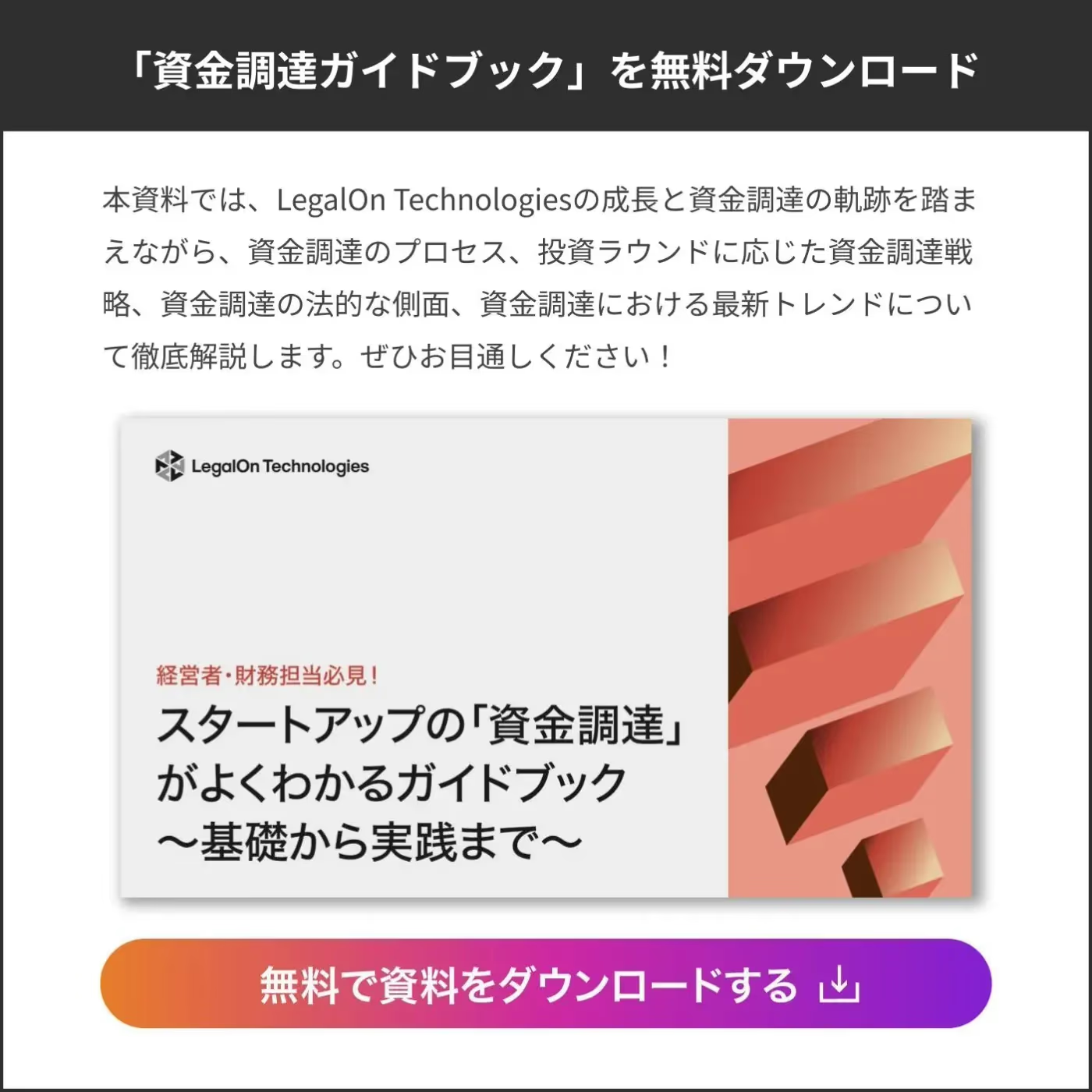公的融資とは?
まずは公的融資について説明していきます。融資や審査という単語は知っていても、仕組みや種類は知らないという方は、ここで概要を押さえて読み進めていきましょう。
公的融資の定義
公的融資とは、国や地方公共団体、または政府系金融機関などが提供する融資制度です。民間の金融機関による融資とは異なり、政策的な目的や社会的課題の解決を主な目的としています。より具体的には、中小企業や個人事業主の支援、創業促進、地域経済の活性化、雇用創出、環境対策など、幅広い分野において活用されています。
公的融資は民間の金融機関に比べて金利が低く、返済期間が長いなどの点がメリットです。また担保や保証人が不要な場合もあります。ただし、利用にあたっては一定の条件を満たす必要があり、審査も厳格に行われます。
公的融資と民間融資の違い
民間融資は、銀行や信用金庫といった民間の金融機関などが行う融資です。公的融資とは一般的に以下のような違いがあります。
公的融資
- 目的:経済の活性化や社会的課題の解決
- 金利:低金利
- 返済期間:長期
- 担保・保証人:不要な場合がある
民間融資
- 目的:利益の追求
- 金利:高金利(市場金利に連動)
- 返済期間:短期~中期
- 担保・保証人:必要
このように公的融資と民間融資では、目的や金利などにいくつかの違いがあります。また、上記の他にも審査の準備や要件にも違いがあるため、どちらの融資制度を利用するかは、事業の状況や資金調達の目的に合わせて検討する必要があります。
代表的な公的融資4選
公的融資における融資元はいずれも公的機関です。企業が融資を受ける場合、利用できる公的融資の種類にはいくつかの選択肢があります。ここからは実際にどのような融資元からどのような制度の融資が行われているのか見ていきましょう。
地方自治体
地方自治体は、地域経済の活性化や産業振興を目的に、独自の融資制度を設けています。その地域に事業所があることなどの条件が設けられており、融資内容や限度額は自治体ごとに異なるため、それぞれ確認が必要です。融資限度額は一般的に数百万円〜数千万円程度の範囲で自治体ごとに異なっています。
例として、東京都が実施している「東京都中小企業制度融資『創業』」を見てみましょう。
東京都中小企業制度融資『創業』
- 融資金額:3500万円
- 融資期間:【運転資金】7年以内(据置期間1年以内を含む)、【設備資金】10年以内(据置期間1年以内を含む)
- 融資利率:1.5% ~ 2.2% (2025年2月時点)
参考:東京都産業労働局 東京都創業NET「東京都中小企業制度融資『創業』」
東京信用保証協会「都創業融資(略称:創業)」
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、中小企業や小規模事業者、農林漁業者などを支援する政府系金融機関です。民間の金融機関では融資を受けにくい創業初期の企業や、経営改善に取り組む企業などに対しても、積極的に融資を行っています。またスタートアップ企業向けの融資制度として「スタートアップ支援資金」などの制度も公開しています。
スタートアップ支援資金
- 融資金額:直接貸付 20億円
- 融資期間:【設備資金】20年以内(うち据置期間10年以内)、【運転資金】20年以内(うち据置期間10年以内)
- 融資利率:上限2.5%(信用リスク、融資期間、担保の有無によって利率が変動)
参考:日本政策金融公庫「スタートアップ支援資金」
商工組合中央金庫
全国の商工会や事業協同組合などを通じて、組合員である中小企業に融資や経営支援を提供しています。融資の種類は多岐に渡り、運転資金や設備資金、事業承継・M&A資金など、様々なニーズに対応しています。一般的な融資限度額は数億円〜数十億円程度ですが、事業規模や内容によってはさらに高額な融資も可能です。金利は低めで、返済期間も長めに設定されているため、中小企業にとって利用しやすい融資制度と言えるでしょう。
商工組合中央金庫の融資制度の一例として、「一般的な融資」という形で紹介されている内容が以下の通りです。
一般的な融資
- 融資金額:利用制度により異なる
- 融資期間:【設備資金】15年以内(うち据置期間2年以内)、【運転資金】10年以内(うち据置期間2年以内)
- 融資利率:金融情勢により変動
参考:商工組合中央金庫「一般的な融資」
商工組合中央金庫の場合、上記のように融資金額や利率が事前に把握しづらい部分があります。しかしこれは、企業個別のニーズに対応する方式を取っているためで、融資金額の上限自体は他の融資と比べて高いといわれています。そのため、商工組合中央金庫を融資の選択肢に入れる場合は、まず窓口で相談するとよいでしょう。
全国信用保証協会連合会
全国信用保証協会連合会は、全国51の信用保証協会を会員とする組織です。全国信用保証協会連合会は、信用保証協会の支援を通じて、中小企業の資金調達を円滑化することを目的としています。具体的な活動としては、信用保証業務の改善に向けた調査研究、中小企業金融に関する調査研究、信用保証協会への情報提供などを行っています。信用保証協会が行っている融資の限度額は、各都道府県の信用保証協会によって異なりますが、数千万円程度が一般的です。
ここでは例として、「スタートアップ創出促進保証制度」を見てみましょう。
スタートアップ創出促進保証制度
- 融資金額:3500万円
- 融資期間:10年以内(据置期間1年または3年以内)
- 融資利率:各信用保証協会所定の創業関連保証の保証利率に0.2%上乗せ
参考:全国信用保証協会連合会「スタートアップ創出促進保証制度」
公的融資の利用の流れ
公的融資の概要を押さえたうえで、次は利用の流れを解説していきます。以下では、公的融資を受けるにあたっての制度選択から返済までの流れを簡単に記載しています。細部は利用する制度や融資元の状況で変わるため、利用前に十分な確認を行うようにしましょう。
融資制度の選択
まずは数ある公的融資制度の中から、自社の事業内容や資金ニーズに合った制度を選ぶことが重要です。公的融資は前述の通り国や地方自治体、政府系金融機関などが提供しており、それぞれ融資対象や条件、金利、融資限度額などが異なります。
例えば創業資金であれば日本政策金融公庫の「新創業融資制度」、事業拡大のための設備資金であれば地方自治体の制度融資などが考えられます。各制度の内容を比較検討し、自社の事業に最適な制度を選びましょう。制度の選択に迷う場合は、地方自治体の窓口や商工会議所、金融機関などに相談することも可能です。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な制度を見つけることができます。
申請書類の準備と提出
融資制度が決まったら、必要書類を準備します。申請書類は制度によって異なるのですが、一般的には事業計画書、財務諸表、本人確認書類などが求められます。事業計画書は、融資を受ける目的や資金の使い道、返済計画などの具体的な記載が必要です。金融機関は、この事業計画書の内容を審査の重要な判断材料とします。また財務諸表は過去の経営状況や財務状況を示す書類であり、企業の安定性や返済能力の判断に用いられます。これらの書類に不備があると審査に時間がかかったり、融資を受けられなかったりする可能性もあるため、丁寧に準備しましょう。
面談・審査
申請書類を提出後、融資元機関の担当者との面談が行われます。面談では、企業による事業内容や資金計画、返済能力などについての詳しい説明が必要です。担当者は、提出された書類や面談内容をもとに、融資の可否や融資額を審査します。審査期間は制度や融資元によって異なるのですが、数週間から数ヶ月程度かかる場合があります。審査に通るためには、事業計画書の内容を充実させ、面談で担当者に正確に説明することが重要です。事前に事業内容や資金計画についてよく検討しておきましょう。
審査のポイントについて、詳しくは「公的融資の審査に通るためのポイント」にて後述します。
融資実行
審査に通過すると、融資が実行されます。融資実行の方法は、金融機関によって異なるのですが、一般的には指定の口座に振り込まれます。融資された資金は、事業計画書に記載した用途に沿って適切に活用しましょう。
返済
融資を受けた後は、返済期日までに返済が必要です。返済方法は制度や融資元によって異なるのですが、一般的に毎月一定額を返済する形で行います。返済が滞ると遅延損害金が発生したり、信用情報に悪影響が及んだりする可能性があります。返済計画をしっかりと立て、期日までに確実に返済しましょう。
公的融資のメリット
公的融資には民間の金融機関による融資と比較して、いくつかのメリットがあります。ここからはそれらのメリットを詳しく解説していきます。自社の状況や資金調達の影響を考慮して、以下に示すメリットの恩恵を最大限受けられるか、検討してみましょう。
早い段階から融資が受けやすい
公的融資は創業間もない企業や、実績の少ないスタートアップ企業でも比較的融資を受けやすい点がメリットです。民間の金融機関は、過去の業績や財務状況を重視する傾向があるのですが、公的融資では事業計画の実現可能性や将来性などを総合的に判断します。そのため、創業初期の企業や、実績の少ないスタートアップ企業でも、事業計画の内容や将来性をしっかりとアピールできれば、融資を受けられる可能性があります。
事業を始めるにあたって資金調達は大きな課題の一つですが、公的融資を利用することで早い段階から必要な資金を確保し、事業を軌道に乗せることが可能です。
金利が低い
公的融資は民間の金融機関による融資に比べて、金利が低いというメリットがあります。公的融資は経済活性化や社会的課題の解決を主な目的としているため、利益を追求する民間の金融機関とは異なり金利が低く設定されています。金利が低いことは返済負担を軽減するだけでなく、資金調達コストを抑えることにもつながるメリットです。資金調達コストを抑えることで、事業の収益性を高め、成長を加速させることができます。
また低金利であることは、長期的な視点での事業計画を立てやすくするというメリットもあります。特に創業初期の企業や、経営基盤の弱い中小企業にとって、公的融資は低金利での融資が大きな助けとなる制度です。
無担保や無保証人で利用できる場合がある
民間の金融機関は、融資を受ける際に担保や保証人を求めるのが一般的ですが、公的融資では、制度によっては担保や保証人が不要な場合があります。これは、担保や保証人を用意できない中小企業や個人事業主にとって大きなメリットです。特に創業前の企業やスタートアップ企業の場合、担保や保証人を用意することが難しい場合があります。公的融資を利用することでこれらの問題を解決し、スムーズに資金調達を行うことが可能です。
無担保・無保証で利用できることは、経営者にとって大きな安心感につながります。担保や保証人の心配をせずに、事業に集中できる環境が整うことで、より積極的に事業展開を進めることができるでしょう。
公的融資のデメリット
経営者にとって喜ばしいいくつかのメリットがある一方で、公的融資のデメリットにも注意しておかなくてはなりません。以下に示すデメリットが自社に与える影響を加味して、どの制度を利用するか、民間融資と比較してどちらがより良いのかを検討してみましょう。
必要書類が多い
公的融資は民間の金融機関による融資に比べて、必要書類が多い傾向があります。これは公的資金を扱う性質上、厳格な審査に詳細な事業計画書や財務諸表、許認可証など、様々な書類の提出が求められるためです。書類の準備には時間や手間といった事務コストがかかり、不慣れな人にとっては大きな負担となることがあります。
特に創業前や創業間もないスタートアップ企業の場合、必要な書類を揃えるのが難しいケースもあります。しかし書類の内容が不十分であったり不備があったりすると、審査に時間がかかったり融資を断られたりする可能性もあるため注意が必要です。公的融資を申し込む際には、必要書類を事前に確認し、余裕をもって準備を進めましょう。
融資を受けるまでに時間がかかる
公的融資は民間の金融機関による融資に比べて、融資を受けるまでに時間がかかる傾向があります。これは審査が厳格であることに加え、申請書類の審査や面談など複数の段階を経る必要があるためです。
また融資制度によっては、地方自治体や政府機関の承認を得る必要があり、さらに時間がかかる場合もあります。そのため急ぎで資金が必要な場合には、公的融資は適していない可能性があることを、認識しておきましょう。
しかし時間がかかる分、融資条件が良い場合が多く、長期的な視点で資金調達を考える場合には、公的融資は有力な選択肢となります。
制度によって限度額が違う
公的融資は制度によって融資限度額が異なります。同じスタートアップ企業向けの融資制度であっても、企業の規模や業種、経営状況などによって、融資を受けられる金額が制限される場合があります。
また創業融資など、特定の目的の融資制度では、限度額が低く設定される点にも注意が必要です。そのため必要な資金調達額を事前に確認し、利用する融資制度の限度額と照らし合わせて検討を進めましょう。もし必要な金額を調達できない場合には、複数の融資制度を組み合わせたり、民間の金融機関の融資も検討したりする必要があります。
公的融資の審査に通るためのポイント
公的融資は、中小企業や個人事業主にとって資金調達の有力な手段ですが、審査に通るためにはいくつかのポイントを押さえることが重要です。ここでは、特に重要な3つのポイントについて詳しく解説します。
説得力のある事業計画を示す
公的融資の審査においては、事業計画書が非常に重要な要素となります。融資元は提出された事業計画書を通じて、事業の実現可能性や将来性、返済能力などを判断します。そのため事業計画書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。
事業内容を具体的に説明する
どのような事業を行うのか、どのような商品やサービスを提供するのか、ターゲット顧客は誰なのかなどを明確に説明しましょう。
市場分析をしっかり行う
競合他社の状況や市場の動向などを分析し、自社の強みや差別化ポイントを明確に示しましょう。
売上計画や収支計画を合理的に示す
過去のデータや市場の予測などを参考に、売上計画や収支計画を具体的に作成しましょう。
事業計画書は単なる書類ではなく、あなたの事業に対する熱意や将来性を伝えるためのツールです。融資元となる機関に「この事業は経済の活性化につながる」「社会的課題の解決を目指せる」と思わせるような、説得力のある事業計画書を作成しましょう。
前もって返済計画を立てる
融資を受けるためには、返済計画を立てておくことが重要です。金融機関は、返済能力があるかどうかを審査の際に重視します。前述した事業計画書に基づいて、無理のない返済計画を立案することで、将来の返済能力を示すだけでなく資金繰りの安定性を示すことも可能です。返済期間が長期になるからこそ、長期的な視点を持っていることを示す良い機会と要素になります。返済期間や返済方法は制度や融資元によって異なるため、融資を受ける内容に合わせて返済計画に反映しましょう。
個人の信用情報の確認
公的融資の審査では、個人の信用情報も重要な判断材料となります。信用情報機関に登録されている情報が融資の可否や融資条件を判断する基準のひとつです。登録されている内容としては、クレジットカードやローンの利用履歴、延滞や滞納の情報などが含まれます。もし過去に延滞や滞納の経験がある場合には、信用情報がマイナスとなり融資審査に影響を与える可能性が少なくありません。そのため公的融資を申し込む前に、自身の信用情報を確認しておくことが大切です。信用情報機関に開示請求をすることで、個人でも自身の信用情報を確認できます。自身の信用情報に不安がある方は、請求して確認しておくと良いでしょう。
担保・保証人を準備する
メリットでは無担保・無保証人で融資を受けられる場合があることに言及しました。しかし融資を受ける際には、担保や保証人が必要となる場合も当然存在します。担保・保証人が必要ないと思って制度選びを始めてしまうと、希望する制度を利用できない可能性があるので、注意が必要です。
担保とは、返済が滞った場合に融資元が回収できる財産のことで、不動産や有価証券などが該当します。また保証人とは、返済が滞った場合に代わりに返済を行う人のことで、企業が融資を受ける場合は代表者が、基本的にこれに該当します。担保や保証人は、融資元にとって融資のリスクを軽減するためのものです。もし担保や保証人を用意できる場合には、融資審査に通りやすくなる可能性があります。
しかし、担保や保証人を用意できない場合でも、諦める必要はありません。公的融資の中には前述の通り、無担保・無保証人で利用できる制度もあります。自社の状況に合わせて、最適な融資制度を選びましょう。
自己資金も準備する
公的融資の審査を有利に進めるには、自己資金の準備も必要になります。金融機関は自己資金の有無や金額から、事業への真剣度や返済能力を判断する場合があるためです。
特に創業融資においては、自己資金が申込条件となっているケースが多く見られます。例えば日本政策金融公庫の創業融資では、融資希望額の10分の1程度の自己資金が求められます。また審査では、直近半年程度の預金通帳の提出を求められる場合があります。これは融資直前に一時的に資金を借り入れて自己資金要件を満たす、といった行為を防ぐためです。そのため自己資金は計画的に、時間をかけて準備する必要があるでしょう。
自己資金の準備は、金融機関からの信頼を得るだけでなく、自身の事業計画に対する自信にもつながります。十分な自己資金を用意し審査に臨むことが、融資成功への近道となります。
公的融資について解説しました
公的融資は国や地方公共団体、または政府系金融機関などの公的機関が提供する融資制度です。創業前の段階や創業間もないスタートアップ企業などでも利用できるほか、金利とハードルが比較的低いこともメリットといえます。その分、審査の厳しさや事務コストの高さがありますが、上手く利用することができれば事業をスムーズに進める資金源を確保することが可能です。
この記事では、公的融資の概要や種類、利用の流れ、メリット・デメリット、審査のポイントを解説してきました。
資金調達手段に悩んでいる企業の方は、この記事を参考に公的融資を選択肢に入れて、利用制度の検討を進めてみましょう。紹介・解説した内容が資金調達の参考となれば幸いです。