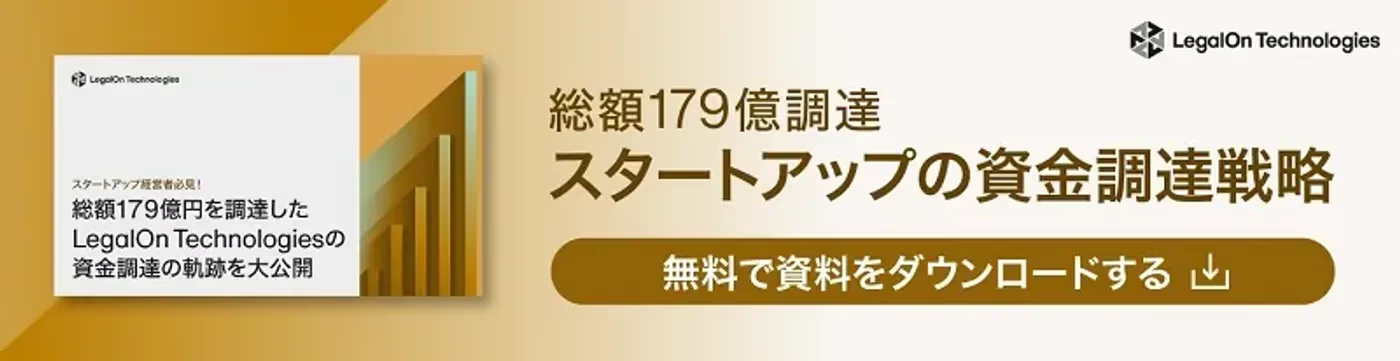公募増資とは
公募増資とは、新規株式の発行によって不特定多数の投資家に株主を募る資金調達方法です。Public Offering(PO)と呼ばれる「既公開株式等の募集・売出し」の一つの手法です。
公募増資は大規模な設備や新規事業、M&Aなどの投資のために一般投資家からの資金調達を目的としている点が特徴です。公募増資は新たな株主から資金を調達することから「自己資本」の1つとして該当します。株式会社の資金調達方法には、銀行からの借入金や社債などの「他人資本」も存在します。公募増資はスタートアップ企業が上場後に利用でき、多くの企業が採用している増資手段です。
公募増資とIPOの違い
公募増資とIPOは、どちらも企業が資金調達のために新たに株式を発行する方法ですが、目的と対象が異なります。公募増資はすでに上場している企業が追加で新株を発行し、不特定多数の投資家に販売することで資金を調達する手法です。主に大規模な設備や新規事業、M&Aなどの投資を目的に行われます。
一方でIPO(新規株式公開)は未上場企業が初めて証券取引所に上場し、一般投資家に向けて新株を公開・販売することです。IPOの目的は資金調達とともに企業の知名度向上や信用力強化にあります。
【公募増資】
- 対象:上場企業
- 目的:大規模な設備投資、新規事業・M&Aのための資金調達
【IPO】
- 対象:未上場企業
- 目的:資金調達、知名度向上、信用力強化
以下の記事では、IPOの基礎知識を分かりやすく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>IPOの基礎知識や申請の動きをわかりやすく解説します!
公募増資の仕組み
公募増資を実施するには、増資に関する決議を行う必要があります。株主総会を開催して決議を行い、特別決議から公募増資による資金調達の同意を得ることが必要です。
基本的に公募増資の手続きは、企業が証券取引所や金融機関と連携しながら進めます。企業は株主総会・取締役会で決めた増資計画や条件を公開し、投資家からの応募を受け付けます。応募者は手続きを経て株式を取得し、企業に資金を提供する仕組みです。
また1億円以上の株式を発行する場合、有価証券届出書を財務局に提出しなければいけません。新たに発行する株式の価格は投資家や専門家の見解を考慮して公募価格を決める「ブックビルディング方式」によって決定され、その価格で公募が開始されます。購入希望者の応募を受け付けて資金提供と引き換えに株式を交付することが、公募増資の仕組みとなります。
公募増資後、株価は下がる?
結論、公募増資を行うと一般的に株価は下がる傾向があります。 これは新株発行により一株あたりの価値が希薄化することや、市場に供給される株式数の増加で売り圧力が高まるためです。特に公募増資の実施を「資金繰り悪化」と捉えられる場合、株価が大きく下落することもあるでしょう。
ただし、投資家が公募増資の目的を「成長投資」と好意的に評価する場合、株価への影響は小さく抑えられることもあります。調達資金を成長投資に活かし業績が向上すれば、長期的に株価が回復・上昇する可能性もあります。
公募増資を実施する5つのメリット
公募増資を実施することで、以下のような5つのメリットがあります。
- 新しい投資家の獲得
- 返済義務がない
- 株式流動性の向上
- 企業信用度の向上
- 既存株主の権益を尊重できる
それでは順番に説明します。
新しい投資家の獲得
公募増資は不特定多数の投資家に株主を募集するため、新しい投資家を獲得できるようになります。既存株主だけでは資金調達に限界があるので、公募増資によって新たな投資家を獲得すれば資金力のある人と出会えます。また、新しい投資家を獲得すれば、一部株主の意見に偏った企業経営を防ぐことが可能です。
さらに会社の認知度も高まりを見せるので、自然と株主層を拡大できます。そのため新たな投資家を獲得できる点は、公募増資の大きなメリットといえるでしょう。
返済義務がない
公募増資によって得られた資金は、返済や利息の支払いはありません。銀行からの借入金や社債などの他人資本の場合、返済や利息の支払いが必要です。企業によっては事業が軌道に乗るまで時間がかかることもあるので、返済に追われると経営を安定させることは難しくなります。
公募増資なら投資家から得た資金を返済する必要がなく将来的な資金繰りに悩まされる心配がなくなります。そのため会社の経営を安定できる点は、公募増資のメリットの1つです。
株式流動性の向上
株式の流動性とは、株式の現金化や取引がしやすくなることです。需要が少ない株式は売買が成立しづらいですが、株式の流通量が増えれば流動性は高くなっていきます。
公募増資を実施すれば発行する株式数が増えるため、市場に流通する株式数も増えて流動性が高くなりやすいです。結果として株主が株式を売買しやすくなり、価格の安定化につながるのです。そのため株式の流動性が向上する点は、公募増資を実施するメリットといえます。
企業信用度の向上
公募増資によって自己資本が増加すれば、企業の信用度が向上します。資本金が少ない企業は市場で人気がないことを証明しているため、投資家や顧客からの信用度が低下してしまいます。
公募増資を実施することで、自己資本比率が改善されて企業としての安定性が高まっていくのです。そのため企業の信用度が向上する点においても、公募増資の実施はメリットとなるでしょう。
既存株主の権益を尊重できる
普通ならば増資によって新しい株式を発行すると、会社の企業価値に対して発行株式数が増えることから、1株あたりの価値が薄まり、既存株主の所有株式が希釈される恐れがあります。
公募増資では、公募価格は時価に近い多少割安な水準で決められることが多いため、既存株主の所有株式の希薄化が低減できます。また優先株を提供することで、既存株主の権益をさらに保護できるようになります。新しい株主だけでなく、既存株主の理解を得ながら実施できる点も公募増資のメリットといえるでしょう。
スタートアップの資金調達についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下のお役立ち資料も併せて確認してみてください。
公募増資を実施する5つのデメリット
公募増資を実施することで、以下のような5つのデメリットも存在します。
- 配当金の支払いが増加
- 短期的利益を求める投資家の影響を受けやすい
- 経営権の希釈化につながる
- 税制優遇が受けられないことがある
- 企業経営が不安定になる恐れがある
良い点と悪い点を比較しながら、ほかの資金調達方法を実施すべきか検討してください。
1. 配当金の支払いが増加
公募増資を実施すると新しい株式が増えるため、配当金の支払い額も増加します。公募増資は新たな資金を獲得できる方法ですが、長期的に見ると配当金の支払いが会社の財務状況に大きな負担を与える可能性があります。増資の資金調達は融資に比べてコストが高いので、早い段階で投資に回しながら収益を得られる仕組み作りをすることが大切です。そのため配当金の支払いが増加する点は、公募増資を実施するデメリットといえるでしょう。
2.短期的利益を求める投資家の影響を受けやすい
公募増資は不特定多数の投資家に株主を募集するため、会社にとって望ましくない株主が現れるケースもあります。公募増資によって短期的な利益を求める投資家が増えてしまうと、企業の長期的な成長戦略に悪影響を及ぼす可能性が高いです。また株式の取引量が少なく株価が低調しているタイミングで公募増資を実施すると、需給悪化の懸念から株価が下落することもあります。
もし短期的利益を求める投資家を増やしたくないなら、特定の第三者を株主とする第三者割当増資の実施がおすすめです。会社の状況を考えながら、利用すべき資金調達方法を検討するようにしましょう。
3.経営権の希釈化につながる
公募増資の実施によって新しい株主が増えると、既存株主の持株比率が低下してしまいます。結果として既存株主の持つ議決権割合が低下するため、経営権の希釈化につながります。
経営戦略の意思決定にブレが生じる恐れがあるので、会社の方針とは異なる状況になる可能性が高いです。そのため経営権の希釈化につながる点は、公募増資を実施するデメリットといえるでしょう。
4.税制優遇が受けられないことがある
公募増資の実施から資本金が1億円を超えた場合、中小企業としての税制優遇が受けられなくなります。税法では資本金1億円以下を中小企業と定めているため、超えていなければ税制上の優遇が受けられます。
資本金が1億円を超えると税制優遇が受けられないだけでなく、外形標準課税の課税対象にもなるので注意が必要です。そのため公募増資を実施するときは、現時点の資本金を事前にチェックしておくようにしましょう。
5.企業経営が不安定になる恐れがある
公募増資は不特定多数の投資家を対象としているため、企業の経営方針に賛同しない株主が増えることもあります。企業経営が不安定になると成長を妨げてしまうので、事業にも悪影響を及ぼします。
企業経営を安定させるためにも、既存株主との株式割合をうまく調整しなければいけません。企業経営が不安定になる恐れがあることから、公募増資を実施するときは気をつけておきましょう。
公募増資を実施する流れ
公募増資を実施するときは、以下のような流れで進めます。
- 増資に関する決議(株主総会・取締役会)を行う
- 有価証券届出書の作成・提出(1億円以上の株式を発行する場合)
- 公募条件の決定・公表
- 株式の引受人から出資を受ける
- 登記変更手続きを行う
はじめに株主総会・取締役会を開催して決議を行い、特別決議から公募増資による資金調達の同意を得ていきます。そして増資計画や公募条件を公開し、投資家からの応募を受け付けます。最後に登記変更手続きを経て、企業に資金を提供してもらう流れです。1億円以上の株式を発行する場合、有価証券届出書を財務局に提出が必要です。
このように公募増資の実施は複数の手続きが必要になるため、証券取引所や金融機関と連携しながら進めるようにしましょう。
公募増資の事例
国内外食チェーン大手の株式会社ゼンショーホールディングスは、2023年11月24日に公募増資と野村證券を引受先とする第三者割当増資によって最大約500億円の資金調達に成功しました。
既存事業の強化・拡大をはじめ海外への事業展開を目的としており、強固な経営基盤の確率・財務体質の強化を図るために資金調達を実施しました。獲得した資金をもとに国内外チェーン店の事業拡大に成功し、現在では安定した収益を得られています。
参考:日本経済新聞|ゼンショーHD 公募増資など最大500億円調達 M&Aに
公募増資とほかの増資方法の違い
公募増資のほかに増資手段として「株主割当増資」と「第三者割当増資」の2種類があります。それぞれの詳細や特徴について説明するので、違いを理解するためにもチェックしてください。
株主割当増資
株主割当増資は、既存株主に持株比率に応じた新株を発行する資金調達方法です。既存株主に新株の購入権利が与えられるため、権利を行使すれば新株を購入できます。
公募増資は不特定多数の投資家に株主を募集するのに対して、株主割当増資は既存株主に株式を発行する方法となっています。株主割当増資は既存株主が持株比率を維持できるので、既存株主全員が新株を引き受ければ株主の構成比率は変化しません。会社の経営権や意思決定の影響を維持できるため、会社は株主の理解を得られやすくなります。
ただし新規の出資者が株主に加わることはできないので、資金力のある投資家に関われない点はデメリットです。既存株主の理解を得られる増資を求めるなら、株主割当増資の実施がおすすめです。
第三者割当増資
第三者割当増資は、第三者に株式を有償で引き受けてもらう資金調達方法です。第三者には社内の役員や従業員、取引先などが含まれています。
公募増資は不特定多数の投資家に株主を募集するのに対して、第三者割当増資は特定の第三者を対象とした新株の発行を行います。第三者割当増資は資金調達だけでなく、他社との関係性強化や事業承継などを目的として実施されるケースが多いです。株式を付与する相手を選べるため、意図しない人物に議決権を持たれる心配はありません。
また第三者割当増資は公募増資のように特別決議の必要はなく、取締役会決議のみで株式発行ができるのでスピーディに進められます。議決権のリスクを回避しながら増資を行うなら、第三者割当増資の実施がおすすめです。
以下の記事では第三者割当増資について詳しく解説しています。理解を深めたい方はぜひ併せて確認してみてください。
<関連記事>第三者割当増資とは?株価は下がる?メリット・デメリットや手続きの手順をわかりやすく解説
公募増資について解説しました
今回は、公募増資の詳細からメリット・デメリット、実施する流れまでわかりやすく解説しました。公募増資は不特定多数の投資家に株主を募集する資金調達方法であり、大規模な設備や新規事業、M&Aなどの投資を目的としています。
公募増資は返済や利息の必要がなく、新たな投資家の獲得、株式の流動性向上、企業の信用度向上など多くのメリットがある一方、経営権の希薄化や株価の低下など注意点も理解しておかなくてはいけません。ほかの資金調達方法と比較しながら、状況に最適な方法を選択するようにしましょう。

.webp?quality=75&format=auto)