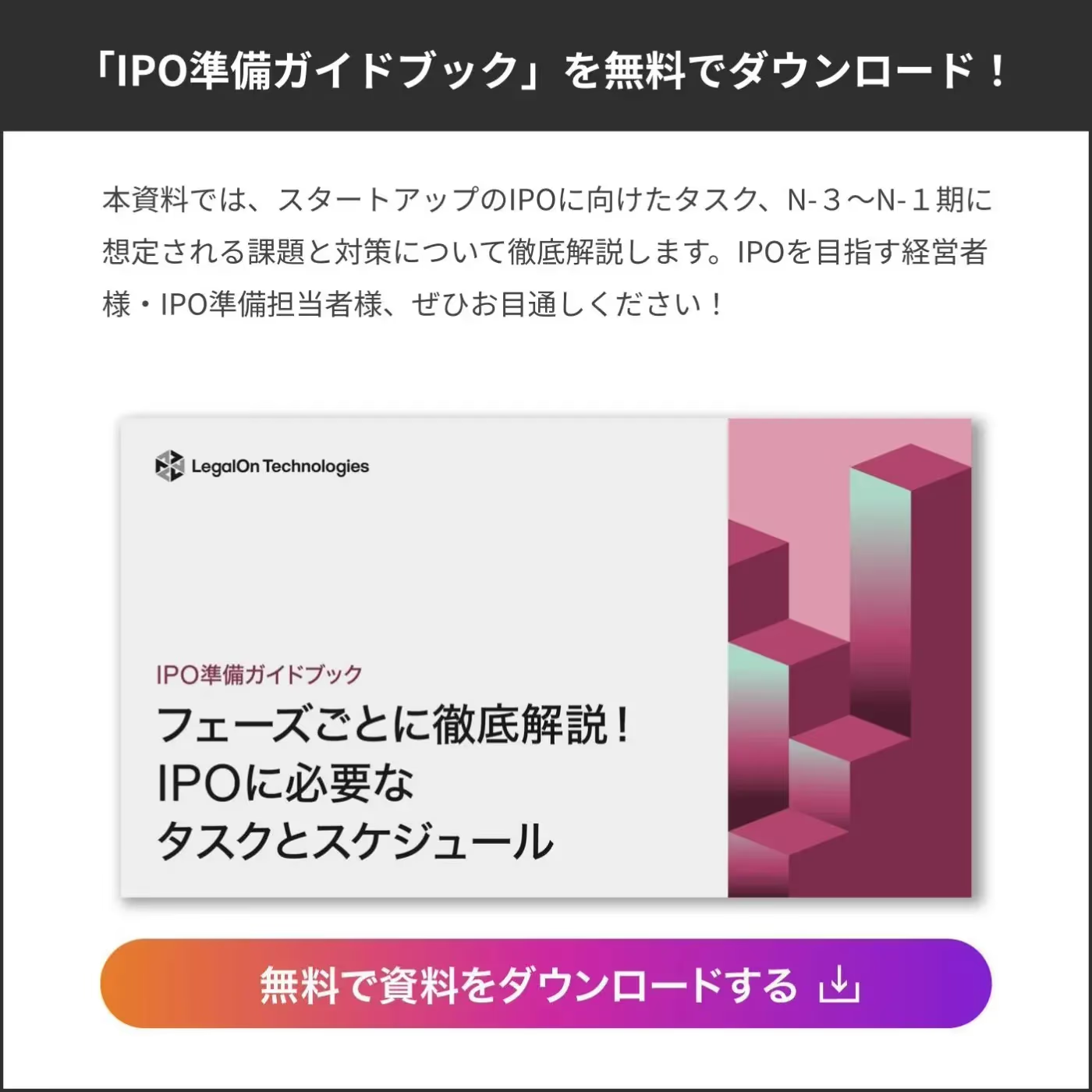ストックオプションとは
ストックオプションとは、株式報酬制度の1つです。
企業が役員や社員に「将来あらかじめ決められた金額で自社株式を購入できる権利」を報酬として与える制度となっています。役員や社員は、権利行使によって会社の株式をあらかじめ定めた価格=権利行使価額で購入でき、将来的に購入した株式の価格が上昇すれば売却して、差額分の利益が得られる報酬制度です。権利の付与・行使に、一定期間勤続や業績などの条件を設ける場合もあります。
仮に対象者に「3年間、単価2,000円で最大500株購入できる権利」を渡し、2年後に会社の株価が1株3,000円まで上がった場合、以下のようになります。
①対象者が権利を行使する
→あらかじめ決められた単価2,000円で500株を会社から購入
2,000円 × 500株 = 1,000,000円
②対象者は購入した株を売却する
→その時点の株価である1株3,000円で売却
3,000円 × 500株 = 1,500,000円
③最終的に対象者が得る収入
→①と②の差額
1,500,000円 - 1,000,000円 = 500,000円
ストックオプションの導入は企業にとって以下のようなメリットがあります。
- 役員や社員の流出を防げる
- 株価を上げるために、社員の企業価値向上へのモチベーションが高まる
- 権利を付与される役員や社員に不利な要因が少ない
<関連記事>IPOを目指す企業必見! ストックオプション徹底解説と法務戦略の重要性
ストックオプションの仕訳(会計処理)を時系列で解説
ストックオプションは報酬として株式の購入権を付与する制度です。そのため、通常の給与や賞与とは会計処理が異なります。
ストックオプションを会計処理する上で、仕訳が必要となるのは以下の3つのタイミングです。
- ストックオプションを付与するとき
- ストックオプションの権利が行使されたとき
- ストックオプションの権利が失効したとき
ここからは上記の時系列ごとにそれぞれどのような仕訳を行うのか、詳しく解説していきます。また本項では、ストックオプションの対象者や単価を以下の数値と仮定して、仕訳を紹介します。
前提となる条件
- 発行するストックオプション総数:100株
- ストックオプションの評価単価:(新株予約権)1株あたり 1,000円
- あらかじめ定めた権利行使価格:1株あたり 2,000円
- ストックオプションの対象者:50名(1名あたり2株付与)
ストックオプションを付与する
企業側が役員や社員にストックオプションを付与したタイミングで、会計処理上の仕訳が発生します。
- 借方:株式報酬費用100,000円
- 貸方:新株予約権100,000円
役員や社員に対する報酬であるストックオプションは、企業にとって給与と同様に費用です。そのため「株式報酬費用」の形で費用の勘定科目で仕訳します。
この際の株式報酬費用は、以下のように計算します。
発行するストックオプションの総数 × 評価単価
100株 × 1,000円 = 100,000円
株式報酬費用の貸方として、資本の勘定科目で「新株予約権」を起票します。
この科目は最終的に全て相殺される点に注意が必要です。
また、上記の例では簡略化のため、1会計期間で評価単価の総額を費用計上しています。
実際には付与される役員や社員が、権利行使を制限されている期間(対象勤務期間)の数年にわたって株式報酬費用を按分して計上します。ただし権利行使期間を設けていない場合は、発行時点で一括して計上するため、上記の仕訳例と同様です。
ストックオプションの権利が行使された
ストックオプションの対象者がその権利を行使したタイミングで、会計処理上の仕訳が発生します。例として、前提条件としていた50名のうち30名が権利を行使した場合の仕訳は以下のようになります。
- 借方:当座預金120,000円、新株予約権60,000円
- 貸方:資本金180,000円
「ストックオプションの権利が行使された」という状態は、企業視点で見ると「あらかじめ定めた権利行使価格で役員・社員が株を購入した」ことを指します。このため、当座預金として以下の金額が計上されます。
権利を行使した人数 × 1人あたりの株数 × 権利行使価格
30名 × 2株 × 2,000円 = 120,000円
また発行した新株予約権のうち、30名分に相当する60株が行使されたため、以下の金額で新株予約権の相殺が必要です。
行使された新株予約権の株数 × 評価単価
60株 × 1,000円 = 60,000円
以上を合計した180,000円を資本金として貸方に計上することで、権利行使の際の仕訳を行います。
ストックオプションの権利が失効した
ストックオプションの権利行使には期間が設定されています。この期間を超過して、ストックオプションの権利が失効したタイミングで、会計処理上の仕訳が発生します。上記で権利を行使した30名を除く、20名分が失効したと仮定して仕訳を行った場合が以下の通りです。
- 借方:新株予約権40,000円
- 貸方:新株予約権戻入益40,000円
20名分のストックオプションが新株予約権に残った状態であるため、借方に計上することで相殺します。計上される金額は以下のように計算されます。
残っている新株予約権の株数(失効させた人数 × 1人あたりの株数) × 評価単価
(20名 × 2株)× 1,000円 = 40,000円
相殺された新株予約権に対して、貸方では「新株予約権戻入益」が発生します。
これはストックオプションを付与した際に、事前に計上した「株式報酬費用」が一部使われず戻し入れが起こるためです。収益の勘定科目で計上することで、費用を清算してストックオプションの仕訳が完了となります。
ストックオプションにおける評価単価の計算方法
ストックオプションを制度として取り入れるうえで、評価単価の算定は非常に重要になります。なぜならこの価格が公正に算定されていなければ、株主・役員・社員のいずれか、または複数にとって納得のいかない制度となりかねないからです。
公正な価格を算定する方法はいくつかあり、株式を公開している企業か否かでも方法が異なります。それぞれの算定方法と事前に収集するべきデータについて見ていきましょう。
評価単価の計算前に収集したいデータ
ストックオプションの評価単価を計算する方法は複数あり、そのいずれでも計算に用いるデータが不可欠です。主に以下のようなデータが事前に収集できていると、スムーズに算定できるとされています。
- ストックオプションの総数
- ストックオプションの権利行使価格
- 付与されてから権利が行使されるまでの期間
- 権利が付与された時点での株価
- 権利を行使した時点での株価
- リスク利子率(リスクフリーレート)
はじめてストックオプションを導入した時点では、自社のデータが無く算定が行えません。そのため、同業他社や規模感の等しい他社の情報を参考に算出を行います。
公開企業の評価方法
公開企業とは、すでに証券取引所に上場し、株式を公開している企業のことです。
ストックオプションの評価単価は、取引されている市場価格も参考に株式オプション価格算定モデル等の算定技法を用いて算出します。
公正な価格を目指すため、ブラック・ショールズ式や二項モデルといった代表的な計算式を用います。しかしこれらの計算式は、あくまで市場で取引される株式の価格算定用に開発されている点に注意が必要です。実際の細かい価格は自社のストックオプションの特性・条件を適切に反映するよう、調整しなくてはなりません。
未公開企業の評価方法
未公開企業とは、証券取引所に上場しておらず、株式を公開していない企業のことです。
この場合は評価単価の参考となる自社の株式情報が市場に無く、公正な評価が困難です。
このため未公開企業の評価単価算定には、「ストックオプションの本源的価値」を利用します。企業の財務状況や動向が会計基準で評価された結果が、本源的価値と呼ばれる評価指標です。企業会計基準委員会による企業会計基準第8号では以下のように定義されています。
未公開企業については、ストック・オプションの公正な評価単価に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積りに基づいて会計処理を行うことができる。
「単位当たりの本源的価値」とは、算定時点においてストック・オプションが権利行使されると仮定した場合の単位当たりの価値であり、当該時点におけるストック・オプションの原資産である自社の株式の評価額と行使価格との差額をいう。
(一部抜粋して引用:企業会計基準委員会「企業会計基準第8号」会計基準 未公開企業における取扱い )
上記の定義に基づく「ストックオプションの本源的価値」の計算式は以下の通りです。
ストック・オプションの本源的価値 = 自社株式の評価額 - 権利行使価格
また、ストックオプションを専門的な知識やノウハウで評価する評価機関が存在しています。参考とする数値が無かったり評価額の算定に不安があったりする場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
ストックオプションの税務上の考え方
ストックオプションによって付与対象者に発生する利益は、課税の対象です。しかし、一部の要件を満たしている場合は税制の優遇が適用されます。この税制適格要件によって、ストックオプションの税務における種類は以下の2つに分けられます。
- 税制適格ストックオプション
- 税制非適格ストックオプション
それぞれの税務処理を含めて詳しく確認していきましょう。
税制適格ストックオプションの場合
税制適格ストックオプションは、権利付与対象者が権利を行使した際の課税を無償とし、株式売却時まで課税を繰り延べる制度です。株式の売却時には、売却価格と権利行使価格の差額を譲渡所得として課税します。
上述の通り税制適格ストックオプションとして税制優遇を受けるには、要件を満たす必要があります。その要件は以下の通りです。
ストックオプションの主な要件
(引用元:経済産業省「ストックオプション税制」)
一般的に企業は、税制面での優遇があり付与される役員・社員にとって最善な、税制適格ストックオプションを導入します。そのためには上記の要件を考慮した設計が不可欠となります。
課税および企業の損金算入
権利を付与された役員・社員が課税されるのは株式を売却するときのみです。
そのため時系列で表すと以下のようになります。
ストックオプションが付与された
- 課税の有無:無
ストックオプションの権利を行使した
- 課税の有無:無
購入した株式を売却した
- 課税の有無:有(譲渡所得に対して)
企業側には税務処理が発生せず、損金算入はありません。
あくまで付与対象者が株式を売却した際に得た利益に対して課税されます。計算式は以下の通りです。
[売却価格] - [株式取得価格] = [利益]
※この[利益]が譲渡所得となり、課税対象になる
このため、企業側にとっても付与対象者となる役員・社員にとってもメリットがあるのが税制適格ストックオプションです。
<関連記事>税制適格ストックオプションとは?要件、確定申告に必要な情報をまとめて解説!
税制非適格ストックオプションの場合
税制非適格ストックオプションは、権利付与対象者が権利を行使した際と、株式売却時の双方で利益に対する課税が行われます。特に要件は無く、税制適格ストックオプションの要件を満たせない場合に非適格となります。
課税および企業の損金算入
権利を付与された役員・社員が課税されるのは権利行使時と株式売却時の2回です。
そのため時系列で表すと以下のようになります。
ストックオプションが付与された
- 課税の有無:無
ストックオプションの権利を行使した
- 課税の有無:有(給与所得に対して)
購入した株式を売却した
- 課税の有無:有(譲渡所得に対して)
ストックオプションの権利を行使したときに発生する課税は給与所得に対して行われます。
[権利行使時の株式時価] - [株式取得価格] = [利益]
※この[利益]が給与所得となり、課税対象になる
このとき付与対象者が注意しなくてはならないのが、権利行使の段階では売却による実際の金銭は未受け取りのため、納税額は自己負担となる点です。
また、購入した株式を売却したときに発生する課税は、適格ストックオプションと同様に譲渡所得に対して行われます。ただし、課税の繰り延べが行われていないため、計算式が異なります。
[売却価格] - [権利行使時の株式時価] = [利益]
※この[利益]が譲渡所得となり、課税対象になる
この場合は企業側でストックオプション付与時の公正価値を、権利行使時に損金算入することが可能です。
<関連記事>税制非適格ストックオプションとは?仕組み・税制適格との違い・活用ポイントを解説
ストックオプションの仕訳について解説しました
ストックオプションは、企業が役員や社員に「将来あらかじめ決められた金額で自社株式を購入できる権利」を報酬として与える制度です。仕訳においては複雑な部分があり、なおかつ税制適格となるような設計や公正な評価単価が必要になります。一方で企業にとっては長期的に見たメリットもあるため、導入が推奨されています。
この記事ではストックオプションの概要、仕訳の方法、評価単価の計算方法、税務上の考え方について解説してきました。
スタートアップ企業にとって、今後導入する報酬制度の有力な選択肢であると同時に、会計処理の確認が必要となる制度でもあります。ストックオプションを導入する上で、本記事で解説した内容を参考にしてみてください。