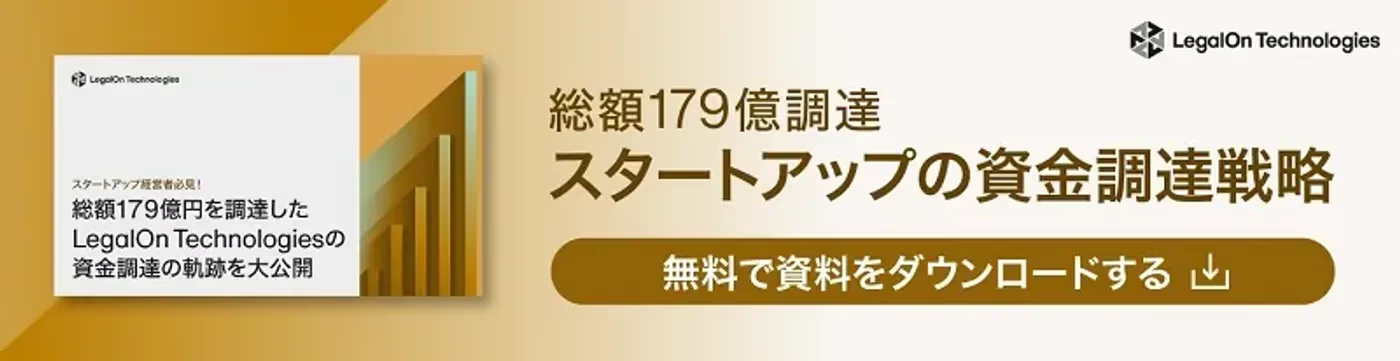ベンチャーキャピタルとは
ベンチャーキャピタルとは、成長段階にある新興企業やベンチャー企業に出資する組織のことです。ベンチャーキャピタルは未上場の企業に出資することで、上場時や他社に買収された際に株式を売却して利益の獲得を目指すことが目的です。
ベンチャーキャピタルは金融機関や事業会社、投資家から資金を調達しており、ファンド(組合)としてまとめて組成します。ファンドはベンチャー企業の資金提供として運用され、出資だけでなく経営コンサルティングとしての活動も行います。
ベンチャーキャピタルの仕組み
ベンチャーキャピタルは、ベンチャー企業専門の投資ファンドです。金融機関や事業会社、投資家などから出資を募集して、ファンドマネージャーとしてベンチャー企業に投資します。
大手ベンチャーキャピタルの場合、自己資金から企業に投資することもあります。集めた資金は将来有望な新興企業やベンチャー企業を見つけ、出資から株式を取得して企業が上場もしくは売買されたタイミングで保有する株を売却します。株式の売却益を出資者に株式譲渡益として配分し、一部を成功報酬としてベンチャーキャピタルが受け取る仕組みです。投資先の企業が成長しなければ収益は見込めないため、ベンチャーキャピタルは出資だけでなく経営コンサルティングとして成長をサポートします。
ベンチャーキャピタルとほかの資金調達との違い
ベンチャー企業はベンチャーキャピタル以外にも、以下のような資金調達が存在します。
- 銀行融資
- クラウドファンディング
- 投資銀行
それぞれの違いを理解するためにも、ぜひ参考にご覧ください。
銀行融資
銀行融資は、企業や個人が金融機関からお金を借りる方法です。ベンチャーキャピタルとの主な違いは、返済義務の有無にあります。ベンチャーキャピタルの出資は資本に該当するため、返済義務はありません。一方銀行融資は負債に該当するので、利息を含めた返済が必要です。
また、銀行融資には審査があり、実績の少ない新興企業やベンチャー企業は融資を受けることが難しいです。ベンチャーキャピタルは将来的な成長性をもとに判断されることから、銀行融資に比べて出資されやすい資金調達方法といえるでしょう。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人々から資金を調達する方法です。自社が展開する商品・サービスの情報を公開し、出資者に対して何らかの見返りを提供します。これからはじめたい事業に共感してくれる支援者を見つけることができ、情報が拡散されることで多くの人から資金を調達可能です。
クラウドファンディングで獲得できる資金調達額はベンチャーキャピタルに比べて低いですが、魅力的な事業を紹介することで多くの人から資金を集められます。インターネットを通じて資金を調達する点は、ベンチャーキャピタルとの大きな違いといえます。
投資銀行
投資銀行は、大口の個人や法人顧客の代わりに金融取引を行う金融機関です。投資銀行は株や債券などの有価証券を取り扱っており、合併や仲介などを行っています。ベンチャーキャピタルは将来的な成長が見込まれるベンチャー企業を投資対象としていますが、投資銀行は成熟した企業が投資対象です。そのためベンチャーキャピタルは、投資銀行と比べて出資が難しい企業も対象としている点に違いがあります。
ベンチャーキャピタルから出資を受ける5つのメリット
ベンチャーキャピタルから出資を受けることで、以下のような5つのメリットがあります。
- 返済義務がない
- 経営知識・ノウハウを活用できる
- 大規模な資金調達ができる
- 信頼性が向上する
- ネットワークを広げられる
それでは順番に説明します。
1.返済義務がない
ベンチャーキャピタルはほかの銀行からの融資とは異なり、原則として返済義務はありません。理由として、出資者には自社の株式を発行するため、譲渡する代わりに出資金を返済する必要がなくなるからです。利息を支払う必要もないので、会社の資金繰りに悩まされずに済みます。そのため返済不要の資金を確保できる点は、ベンチャーキャピタルから出資を受ける大きなメリットといえるでしょう。
2.経営知識・ノウハウを活用できる
ベンチャーキャピタルはベンチャー企業の出資だけでなく、経営コンサルタントとして企業に関わるので経営知識やノウハウを提供してもらえます。企業成長につながるノウハウや知識、経験を提供してもらえるため、正しい経営戦略を身につけられるようになります。また、課題解決の方法もアドバイスを得られるので、起業や経営の経験が少ない経営者も安心です。そのためベンチャーキャピタルを通じて経営知識やノウハウを活用できる点は、メリットの1つといえます。
3.大規模な資金調達ができる
ベンチャーキャピタルから出資を受けることで、一度に大規模な資金調達ができます。クラウドファンディングのように手軽な出資を受ける方法もありますが、紹介する事業内容によっては資金調達が難しくなります。ベンチャーキャピタルであれば1案件あたり1億円〜2億円の投資を受けられるので、事業や設備投資に活用することが可能です。そのため大規模な資金調達ができる点は、ベンチャーキャピタルならではのメリットといえるでしょう。
4.信頼性が向上する
ベンチャーキャピタルからの出資をもとに自社の実績を増やせば、外部からの信頼性が向上します。とくの大手ベンチャーキャピタルから出資を受けられた場合、業会内の評価が上がり新たな顧客や取引先を獲得できるきっかけになります。そのため外部からの信頼性が向上する点は、ベンチャーキャピタルからの出資を受けるメリットの1つです。
5.ネットワークを広げられる
ベンチャーキャピタルは多くの金融機関や事業会社、投資家と契約しているため、事業提携や人材紹介のサポートを受けられることがあります。独自のネットワークを通じてこれまで関わりのなかった企業とつながれるので、新たな事業戦略や業界知識などの情報を得ることが可能です。今後の事業拡大につながるネットワークを広げられる点は、ベンチャーキャピタルから出資を受けるメリットといえます。
ベンチャーキャピタルから出資を受ける4つのデメリット
ベンチャーキャピタルから出資を受けることで、以下のような4つのデメリットも存在します。
- 経営の意思決定に関与される
- 持株比率が低下する
- 将来性のプレッシャーがある
- 早急な成果を求められる
良い点だけでなく悪い点も理解しながら、出資を受けるべきか検討しましょう。
1.経営の意思決定に関与される
ベンチャーキャピタルは出資だけでなく企業の経営にも関わるため、方向性の意思決定に関与される恐れがあります。ベンチャーキャピタルは投資先企業からのリターンを求めているので、自社の経営陣とは異なる経営を強いられるケースも存在します。そのため自社が求める経営ができなくなりやすい点は、ベンチャーキャピタルから出資を受けるデメリットといえるでしょう。
2.持株比率が低下する
ベンチャーキャピタルからの出資を受ける場合、自社株式を譲渡するので持株比率が低下します。多くの出資額を得るほど経営に関する発言権や議決権に影響が出る恐れがあることから、自由に事業を進められなくなる可能性が高いです。そのためベンチャーキャピタルからの出資を受けるときは、持株比率の変動に注意しなければいけません。
3.将来性のプレッシャーがある
ベンチャーキャピタルはファンド契約によって期限が設定されており、期限までにイグジット(投資した資金を回収すること)の達成が求められます。ベンチャーキャピタルに定期的な報告や要求があるので、将来性のプレッシャーがかかりやすい点はデメリットといえるでしょう。
4.早急な成果を求められる
ベンチャーキャピタルは早期のリターンを求めていることから、出資先の企業に投資額に見合った成果を期待しています。もし成果を出せなければ、ベンチャーキャピタルが撤退するケースも少なくはありません。将来的な成果に不安を抱かれないようにするためにも、長期的な事業計画や成果を提示するようにしましょう。
ベンチャーキャピタルの種類
ベンチャーキャピタルはさまざまな種類があります。ここからは、代表的な6種類を紹介していきます。
金融機関系ベンチャーキャピタル
金融機関系ベンチャーキャピタルは、銀行や証券会社などの金融機関が設立したベンチャーキャピタルです。豊富な資金力を持つため、大規模な投資案件にも対応しやすいのが特徴です。
具体例としては、メガバンク系列のベンチャーキャピタルである三菱UFJキャピタル(三菱UFJ銀行系)、SMBCベンチャーキャピタル(三井住友銀行系)、みずほキャピタル(みずほ銀行系)があります。
事業会社系ベンチャーキャピタル(CVC)
事業会社系ベンチャーキャピタル(Corporate Venture Capital)は、事業会社が運営するベンチャーキャピタルです。略してCVCとも言われます。
事業会社系ベンチャーキャピタルの例としては、ゲーム事業で知られるGREEが運営するSTRIVEや、大手通信企業のNTTドコモが運営するNTTドコモベンチャーズなどがあります。
大学系ベンチャーキャピタル
大学系ベンチャーキャピタルとは大学が直接出資するベンチャーキャピタルです。大学系ベンチャーキャピタルの例としては、東京大学エッジキャピタル(UTEC)や大阪大学ベンチャーキャピタル(OUVC)が挙げられます。
政府系ベンチャーキャピタル
政府系VCとは国や地方自治体などの公的資金をもとに投資しているベンチャーキャピタルです。国内産業の育成や、技術の革新に関する投資が多いという特徴があります。政府系ベンチャーキャピタルの例としては、東京中小企業投資育成や、日本政策投資銀行系のDBJキャピタルなどがあります。
独立系ベンチャーキャピタル
独立系ベンチャーキャピタルとは特定の親会社を持たずに、独自の資本で運営されているベンチャーキャピタルです。独立系ベンチャーキャピタルの例として、株式会社SmartHRや株式会社メルカリを投資した株式会社WiLや、株式会社kubell(旧Chatwork株式会社)への投資実績を持つ株式会社ジャフコが挙げられます。
地域特化型ベンチャーキャピタル
地域特化型ベンチャーキャピタルは、特定の都道府県や市町村にある企業を対象に出資するベンチャーキャピタルです。地域特化型ベンチャーキャピタルの例として、北海道ベンチャーキャピタル(HVC)、新潟ベンチャーキャピタルはなどがあります。
海外系ベンチャーキャピタル
海外系ベンチャーキャピタルとは、外資系企業が運営するベンチャーキャピタルです。日本国内のベンチャーキャピタルと比べて投資額が大きい特徴があります。また出資先を検討する際は、経営の合理性を優先する傾向があります。海外系ベンチャーキャピタルの例として、Google・Appleへの投資実績を持つSequoia Capitalや、シリコンバレーを拠点としたAndreessen Horowitz(2024年、日本拠点の設置を発表)が挙げられます。
スタートアップの資金調達についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下お役立ち資料も併せて確認してみてください。
ベンチャーキャピタルが出資企業を選ぶポイント
ベンチャーキャピタルが出資企業を選ぶときは、以下のようなポイントをチェックしてください。
- 高いリターン率を期待できるかどうか
- 市場の成長性・ニーズ
- 明確な事業戦略
- 経営陣・従業員の魅力
- 独自技術の展開
それでは詳しく解説します。
高いリターン率を期待できるかどうか
ベンチャーキャピタルは株式の売却を最終的な目的としているため、新規公開株式(IPO)で高いリターン率を期待できるベンチャー企業に投資します。もちろん投資した企業を成長させるには経営をサポートする必要はありますが、企業の株価は新規公開株式によって数千倍まで上昇することもあります。そのため高いリターン率を期待できるかどうかは、ベンチャーキャピタルが出資企業を選ぶ重要なポイントといえるでしょう。
市場の成長性・ニーズ
市場が成長しており、ニーズがある企業は投資を検討される判断材料となります。例えばIT業界はAIテクノロジーの進化によって市場が急激に成長しているため、AI事業を展開する企業はベンチャーキャピタルにとって魅力的です。また、成長の早さだけでなく、ベンチャーやスタートアップが参入する市場の将来性も投資を判断されるポイントとなっています。
明確な事業戦略
明確な事業戦略が公開されている企業は、ベンチャーキャピタルが投資すべきか判断できるポイントになります。ベンチャーキャピタルは投資する資金がどのように使われるのかを知りたいので、財務戦略が具体的かつ明確に公開されていることを重要視しています。
経営陣・従業員の魅力
成長段階にあるベンチャー企業には経営メンバーが揃っている必要はありませんが、将来性のある人材がいる企業はベンチャーキャピタルが魅力を感じます。ベンチャーキャピタルは投資先の企業に経営コンサルティングを行うため、経営陣や従業員の人間性や特性がチェックされます。
独自技術の展開
他社にはない独自技術を展開しているベンチャー企業は、ベンチャーキャピタルから注目されやすいです。独自技術は将来的に大きな成長を見込めるため、早い段階で投資を検討している投資家も少なくはありません。また、他社が参入しづらい事業を展開しているかどうかは、差別化を図る要素となっています。
ベンチャーキャピタルとのコンタクトの取り方
ベンチャーキャピタルとのコンタクトを取るには、以下のような方法があります。
- 知人からの紹介
- イベントの参加
- 直接連絡を取る
- 金融機関からの紹介
それでは詳しく説明します。
知人からの紹介
知人にベンチャーキャピタルを紹介してもらうことで、コンタクトが取れることもあります。著名なベンチャーキャピタルに直接連絡したとしても、コンタクトを取ることは難しいです。もちろん知人からベンチャーキャピタルを紹介してもらったとしても必ず投資につながるわけではないため、事業の成長性についてプレゼンや交渉力が求められるでしょう。
イベントの参加
ベンチャーキャピタルが開催するイベントに参加することで、主催者とコンタクトを取れることがあります。ベンチャー・スタートアップ企業の展示会にベンチャーキャピタルが参加していることも多く、名刺交換や連絡先交換をすればコンタクトが取れます。ベンチャーキャピタルも新たな投資先を探すためにイベントの開催や参加をしているので、お互いのニーズがマッチしていれば交渉を進められるようになるでしょう。
直接連絡を取る
ベンチャーキャピタルの公式サイトやSNSから直接連絡を取る方法もあります。ほかの方法に比べてコンタクトを取れるケースは少ないですが、自社のビジネスプランが相手とマッチしていれば交渉につなげられます。
金融機関からの紹介
銀行や信用金庫などの金融機関からベンチャーキャピタルを紹介してもらう方法もあります。金融機関はベンチャーキャピタルと連携していることが多いため、担当者を通じて紹介してもらえる可能性が高いです。ほかのコンタクトの取り方と合わせて、金融機関からの紹介も検討しましょう。
ベンチャーキャピタルから出資を受ける流れ
ベンチャーキャピタルから出資を受ける流れは、以下の通りです。
- 審査に必要な書類を提出
- ベンチャーキャピタルが投資先を選定
- 投資審査会の開催・合意を得る
- 契約の締結
はじめに事業計画書や決算書、株主名簿などの書類を投資してもらうベンチャーキャピタルに提出します。とくに事業計画書はベンチャーキャピタルが企業を選定する重要な要素となるため、具体的な記載が必要です。
そしてベンチャーキャピタルからの選定に通過後、投資家による投資審査会が開催されます。審査期間は1ヶ月〜2ヶ月程度となっており、通過すればベンチャーキャピタルとの契約締結へと進み、出資を受ける流れです。
契約書に締結するときはベンチャーキャピタルの要望ばかりを受けるのではなく外部の税理士や弁護士と相談して進めるようにしましょう。
ベンチャーキャピタルについて解説しました
今回は、ベンチャーキャピタルの詳細やメリット・デメリット、出資を受ける流れについてわかりやすく解説しました。ベンチャーキャピタルは成長段階の新興企業やベンチャー企業に出資しているため、資金調達方法の1つとして利用されています。銀行融資と比べて返済義務がなく、経営知識やノウハウを活用できる点も魅力です。ただし早急な成長を求められるので、成果を出すための戦略を考えなければいけません。
当記事で紹介したメリットやデメリットを理解しながら、ベンチャーキャピタルから出資を受けるべきか判断するようにしましょう。