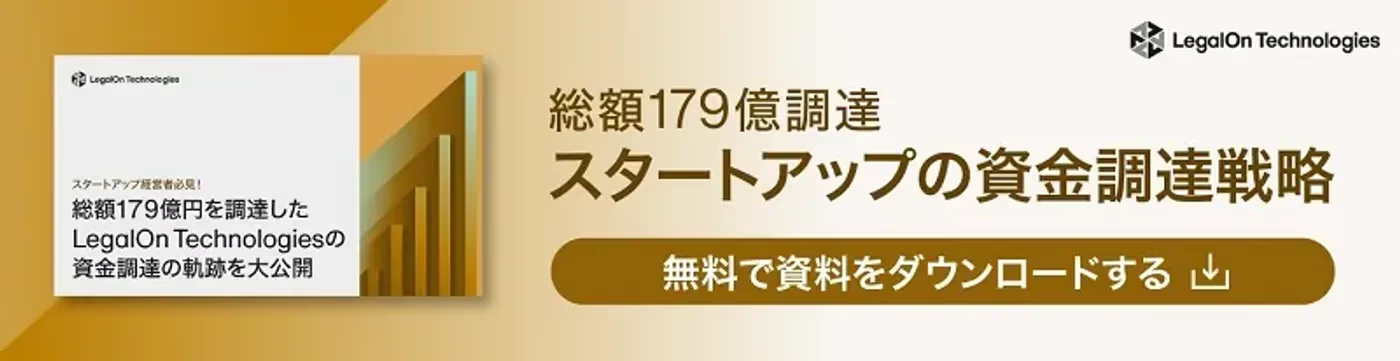ベンチャー企業における資金調達の重要性
ベンチャー企業とは、革新的な技術・アイデアなどを活用し、新事業に挑戦する企業の総称です。一般では「ベンチャー」や「スタートアップ企業」などと呼ばれることもあります。
創業から間もない時期のベンチャー企業は、「自己資本による運営である」や「経営基盤が未確立である」などの背景から、資金面の問題を抱えやすいです。
こうしたなかで、事業拡大に向けて優秀な人材の獲得や設備投資などを行っていくためには、外部からの資金調達をする必要があります。
また、会社や事業を始めたばかりの時期は、外的環境の影響も受けやすいでしょう。
特に近年はVUCA時代といい、コロナショックのような予測不能な出来事が起こりやすくなっています。こうしたなかでベンチャー企業が新事業を軌道に乗せ、安定性の高い経営を実現するうえでは、自社の現状に合う方法での資金調達が必要となるでしょう。
<関連記事>ベンチャー企業とは? スタートアップやユニコーンとの違いも解説
ベンチャー企業の資金調達における4つの大分類
ベンチャー企業における資金調達の方法には、以下4つの大分類があります。各概要を紹介しましょう。
- エクイティファイナンス
- デットファイナンス
- アセットファイナンス
- その他
エクイティファイナンスによる資金調達
エクイティファイナンスとは、「出資」による資金調達のことです。会社の事業・取り組み・将来性などへの評価のもとで、株式発行等の対価として企業や個人から「出資」による資金提供を受けるものになります。
出資はいわゆる借金ではないため、返済義務がありません。ただし、出資で資金調達をした場合、株式の発行を通じて一部の経営権を投資家に譲渡することになります。
参考:エクイティ・ファイナンスに関する基礎知識(経済産業省)
出資の種類には、主に以下のものがあるでしょう。
- VC(ベンチャーキャピタル)
- CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)
- エンジェル投資家
- プライベートエクイティ
- クラウドファンディング
デットファイナンスによる資金調達
デットファイナンスとは、融資による資産調達の総称です。融資とは、金融機関からの借入や債券発行などの負債を通して資金調達する方法になります。
融資はいわゆる借金です。この方法で資金調達をした場合、当然のことながら定期的な返済が求められます。銀行などから融資をしてもらううえでは、審査に通ることも必要です。
融資による資金調達には、以下の種類があります。
- 日本政策金融公庫
- 信用保証協会
- 民間金融機関
- 社債
- ノンバンクのビジネスローン
アセットファイナンスによる資金調達
アセットファイナンスとは、企業もしくは経営者の「資産の信用力」で資金調達する方法の総称です。一方で、先述の融資や出資などの資金調達方法は、「会社の信用力」や将来性などに着目する方法になります。
一般では、会社の価値・信用力に着目するものが「コーポレートファイナンス」であるのに対して、資産による資産調達は「アセットファイナンス」と呼ばれることが多いです。
アセットファイナンスの場合、その方法は多岐にわたります。なかでもベンチャーの資金調達に使いやすいものには、以下の種類が考えられるでしょう。
- 売掛債権の活用(ファクタリング)
- 固定資産の売却
- リースバック
「その他」の資金調達
この記事では、出資と融資以外の資金調達方法を「その他」としてまとめています。ベンチャー企業でも利用しやすい種類としては、以下のものが挙げられるでしょう。
- 補助金・助成金
- ベンチャーデット
スタートアップの資金調達についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ以下のお役立ち資料も併せて確認してみてください。
ベンチャー企業の「出資」による資金調達の方法5選
ベンチャー企業でも利用できる「出資」の資金調達方法には、以下の5つがあります。各概要・メリット・デメリットを紹介しましょう・
- VC(ベンチャーキャピタル)
- CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)
- エンジェル投資家
- プライベート・エクイティ
- クラウドファンディング
VC(ベンチャーキャピタル)の概要とメリット・デメリット
VC(ベンチャーキャピタル)は、ベンチャーのような未上場の新興企業への出資(株式取得)を行い、その会社が将来的に上場したタイミングでの株式売却を目指す投資ファンドや投資会社の総称です。
■ VC(ベンチャーキャピタル)のメリット
VCの魅力は、その名のとおりベンチャーやスタートアップのような未上場企業でも利用できるうえに、返済義務がない点です。VCのネットワークに入ることで、ビジネスノウハウや知識などの習得や各種支援を受けられたりするメリットも期待できます。
■ VC(ベンチャーキャピタル)のデメリットと注意点
VCは、投資先企業の上場による株式売却を目指していることから、VCとの継続的なコミュニケーションを求められるのが一般的です。また、株式買取請求を迫られたり、出資比率によっては経営権を握られたりすることもあります。
<関連記事>ベンチャーキャピタルとは?メリット・デメリット・出資を受ける流れをわかりやすく解説
CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)の概要とメリット・デメリット
CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)の多くは、大企業の事業会社が、事業シナジーが期待できそうなベンチャー企業やスタートアップ企業に投資をするために設立されています。
先述のVCとCVCの大きな違いは、投資目的です。
VCの場合、多くの目的は「財務的なリターン」になります。一方でCVCは、新規市場の開拓・最新ノウハウ・最新技術・アイデアなどの獲得に重きを置くことが多いです。その背景には、近年のようにニーズが多様化するなかで、大企業でも自社のリソースだけでは対応しきれなくなっている実情などが関係しています。
■ CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)のメリット
CVCの場合、規模が大きく信用力が高い事業会社と連携することで、資金に加えてさまざまな経営資源の提供を受けられる可能性が高まります。また、大企業との資本提携などのプレスリリースを出すことで、自社の信用力や認知度向上なども期待できるでしょう。
■ CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)のデメリット
CVCの注意点は、経営の自由度が下がる可能性がある点です。たとえば、CVCの設立母体との連携・提携をすれば、母体の競合他社との取引は難しくなるでしょう。
場合によっては、ベンチャー企業の経営にCVCが介入する可能性もあります。注意が必要です。
エンジェル投資家の概要とメリット・デメリット
エンジェル投資家とは、起業して間もないベンチャーなどに資金を出資する個人投資家の総称です。エンジェル投資家の多くは、これまでの実績よりも新規性・将来性・ビジネスモデルなどから出資の判断をする傾向があります。
■ エンジェル投資家のメリット
エンジェル投資家は、自分自身も起業や事業の経験を持つことが多いです。
ビジネス経験豊富なエンジェル投資家から出資を受けると、自らの経営経験を活かした助言や人脈を活かした支援を受けられるかもしれません。
また、エンジェル投資家も出資ですから、VC同様に返済義務は不要です。
■ エンジェル投資家のデメリットと注意点
エンジェル投資家もVCと同様に、出資先企業の上場や事業の成功などを期待することが多いです。
事業計画などを総合的に見た段階で「成長が見込めない」などの判断になれば、出資は難しいでしょう。また、出資を受けるからには、期待通りの頑張りが求められるかもしれません。
なお、エンジェル投資家は個人であることから、企業のVCと比べると出資額が少ない可能性も考えられます。
<関連記事>エンジェル投資家とは?目的やメリット、探し方や出資してもらう際の注意点を解説
プライベート・エクイティの概要とメリット・デメリット
プライベート・エクイティとは、未公開企業や不動産に投資を行うファンドの総称です。プライベート・エクイティの投資形態には、以下のようにさまざまな種類があります。
- 成長見込みのあるベンチャー企業への投資
- 割安な上場株式を一部保有
- 経営陣による自社の買収サポート など
■ プライベート・エクイティのメリット
プライベート・エクイティの場合も、VCなどと同様に経営ノウハウ面での支援を受けられることが多いです。
また、ファンドではさまざまな投資などを通じて多くの企業や経営者との関係を構築していることから、場合によっては、自社に合う優秀な人材を紹介してもらえるケースもあります。
■ プライベート・エクイティのデメリット
プライベート・エクイティのファンドも、資金の回収を目的に投資を行います。したがって、ファンドから出資を受けた分の返済は原則不要となりますが、利益獲得によるイグジットを目指す必要はあるでしょう。
また、ファンドでは、利益に直結する選択を重視・優先します。プライベート・エクイティによる資金調達をした場合、株主であるファンドの意思決定に従わざるを得ないケースが出てくるかもしれません。
クラウドファンディングの概要とメリット・デメリット
クラウドファンディングは、インターネット上で不特定多数の人たちが他の人・団体・企業に対する資金提供を行う仕組みやサービスの総称です。購入型・融資型・ファンド型・寄付型・株式型とさまざまな方式があります。
■ クラウドファンディングのメリット
具体的なメリットは活用する方式やプロジェクトによって異なりますが、従来の融資方法などと比べて迅速な資金調達が容易にできるサービスとして紹介されることが多いです。
また、たとえば新製品の開発・宣伝費用などへの出資を募ると、マーケティングやリアルなフィードバックなどの副次的な効果が得られたりもします。
■ クラウドファンディングの注意点とデメリット
クラウドファンディングの注意点は、利用目的・実施方式・注目度などの影響を受けやすいことです。目標額に達成しないまま終了するケースも多くあります。クラウドファンディングで資金調達を目指す場合、各方式やサービスの成功確率などを分析し、適切なやり方を実践することが大切です。
ベンチャー企業の「融資」による資金調達の方法5選
次に、「融資」で資金調達を行う以下6つの方法について、各概要・メリット・デメリットなどを紹介しましょう。
- 日本政策金融公庫
- 信用保証協会
- 民間金融機関
- 社債
- マル経融資
日本政策金融公庫の概要とメリット・デメリット
日本政策金融公庫は公的機関です。幅広い事業者が利用できる多彩な制度を取り扱っています。
たとえば、ベンチャーなども利用しやすい「新創業融資制度」は2024年3月で廃止となり、その代わりに「新規開業資金」という制度が拡充されることになりました。新規開業資金とは、新たに事業を始める人もしくは事業開始後おおむね7年いないであれば利用できる制度になります。
また、日本政策金融公庫のホームページで「ベンチャー」などと入力し、融資制度を検索すると、以下の制度も表示されます。(2024年12月時点)
挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)(日本政策金融公庫)
スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
■ 日本政策金融公庫のメリット
ベンチャー企業が日本政策金融公庫を利用するメリットは、創業初期でも申し込みやすい点です。
たとえば、先述の「新規開業資金」の場合、無担保・無保証人で融資が受けられる制度になっています。また、今回の拡充で自己資金要件が撤廃され、金利や返済期間の面でも利用しやすいものになりました。
日本政策金融公庫には、「新事業・多角化」「ソーシャルビジネス」「海外展開・事業再編」といった多彩な利用目的・テーマに合う制度が用意されています。自社に合うものを選択することで、効果的な資金調達を行えるでしょう。
参考:
■ 日本政策金融公庫のデメリットと注意点
日本政策金融公庫で中小企業事業の融資制度を利用した場合、繰り上げ返済ができません。
また、日本政策金融公庫の審査期間は、1ヵ月半程度と長めです。急な入り用などでスピーディーな審査や融資を求める場合、後述するほかの方法を選んだほうが良いケースもあるでしょう。
なお、具体的な注意点は制度ごとに異なります。詳細は、日本政策金融公庫の最新情報を確認してください。
信用保証協会の概要とメリット・デメリット
信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、ベンチャーなどの小規模事業者や中小企業に対する円滑な資金調達を支援する目的で設立された公的機関です。
■ 信用保証協会のメリット
信用保証協会を利用するメリットは、大企業と比べて経営リスクが大きいベンチャーやスタートアップ企業などでも、公的機関の信用保証協会が事業者と金融機関の間で債務保証をすることで、いわゆる市中の金融機関からの融資が受けやすくなる点です。
■ 信用保証協会のデメリットと注意点
信用保証協会の利用が必要だということは、そのベンチャー企業の信用力が比較的低いこともを意味します。
そのため、信用保証協会付きの融資を受ける場合、金融機関からのプロパー融資は難しくなるでしょう。また、銀行などに支払う利息に加えて、協会に対する信用保証料が課せられます。
民間金融機関の概要とメリット・デメリット
メガバンク・地方銀行・信用金庫などから受ける融資の総称です。プロパー融資と呼ばれたりもします。
■ 民間金融機関のメリット
民間金融機関は、審査日数が短く限度額に上限がないことが多いです。また、民間金融機関からプロパー融資を受けられることには、自社の信用力を高められる効果もあります。
信用力を高めながら、さらなる事業拡大に向けた次の融資を検討する場合、民間金融機関を利用するメリットは大きいかも知れません。
■ 民間金融機関のデメリットと注意点
民間金融機関のデメリットは、銀行などが貸し倒れリスクを恐れることから、審査が厳しい点です。ベンチャー企業の経営状況が悪ければ審査に通過しませんし、限度額に上限がないといっても、申請した金額すべての融資が実現するとは限らないでしょう。
社債の概要とメリット・デメリット
社債とは、投資家から借入れをする方法です。基本的な仕組みは、投資家などに社債を購入してもらったあと、期日が来たタイミングで社債券などに書かれた金額を一括償還するというものになります。
社債には、大きく分けて以下の2種類があります。各概要は以下のとおりです。
- 【公募債】幅広い募集をかけて、一般の投資家から多くの借入れを行うもの
- 【私募債】市場では募集を出さず、企業が個別の対象者に社債購入をお願いするもの
■ 社債のメリット
社債は株式ではないことから、購入した投資家に経営権が渡ることはありません。調達資金の使途も基本的に自由です。このほかに、募集事項に従った償還・支払いの発生となるため、資金計画を立てやすい利点があります。
■ 社債のデメリットと注意点
社債を発行すると、事務手続きの手間やコストがかかります。また、法律に則った手続きが求められることから、発行までに時間がかかるケースも多いです。株式とは異なり、債権者への弁済・償還に向けた積立も必要となります。
ノンバンクのビジネスローンの概要とメリット・デメリット
いわゆる信販会社や消費者金融のなかには、事業用資金の専用融資であるビジネスローンを取り扱っているところもあります。
■ ノンバンクのビジネスローンのメリット
ノンバンクのビジネスローンの場合、民間金融機関と比べて審査のハードルが比較的低く、申し込みから融資までのスピードも速いことが多いです。無担保・無保証で利用できることが多い点も魅力でしょう。
■ ノンバンクのビジネスローンのデメリットと注意点
ノンバンクのビジネスローンは、民間金融機関と比べて金利が高めです。また、返済期間が短い傾向もあります。スタートアップの事業が軌道に乗るまでに少し時間を要するときなどは、注意が必要です。
ベンチャー企業の「資産活用」による資金調達の方法3選
会社もしくは経営層の資産を活用した資金調達の方法(アセットファイナンス)のなかで、ベンチャー企業が活用しやすいものには、以下の3種類があります。
- 売掛債権の活用(ファクタリング)
- 固定資産の売却
- リースバック
ファクタリングの概要とメリット・デメリット
ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却することで現金を得る仕組み・サービスの総称です。2社間と3社間の2種類があります。両者の大きな違いは、以下のとおりです。
- 【2社間ファクタリング】利用企業とファクタリング会社の「2社」で契約完了するもの。売掛先企業に売掛債権譲渡の承諾を得る必要はない。
- 【3社間ファクタリング】利用企業・ファクタリング会社・売掛先の「3社」で契約するもの。売掛債権を譲渡する旨を、売掛先企業に通知することになる。
■ ファクタリングのメリット
ファクタリングの利点は、売掛金の回収期日よりも早く現金を受け取れる点です。たとえば、いま請求書を発行したデザイン料の支払いが2ヵ月後の末日の場合、それまでの期間は売掛金の回収ができない状況になってしまいます。
そこでファクタリングを利用した場合、即日や翌日などの早いタイミングでお金を受け取れることになるでしょう。
■ ファクタリングのデメリットと注意点
ファクタリングを利用すると、一定の手数料がかかります。先述のデザイン料が仮に10万円であれば、手数料を差し引かれた金額が振り込まれるイメージです。手数料の相場は、以下のとおりになります。
- 【2社間ファクタリング】10~30%程度
- 【3社間ファクタリング】1~9%程度
3社間を利用した場合、売掛先企業に売掛債権を譲渡する旨の通知が行われます。場合によっては、その通知から「財務状況があまりよくない」などの悪印象を与えることにもなるかもしれません。
固定資産売却の概要とメリット・デメリット
以下のような有形・無形の固定資産を売りに出すことで、資金を調達する方法です。
- 不動産
- 機械設備
- 車両
- 借地権
- 特許権 など
■ 固定資産を売却するメリット
仮に、有効活用されていないにも関わらず、定期メンテナンスが必要な車両や設備等がある場合、それらの売却による資金調達を選択することで、維持管理費の節約につながることもあるかもしれません。
また、企業としての信用・価値が低い創業間もない時期でも、固定資産の売却であればその資産に高い価値がありさえすれば、容易に資金調達も行えるでしょう。
なお、資産売却を行うと、貸借対照表から「資産」の項目が減る一方で、「現預金」が増えることになります。これは総資本利益率の向上を意味するものです。自社の信用力を高めるうえでも、固定資産の売却には高い効果が期待できます。売却で得た現金は、誰かに返済する必要もありません。
■ 固定資産を売却するデメリット
固定資産の売却による資金調達は、保有資産に高い価値がある場合に限り有効です。仮に機械設備や車両が古すぎたり、需要が低すぎる場合は、売却しても二束三文になる可能性もあるでしょう。
また、たとえば「社長個人のマンションを知人に売る」などの個人間取引では、トラブルが起こりやすい傾向があります。高い価値のある固定資産を売る場合、専門家のサポートを受けることが大切です。
リースバックの概要とメリット・デメリット
リースバックとは、保有不動産を売却したあとに、その物件の賃貸契約を締結しそのまま利用し続けることです。
■ リースバックのメリット
リースバックの利点は、不動産の売却で自分(自社)が所有者ではなくなっても、その物件をそのまま利用できる点です。たとえば、「どうしても資金調達をしなければならないが、マンションを手放したら社長の家がなくなってしまう」などの場合、売却後の利用も可能なリースバックが選択肢の一つになるでしょう。
■ リースバックのデメリット
たとえば、不動産のローンを支払い続けている最中の場合、それを超える売却益でなければ、資金調達はできません。
また、売却後した物件の取り扱いは、新オーナーの自由です。たとえば、新オーナーがその物件を売却すれば、旧オーナーが取り戻すことは不可能になります。近年では、「買い戻しに応じてもらえない」や「不動産会社が倒産してしまった」などのトラブルも増加するようになりました。
【その他】ベンチャー企業における資金調達の方法2選
出資と融資以外でベンチャー企業でも利用できる「その他」の資金調達方法には、以下のものがあります。各概要とメリット・デメリットを確認しましょう。
- 補助金・助成金
- ベンチャーデット
補助金・助成金の概要とメリット・デメリット
補助金・助成金は、各省庁や各自治体などが管轄する支援金の総称です。
■ 補助金・助成金のメリット
補助金・助成金は返済不要です。
年間で数千以上もの種類が募集されていることから、複数への応募で審査通過すれば、それだけ多くの資金調達をすることも可能となります。
また、民間金融機関や信販会社のように万が一審査落ちしても、その内容が信用情報に記録されることもありません。準備を行う余裕がある場合は、さまざまな補助金・助成金の申請に挑戦してみてもよいでしょう。
■ 補助金・助成金のデメリットと注意点
補助金・助成金は、すべてが必ず採択されるわけではありません。たとえば、ものづくり補助金の場合、採択率は50%前後です。また、補助金・助成金の申請では、書類の準備などで多くのコストがかかることが多い傾向があります。
ベンチャーデットの概要とメリット・デメリット
ベンチャーデットとは本来、先述のエクイティファイナンス(出資)とデットファイナンス(融資)の両方の性格を持つものです。ベンチャーなどのスタートアップ企業は、融資を受けたタイミングで自社株式をあらかじめ設定された価格で購入できるストックオプション(新株予約権・ワラント)を付与します。
なお、日本国内では、ベンチャーデットのニーズの高まりを受けて、ストックオプションの有無を問うことなく、スタートアップ向けのデットをすべて「ベンチャーデット」と位置づける傾向があるようです。
■ ベンチャーデットのメリット
ベンチャーデットの利点は、返済優先度の高さや融資の側面を持つ性質から、エクイティファイナンス(出資)と比べて審査期間が短期間になりやすい点です。また、日本国内に多いストックオプションがない融資の場合、株式の希薄化をおさえた資金調達が可能となります。
■ ベンチャーデットのデメリットと注意点
ベンチャーデットで資金調達すると、返済義務が発生します。
また、ベンチャーデットで資金調達した企業が次に出資を受ける投資家からすると、自分の出資金がベンチャーデットの借金返済に使われることに抵抗を覚えることがあるかもしれません。
ベンチャー企業のラウンドとおすすめ資金調達の方法
ベンチャー企業やスタートアップ企業が資金調達を行う場合、自社の成長段階に応じた調達先を選ぶことが大切です。
この成長段階は、以下の「資金調達ラウンド(投資ラウンド)」というステージで分けられます。ここでは、各資金調達ラウンドの特徴と、それぞれのおすすめ調達先を紹介しましょう。
- シード期
- アーリー期
- シリーズA
- シリーズB
- シリーズC
- シリーズD
シード期の概要とおすすめの調達先
シード期は、創業前後でプロダクト・サービスがまだ形になっていないアイデアの段階です。この時期のベンチャーは、まだすぐに大きな売上を見込める状態ではないことが多いでしょう。資金調達のポイントは、以下のような調達先から「少額を広く集めること」です。
- エンジェル投資家
- ベンチャーキャピタル
- クラウドファンディング
- 日本政策金融公庫
- 補助金・助成金
シード期における調達額の相場は、数百万〜数千万円程度になります。
<関連記事>シード期を成功させるには?資金調達方法も合わせて解説します!
アーリー期とおすすめの調達先
アーリー期は、製品・サービスを市場に投入していく段階です。自社に合う市場に受け入れてもらい、収益を得るための多くのお金を使って施策を講じるステップになります。
この時期にたくさんのお金を集めるうえでは、株式をうまく使うことが大切です。残余財産や配当の分配で優先権のある優先株式などを発行し、有利な条件で投資家に投資を促すことも一つになります。
また、シード期と同様に、以下の調達先の活用もおすすめです。
- エンジェル投資家
- ベンチャーキャピタル
- クラウドファンディング
- 日本政策金融公庫
アーリー期における調達額の相場は、数千万円程度です。
シリーズAとおすすめの調達先
シリーズAは、事業拡大に向けて資金調達をしていく段階です。シリーズAの段階では、手元の資金や売上がまだ少ない一方で、想定外のコストが発生しやすくなります。コストが増大すれば、資金繰りも苦しくなるでしょう。
シリーズAでの契約交渉では、自社の資金繰りを圧迫しないようにするために、不利な契約をしない慎重さも大切になります。また、アーリー期に続く形で、種類株式を活かした調達に力を入れることも一つです。
シリーズAのベンチャー企業には、以下3つの調達先がおすすめとなります。
- ベンチャーキャピタル
- コーポレート・ベンチャーキャピタル
- 日本政策金融公庫
シリーズAにおける調達額の相場は、数千万円~数億円です。
<関連記事>シリーズAとは?資金調達成功の準備・プロセス・成功のポイント
シリーズBとおすすめの調達先
シリーズBになると、自社の製品・サービスが市場で評価され始めます。ビジネスも軌道に乗ってきて、大規模な拡大に向けて動き出す段階です。
大規模な拡大を目指すということは、やはり多くの資金が必要となります。この段階での調達相場は、数億円程度です。シリーズAと同様に、以下の調達先がおすすめとなるでしょう。
- ベンチャーキャピタル
- コーポレート・ベンチャーキャピタル
- 日本政策金融公庫
<関連記事>シリーズBとは?資金調達方法や成功させるためのポイントを解説!
シリーズCとおすすめの調達先
シリーズCに入ると黒字経営が安定化します。この時期の企業には、海外展開を目指すところもあります 。
シリーズCでは、これまで紹介してきた方法に加えて、IPO(新規公開株式)も選択肢の一つになるでしょう。IPOの活用には、自社の知名度や社会的信用度を向上させる利点があります。
また、シリーズCの場合、以下のようにおすすめの調達先の選択肢も増える点も特徴です。
- ベンチャーキャピタル
- コーポレート・ベンチャーキャピタル
- 民間金融機関
- プライベート・エクイティファンド
<関連記事>シリーズCとは?A・Bとの違いや資金調達方法・事例まで解説
シリーズDとおすすめの調達先
シリーズDになると、安定的な収益が出せる状態で、新規の株式公開やM&Aなどを目指す最終段階に入ります。この時期に調達した資金は、新規事業の開発や市場拡大などに使われることが多いです。資金調達額の規模も多くなり、数十億円以上が相場になるでしょう。
おすすめの調達先は、シリーズCと同じです。
- ベンチャーキャピタル
- コーポレート・ベンチャーキャピタル
- 民間金融機関
- プライベート・エクイティファンド
<関連記事>シリーズDとは?定義や資金調達の金額・方法・実例までわかりやすく解説!
ベンチャー企業の資金調達で注意すべきポイント
資金調達の各ラウンドに対応した調達先は、あくまで企業の成長段階「だけ」にフォーカスしたものです。ベンチャー企業が自社の経営方針に合う方法で資金調達するうえでは、先述の投資ラウンドに加えて以下の4点の確認も必要です。詳しく見ていきましょう。
- 経営の自由度
- 納得できる調達条件
- 審査通過の難易度
- 資金調達までの時間
経営の自由度
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの資金調達では、株主になった投資家が経営の一部に関与することがあります。また、投資家に対して多くの株式を付与した場合、経営権を握られてしまうかもしれません。
一方でベンチャー企業に「自分たちはこうありたい」などの明確なビジョンがあったり、自由かつ柔軟性の高い経営を行ったりしたい場合、投資家からの出資以外の方法による資金調達を検討したほうがよいでしょう。
納得できる調達条件
たとえば、「自分が出資をする」と名乗り出た投資家が1者(1社)だけの場合、比較対象がないことから、企業にとって不利な条件が提示される可能性があります。場合によっては、自社の価値が低く見積もられることもあるでしょう。
この問題を防ぐためには、1者(1社)だけに依存せず、複数の投資家に話を持ちかけることが大切です。複数に話を持ちかけることは、世間一般でいう相見積もりに近い意味合いがあります。
何人かの投資家とやり取りをすると、自社の市場価値や最適かつ有利な調達条件も見えやすくなるでしょう。
審査通過の難易度
民間金融機関の融資による資金調達では、厳しい審査を通過する必要があります。また、補助金・助成金の場合、制度の種類によって審査通過の難易度が大きく異なることが多いです。
採択率は時期ごとに変わる傾向もありますが、たとえばものづくり補助金は約50%です。これに対してIT導入補助金のインボイス対応類型(1次~11次締切分)では、90%以上の数字が並んでいます。
申請リソースにあまり余裕がない創業期などの場合、以下のような情報を参考にしながら、審査通過や採択の可能性が高い方法にチャレンジしたほうが良いかも知れません。
参考:IT導入補助金2024 交付決定事業者一覧(中小企業庁)
参考:ものづくり補助金総合サイト 採択結果(中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構)
資金調達までの時間
キャッシュフローを正常化するためには、資金調達までの時間も意識する必要があります。
たとえば、民間金融機関とそれ以外のビジネスローンを比べた場合、審査通過や融資までのスピードが速いのは後者です。また、資金の緊急度が高い場合、売掛債権を活用するファクタリングも選択肢に入ってくるでしょう。
ベンチャー企業が資金調達を成功させる戦略ポイント
ベンチャー企業が資金調達を成功させるうえでは、自社に合う調達方法の選択以外にも、大切にすべき戦略面のポイントが7つあります。詳細を確認しましょう。
- 中長期な事業計画を考える
- 希望資金額と使用目的を明確にする
- 中長期的なパートナーシップを意識する
- 多くの投資家とコミュニケーションを図る
- 契約内容は細かく確認する
- 資金調達のタイミングを意識する
- 補助金・助成金申請を積極的に行う
中長期なビジネスプランを考える
出資や融資による資金調達では、投資家や金融機関などに自社のビジネスプランを伝えることになります。その際に、「このベンチャー企業には期待ができそうだ」と感じてもらうためには、以下のような内容を含めた中長期的な事業計画やドキュメントが必要でしょう。
- 経営陣の経歴
- 事業を立ち上げた背景
- 市場分析
- 競合分析
- 収益予測 など
また、説得力のあるビジネスプランは、一度作成して終わりではありません。自社や外的環境の変化を意識しながら、十分な時間と労力をかけてブラッシュアップする必要があります。
事業計画のなかで作成する資金面のプランでは、定期的な返済や償還期限なども意識する必要があるでしょう。
中長期的なパートナーシップを意識する
ベンチャー企業が事業を成功させるうえでは、経験豊富な投資家や金融機関からの助言やサポートが欠かせません。その意味で資金調達は、投資家や金融機関と事業パートナーとしての関係が始まる入口でもあります。
ベンチャー企業が資金調達をする際には、「資金が効率的に得られるか?」に加えて、「その投資家と中長期的なパートナーシップを築けるか?」の視点を持つことが大切です。また、その投資家が持つネットワークに加わることなども、一つの動機や選定理由になるでしょう。
希望資金額と使用目的を明確にする
先述のビジネスプランと関係することですが、自社に合う投資家を選び、資金を出してもらうためには、「何の目的でいくらの資金が必要か?」を明確にすることも大切です。この作業をしっかり行うことで、必要額や目的に合う投資家に話を持ちかけやすくなります。
また、資金調達前に希望額と使用目的を明確にする作業には、たとえば実際にプロジェクトを動かし始めてから生じる資金不足などを防ぐ効果もあるでしょう。
多くの投資家とコミュニケーションを図る
これは、先ほど紹介した相見積もりに近い戦略です。
1者(1社)の投資家やオファーだけに固執すると、提示された条件や自社の価値の妥当性が判断しづらくなります。また、1社しか資金を出してくれない状況では、不利な条件をのまざるを得ない可能性もでてくるでしょう。
この問題を防ぐためには、1者(1社)への依存や固執をやめて、複数の投資家との交渉を進めることが大切です。さまざまな投資家や金融機関と話をすることで、自分たちだけでは気づかなかった新たな方向性などが見つかることもあるかもしれません。
契約内容は細かく確認する
契約内容の不明確さや納得できない項目は、将来のトラブル原因になり得ます。投資家と長期的な二人三脚を続けていくうえでは、契約書の細かな部分もしっかり確認し、自社の戦略やビジョンと整合性がとれた内容での契約をする必要があるでしょう。
なお、投資契約のチェックには、専門知識が必要です。社内での確認・判断が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することも必要となります。
資金調達のタイミングを意識する
資金調達には「挑戦すべきタイミング」と「挑戦にはあまり適さないタイミング」の2つがあります。
たとえば、自社の業績が好調であったり、業界全体への注目が集まるなどのポジティブなニュースがある時期は、企業評価も高まりやすく資金調達におすすめのタイミングです。
一方で、資金が底をつく直前などの緊急度が高い状態では、調達を急がざるを得ない事情から、理不尽な条件を飲まざるを得なくなるかもしれません。
自社の経営に負担のない資金調達を目指すうえでは、なるべく最適なタイミングで申請や交渉などに臨むことが理想でしょう。
資金調達への挑戦を積極的に行う
ベンチャー企業の資金調達を成功させるためには、創業間もない時期であっても、自社に大きな負担がかからない範囲内で、申請や交渉などの挑戦を積極的に行うことが大切です。
また、補助金・助成金は返済不要ですし、民間金融機関や信販会社の審査とは違って、自社の信用情報に傷がつくこともありません。申請手続きは複雑で手間がかかりますが、返済することがないお金が手に入ると考えれば、取り組む価値は大いにあるといえるでしょう。
専門家にサポートしてもらう
ベンチャー企業が初めての資金調達を目指す場合、申請手続きの流れから契約内容のチェックポイントなどで「わからないことだらけ」になることも多いです。こうしたなかで、経営面や法的なリスクを防ぐためには、各士業の専門家の助言を受けることも大切になります。
なお、いわゆる経営相談は、以下のような機関や場所でも実施されています。無料相談も多いです。どの専門家に相談すればよいかわからず悩んでいるときには、一度問い合わせてみてもよいでしょう。
参考:経営に関する相談(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
参考:ワンストップ総合相談窓口(公益財団法人 東京都中小企業振興公社)
ベンチャー企業の資金調達と税金面の注意点
ベンチャー企業が資金調達をする場合、税金の取り扱いにも注意する必要があります。
具体的なポイントは、資金調達の方法によって異なるものです。以下のようにそれぞれに異なる注意点があることを考えると、「この方法だと税金面にどういう影響があるか?」を調べてから意思決定をすることも必要でしょう。
- 【出資】資本金の増加は原則として非課税、株式発行時には登録免許税が発生
- 【民間金融機関】支払利息が営業外費用になり、法人税に影響
- 【補助金・助成金】原則は課税対象
- 【資産売却】譲渡所得となり課税対象 など
なお、ベンチャー企業やスタートアップ企業がエンジェル投資家から出資を受ける場合、要件に該当すれば「エンジェル税制」という優遇措置を受けられる可能性もあります。エンジェル税制は、ベンチャー企業と個人投資家の双方にメリットがある制度です。
資金調達における税金面の取り扱いでわからない点がある場合は、税理士に相談をしたほうがよいでしょう。
ベンチャー企業における資金調達の具体例
ベンチャー企業が資金調達を行い、事業拡大などにつなげていくうえでは、他企業の成功事例を参考にするのも一つです。
そうすることで、「どういう方法でどの程度の調達が可能になるか?」というイメージも掴みやすくなるでしょう。ここでは、以下の2社における資金調達の成功事例を紹介します。
- ソニア・セラピューティクス株式会社
- 株式会社斎藤企画
ソニア・セラピューティクス株式会社
ソニア・セラピューティクス株式会社は、いわゆる大学発ベンチャーです。大学発ベンチャーとは、大学や研究機関の研究成果をもとに製品開発などを行う挑戦的な企業の総称になります。
ソニア・セラピューティクス株式会社の設立は、2020年2月です。そこから、切除不能膵癌に対する無作為比較試験および事業化を目的とするシリーズBの資金調達を目指すことになります。その結果、新規投資家6社および既存投資家5社を引受先とする第三者割当増資に成功し、総額で23.5億円の資金を調達できました。
同社は、2022年12月における国内スタートアップの資金調達ランキングで2位になっています。2024年には、高い技術力・ステークホルダーとの調整力・国際展開への実行力などが高く評価されて、経済産業省の「大学発ベンチャー表彰2024」も受賞しています。
参考:国内スタートアップ資金調達金額ランキング(2022年1月-12月)(STARTUP DS)
株式会社斎藤企画
株式会社斎藤企画は、カプセル玩具のいわゆる「ガチャガチャ」市場で大手になることを目指すベンチャー企業です。
この企業では当初、十分な利益が出ないことで民間金融機関からの思うような資金調達ができない課題を抱えていました。そんなときに、あるメインバンクが成長性が期待できるベンチャー企業を対象とするファンドを立ち上げます。このファンドに注目した社長は、これまでの事業計画を練り直して申込みを行い、3,000万円もの資金調達に成功しました。
そこから、メインバンクの新事業支援担当部署の紹介を受けて、地元の商工会議所が主催する事業を活用し、中小企業診断士のサポートを受けながら19人の投資家より1,450万円もの資金調達に成功しています。
この事例は、戦略ポイントのところで紹介した投資家との中長期的なパートナーシップの重要性を示すものとなるでしょう。
なお、株式会社斎藤企画の事例は、全国商工会連合会の以下資料に掲載されているものです。この資料には、さまざまな成功事例が載っています。ぜひ参考にしてください。
参考:直接金融による資金調達事例集(第2版)(全国商工会連合会)
ベンチャー企業の資金調達について解説しました
ベンチャー企業の成長を加速させるためには、自社に合う方法での資金調達が必要です。ただし、選択した方法や調達先によっては、経営の自由度低下などの課題が生じることもあります。
自社が思い描くビジョンやミッションを達成していくうえでは、複数の投資家とコミュニケーションを図りながら、中長期的な視点で資金の調達先を決めることも大切でしょう。