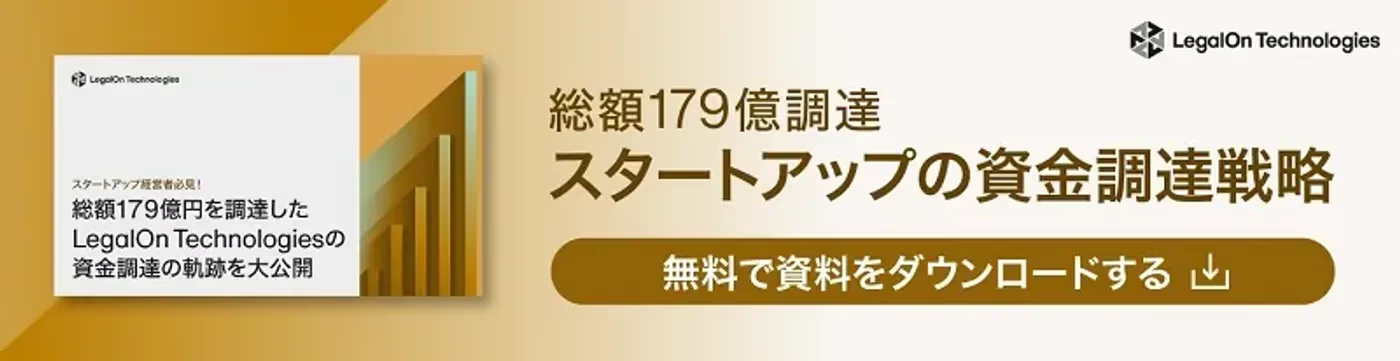経常運転資金は日々の事業活動に必要な資金
経常運転資金は企業経営において、日々の事業活動を円滑に進めるために必要不可欠な資金です。具体的には以下のような支出が該当します。
- 仕入れ代金の支払い
- 従業員への給与支払い
- 光熱費や通信費などの経費
- 在庫の確保や管理 など
経常運転資金の特徴
経常運転資金の特徴は、事業活動の継続性を支える「循環型の資金」である、という点です。仕入れた商品は販売されて売上となり、その売上から次の仕入れ資金が生まれるという循環が形成されます。
しかし支払いのタイミングと入金のタイミングにはズレが生じるので、このギャップを埋める資金の確保が必要です。一般的には3〜6ヶ月分の経常運転資金を確保しておくことが推奨されますが、必要額は業種や事業規模、取引条件によって大きく異なります。
また経常運転資金の特徴は継続的に必要な資金ですが、事業規模や季節的要因、業界の特性によって、必要な金額が変わります。
経常運転資金の重要性
経営運転資金が不足すると、事業の継続に支障をきたす可能性があります。安定した事業運営のためには、余裕を持った運転資金の確保と資金繰りの管理が欠かせません。
特に成長期の企業では、事業拡大に伴う運転資金の増加に注意を払う必要があります。適切な資金計画を立て、必要に応じて金融機関からの融資を受けるなどの対策を講じましょう。
経常運転資金の計算方法と計算例
事業を円滑に運営していくために必要な運転資金の見積もり方を理解することは、経営において重要な課題です。ここでは具体的な算出方法と、資金額の目安を業種別に見ていきましょう。
経常運転資金は、以下の計算式で算出されます。
- 売上債権+棚卸資産-仕入債務=経常運転資金
売上債権は得意先への売掛金や受取手形など、将来回収する予定の売上代金です。また棚卸資産は商品や原材料、仕掛品など、販売や生産のために保有している在庫の資産額を指します。仕入債務は仕入先への買掛金や未払金など、将来支払う予定の仕入代金です。
例えば、売上債権が3,000万円、棚卸資産が2,000万円、仕入債務が1,000万円の場合、必要な運転資金は以下のように算出されます。
- 売上債権 3,000万円
- 棚卸資産 2,000万円
- 仕入債務 1,000万円
3,000万円+2,000万円-1,000万円=4,000万円
経常運転資金は4,000万円となる計算です。
その他運転資金の種類
ここまでは経常運転資金について紹介しました。実は企業が必要とする運転資金には、さまざまな種類があります。ここでは経常運転資金以外に、企業経営に必要な運転資金を見ていきましょう。
増加運転資金
増加運転資金は事業拡大や売上増加に伴って、新たに必要となる運転資金のことです。新規取引先の獲得、新規出店、生産能力の増強、新商品の開発など、事業拡大の形態に応じて資金需要が発生します。
増加運転資金は売上増加の時期と、資金需要の発生時期にタイムラグが生じやすいのが特徴です。新規取引を開始する場合には原材料の仕入れや人員の確保など、先行した投資が必要になります。しかし売上回収までには一定期間が必要です。資金繰りが一時的に悪化するリスクに留意しましょう。
減少運転資金
減少運転資金は事業不振による売上減少時や、事業縮小時に必要となる運転資金です。
売上が減少しても人件費や家賃といった固定費の支払いは継続的に発生します。また店舗閉鎖に伴う原状回復費用、在庫の廃棄費用、引越費用など、事業縮小に伴う追加の支出も必要となります。
こうしたケースでは売上に対して経費が余分にかかる状態が続くため、資金繰りが悪化しやすくなります。減少運転資金は経営立て直しまでの「つなぎ資金」としての役割を果たすものです。状態が長期化すると資金がショートし、経営破綻のリスクが高まります。
売上回復や経費削減などの経営改善策を迅速に実行し、できるだけ早期に正常な収益体質に戻すことが重要です。
賞与資金
従業員への賞与支給に必要な資金であり、多くの企業では年2回、月例給与の数ヶ月分に相当する金額が支給されます。賞与資金はそのための財源となる資金です。
賞与支給額は企業の業績や従業員数によって変動しますが、前年実績や当期の業績見通しを基に概算を算出することができるのです。多くの企業では月次決算の段階から賞与引当金を計上し、計画的な資金準備を行います。
資金繰りの状況によっては、金融機関からの借入れや他の運転資金との調整を検討すると良いでしょう。
季節資金
季節資金は事業活動の季節的な変動に対応するために必要な資金です。業種や取扱商品によって、発生時期や規模が大きく異なります。
アパレル業界では季節商品の仕入れ、小売業では年末商戦向けの在庫確保、観光業では繁忙期の人員増強など、それぞれの事業特性に応じた資金需要が発生します。毎年同じような時期に発生する、計画可能な資金です。
一方で、気候変動や消費者ニーズの変化によっては、突発的に想定以上の資金が必要になるリスクもあります。
赤字補填資金
赤字補填資金は、事業活動で生じた損失(赤字)を補うための資金です。一時的な業績悪化や市場環境の変化、予期せぬコスト増加などにより経営的な収入が支出を下回った場合に、差額を補填する目的で使用されます。
赤字補填資金は事業の継続性を維持するための「救済的な性質」を持ちます。売上の急激な減少により固定費の支払いが困難になった場合や、原材料価格の高騰で利益率が低下した場合に活用される資金です。
なお赤字補填資金は経常運転資金として考えられることも多い項目ですが、本質的には企業の損失を補填する資金です。通常の営業活動によって必要となる経常運転資金とは少し区別して考えましょう。
経常運転資金の調達方法
経常運転資金の調達にはいくつかの方法があります。借入や公的制度の利用のほか、最近ではクラウドファンディングによって広く資金を集めることも一般化しています。
事業の状況や資金ニーズに応じて、最適な調達方法を選択しましょう。
民間金融機関からの借入れ
民間金融機関からの借入れは、運転資金調達の代表的な方法のひとつです。メインバンクとの取引実績が融資の判断材料となるため、日頃から良好な関係を築いておくことが重要となります。
証書貸付のほか、当座貸越や手形貸付などの融資形態があり、担保が不足している場合でも、信用保証協会の保証制度で借入れが可能になることがあります。ただし、金融機関との交渉や審査には時間がかかることを考慮しておきましょう。
日本政策金融公庫からの融資
日本政策金融公庫は政府系金融機関として、中小企業の資金調達を支援しています。一般的な融資に加え、創業融資や新事業展開向けの特別融資なども用意されているのが特徴のひとつです。また民間金融機関と比べて金利が低く、返済期間も長めに設定されています。
創業時や新規事業の立ち上げ時など、実績が少なく民間金融機関からの借入れが難しい場合にも、資金調達の有力な選択肢となります。
ビジネスローンの利用
ビジネスローンは比較的少額の資金を迅速に調達できる方法です。オンラインでも申込みが可能で、最短当日での融資実行を謳うサービスも増えています。審査基準も緩やかな傾向にありますが、金利が高めに設定されているため、短期的な資金需要への対策として利用しましょう。
無担保・無保証人で借り入れできることが多く、創業間もない企業でも利用しやすい点が特徴です。また事業用途であれば使途が比較的自由で、運転資金として柔軟に活用できます。ただし融資額は企業の売上規模や業歴によって制限されることが多く、金利も年率10%を超えるケースもあるため、慎重な検討が必要です。
補助金・助成金の活用
補助金や助成金は返済不要な資金として、運転資金の有効な調達手段のひとつとなります。国や地方自治体、各種支援機関が実施する制度があり、事業の成長段階や目的に応じて選択可能です。特に新規事業の立ち上げや設備投資、研究開発、人材育成など、特定の目的に対する支援制度が充実しています。
ただし申請から交付までに時間がかかることや、使途に制限があることは考慮しなければいけません。また補助金・助成金は競争率が高く、採択されるとは限りません。交付後も厳密な経理処理や報告義務が求められるため、適切な管理体制を整える必要があります。
さらに補助金・助成金は基本的に後払いとなることが多く、他の調達手段と組み合わせて活用してください。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を募る方法です。新商品開発や新規事業などのプロジェクトに対して、支援者から資金を集めます。
リターンの形態によって「購入型」「寄付型」「投資型」があり、運転資金の調達だけでなく、商品の市場性の検証や顧客との関係構築にも活用できます。
支援者との約束したリターンの実現が重要で、プロジェクトの実現性や説明力が求められる方法です。
そのほか企業が保有する売掛金を専門業者に売却して資金化する「ファクタリング」や、インターネット上で、企業と投資家をマッチングさせる「ソーシャルレンディング」などの方法があります。
こうした手法はネット上で完結することも多く、偽の情報や詐欺などのトラブルに巻き込まれることも少なくありません。情報は十分吟味し、信用できるサービスを利用しましょう。
スタートアップの資金調達について詳しく知りたい方は、ぜひ以下お役立ち資料も併せて確認してみてください。
経常運転資金管理の3つのポイント
日々の事業活動に必要な経常運転資金を適切に管理することは、企業経営の基盤となります。ここでは運転資金を安定して管理するための、3つのポイントを解説します。
必要な経常運転資金は状況に応じて変化する
経常運転資金は状況に応じ、日々変動しています。業績の拡大や縮小や取引条件の変更、市場環境の変化などの要因で、企業経営に必要な金額は変わるからです。
例えば売上が増加基調にある場合、仕入れや人件費などの先行投資が必要となって運転資金も増加します。また業務効率化や在庫の適正化を進めることで、必要額を抑制できることもあります。
重要なのはこうした変化を早期に把握し、適切な対応を取ることです。業績だけでなく企業を取り巻く社会情勢にもアンテナをはり、資金管理に反映させましょう。
経常運転資金を削減するには?
経常運転資金の削減は資金効率を高め、財務体質を強化する有効な手段です。
まずは在庫の適正化から見直してみましょう。需要予測の精度を上げ、過剰在庫を抑制することで、資金の滞留を防ぐことができます。
次に売掛金の回収期間短縮です。取引先との交渉や早期回収のインセンティブ導入などを検討します。また支払条件の見直しや業務プロセスの効率化、固定費の見直しなども、運転資金削減の重要な施策となります。
ただし取引先との関係悪化や業務品質の低下を招かないよう、バランスの取れた対応が必要です。企業経営は取引先や顧客との関係性の上で成り立つことにも留意しながら、対策を進めていきましょう。
経常運転資金が不足したときの対応
運転資金の不足は、事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。不足が予想される場合は早急に原因を特定し、短期的・中長期的な対策を並行して進めていきましょう。
短期的には売掛金の早期回収促進や不要な支出の抑制、金融機関からの借入れなどが有効です。中長期的には事業構造の見直しや収益性の改善、資金調達方法の多様化などを検討します。
また定期的な資金繰り予測を行い、不足を事前に察知できる体制を整えることも重要です。
企業経営において、資金不足はいつでも起こり得るトラブルのひとつです。日常的に対策と備えを進めておきましょう。
経常運転資金について解説しました
運転資金は企業活動の血液とも言える重要な要素です。適切な管理と調達が、経営の安定性を左右します。業種や事業規模、取引条件などを考慮し、適切な運転資金の水準を見極めましょう。また定期的に必要額を見直し、環境変化に応じて柔軟に調整することで、効率的な資金管理が可能となります。
資金調達方法としては、金融機関からの借入れのほか、公的支援の活用やクラウドファンディングなどの新しい調達手法も選択肢となります。複数の選択肢を持っておくことで、必要な時に、適切な方法での資金調達が可能です。
運転資金の管理は、一度整えれば終わりというものではありません。事業環境の変化に応じて継続的に見直し、改善を図ることで、盤石な持続的な企業成長の基盤となるのです。